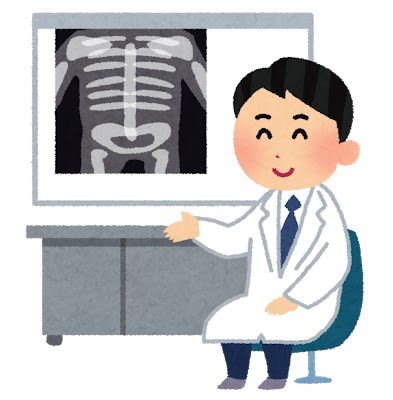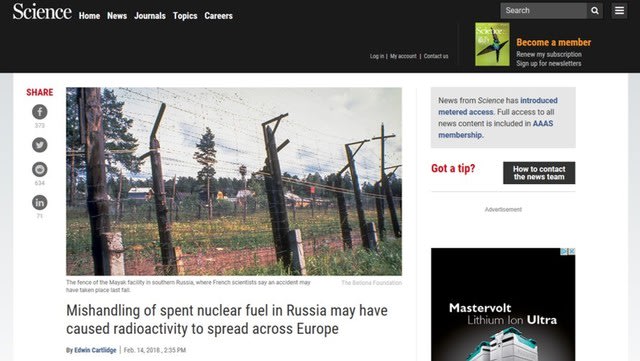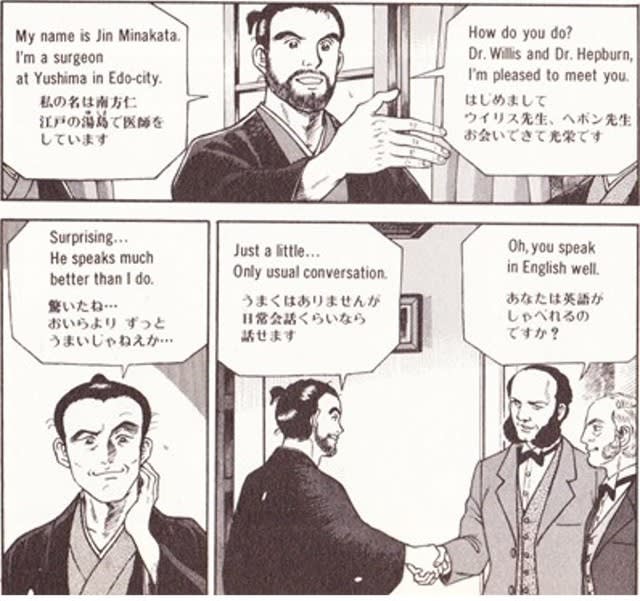ここ最近体調が悪い中、私の好きなイチロー選手まで事実上引退というニュースを見て「一つの時代が終わってしまった」ことを知り、すこし落ち込んでいます。まるでいつまでも元気でいると思っていた親がいつの間にか老いているのを見て、流れてしまった時間を感じられずにはいられないような、そんな寂寥感に似たものを感じます。かつて世界一の'Hit King'であった彼の引退というものは、いつか来るモノとはいえ、やはり見たくはなかったですね。
祗園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり
娑羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす
おごれる人も久しからず
唯春の夜の夢のごとし
たけき者も遂にはほろびぬ
偏に風の前の塵に同じ
さて、今回は「Impact Factor(以下IF)」についてです。
自然科学界では、ここ数十年にわたってIFというものに支配されてきました。IFについては、このブログ上でも幾度か触れてきましたし、詳細はここでは省きます(ご存知ない方は算出方法などGoogleなどで検索して頂ければ直ぐに判ります)。
もともとは科学ジャーナルの評価に用いられるはずの指標でしたが、いつの間にやら研究者や学術機関の評価に用いられるようになり、研究者たちは高いIFを持つジャーナルでどれだけ多くの論文を発表できるかを競わされる羽目になりました。たとえば、競争的研究資金の評価において、業績欄に並ぶ論文が掲載されたジャーナルのIFを見て評価するという方法が横行するなどしたため(実際に某K大学の某Y教授のブログでは「審査の際にはやはり業績を見る」旨が書かれていました)、研究者たちは論文をジャーナルへ投稿する際にはそのジャーナルのIFを気にせざるを得なくなったのです。
それは私のボスのような放射線学界における大御所であっても同様で、彼もいつもIFやらCiteScore(IFとはまた別の指標)に気をつけているようです。実際、私が所属する研究センターはがん研究に特化しているのですが、他の部門に比べて、我々の放射線治療学・生物学部門は出版する論文数では勝るのですが、総IF値で苦戦を強いられるという状況がここ数年続いていて辛いところです。
最近、私もこのImpact Factorに翻弄されています。
ボスに言われて、私も日頃から色々な研究費や助成金に応募することがあるのですが、その際に自身がこれまで積み上げてきた業績を示す必要があります。つまり発表してきた論文などを明示するのですが、最近、それらの論文が掲載された全ジャーナルのIFの和を添えて出すように指示されたものがあり、改めて放射線学界の不遇ぶりを痛感させられる機会がありました。
レントゲンやキュリー夫人の時代にはノーベル賞といえば放射線研究者でしたが、残念ながら現在の放射線研究は世界的にもマイナーな領域になってしまっています(そのせいで「福島」のこともよく判らんことになっているわけですが)。そして、IFは時代の流行などを反映するものでもありますから、放射線科学ジャーナルのIFが低くなってしまうわけです。
たとえば、生命科学系における三大誌と言われる下記のジャーナルでは、目が飛び出るほどに高い、世界最高峰のImpact Factorを誇っています。そろそろIF 2017が発表される頃ですが、ここにはとりあえず2016版をば。
Nature 40.137
Science 37.205
Cell 30.410
一方、放射線生物学に関係するジャーナルとしては下記があります。
IJROBP(米国放射線腫瘍学会誌、別名Red Journal) 5.133
Radiation Oncology(欧州放射線腫瘍学会誌) 4.328
Radiation Research(米国放射線科学会誌、放射線科学の総合誌) 2.539
IJRB(放射線生物学の国際専門誌) 1.992
Journal of Radiation Research (日本放射線影響学会誌) 1.788
お分かり頂けただろうか。
放射線学界の不遇ぶりを…
つまり、Red Journalみたいなトップジャーナル(放射線腫瘍学、生物学、物理学の中から優れた論文だけを掲載する業界最高峰)でもIFは5くらいしかないわけです。私もRed Journalに論文を載せたことがありますし、編集部から査読を依頼されることもあります。このことは放射線研究者の端くれとしては一応名誉なことではあるのですが、残念ながら他の研究分野の人からは「IF 5程度のジャーナルでしょ?」と思われてしまうかもしれません。
上記を見て頂ければ判る通り、放射線科学分野では、ほとんどの主な論文はIF 1~2程度のジャーナルに出版されます。Natureの40と比べると、当然ですが、圧倒的に低いですね。基礎医学の中にはもっと不遇なマイナー分野もあるかもしれませんが、この放射線生物学もなかなか酷いです。これでは、他の分野にいる研究者と競合する場合、なかなか勝ち目がありません。例えば、再生医学・生物学や免疫学などの分野のジャーナルのIFはもっとはるかに高いのです。
こりゃ、勝てんわい。
現在、ボスに言われて、とある研究助成への応募書類を書いているのですが、正直「なかなか難しいだろうな」と少々諦めムードです。他の研究分野と競合する場合、純粋にIFの値だけ見ると、いつも苦戦を強いられるからです。
う~む、厳しい。
祗園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり
娑羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす
おごれる人も久しからず
唯春の夜の夢のごとし
たけき者も遂にはほろびぬ
偏に風の前の塵に同じ
さて、今回は「Impact Factor(以下IF)」についてです。
自然科学界では、ここ数十年にわたってIFというものに支配されてきました。IFについては、このブログ上でも幾度か触れてきましたし、詳細はここでは省きます(ご存知ない方は算出方法などGoogleなどで検索して頂ければ直ぐに判ります)。
もともとは科学ジャーナルの評価に用いられるはずの指標でしたが、いつの間にやら研究者や学術機関の評価に用いられるようになり、研究者たちは高いIFを持つジャーナルでどれだけ多くの論文を発表できるかを競わされる羽目になりました。たとえば、競争的研究資金の評価において、業績欄に並ぶ論文が掲載されたジャーナルのIFを見て評価するという方法が横行するなどしたため(実際に某K大学の某Y教授のブログでは「審査の際にはやはり業績を見る」旨が書かれていました)、研究者たちは論文をジャーナルへ投稿する際にはそのジャーナルのIFを気にせざるを得なくなったのです。
それは私のボスのような放射線学界における大御所であっても同様で、彼もいつもIFやらCiteScore(IFとはまた別の指標)に気をつけているようです。実際、私が所属する研究センターはがん研究に特化しているのですが、他の部門に比べて、我々の放射線治療学・生物学部門は出版する論文数では勝るのですが、総IF値で苦戦を強いられるという状況がここ数年続いていて辛いところです。
最近、私もこのImpact Factorに翻弄されています。
ボスに言われて、私も日頃から色々な研究費や助成金に応募することがあるのですが、その際に自身がこれまで積み上げてきた業績を示す必要があります。つまり発表してきた論文などを明示するのですが、最近、それらの論文が掲載された全ジャーナルのIFの和を添えて出すように指示されたものがあり、改めて放射線学界の不遇ぶりを痛感させられる機会がありました。
レントゲンやキュリー夫人の時代にはノーベル賞といえば放射線研究者でしたが、残念ながら現在の放射線研究は世界的にもマイナーな領域になってしまっています(そのせいで「福島」のこともよく判らんことになっているわけですが)。そして、IFは時代の流行などを反映するものでもありますから、放射線科学ジャーナルのIFが低くなってしまうわけです。
たとえば、生命科学系における三大誌と言われる下記のジャーナルでは、目が飛び出るほどに高い、世界最高峰のImpact Factorを誇っています。そろそろIF 2017が発表される頃ですが、ここにはとりあえず2016版をば。
Nature 40.137
Science 37.205
Cell 30.410
一方、放射線生物学に関係するジャーナルとしては下記があります。
IJROBP(米国放射線腫瘍学会誌、別名Red Journal) 5.133
Radiation Oncology(欧州放射線腫瘍学会誌) 4.328
Radiation Research(米国放射線科学会誌、放射線科学の総合誌) 2.539
IJRB(放射線生物学の国際専門誌) 1.992
Journal of Radiation Research (日本放射線影響学会誌) 1.788
お分かり頂けただろうか。
放射線学界の不遇ぶりを…
つまり、Red Journalみたいなトップジャーナル(放射線腫瘍学、生物学、物理学の中から優れた論文だけを掲載する業界最高峰)でもIFは5くらいしかないわけです。私もRed Journalに論文を載せたことがありますし、編集部から査読を依頼されることもあります。このことは放射線研究者の端くれとしては一応名誉なことではあるのですが、残念ながら他の研究分野の人からは「IF 5程度のジャーナルでしょ?」と思われてしまうかもしれません。
上記を見て頂ければ判る通り、放射線科学分野では、ほとんどの主な論文はIF 1~2程度のジャーナルに出版されます。Natureの40と比べると、当然ですが、圧倒的に低いですね。基礎医学の中にはもっと不遇なマイナー分野もあるかもしれませんが、この放射線生物学もなかなか酷いです。これでは、他の分野にいる研究者と競合する場合、なかなか勝ち目がありません。例えば、再生医学・生物学や免疫学などの分野のジャーナルのIFはもっとはるかに高いのです。
こりゃ、勝てんわい。
現在、ボスに言われて、とある研究助成への応募書類を書いているのですが、正直「なかなか難しいだろうな」と少々諦めムードです。他の研究分野と競合する場合、純粋にIFの値だけ見ると、いつも苦戦を強いられるからです。
う~む、厳しい。