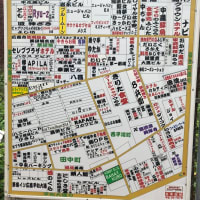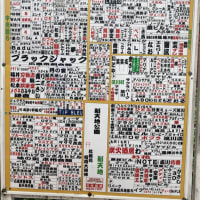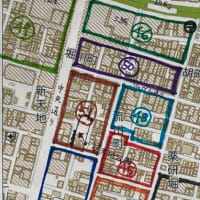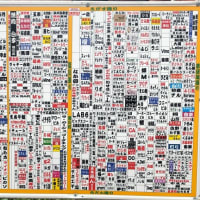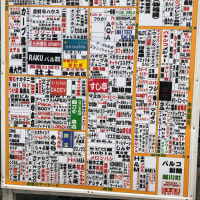岡山県人以外で、早島町はどこに在るのか知っている人は、そんなに多くは無いと思います。
勿論、広島県人の私も知りませんでした。
倉敷で仕事をしている友人に、
岡山県で、倉敷以外で古い町並みが見れる所を聞いたら、
「早島ですかね。古い建物の町並みがあるのは・・・」の返事があったので、
3月21・22日に行われる瀬戸内倉敷ツーデーマーチに参加する前日に、早島町に行く事にしました。
20日は朝から雨が降り出しましたが、「雨も又自然」と言うことで、雨の早島の街ウォークです。
JR早島駅に行くには、岡山駅より瀬戸大橋線のマリンライナー(早島駅に停車しない便もあります)に乗るか、
宇野線の各駅停車の電車でも行けます。
JR早島駅。有人の駅でした。 駅前のロータリー。


早島駅から町の方に向かう通りだが、人がいない。駅前の商店街など無い。
食べるお店もこの通りに2軒だけだったと思う。
岡山駅で食べてきたので良かった。
何時もは知らない町に行く時は、どこにでも必ず有る駅前の食堂で食べる事にしているが、
今回は岡山に着いたのがお昼時でお腹がペコペコなので、早島まで我慢が出来なかった。

駅前からのメイン道路?を歩いていくと、倉敷で見かけるなまこ壁の古そうな家がありました。(左の写真)
白壁の塀に囲まれた渋い和風の母屋と蔵風に造られたガレージの建物。
ガレージの扉は板で造られていて、その板が良い味を出していた。


メイン道路?から早島町役場の方に向かって歩いていると、藁屋根の家を見つけました。
周りは新しい住宅地になってきているが、藁屋根は貴重だ。
早島町役場の近くの歴史民族資料館の建物。
特産だったイ草関連の展示があるようだが、閉まっていた。


役場の前の「ゆるびの舎(や)」の建物。
早島町ガイドマップより…心の健康づくりを基本コンセプトとして、文化ホールや図書館、
健康づくりセンターなどからなる総合複合施設です。
「ゆるび」とは、「心がくつろぐ」という意味があります。
町の規模の割りに立派な建物です。役場も鉄筋コンクリート造の3階建ての建物で、役場のイメージではありません。
町自体が、岡山市と倉敷市に囲まれているのにどちらとも合併しないで、今回の平成の町村大合併でもしないで、
町で頑張っているのは豊かな財政があるのだろう。

江戸時代の終わり頃には金比羅詣で賑わった道も、雨が降っているので人影も無い。
ここは、道路も拡張されて建物は建替えられているので、昔の建物の町並みは見られなかったが、
藁屋根をトタンで蔽った家が目に付いた。
ちょっと横道に入ると焼板壁の家が遺されている。


上の左の写真の建物。

ここまでは、友人が言った「古い建物の町並みが在る」は見当たりませんでした。続く。
勿論、広島県人の私も知りませんでした。
倉敷で仕事をしている友人に、
岡山県で、倉敷以外で古い町並みが見れる所を聞いたら、
「早島ですかね。古い建物の町並みがあるのは・・・」の返事があったので、
3月21・22日に行われる瀬戸内倉敷ツーデーマーチに参加する前日に、早島町に行く事にしました。
20日は朝から雨が降り出しましたが、「雨も又自然」と言うことで、雨の早島の街ウォークです。
JR早島駅に行くには、岡山駅より瀬戸大橋線のマリンライナー(早島駅に停車しない便もあります)に乗るか、
宇野線の各駅停車の電車でも行けます。
JR早島駅。有人の駅でした。 駅前のロータリー。


早島駅から町の方に向かう通りだが、人がいない。駅前の商店街など無い。
食べるお店もこの通りに2軒だけだったと思う。
岡山駅で食べてきたので良かった。
何時もは知らない町に行く時は、どこにでも必ず有る駅前の食堂で食べる事にしているが、
今回は岡山に着いたのがお昼時でお腹がペコペコなので、早島まで我慢が出来なかった。

駅前からのメイン道路?を歩いていくと、倉敷で見かけるなまこ壁の古そうな家がありました。(左の写真)
白壁の塀に囲まれた渋い和風の母屋と蔵風に造られたガレージの建物。
ガレージの扉は板で造られていて、その板が良い味を出していた。


メイン道路?から早島町役場の方に向かって歩いていると、藁屋根の家を見つけました。
周りは新しい住宅地になってきているが、藁屋根は貴重だ。
早島町役場の近くの歴史民族資料館の建物。
特産だったイ草関連の展示があるようだが、閉まっていた。


役場の前の「ゆるびの舎(や)」の建物。
早島町ガイドマップより…心の健康づくりを基本コンセプトとして、文化ホールや図書館、
健康づくりセンターなどからなる総合複合施設です。
「ゆるび」とは、「心がくつろぐ」という意味があります。
町の規模の割りに立派な建物です。役場も鉄筋コンクリート造の3階建ての建物で、役場のイメージではありません。
町自体が、岡山市と倉敷市に囲まれているのにどちらとも合併しないで、今回の平成の町村大合併でもしないで、
町で頑張っているのは豊かな財政があるのだろう。

江戸時代の終わり頃には金比羅詣で賑わった道も、雨が降っているので人影も無い。
ここは、道路も拡張されて建物は建替えられているので、昔の建物の町並みは見られなかったが、
藁屋根をトタンで蔽った家が目に付いた。
ちょっと横道に入ると焼板壁の家が遺されている。


上の左の写真の建物。

ここまでは、友人が言った「古い建物の町並みが在る」は見当たりませんでした。続く。