
The Return Of Pulcinella
道化師の帰還
ある1月の午後、ニューヨーク。ダークブラウンの髪の女性が1人地下鉄に座っていた。カーキ色のセーター、1月の寒さから身を守るための黒いロングコート姿の控えめな外見。本を読んでいる彼女は自分が密かにカメラで撮影され、イヨネスコ(フランスの劇作家で、 不条理劇で有名)でさえ自慢に思うに違いない不条理劇の主役になるなんて想像も付かなかったはず。駅で地下鉄が止まると男が1人乗り彼女の前に立った。男は平凡な身なりで、コートを着てバックパックを背負っていた・・・唯一彼に欠けているもの、それはズボンだった。その駅から6駅連続して同じ車両にズボンを穿いていない男が1人ずつ計6人乗り込んできた。車両に乗り込んだ男たちはお互い全く無反応で、その様子に女性は訳が判らず少なからず恐怖を感じていたに違いない。しかし10分後、彼女は彼女の向かいに座っている乗客と目を合わせ、その瞬間初めて彼女の緊張は解け顔に笑みが広がった。同じ境遇の傍観者と状況を共有することで彼女はこのばかげた状況を楽しむ事が出来るようになり、恐怖が消えた瞬間だった。たった1人の孤独な目撃者だった彼女が特異な経験を他の人々とシェアしたこの瞬間、これがこの劇を僕が見た中でも最高のストリート・パフォーマンスの1つにしている。で、僕の頭の中はこんな考えで一杯だ・・・こういったパフォーマンスは実際に世の中を少しはましにすることが出来るのかって。
この動画は2002年のチャーリー・トッドによる作品だ。彼はニューヨークのストリート・パフォーマンス劇グループ「Improv Everywhere」のディレクターで、世界中で100以上のフラッシュ・モブ作戦を実行している。ここ何年かでフラッシュ・モブの文化的知名度は上がった。ニューヨークのデパートの窓際で振り付けされたダンスを意味もなく踊る50人に遭遇したり、何百人もの人々がiPodで同じ音楽を聴きながら駅の真ん中で始めるでたらめなダンスを見る楽しさ・・・誰がそれを否定できるだろう?フラッシュ・モブでは参加した志望者だけでなく、その場に居合わせた観客もパフォーマンスの一部なんだ。フラッシュ・モブは他にすることが無い失業者が引き起こす意味の無い騒動だって否定的な目で見られていたりもするけれど、これは間違った解釈だ。企業が製品を売るためにこのコンセプトを悪用して貶めている事実に関わらず、元々の形は僕たちの生きる「今」に関わる文化的に意義のある活動で、何百年も前から行われている。
似たパフォーマンスを1950年代パリのメトロで不条理劇作家ウジェーヌ・イヨネスコが行っていたという話が伝わっている。彼は顔見知りでは無いらしい1人の女性と会話を始める。お互いに質問をし、それが2人とも同じ答えなので驚きあう。質問は徐々に個人的な事に及び会話はかなり盛り上がる・・・それを周りの乗客は全部聞いている。最後にイヨネスコと女性が夫婦だって事が判ってクライマックスを迎える。2人とも幸せな様子で抱き合い、一緒に駅を降りる・・・あっけに取られた乗客を後にして。 ニューヨークの「失われたズボン」パフォーマンスの時と同様に、乗客は同じ経験を共有して一体になり、たぶん以前よりずっと幸せな気分でちょっと元気になったはずなんだ、演ずる側は気づかなかったかもしれないけれど。
人間って時として自分が自分の最悪の敵なんだ。僕たちはいつも生きる意味と価値を必死で探している。その問いに本当の答えを見つけることは不可能だって判っていても。僕たちの周りには多すぎる情報と不確実さが溢れていると言うのに、どうしたら確実な答えを見つけられる?答えを探すこと自体が不条理なことなんだ。僕はよく電車に座り、周りの世界を遮断している自分に気づく。僕の望む物、僕の究極のゴールは自分の存在理由と存在する価値を正当化すること。そしてその願望に僕はコントロールされ、不幸せな気分にさせられるんだ。「失われたズボン」のような出来事は僕にその確かな存在感で元気を与え、目の前にある人生の美に気づかせてくれるだろう。
不条理(ばかばかしさ)は世界をもっと包容力に満ちた場所にする助けになるかもしれない。ニューヨークで最後には状況を笑い飛ばしたブルネットの女性は、ほんのちょっと開放された気分を味わったに違いない。彼女は落ち着き、楽しんでいた。ズボンを穿いていない男を受け入れ、それが良いか悪いかの判断を下す必要はもうなかった。男たちは皆を笑わせ、ほんの少しだけど彼らには価値があるって事を彼女は知った。彼女の微笑みはその日、彼女の最も哲学的な意思決定だったんだ。君がとても嬉しいニュースを受け取った時の事を思い出してごらん、君は上機嫌になり嫌な事も気にならなくなって、いつもはむかつく事もそれが見当違いの怒りに思えてこないか?たとえば誰かに恋してる時、見知らぬ人にまで君は優しく出来るだろう。こういう気分の時、天国だの地獄だの神様も必要ないし、何が正しくて何が間違っているかなんて事も曖昧だし、希望さえも必要じゃないんだ。しかしもし君が希望という選択肢を与えられなかったら、その代わりの何か絶対的なものを作り出さざるを得ないだろう。政治家みたいに「いつか良くなる」なんて言わないで欲しい、「人生がちょっと良くなる事をした。これからも続けてもっと同じ事をしていくんだ」って言う方がいい。それが良いのか悪いのかって言う確実な基準は無い、だから誰も非難されないし、誰も聖人じゃない。その代わり僕たちはもっとお互いに寛容であることを求められるだろう。そして人生とは、憎しみとは不条理でばかばかしいものなんだってことに気づく。
このコンセプトは珍しくない。毎日の様に僕たちの周りに存在する。残念なことにほとんどがアートの形で、政治では滅多に見られない。ヴィットリオ・デ・シーカの「ミラノの奇蹟」、フェリーニの「甘い生活」、ウェス・アンダーソンの「ザ・ロイヤル・テネンバウムズ」、ウッデイ・アレンのほとんどの作品、サン=テグジュペリの「星の王子さま」、A.A.ミルンの「くまのプーさん」、そして僕のヒーローであるダリオ・フォーの「アナーキストの事故死」といった作品がそうだ。
17世紀のナポリでは仮面劇の不条理キャラとしてプルチネルラがヒーローになっていた。この役はいつも無言で演じられ、彼自身と観客をネタにして笑いを取っていた。彼は不条理なストーリーで政治を批判し、ローマン・カソリック教会指導者にさえも人間味を与えた。僕たちは今でもプルチネルラを必要としている。こんな不安定な時代だからこそ政治や宗教の先導者たちは2002年のニューヨークのあの美しい瞬間から学ぶべきなんだ。だけど彼らがそうしないのはその「ばかばかしさ」が虐げられた力を是正し、僕たちが皆同じ基本的な苦しみを共有している事を認めることで一体になれる、そのことを伝えようとしない僕たち1人1人の責任かもしれない。この疑問は政府と宗教団体の実態で僕が恐れている事なんだ。
元記事
道化師の帰還
ある1月の午後、ニューヨーク。ダークブラウンの髪の女性が1人地下鉄に座っていた。カーキ色のセーター、1月の寒さから身を守るための黒いロングコート姿の控えめな外見。本を読んでいる彼女は自分が密かにカメラで撮影され、イヨネスコ(フランスの劇作家で、 不条理劇で有名)でさえ自慢に思うに違いない不条理劇の主役になるなんて想像も付かなかったはず。駅で地下鉄が止まると男が1人乗り彼女の前に立った。男は平凡な身なりで、コートを着てバックパックを背負っていた・・・唯一彼に欠けているもの、それはズボンだった。その駅から6駅連続して同じ車両にズボンを穿いていない男が1人ずつ計6人乗り込んできた。車両に乗り込んだ男たちはお互い全く無反応で、その様子に女性は訳が判らず少なからず恐怖を感じていたに違いない。しかし10分後、彼女は彼女の向かいに座っている乗客と目を合わせ、その瞬間初めて彼女の緊張は解け顔に笑みが広がった。同じ境遇の傍観者と状況を共有することで彼女はこのばかげた状況を楽しむ事が出来るようになり、恐怖が消えた瞬間だった。たった1人の孤独な目撃者だった彼女が特異な経験を他の人々とシェアしたこの瞬間、これがこの劇を僕が見た中でも最高のストリート・パフォーマンスの1つにしている。で、僕の頭の中はこんな考えで一杯だ・・・こういったパフォーマンスは実際に世の中を少しはましにすることが出来るのかって。
この動画は2002年のチャーリー・トッドによる作品だ。彼はニューヨークのストリート・パフォーマンス劇グループ「Improv Everywhere」のディレクターで、世界中で100以上のフラッシュ・モブ作戦を実行している。ここ何年かでフラッシュ・モブの文化的知名度は上がった。ニューヨークのデパートの窓際で振り付けされたダンスを意味もなく踊る50人に遭遇したり、何百人もの人々がiPodで同じ音楽を聴きながら駅の真ん中で始めるでたらめなダンスを見る楽しさ・・・誰がそれを否定できるだろう?フラッシュ・モブでは参加した志望者だけでなく、その場に居合わせた観客もパフォーマンスの一部なんだ。フラッシュ・モブは他にすることが無い失業者が引き起こす意味の無い騒動だって否定的な目で見られていたりもするけれど、これは間違った解釈だ。企業が製品を売るためにこのコンセプトを悪用して貶めている事実に関わらず、元々の形は僕たちの生きる「今」に関わる文化的に意義のある活動で、何百年も前から行われている。
似たパフォーマンスを1950年代パリのメトロで不条理劇作家ウジェーヌ・イヨネスコが行っていたという話が伝わっている。彼は顔見知りでは無いらしい1人の女性と会話を始める。お互いに質問をし、それが2人とも同じ答えなので驚きあう。質問は徐々に個人的な事に及び会話はかなり盛り上がる・・・それを周りの乗客は全部聞いている。最後にイヨネスコと女性が夫婦だって事が判ってクライマックスを迎える。2人とも幸せな様子で抱き合い、一緒に駅を降りる・・・あっけに取られた乗客を後にして。 ニューヨークの「失われたズボン」パフォーマンスの時と同様に、乗客は同じ経験を共有して一体になり、たぶん以前よりずっと幸せな気分でちょっと元気になったはずなんだ、演ずる側は気づかなかったかもしれないけれど。
人間って時として自分が自分の最悪の敵なんだ。僕たちはいつも生きる意味と価値を必死で探している。その問いに本当の答えを見つけることは不可能だって判っていても。僕たちの周りには多すぎる情報と不確実さが溢れていると言うのに、どうしたら確実な答えを見つけられる?答えを探すこと自体が不条理なことなんだ。僕はよく電車に座り、周りの世界を遮断している自分に気づく。僕の望む物、僕の究極のゴールは自分の存在理由と存在する価値を正当化すること。そしてその願望に僕はコントロールされ、不幸せな気分にさせられるんだ。「失われたズボン」のような出来事は僕にその確かな存在感で元気を与え、目の前にある人生の美に気づかせてくれるだろう。
不条理(ばかばかしさ)は世界をもっと包容力に満ちた場所にする助けになるかもしれない。ニューヨークで最後には状況を笑い飛ばしたブルネットの女性は、ほんのちょっと開放された気分を味わったに違いない。彼女は落ち着き、楽しんでいた。ズボンを穿いていない男を受け入れ、それが良いか悪いかの判断を下す必要はもうなかった。男たちは皆を笑わせ、ほんの少しだけど彼らには価値があるって事を彼女は知った。彼女の微笑みはその日、彼女の最も哲学的な意思決定だったんだ。君がとても嬉しいニュースを受け取った時の事を思い出してごらん、君は上機嫌になり嫌な事も気にならなくなって、いつもはむかつく事もそれが見当違いの怒りに思えてこないか?たとえば誰かに恋してる時、見知らぬ人にまで君は優しく出来るだろう。こういう気分の時、天国だの地獄だの神様も必要ないし、何が正しくて何が間違っているかなんて事も曖昧だし、希望さえも必要じゃないんだ。しかしもし君が希望という選択肢を与えられなかったら、その代わりの何か絶対的なものを作り出さざるを得ないだろう。政治家みたいに「いつか良くなる」なんて言わないで欲しい、「人生がちょっと良くなる事をした。これからも続けてもっと同じ事をしていくんだ」って言う方がいい。それが良いのか悪いのかって言う確実な基準は無い、だから誰も非難されないし、誰も聖人じゃない。その代わり僕たちはもっとお互いに寛容であることを求められるだろう。そして人生とは、憎しみとは不条理でばかばかしいものなんだってことに気づく。
このコンセプトは珍しくない。毎日の様に僕たちの周りに存在する。残念なことにほとんどがアートの形で、政治では滅多に見られない。ヴィットリオ・デ・シーカの「ミラノの奇蹟」、フェリーニの「甘い生活」、ウェス・アンダーソンの「ザ・ロイヤル・テネンバウムズ」、ウッデイ・アレンのほとんどの作品、サン=テグジュペリの「星の王子さま」、A.A.ミルンの「くまのプーさん」、そして僕のヒーローであるダリオ・フォーの「アナーキストの事故死」といった作品がそうだ。
17世紀のナポリでは仮面劇の不条理キャラとしてプルチネルラがヒーローになっていた。この役はいつも無言で演じられ、彼自身と観客をネタにして笑いを取っていた。彼は不条理なストーリーで政治を批判し、ローマン・カソリック教会指導者にさえも人間味を与えた。僕たちは今でもプルチネルラを必要としている。こんな不安定な時代だからこそ政治や宗教の先導者たちは2002年のニューヨークのあの美しい瞬間から学ぶべきなんだ。だけど彼らがそうしないのはその「ばかばかしさ」が虐げられた力を是正し、僕たちが皆同じ基本的な苦しみを共有している事を認めることで一体になれる、そのことを伝えようとしない僕たち1人1人の責任かもしれない。この疑問は政府と宗教団体の実態で僕が恐れている事なんだ。
元記事










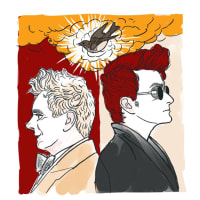

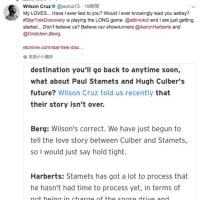


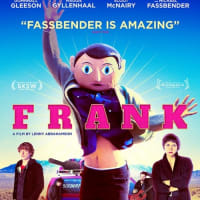




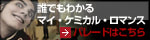









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます