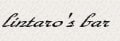吉田拓郎が6月にベストアルバム「Another Side Of Takuro 25」をリリースした。
そもそも拓郎は2022年、76歳で引退したはずである。ライブも卒業。リリースもアルバム「ah-面白かった」を最後とする。メディアもTVは「LOVELOVEあいしてるスペシャル」で終わり。そして年内12月まで続けたラジオのレギュラー番組を、僕はいとおしむように聴いていた。
拓郎の引退をもちろん完全に信用していたわけではない。過去、何度もそれに類したことを言っていたが音楽活動は続けていたし、元来気まぐれな人でもある。しかし70歳代も後半となり、今回の宣言は信憑性があった。
拓郎は、その後特番でラジオに復帰、そして今もぽつぽつとラジオ出演をしている。それでいい。またラジオ内では、ラジオに特化した企画アルバム制作の話をしている。それもいい。マイペースでやってください。元気であればいいのだ。
さて、アルバム「Another Side Of Takuro 25」はどうしようか。
拓郎のベストアルバムというものは、過去に誇張ではなく何十枚もリリースされている。僕は基本的にベストアルバムというのは音源的にダブるので買わないし、そもそもここで書いたように、引越及び老後の準備のために所持する過去音源を、断腸の思いでことごとく処分した。拓郎のアルバムは、もう一枚も手元に残っていない。そして、形ある音源は今後入手しないとかたく誓った。
しかしながら、このアルバムは前作ベストである 「From T」のように avexではなく、何とフォーライフからの発売。拓郎が自ら過去曲を徹底的に聴き直し、25+1(ボーナストラック)曲を選び出した。そのライナーノーツだけは、読みたい。
「Another Side Of Takuro 25」というタイトルは無論ボブディランの「Another Side Of Bob Dylan」のオマージュだろうが、そのアナザーサイドという言葉に意思を感じる
このアルバムには、例えば「人生を語らず」「流星」「結婚しようよ」「旅の宿」「夏休み」「落陽」など、拓郎ベストといえば、の曲はあまり入っていない。ヒット曲、人気のある曲、人口に膾炙したうたを集めようという意識は低いような気がする。
僕は拓郎の中では「大阪行きは何番ホーム」といううたが私的ベストで、20年前このブログを立ち上げたとき最初に採り上げた。このシングルでも何でもないうたが、25曲の中に入っている。嬉しい。他にも「この歌をある人に」等、自分でベストアルバムを組むならこれだな、という曲がいくつも入っている。嬉しい。そしてそれらの曲を拓郎がどう思っているのかは、知りたい。
冒頭の一曲は「どうしてこんなに悲しいんだろう」だった。
エレックレコード時代のアルバム「人間なんて(1971年)」所収。拓郎はかつてラジオで、ゲストの竹内まりやに「ご自分のうたの中で一番好きな曲は何ですか?」と問いかけられた時に「"どうしてこんなに悲しいんだろう"が好きですね」と即答していたのが印象に残る。自分でもかなり思い入れの強いうたであることは確かで、それを一曲目にしているところからも、拓郎の本気度がみえる。僕ももちろん大好きなうたである。
なので、発売後しばらく逡巡していた。
そんな頃、夜に僕の携帯が鳴った。母親からだった。
母親が僕に電話をしてくることは、まずない。認知症が深度を増してからは、必ず僕からかけている。何かあったのか。僕は少し緊張して、通話ボタンを押した。
「もしもし、どないしたん?」
「いや別になんちゅうことはないんやけど、ちょっと声が聞きとうなってなあ」
拍子抜けしたが、特に用事はない様子。少し他愛もない話をして、おやすみと電話を切った。
ここ何年かは、月に一度は実家へ行くようにしている。しかしその月はどうにも立て込んでしまっていくことが出来なかった。ごめんな。しかし電話をしてくるとは、珍しいこともあるもんだ。明日は雨が降るんじゃないかな。でも声は元気だったし、特に心配はいらないかな。
そんなことを妻と話していた。
その3日後、母は死んだ。
夕刻、兄から「お母さんの呼吸が止まったらしい」と電話が入った。僕は何もかもおっぽり出して高速道路に車を乗り入れた。
運転しながら、いろいろ考えていた。
呼吸が止まったとは、婉曲表現だろう。それはつまり、死んだということだ。仮に病院で蘇生したとしても、脳に血がいってないだろう。あくまで無理やりの延命措置、くらいが関の山。
母には、心臓に持病がある。何度カテーテル施術をしたことか。逝くなら心臓だと当然思っていた。後から聞いたことだが、その日母は週2回のデイサービスにあたっていて、朝は普通に送迎車に乗って出かけたという。施設でも元気で過ごしていたが、帰りの車中で動かなくなった。同乗の職員さんがその場の路上でAED処置、さらに救急車が到着して緊急搬送、という流れらしい。
救急病院へ到着すると、父と兄、妹が憔悴しきった顔で待合室に座っていた。どうやら、駄目らしい。天を仰いだ。
母は検査(という名目の検死か)が続けられていたのだが、僕の到着後、医者からの説明があり、死亡が確認された。
そうか。おかん。死んじゃったか。
不思議なことだが、あの電話は、何か予感めいたことがあったのか。
経験のある方なら共感していただけるかもしれないが、まだ実感が伴っていないからだろうか、急に悲しみは襲ってこない。それよりも、忙しい。
既に夜も深い時間になっているのだが、やらねばならないことが積載している。
母の遺体には兄が付く。様々な手続きや葬儀の手配等がある。老いた父は家に戻らせ、妹が付き添う。僕はと言えば、まず警察の相手をしなくてはいけなかった。
母は、道端で死んだということ。なので警察が動き出す。深夜にご苦労様なことだが、調書を作成せねばならないらしい。僕の姓名年齢現住所職業から始まり、こまごまとした質問が続く。保険金の有無を聞かれたときには流石に頭にきたが、しょうがないので淡々と答える。どんな薬を服用していたかなんて、全部掌握してないよ。
さらに現場検証に行くという。形式主義が本当に嫌だ。だいたい死亡現場なんて僕はちらりと聞いただけだし、立ちあってもいない。しかし連れていかれる。向うも書類を作らないと帰れないのだ。
解放された頃には、日付がかわっていた。
そのまま、葬儀場へと向かう。母は霊安室に既に運び込まれていて、横たわっている。その隣で、兄が山ほどの書類と対峙している。
葬儀場の担当の方と打合わせ。こんなド深夜にご苦労様なことである。
両親は既に、葬儀社と契約している。「死んでから子供に迷惑かけたくない」が母の口癖で、もう葬儀代は払い込んであるという。「これで、あんたらには一銭もかからんようになっとるからな。心配せんでええで(笑)」と常々言っていた。
しかし、だ。両親がそのように葬儀社と契約をしたのは、20数年前だ。両親は長命した。その間に時代も社会情勢も変わっている。
「積み立て頂いている金額では、祭壇を作るのにも足りません」
葬儀社が示すパック料金のような見積書には、その金額+100万円くらいで提示されていた。
「祭壇は要りません」と僕は言った。兄は驚いたような顔で僕を見る。
しかし、母は昔から言っていた。葬式なんか形式ばっかりでみんなで話す時間もあらへん。あんなんいややわほんまに。もっとなんかわいわいやって送り出してくれんのがええわ。
坊さんもなしでええんやないの、と僕は提案した。一応家に宗派はあるが、どこかの檀家というわけでもない。いや正確にはかつてはそれに該当する寺はあったが、引っ越しして寺との付き合いも絶えて久しい。読経って今の時代必要か? 無宗教で良いのではないか。
香典も受け付けないことにしよう。さすれば香典返しもしなくていい。どうせ参列者はごくわずか。母の兄弟含め親戚くらいだ。母の個人的知り合い関係はほぼ居ない。長命すれば自然とそうなる。みんな物故者か、動けない人ばかりだ。さらに、僕も含め子供の関係者には「密葬」であると伝え、もう呼ばないようにしよう。不義理にはなるが、母を知らない人に来てもらってもしょうがない。
そうやってリストラしていったら、徐々に母が積み立てた金額に近づいていった。これでいいんじゃないか。母も賛同しているように思った。
「供花だけは必要です。故人は花が好きだったので飾ってあげたい」
そうして夜中の3時頃に葬儀社との打ち合わせが終わった。日付がかわって今日が仮通夜。明日が本通夜で、葬儀は明後日になる。そこで僕は一度家に帰ることにした。
家に帰ったころには、空が徐々に白々としてきていた。妻が突っ伏して寝ている。すまんな。ちゃんと寝てくれと言ったのに。
僕も寝なくては持たないのだが、脳が興奮している。そういえば昨日は晩御飯も食べていない。しかし全く食欲はなく、身体に悪いがウイスキーを流し込み布団に入った。
昼頃に再び葬儀場に向かう。兄と交代し引き続き様々なこと。人が一人死ぬだけで実に忙しい。
「その忙しさから人はいっとき悲しさを忘れるのだ」たいていの人はそういう。だが、僕はこの時、なんだか腹立ちさえおぼえていた。最も忙しい原因であるはずの葬儀というイベントを最大限簡略化してこれなのだ。現場検証に始まり、行政その他はどうしてこんなに書類を欲しがるのか。
湯灌の時間が来た。
湯灌に立ちあうつもりはなかった。死後硬直している遺体を動かすと強引に骨を軋ませる音も聞こえるというし、母も老いた裸体を見せたくないだろう。
しかし「立ち会って下さい」と言われた。そういう湯灌は昔の話だという。
納棺師が来られた。昔は別室の湯舟に入れてほぐすと聞いていたが、今は霊安室に簡易プールのようなものが持ち込まれ、そこで体を洗う。基本的には死衣装のまま湯に入れられ、まるで寝たきり病人が行水をするかのようだ。前をはだける時はタオルで目隠しをし、髪を洗い着替えて死化粧が施される。おくりびとのプロの仕事をまざまざと見た。すごいな。ありがとうございます。
お棺に入った母は、まるで生けるが如く血色がいい。本当に寝ているだけに見える。遺体を見る機会などそうそうは無いが、かつて祖父母の葬儀の際、遺体は一日経つと既に「死骸」だった。見るから冷たく固まって鋭角的ですらあった。母は、やわらかい顔で揺すれば起きそうだ。エンバーミング技術の進歩なのか。なので、ここに至っても実感がわかなぃ。
通夜は最も小さな部屋にした。それでも、祭壇もないためガランとしている。祭壇の場所には遺影と花だけ。お棺は部屋の真ん中に置き、蓋は閉めないことにした。今も生きていた時と変わらない姿であり、これで閉めたら母も寂しかろう。
通夜は、全くのプライベートにした。父と子供とその配偶者、孫だけ。従って平服である。寿司桶をいくつか出前してもらい、母を囲んで座り、意識的に母の思い出話、笑い話をして周りで飲み食いをした。
葬式当日。親戚も来るため、喪服に着替えて様々な手配をする。
この日は、強い雨が降った。
晴れ女だった母。何故か大切な日には必ず晴れた。やはり晴れ女などというのは非科学的な迷信でしかない。自らの葬式はえらい雨じゃないか。だがその雨が「そうか、晴れ女のおかんはもういないのか」ということをまた想起させる。気持ちが揺れる。
葬儀と言っても、坊さんを呼ばなかったため儀式めいたことは何もない。母の周りに椅子を並べ、茶話会とした。父に一応挨拶をせよと言うと、母との馴れ初めの話から始めた。初めて聞く話も多い。また様々な思い出話。笑い声も出た。誰も泣く人などいない。
これでよかったのだな。
後から聞くと、いい葬式だったと皆口々に言ってくれた。僕も、明るく笑い上戸だった母に相応しい時間だったと思った。
出棺。火葬場へと向かう。
雨に煙る街。霊柩車を追走する。ワイパーは最大回転だ。そして、こんな町中にあるのか、と驚くような場所に斎場が存在していた。
斎場で、雰囲気が一転してしまう。重々しくない葬儀のあとだけに、静謐な空気が漂う。電話で伝えてはあったが、現地の職員さんも、坊さんもいない一行に戸惑っている様子がうかがえる。
「最期のお別れの時間でございます」
こういうの、正直キツいな。死という現実から逃げていたつもりはないけれども、荼毘に付す、つまり母の寝ている棺桶が炉に吸い込まれていく瞬間というのは、去来するものが多すぎる。とうとういっちゃうのか。
息を引き取る瞬間に立ち会っていれば、今更こんな気持ちにはならなかったのかもしれない。ただ死んだ後も生けるが如き母とずっと対面しつづけたことで、気持ちの整理をする時間が確保できないままになっていたのか。
当然ながら、骨あげまでしばらく時間がある。待合のソファーで親戚の雑談に入っていたのだが、なんだか居心地が悪くなって、電話をするフリをして外に出た。
ぼんやりと歩いて斎場の裏手に出た。外は小雨になっている。墓地がある。その石塔の林立する中に、ひとり佇んだ。
ここまで、漠然とした寂寥感は確かにあったが、強い悲しみというものは自らに襲い掛かってはこなかった。それは、なかなか実感というものがわかない人間の生理や、忙しさに紛れたこと、死に立ちあわずちゃんとした別れをせずに至ってしまったことなど様々な要因はあるにせよ、基本的には感受性の摩耗だと自己分析していた。
学生の頃、突然母親が死んだ友人の、その死を知らせる瞬間に同席していたことがある。その時友人は即座に号泣した。普段冷静な男だった彼の慟哭を呆然として見ていた。僕も若ければそうだったかもしれない。だが今の僕は人生経験も積み、母も90歳を超えてやはり覚悟もあった。脳内シミュレーションが完了していたとも思える。さらに、若い頃と比べ感情の振れ幅というものは明らかに減少している自覚はあった。
のど赤き玄鳥ふたつ屋梁にゐて足乳根の母は死にたまふなり
斎藤茂吉が「遠田のかはづ天に聞ゆる」をはじめとする連作「死にたまふ母」を詠んだのは30歳そこそこのとき。「我が寂しさは極まれにけり」と叫ぶ心情にはなかなかなれないと思っていた。
茂吉の息子である北杜夫は、その茂吉の死に直面した時にやはり慟哭している。
兄である斎藤茂太から電話で「ゲシュトルベン(死亡)」と聞いたとき、
突如として涙がこみあげ、声がどうしようもなく震えるのを私は抑えることができなかった。それは唐突な、自分でも思いがけない感情の激動だった。
と、短編「死」で描写している。「ひっきりなしに涙がこみあげてきた」と。北杜夫はそのときまだ20歳代だった。
北杜夫はまた、母である斎藤輝子さんの死についても短編「ついの宿り」で描写しているが、そのときは死に直面した時も、葬式の時も「一滴の涙もこぼさなかった」と書いている。その時輝子女史は89歳。北さんも今の僕の歳に近い。北杜夫が突如とした悲しみに襲われるのは、葬式より幾日か後に、輝子さんのスーツケースを見た時だった。やはり、時間差がある。
北杜夫に感受性の摩耗があったとはさすがに思えないが、そういうものなのだろうと思っていた。
いわゆる「昭和ヒトケタ」と呼ばれる世代なのだが、僕の観察範囲だけだと結構長命している。妻の両親である義父母も健在。兄の義父は不慮のことで亡くなったが義母は元気にしている。妹の義父母も。
かつて「昭和一桁短命説」というものがあった。焼け跡派は育ち盛りが食糧難であり、発育に十分な栄養がとれず成長したため長寿は難しかろうと言われた説である。空論であったことが証明されてしまったようだ。むしろ飽食の時代に生まれた世代の方が身体に負担がかかっているのではないか。
もちろん、長命してくれるのは有難い。
ただ親のここまでの長寿を想定していなかったことも、これまた事実ではある。
こう書くのは複雑な心境なのだ。まるで早く死ねと言わんばかりに聞こえる。そんなことは無論考えていない。ただ覚悟が必要にはなってくる。
近年は兄弟で話し合うことが増えた。かつては疎遠だったとまでは言わないが、こんなに密に兄弟間で連絡をとることなど思いもよらなかった。昔と違い、今はLINEグループなんていうものもある。あれはどうしよう、これはどうしようといつも鳩首密議している。内容はもちろん親の認知症と介護のことである。
詳細を書くとキリがないのだが、身体能力は当然加齢で下がり、動けなくなってくる。脳機能も衰える。しかし臓器には問題がない。この先にある道は、惚けて寝たきりで長生きする、という事実である。だから覚悟が必要になる、ということ。
僕は言った。「これは100歳を想定せんとあかんぞ」
我々はその頃、70歳前後だ。老々介護ってこういうことか。悩みは尽きない。
従兄弟から連絡があった。「〇〇子さんについて弁護士から照会があったんやがそっちにも来とる?」
叔母のことである。父は六人兄弟の長男だが、弟4人は全て亡くなり、存命は妹がひとり。その叔母は子供がなく独居生活が続いていて、正直疎遠になっていた。内容は、どうも認知症になり身体も弱っていて施設に入れたいのだが、身内の手続き及び様々な手伝いがいるという。
「いやワシのとこには来てへんで。なんでやろ」
そうか。うちには父がまだいるからおそらく連絡は父にきているのだ。なのでこちらにまで下りてこない。従兄弟のお父さん(叔父)は先年亡くなっている。
父はそんな連絡を見てないだろう。かと言って連絡相談するとそんなん聞いてないぞ見てないぞお前ら頭越しに勝手にやりやがって子供のくせに俺が指示する俺の指示通りにみな動けと沸点が上がりキレ散らかして挙句何も進まなくなるだろう。認知症というものは恐ろしい。
叔母さんの諸般のことは手分けして行ったが、家をひとつ仕舞うというのは存外大変なことである。それでも叔母さんは独居となった段階で家財道具など所有物を明らかに減らしていた。これは、助かった。
「断捨離」という言葉は、嫌いだ。正確には、徐々に嫌いになっていった。
その言葉が持つ思想的背景は措いて、遣われ方に何だか引っ掛かる。一年使ってないものはもういらないよ。シンプルライフ。ミニマリストは素晴らしい。こんまり的世界観。上っ面だけを心棒する人々が追憶否定にかかる様子に辟易していた。うるせー何でも捨てろと言うな。
しかしながら、この長寿時代。身辺整理はやはり必要なのではないか。自分で処理処分できなくなってしまう前に。人に迷惑をかけないためにも。
実家は、モノだらけである。常軌を逸するほどモノがある。どうするこれ。親父が死んでからやればいい、とぼんやりと思っていたが、僕らが70歳を過ぎてからそれが出来るのか。今直ぐにでもやりたいのだが、判断能力の鈍っている親との戦いは心身を耗弱させる。
本当に頭が痛い。
しかし僕も実家ほどではないが、かなりの物持ちではある。蒐集癖はある。さらにはモノを捨てられない。こういうのは経済状況とも関わりがあるのだろう。資産家は、捨てても必要になればまた買えばよい、と思って整理できるが、僕らのような庶民は「いつかまたこれも必要になるかもしれない」とどうしても考えてしまう。結果、紙袋や戴きもののタオルやホテルの歯ブラシやモロゾフのプリン容器等が無限に増えていく。
数年前の話だが、一度「断捨離」の機会があった。市域のゴミ袋が有料になるという。可燃物とプラスチックごみの袋。
少額とはいえ、捨てるものに金がかかるというのは業腹な話である。これを機会に整理しようじゃないか。
決定から半年ほどの猶予期間があった。その間に、不要物と考えられるものを絞り出して、景品や新聞業者さんが持ってきたゴミ袋(これも相当に溜まっていた)やレジ袋(スーパーの袋有料化により過去のものを捨てなくなっていた)を総動員し、断腸の思いを繰り返しながらかなりのものを処分した。おそらく、40ℓくらいのゴミ袋で5~60袋くらいは出したのではないか。
「だいぶスッキリしたんやないか?」
「そうねえ…?」
あれだけ捨てたのに全然変わってないように見える。どうしてなんだろうか。
今年の夏の話。
マンションの大家さんから会いたいと言われた。
「申し訳ありませんがマンション老朽化により取り壊しを決断せざるを得ませんでした。ご退去頂きたい」
「えっ?!」
えらいことになった。青天の霹靂である。
このマンションにはもう25年も住んでいる。最初は社宅借り上げという形で住み、その後期限が切れたが気に入っていたので再契約して住み続けた。僕は生まれた家を22歳のときに出たので、生涯で最も長く住んだ家になっている。
このマンションは、僕より年上である。その間に阪神大震災に遭い、相当な補修をしている。しかしもう限界が来たのだという。大家さんも老朽化(失礼)し、後継者もなく売ることも出来ず、仕舞いたい、と。
ここには、65歳までは住もうと思っていた。そのあとのことを考えていたわけではないが、とりあえずその頃には第二の人生を迎えているだろう。それまでは。だがそれは叶わなくなった。
色々なことは省くが、致し方なく引っ越しをしなくてはいけない。面倒なことになった。
その慌てていた時期が、先程の叔母の話の頃やなんやと重なっている。
僕らには、子供がいない。親父のように「あとは任せた」と言って死ねない。僕がまだ若いうちにポックリいけば、妻は大変に苦労してしまう。若いうちならおそらく兄や妹も手伝ってくれるとは思うが、それでも…。さらに、親のように長命した場合はどうなるか。
叔母のように、甥や姪に迷惑をかけることになる。叔母の場合、僕ら第二世代はまだたくさんいたのでみんなで頑張れたが、僕の甥姪は3人。彼らがその頃どこに住んでいるかもわからないし、当然あてには出来ない。とにかく、自分たちで道筋を作っておかなければ。
そんな折の引っ越し通告である。
以前多少のものは処分した、と言っても、可燃ゴミが大半である。紙のものや不燃物は全くの手つかず。あの時は「引っ越しするつもりで捨てよう」と言っていたのだが、本当に引っ越しするわけではないからやはり甘さがあった。今度は背水の陣になる。本気で思い切らないと。
例えばうちには冷蔵庫が二つある。一つは僕が独身時代に使っていた小さなもので、今は電源も入れずに収蔵庫と化している。ただまだ動く。主要冷蔵庫が突然壊れたときに試しに電源を入れてみたら冷えて助かった。使えるものを捨てるのには抵抗がある。リサイクル料金もかかる。しかし、もう処分しよう。このサイドボードも捨てよう。このホットプレートも処分しよう。この釜めし容器も捨てよう。
しかし、そんなの微々たるものなのである。
だいたい、生活に関わるもの以外でうちにある荷物の大半は、書籍なのだ。
昔(もう18年前か)、book batonという企画をやって、その時にうちに何冊本があるか、と数えたことがある。約3000冊が答え。それから約20年で、全然減っていない。しばしば処分はしているのだが。本を整理するという記事を書いたこともあるが、こういうのは減っただけ増えるものなのである。だいたい、これらの記事を書いたときから書棚がひとつ増えている。全部で10棚。
減らそう。無くしてしまうことは出来ないが、減らそう。
本というものは、縛ってゴミにするのは簡単であるが、他人がやるならともかく、所有者がそれをやるのは結構なストレスである。本好きでなくとも分かってもらえるのではないか。しかししょうがない。雑誌のバックナンバーはそうやって心を痛めつつ大半を処分した。
書籍や漫画本は、ブックオフである。週末になれば、リンゴ箱に詰めた本を何箱も持ち込んだ。こういうものは、金にはならない。ほとんど値はつかないが、どこかで誰かが手に取るかもしれない、という一縷の望みを励みに勤しんだ。だがこの電子書籍の時代に、そんなの妄想であることはわかっている。しんどい。辛い。鬱になりそうだ。しかし、もっと高齢になればこんなことも出来なくなる。
しかしながら結局、1/3くらいしか処分できなかった。まだまだ自分に甘い。
持っているのは書籍だけではない。もうひとつ山がある。それは「音源」。
あるのは、レコード、CD、カセットテープ。そしてビデオテープ。DVDなどもあるが、自分にとって歴史が浅いためすぐに処分出来た。だが、思い入れのあるものはなかなか決断が出来ない。ほとんどが、青春期から20歳代に入手したもの。
ブログを書きだしたのは約20年前だが、書いていることの多くはこれら書籍と音源に寄っている。その間、思い出を反芻する作業を続けたせいか、愛着がさらにわいてしまっている。駄目だ駄目だ。
ただ、今は配信も、サブスクもYoutubeもある。ああいうものは所有しているわけではなくいつ消えるかわからないうたかたのものだが、それでもアクセス出来る可能性が高いものであればまだ良い。僕は「処分したらもう二度と聴けない視られない」ものをまず残す基準にした。次に、そのもの自体に思い入れが深いもの。入手経路や聴いていた時の風景も全て思い出せるものは、人生の一部だ。そんな甘いことを言っていては駄目なのだが、あまりやりすぎても鬱になってしまう。
レコードは、1/10まで減らした。LPは20枚、シングルは10枚だけ残した。あとは捨てるのではなく(前述したように書籍と違って可燃ごみなので業腹なことに金がかかるので)、全て売った。
書籍とは異なって、レコードにはだいたい値が付いた。レコード復権の時代がきていることは知っていたが、これは意外だった。中古レコード市場というものが復活していたのだ。
中島みゆきの「グッバイガール」などは、買った時の倍の値が付いた。そうかこのLPって、みゆきさん最後のLPなのだな。以後はCDリリースだけになっていく。そんなこともあるのかもしれない。これなら、必ず誰かが手に取ってくれるだろう。世の中のどこかに残る、という思いだけで、なんとなくストレスが減っていく気がする。
ビデオテープは、8本を残して全て処分した。全てプロレスのテレビ録画である。だいたいもうビデオデッキを持っていない。どうするんだと言われそうだが、許してほしい。
カセットテープが一番苦しんだかもしれない。300本くらいあっただろうか。
買ったものは数本を残して処分した。前述したようにアクセス可能だからである。例えば松山隆宏さんの「時代を渡る風」なんてのはもう入手不可でありさすがに手放せないが、そんなの以外は目を瞑って。またレンタル店を利用したアルバムのコピーやダビングものは、えいやっと捨てた。ただエアチェックは、本当に思い入れがあり選別できない。大げさに言えば人格形成に寄与したものとも言える…やっぱり大げさだな。処分処分。
だが、カセットが一番残してしまっただろう。半分以下にはなったが。
それらに比べれば、CDはそうでもない。DVDと同じく、自分にとって歴史が浅いからだろう。追憶ともあまりリンクしていない。なのでみんな処分してしまおう。
…と思ったのだが、なかなかそうはいかない。
引越に関わる作業中は、CDを主として流していた。レコードやカセットをかけようとすると少し手間である。CDはお手軽なので、処分前に供養のつもりで次々とかけた。
こういうのは、失策である。惜しくなるから。
沖縄で買い集めた民謡集は、もう一年だけ待つか。次の夏が来るまでは。喜納昌吉「BLOOD LINE」ももう少し置いておくか。りんけんバンドは…ダメだこりゃ。拓郎も陽水もかぐや姫も正やんもふきのとうもNSPもみんな手放したのに。洋楽はほぼ手放したのに。聴いちゃダメなんだ。
こういうことをやっていると進まなくなる。
小谷美紗子の「PROFILE」はもうちょっとだけ置いておこうか。名盤だしなあ…。あれ、小谷美紗子ってサブスク解禁したんじゃなかったっけ?
全くのところ、なっていない。葛藤の中、10数枚の盤を残した。
その中に、早川義夫の「この世で一番キレイなもの」もある。
早川義夫さんのこのCDは、僕が最も新しく購入したCDのような気がする。六文銭の「はじまりはじまる」とどっちが後に購入したかははっきりと覚えていないが、もしかしたら「僕が最後に買ったCD」だったかもしれない。
本当に最近は…10年以上も盤を買っていない。感受性の摩耗と面倒くささと…様々な要因があるが、音楽はネットで済ませている。そういう人は多いと思う。盤を買わないことが業界の衰退につながるのは重々承知している。ごめんなさい。
「この世で一番キレイなもの」は、しかも新譜で入手していない。中古で見つけて買った。
以前、早川さんが作った「サルビアの花」をお題にして記事を書いたことがある。2007年のこと。→もとまろ「サルビアの花」
このうたは非常に著名で、僕より上のフォーク好きならだいたい知っている。僕も好きな歌なのでブログに書いてみたいと思ったのだが、その記事の中でも、ジャックス乃至は早川義夫さんのことを「知るところが全然ない」「僕はジャックスについては全然知らなくて」と繰り返し書いている。知らなくても記事は書けるのだが、中身はジャックスに在籍していた木田高介さんのことと、うたをこねくり回した解釈みたいなものに個人的な追想を付けてひとつの記事にしている。なので、薄っぺらい。
その後に、僕は早川義夫というミュージシャンに改めて興味を持ち、著作「ラブ・ゼネレーション」「ぼくは本屋のおやじさん」を古本屋で見つけ、さらにアルバム「この世で一番キレイなもの」を中古店で掘り出した。
早川さんがジャックス解散後、ソロアルバム「かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう」を1969年にリリース(「サルビアの花」所収)し、その後音楽から距離をおき書店主となった。以後20数年。1994年にアルバム「この世で一番キレイなもの」で復活を遂げた。
僕はその復帰した頃のことも、当時あまり詳しくは知らない。ただ「サルビアの花」が好きで2007年にブログ記事を書いただけ。それがきっかけで、時を措かずして本とCDを買った。
そのことは別に記事にもしてない。このブログは基本的には思い出ブログで、聴いたばかりのうたはあまり採り上げてはいない。自分の中で熟成していないし、付随する追憶もない(当然だ)ので、あまり書くことがないからだ。ただ当時は、このアルバムに非常に感銘を受けたことは記しておきたい。有体に言えば、感動的だった。中でも同名の表題曲は、繰り返し聴いた。CDはレコードやカセットと異なり、早戻し(巻き戻しとはいわない)が容易だ。なのでついもう一度と一曲戻しを繰り返したような覚えがある。
弱い心が指先に伝わって 痛々しいほどふるえている
以来、しばらくぶりに聴いた。
あれから16年くらい経った。十分に熟成期間を置いたが、特に追憶が付随したわけでもない。ただ、聴いていて涙が滲んだ。それだけ。
もう、この歳になると涙腺が弱くなっていて、まあ生理現象みたいなものだろうと思う。
もっと強く生まれたかった 仕方がないね これが僕だもの
思い出を否応なしに断ち切るような作業をずっと続けていると、心が弱る。
この世で一番キレイなものは あなたにとって必要なもの
ずいぶん昔に、僕は「結局人生とは追憶なのだ」という結論に達している。その考えは今も変わらない。人生が終わるときに一番大切なもの、それは思い出である。極論すれば、死ぬときに莞爾として人生を終われるかどうかは、自分の中にめぐる美しい記憶があるかないかだ。地位も名誉も関係ない。財産も持って死ねない。歴史に名を残そうと頑張っても、結局その歴史に残った自分を見ることは叶わない。
自分に残るのは、追憶だけなのだ。
だから、持って死ねない書籍や音源は必要ない、とも言える。
しかし、「いやいやそうではない」という思いもある。
莞爾として死んでゆくためには、キレイな思い出だけあればいい。それさえあればいい。それは分かっている。だが、その思い出を失ってゆく老人たちを、僕はここしばらく見続けてきているではないか。
一番キレイなものを失ってしまう恐怖にお前は耐えられるか。だから追憶は常に反芻し、上書きし更新して失わない努力をせねばならない現実があるのだ。その補助材として、記念品や写真や書籍や音源があるのではないか。
そんな葛藤も、心が弱っているせいだろう。とりあえず今はそういう屁理屈はどっかにおっぽり投げて、ダンボールに詰める作業を続けないと、終わらないよ。後ろでカミさんの「何ボーっとしてんの」という声が聞こえる。ごめんごめん。
引越は11月半ばに決行。
別に遠くに居を移すわけではなく、市内の近隣地域に越しただけであり、断捨離が成功したとは言い難いけれども多少荷物も減ったので、傍目には楽な引越に見えたはずである。もちろん当人にとっては楽とは言い難い引越だったが、何とか無事に終了した。
新居はダンボール箱の山が連なり居場所がない。その積み重なった荷物を解くのに、ずいぶん時間がかかってしまった。ひと月以上経って、ようやく全てのものが収まった感じ。
「この世で一番キレイなもの」も、持ってきてしまった。ダンボール山脈の中から比較的早期に発掘し、そしてまた聴いている。なんだかこの怒涛の引っ越し期間のテーマ曲のように思えている。
キレイなものはどこかにあるのではなくて あなたの中に眠っているものなんだ
次の年はどうなるかな。まだまだ問題が積載してるけど、とりあえずひと段落とさせてくれ。
心の焦点があわない日々が続く。
今年は秋から冬にかけて、葬式によく出た。
冠婚葬祭の中でも葬式は前触れなく行われるもので、なんともいたしかたないのだが、3ヶ月で4回は多くないかい? どうしてみんなそう足早に逝ってしまうのか。
なんだかどうも葬儀会場にばかり足を運んでいたような気がする。葬式は今、都市部ではほとんどが専門の葬儀会場で執り行われるので、お宅へ伺ったりすることは、ほぼない。無味乾燥であるような気もするが、時代だろうか。
どこも同じようなつくりであるため、ふと錯覚を起こし「先週も来たな」とか思ってしまう。
話が変わるが、こういう葬儀会場が増えてきたのはいったいいつごろからなんだろう。
高度成長期だろうか。家の主流がマンションなどの集合住宅となれば、そこで葬式をするわけにもゆくまい。寺院で執り行うこともあっただろうが、非檀家の核家族の割合が高くなればお寺さんでの葬式も難しくなっていく。
僕の祖父母の時代は、まだ自宅葬だった。家に祭壇が作られ、そこから出棺した。まだまだ昭和の時代のこと。ただ母方の祖母は長命し、亡くなったのは平成になってからで、葬儀は斎場で行われた。時代が変わったのだ。
今は老人人口が多くなり、葬儀会場がどんどん新設されているように思える。介護施設と並んで盛況なビジネスとなっているのではないだろうか。もしかしたら過当競争になっているかもしれない。新聞にも毎日のように斎場のチラシが入っている。
電話による勧誘も多い。とある日に僕が電話に出れば「セレモニーホール○○ですが」と。あちらも仕事でやっていることで大変だろうとは思うが、葬儀の予定などを訊ねられるのは気分の良いものではない。妻に尋ねると、平日もあちこちからかなり掛かってきているようで、電話に出るのが嫌になったと言う。
11月には叔父が死んだ。急死だった。
父の弟だが、これで6人兄弟の長兄である父も、三人の弟を失ったことになる。
さすがに父の落ち込みは見ていて辛くなるほどで、最も年長である自分が何故生きているのか、などという。もう一人の弟も、今は車椅子でしか動けない。僕からすれば、他の叔父たちと違い酒も煙草もやらずストイックに過ごしてきた父は長生きしてもらわねば困るのだが、本人としてはいたたまれないのだろう。
叔父の葬儀も、やはり会場で行われた。
慟哭を聞くのは、辛いものだ。
葬儀が始まると、音楽が流れた。どこかで聴いたことがあるのだが、すぐには思い出せない。「これ、何の曲やったかな?」と僕が独り言のように言うと、隣にいた叔母(父の妹)が「ロッホ・ローモンドや」とすぐに言ってくれた。あっそうか。
スコットランド民謡の名曲だが、こういう澄んだ美しいメロディは、もしかしたら葬儀に合うのかもしれないと思って聴いていた。聴くうちに、涙が出た。
ただ、叔父が指定したわけではあるまい。葬儀場が用意していたものだろう。血管が破れ救急車の車中ではもう既に意識が無かった叔父が、そんなことまで遺言をしたはずがない。
葬式に音楽を流す、というのは、おそらく葬儀場が始めたことではないか。自宅葬の頃は、そんな習慣は無かったのではないかと思う。つたない経験からの話で、実際はそうではないかもしれないが。あれ、キリスト教の葬儀では讃美歌が流れるのだったっけ。「主よ御許に近づかん」というのは、フランダースの犬の最終話を観て泣いた世代の僕としては、馴染みなのだけれど。しかし仏式だと、読経だよなあ。
最近は自宅葬においても音楽は流れるようで、以前とある田舎で葬儀に参列したとき、出棺の際になんとも言えない悲しい曲が流れた。曲名はわからない。インストだがどちらかといえば演歌調の曲で、ただ悲しみを助長させるだけに思えた。ああいうマイナー調の曲はどうなのかと思う。おそらく互助会が用意したのだろうと思うが、例えば結婚式の花束贈呈で「かあさんのうた」が流れるようなものだ。
ただ、葬儀に音楽が定着していることはわかった。
別の機会。「自分の葬式にどういう音楽を流したいか」という話題が妙に盛り上がった。主体は若い人で、葬儀に音楽は当たり前の世代らしい。
驚くことにその場にいただいたいの人はもう決めているようで、尾崎豊がいいだの「私は絶対にハナミズキ」だのと言っている。そうか。
僕は、そんなこと考えたこともなかった。叔父の葬儀の前で、ロッホローモンドなどもまだ聴いてない。尋ねられたのだが気の利いた答えも言えず窮して「どうせ自分は死んどるんやしそれを聴くこともできんやないか」などと冷や水を浴びせるようなことを言ってしまった。場の空気もみず誠に申し訳ない。
僕は、葬式自体が必要ないと思っている。
昨年、別ブログで村落墓地の連載をしたため、民俗学的に葬儀というものの歴史と実態についてかなり様々な書籍を読んだ。考えるに、現在の葬儀というものは江戸時代の檀家制度、寺請制度の名残で、そんなものは僕個人には関係ない。信仰心もなく、死んで浄土に行くとも地獄に落ちるとも思えないので、戒名とかはどうでもいい。
夏に、内臓にヘンなものが見つかって入院した。僕も死を考え、妻に「葬式はせんでええぞ。金がかかりすぎる。どうしてもと周りがやかましく言うなら、とにかく最低ランクでやって。金は残せ」と言ったら、妻が「縁起でもないことを」と怒った。
そのときも、さすがに音楽までは考えなかった。
葬式にふさわしい音楽とは、なんだろうか。
おそらくは、インストがいいのだろうと思う。そしてきれいな曲で、マイナー調でないほうがいい。葬式と言ってすぐに思いつくのはショパンの葬送行進曲だが、これが掛かっていたのを聴いたことがない。おそらく、生々しすぎるのだろう。
まあクラシックか。「G線上のアリア」とか「亡き王女のためのパヴァーヌ」とか。ラヴェルは実際に聴いたことがある。
歌詞があるものは、相応ではないような気がする。まあ洋楽であればいいか。言葉の意味がわからないほうがいい。ロッホローモンドは、そういう意味でもふさわしい気がしてきた。もっとも、僕が実際に聴いたのはインストだったけれど。
もっと明るくゆくなら、カントリーの名曲「Will The Circle Be Unbroken」がある。加川良さんのカバー(その朝)や、なぎらさんのカバー(永遠の絆)が有名だが、やはりここは原曲か。
will the circle be unbroken
by and by load by and by
there's a better home a-waiting
in the sky, lord, in the sky
やっぱりダメだな。なんか泣きそうになる。
ハンバートハンバートの「大宴会」なんかもいいとは思うんだけれど、こういうのはBGMになりにくいからやっぱりふさわしくないかな。
今は、自分が死ぬときに、どんな音楽が流れていたらいいか、を茫洋とした心のままに考えている。
葬儀は必要ないし、もしも自分の葬儀がなされたとしても、僕はそれに出席していないのだから、どうでもいいと言える。
いちばん好きな歌を聴きながら逝くかな。そうなると「他愛もない僕の唄だけど」とかになるけど、なんか違うな。
終焉を迎えるときに去来するものとは何だろうか。
それは、自分自身にとっては、追憶しかないと思っている。
おそらく「思い出」だけが、最後に残るものだ。あの世が信じられない以上、歩んできた足跡だけが僕には残される。そのめぐる追憶というものが幸せなものであったならば、莞爾として人生を終えることが出来る。
そのとき、僕が独りであれば、もう何も思い残すことはない。
僕には子供がいないため、心配なのは妻だけだ。彼女を残してゆくのは忍びない。つまり妻より一日でも長生きすればいい。だから、老いるまで何としても生き延びなければならない。
そしてこの世を去ったあとは、いったい何が残るだろうか。
墓標などいらない。骨なんかは産業廃棄物でいいと思っている。そもそも、子孫がいない僕の墓など一瞬で無縁となる。だいたい墓を建ててくれる人などいるのだろうか。甥や姪に金を置いて死ねば建ててはくれるだろうが、無駄なことだ。
近親者や友人が、まだそのときにいるとすれば、彼らに多くは望まない。すぐに忘れ去られるのも寂しいから、なんとなしにあんな男がいたと記憶の片隅に置いておいてくれればいい。
功成り名を遂げた一部の人とは違い、僕も含めた市井の人間は、居なくなれば語り継がれることなどない。だから、僕が居なくなって、さらに僕のことを直接知っている人も居なくなれば、僕という概念上の人間もまたこの世から消える。
そこまで思いめぐらして、べーやんの「忘れな詩」が浮かんできた。
もしも私がうたい終わってギターをおいてこの場所を遠く去る時に
誰一人うしろ姿にふり向く人はいないとしても それでいい 想い出一つ残せれば
この詩を書いた中村行延さんは、今どうしてらっしゃるのかなあ。公式サイトも消えている。行延さんが出なくなってから「きらきらアフロ」も見なくなった。喫茶店を閉店したあと、就職されたというような話はおっしゃられていたが…おそらくはどこかで歌っておられるとは思うのだけれど。
けれどあなたの青春のどこかの季節に まぎれもなく私がそこにいたことを
いつまでも いつまでも 忘れないでいてほしい
あなたにだけは この詩 忘れないでいてほしい
忘れないで欲しい、というのは、本音ではあるけれど、そこまで強くは望んでいない。何かの機会に、思い出してもらえる存在であったならいいな、という程度。そんな気持ちを、べーやんの歌に託したいという思いが、今はある。
そしてそれは、逆に今を生きる僕の気持でもある。
今年も、何人もの人を見送ってきた。僕の人生に強く影響を与えてくれた人、優しくしてくれた人、力になってくれた人。僕は、あなたたちのことを生涯忘れない。いつまでも、いつまでも、僕の追憶の中に生き続けてもらう。
でも、もうあえないんだな。さびしいね。
北陸に住んでいた頃は、12月どころか11月でも降雪があったものだが、西日本の平野部ではまずそういうことはない。爆弾低気圧、なんて言葉も出てきた。先んじて寒波がおそったため、例年のクリスマス寒波は来ず、今は比較的穏やかに推移しているが。
過去の寒かった年のことを思い出す。
北陸に住んでいたときは「三八豪雪」「五六豪雪」というえげつない雪害が半ば伝説的に語られていて、二階から外に出たとかいろんな話を聞いたものだが、その頃は京都に居たので全く覚えがない。ただ、昭和58年の暮れから59年にかけて降り出したいわゆる「五九豪雪」は、日本海側だけではなく山を越えて太平洋側でも降雪があったために、よく記憶している。
この年は、大学受験の年だった。
生来の怠け癖のせいか、受験というものをずっと薄くしか意識してこなかった。
もちろん怠惰な性格のためであって、これを学校のせいにしてしまうと「馬鹿者」と言われてしまうのだが、なんとなく高校生活においてはずっと「進学」ということが遠い世界のように僕には思えていた。
僕が住んでいた地域の公立高校には、当時、学校間格差というものがなかった。「十五の春は泣かせない」という言葉を今もおぼえているが、当時の京都の公立高校は「高校三原則(小学区制・総合制・男女共学)」を堅持していて、公立であれば近所の高校へ進学することになっていた(これが小学区制)。そのため公立高校のレベルはどこも同じで、高校入試も特に苦労した記憶も無く、その高校に入ればアタマのいいヤツからそうでないヤツまで様々なレベルの生徒が混在していた。ガリ勉から不良まで雑多で、制服も無くそれは面白い高校生活だったが、こと進学ということに関しては学校としてはあまり手を打っていなかったというのが実情だったろう。そりゃしょうがない。同じクラスの中に、国立大学を目指すヤツもいれば植木屋を目指すヤツもいたのだから。特別な授業など出来ない。
なので進学のための勉強は、個人に委ねられていた。レベルの高い勉強をしたいヤツは予備校や塾に通う。
僕は怠惰な性格なので、そういうことを放置して青春時代を謳歌していた。ぼんやりと大学に行きたいとは思っていたが、特別なことは何もしていなかったと言っていい。そうして、いつしか3年生になっていた。
夏に、模試をいくつか受けた。
そこで、これではダメだということを思い知らされた。歯が立たないのである。尻に火が付いた。
しかし火はすぐに熾火となってしまう。こりゃ今からじゃ間に合わないんじゃないか。そしてすぐに、一年浪人すればなんとかなるかも、というところに思考が飛んでゆく。
親にそのことを言うと「阿呆か」と言われた。そんな経済的余裕はないぞと。兄弟も居て、教育費だけでパンクしてしまうではないか。現役でどっか入ってくれ。最も望ましいのは、家から通える学費の安い国公立大学であると言う。
しかし地元の国立と言えば京大である。そんなんは逆立ちしても無理や、あんたらの息子やでオツムのレベルくらい想像がつくやろ、と言うと、せめて安めの私立なら良い、しかし地方へやるのは無理だから、家から自転車で通えるところにしろ、と。
18歳の僕は、岐路に立たされていた(遅いっつーの)。
僕は、数学が致命的なほどに出来ない。
ならば私立文系ということになるが、これもアタマを抱えることになる。英語が不得手なのだ(数学と英語が出来ないで進学を考えるなど身の程知らずも甚だしい)。
ただ、国語と日本史は、模試では結構いい成績をとっているのである。古文も得意だし、当時から歴史ヲタクだった。しかし偏りが大きすぎた。
私立文系の入試の形態は、大学により様々である。だが、困ったことに多くは英語の比率が大きい。英語200・国語100・社会100とか。英語150・国語150・社会100なんてのも。これでは受からない。その中で、英語国語社会で100点づつの300点満点の大学があった。それがどういう天の配剤か「自転車で通える大学」だった。そして、その大学は大学野球でいつも応援していてファンであり、父の母校だった。
狙いは定まった。
しかし定まっただけで、そこから受験モードに急に切り替わったわけではない。夏休みの宿題は9月1日に始め、試験は一夜漬けを得意としてきた僕だ。とりあえず問題集などを買い込んだが、なかなか勉強に手がつかない。ついTVを見てしまう。
そうしているうちに、秋も過ぎ冬を迎えようとしていた。
学校の授業は、あいかわらず平常営業である。特に受験体制ではなく教科書を追っている。僕は微分積分などどうでもいいので、内職をしていた。机の下の「試験に出る英単語」を暗記している。他にもそういうヤツはいっぱいいた。教師も黙認していた節がある。そのうち、欠席が目立つようになってきた。授業より受験勉強を優先しているのだろう。
欠席という手もあるか。出席日数を計算すると、このあと2学期全休しても落第にはならないようである。僕は、ちょっと籠ろうと思った。
その年、親父が滋賀県で中古の家を購入していた。
京都の家は借家であり、仕事もありそのまま住み続けていたが、いずれ定年後のことを考えて安い家を買ったらしい(だから貯金が無くて浪人を許さなかったのか)。したがってその家は現状空家だった。
その家は、電気水道ガスは何とか通じていたが、電話もTVもまだ無かった。余計なものは何も無い。意志の弱い僕には大変好都合である。TVがあるとつい見てしまう。
12月も初旬を過ぎた頃、僕は親父の車にストーブと小さなコタツ、布団、参考書と問題集、食料を積んで、その家に送ってもらった。そして、自ら篭城を始めた。
その家に年末まで20日間ほど居たのだが、よく生活していたなと自分でも思う。何食ってたんだろう。ほとんど記憶がない。冷蔵庫も無かったはず。外出もしなかったし、おそらくカップラーメンばかり食べていたのではないか。二度ほど親が来たが、食料と着替えを置いていったくらいだっただろう。だいたい電話も無く(もちろんケータイもない)、僕の人生であそこまで世俗を外れたことはなかったように思う。
雨戸も閉めたまま。だんだんいつが昼か夜かもわからなくなっていた。眠くなったら寝る。ハラが減ったら何か食う。あとはひたすら、勉強。
ただ、ここが僕の意志の弱いところなのだが、ラジオだけは小さいのを持ち込んでいた。疲れたら、スイッチを入れた。唯一の娯楽だったか。
AMしか入らないラジオだったが、音楽は流れていた。
よく聴こえてきたのは、松田聖子の「瞳はダイヤモンド」。小泉今日子の「艶姿ナミダ娘」。そして山下達郎の「クリスマス・イブ」。
映画色の街 美しい日々がきれぎれに映る
いつ過去形にかわったの
これらを聴くと、あの孤独を感じる間もなかった受験勉強の頃が思い出される。それはそれで、充実した日々だったと今になって思う。
夕暮れ抱き合う舗道 みんなが見ている前で
あなたの肩にちょこんとおでこをつけて泣いたの
トイレに行こうとして、ふと窓の外を見た。
雪が降り積もっていた。全然気が付いていなかった。ここまで積もった雪をあまり見た記憶がなかった。冷えるはずだ。空からはまだ絶え間なく白い雪が降り続いている。
心深く秘めた想い 叶えられそうもない
街角にはXmas tree 銀色の煌き Silent night Holy night
このうたは、あれから30年以上過ぎたのに、まだ命脈を保っている。僕にとっては、このうたはやはり1983年12月のうたとして鮮烈に記憶に残っている。
年が明けると、すぐに共通一次試験。無駄とは知りつつ、マークシートだものどう転ぶかわからないので、一応受験した。
結果、惨敗。100点満点の日本史の点数を200点満点の数学Ⅰの点数が大幅に下回るという恐ろしい結果となった。しょうがない。さあもう本命に絞っていこう。
そして、その本命の受験日。また雪が降った。この冬は本当によく降った。
僕は自転車で受験会場である大学へ向かったのだが、路面は凍結しており、途中坂道で思い切り滑り横転し、腕を痛めた。だがそんなことは言っていられない。動揺しつつも、何とか受験会場には間に合った。
試験は、全然出来た気がしなかった。難しすぎた。駄目だ。やはり、付け焼刃の勉強では追いつかなかったか。僕は憔悴して空を見上げた。雪が少し小降りになってきた。
それから合格発表までの数日間のことをまた思い出す。
2月以降、もう学校も授業などはやっていない。だから行ってもしょうがないのだが、なんとなく顔を出すと、受かったヤツ、落ちたヤツらが報告に現れる。予備校の相談もしている。その悲喜交々とした様を見ているのも、まだ着地していない僕にはしんどかった。3月になればすぐに卒業式がある。就職組や合格組は様々に相談をしているが、輪に入る気にもなれない。
僕はこれからどうなってゆくのだろう。先行きが見えず足が地に付かないこの中途半端な「あわあわ」とした気持ち。それは今まで味わったことのない時間だった。
僕は、ひとりで街へ映画を見に行った。アニメーション「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」が封切りとなったので、ラムちゃんのファンだった僕は、せめてこれくらいは見ようと思った。
映画は、傑作だった。非常に面白かった。公開は二本立てで、併映は吉川晃司主演のアイドル映画だったのだが、入替制でないのをいいことに吉川君の映画の間は居眠りをして、2回見た。映画など頭に入るかな、と最初は思っていたのだが、しばしそういうことは忘れた。
外に出れば、もう暗くなっている。吉川晃司の映画を挟んで3本見たことになるので、ずいぶん時間も過ぎていた。
空を見ると、また細かな白いものが舞っている。
僕の頭の中ではずっと映画のエンディングテーマだった「愛はブーメラン」が繰り返し流れていた。
今 あの娘の細い腰 手を回した 悲しいわ これっきりね
今 想い出永遠に消しましょうか ため息で So long in my dream
そのときの繁華街の風景を今もよくおぼえている。ポケットに手を突っ込みながら、帰りのバス停へ向かうでもなく、うつろな目で歩いた。
湧き起こる「あわあわ」とした気持ちを「愛はブーメラン」がいっとき押し流す。そしてまた再び空虚感が襲ってくる。
今、同じような状況に至っても、こんな気分にはなるまい。若かったのだろう。アーケードから出ると、また雪。
もしか もしか 愛はもしかして 放り投げたブーメラン
大学には奇跡的に合格していた。当日僕は合格発表を見に行く気にもならずフテ寝していたが、母と妹が見に行ったらしい。叩き起こされた。そして、春が来た。
今も、あの気持ちが揺れた冬のことを懐かしく思い出すときがある。
もちろん太宰治の有名な一節だが、その太宰は「人間失格」を書き終えて、自死を選んだ。39歳の誕生日を迎える数日前。
僕も同年齢にして、「死」というものを意識するようになったことを記憶している。無論のこと太宰とは異なり自ら死を選ぼうなどとは微塵も考えてはいなかったが、少なくとも人生は有限である、ということをはっきりと認識したように思う。
それには様々な要因があったのだが、同時に「自分史」というものを無性に記したくなった。自分史といえば大仰でありそんな大層なものではないが、自分の軌跡を、その追憶の断片をどこかに残しておきたくなった。
ブログというツールを知ったのはいつだったか。
はっきりとは憶えていないが、それまでWeb上で日々雑感を書いていた日記ツールに限界を感じはじめた頃、おそらく2004年の夏くらいではなかったか。下書きが出来る(執筆に時間をかけられる、また推敲・修正も可能)、字数制限が厳しくない、活字の大きさ等紙面上の自由さやデザインの選択幅の大きさなど、非常に魅力を感じた。
ただ、しばらくは使用に踏み切ってはいなかった。
その頃、日記ツールやBBSなどをWeb上で運営していた以外に、僕はHPを作りたいと思い、その準備をコツコツと行っていた。これがつまり、人生が有限であると気付いた僕が書き残そうと思った自分史にあたる。
しかしそれは公表するまでには至らなかった。少し身体を悪くしてしまい、そのため長時間座って作業を続けることが叶わなくなった。
では、書き溜めていた文書、またこれから書こうと温めていた思いをどうやって吐露してゆくか。
僕は、ブログツールを使おうと思った。それが、このブログにあたる。
2004年も暮れに差し掛かった頃、僕はとりあえず最初の記事を書いた。以後、昔話を中心として記事を積み重ね、これでちょうど10年になる。
この10年というもの、ずっとブログを書いてきた。途切れることなく。稼動させたブログサービスはいくつもある。僕の中の引き出しはとうに空っぽになり、つまり内面にもうネタは無く、自分史という段階は超え、今はもう好奇心に引っかかったものを引きずり出し調査して思考して書くという状況になっている。それでも飽かず、書くことに多くの時間を費やしてきた。
僕にとってのこの10年とはいったいなんだったのだろうか。そんなことを今考えている。
厳しく見れば、それはただの浪費だったのかもしれない。
この費やした時間というものを、もっと有効活用していれば、と人は言うだろう。事実、いくらWeb上に書き続けても、それは何も生み出していないに等しい。
だが、それでも書いてきた。
そして、いつしかこれは僕の「墓標」であると思うようになった。
人は、いつか死ぬ。
そして、死んだ人の軌跡というものは、史上に残る事績を成したひとにぎりの群像を除いては、何も残らない。多くの市井の人々は、忘れ去られてゆく。
例えば子孫や親しい友人は、彼らのことを憶えているかもしれない。だがそれらの人々の人生も有限であり、人は死んだ瞬間から、忘却の波に呑まれていく運命にある。
市井の人が生きてきた証しというものは、極端なことを言えば墓標しか残らない。しかしその墓標すら現代社会においては、建立も難しい時代となっている。そして仮に墓を建てても、祭祀者が途絶えれば終る。
ふつうの人は、何も残らない。
まして、その故人が何を思い、どのように人生を積み重ねてきたかということなどは、その人の脳内にしか存在しないもの。
生きるということは、そういうことなのだ。
彼らが育まれ、努力し、恋をし、幾多のことに感動し、辛いことを潜り抜け、褒められ励まされ、愛情を注ぎ、笑ったり泣いたりしてきたことは、全て無になる。
もちろん、それは自明のことである。消失することに対して抗うことは出来ない。銅像を建てたり、小惑星に名前を冠したりしても、その人の思い、その人の追憶というものは残らない。
ただ、こうして書くことは、銅像よりも彼の人の追憶を留めておくことにはならないだろうか。
Webというものに自分を表現することが可能になってから、しばらく経つ。
以前は、自分の思いを吐露したものを残しておくことは、ごく限られた人にしか不可能だった。作家になるか、あるいは芸術家になるか。自伝を書ける人は幸いである。いくら史上に残る大物であっても、伝記をしるされたり小説の題材になったりするのは、自分の思いを残したとは言いがたい。
今は、誰でもこうして書ける。自分の思考を公表できる。いい時代になったと思う。
同時に、恥を晒しているという見方も出来る。内面を公表するというのはそういうことで、だからHNで書いている。
あらためて昔の記事を読むと、耳まで赤くなる。恥の多い人生であったとつくづく思う。
それでも、こうして自分の軌跡を残しておけるのは、幸せなことだと感じている。
ブログサービスに限れば、例えば日本においては今世紀に入ってから隆盛し、歴史はそろそろ15年になる。
既に管理人がこの世にいないブログも数多くあるだろう。震災のときに「更新が止まったブログ」のことが話題になったが、そんなブログは数多いに違いない。さすればそれは、サーバー上に残る彼の人の墓標であることになる。
願わくは、いつまでも残しておいてやってほしい、と思うのである。無縁仏として片付けてしまわずに。先方も商売でやられていること、難しいとは思うが、何とかならないものかと思う。
わたしは今日まで生きてみました
時にはだれかの力を借りて
時にはだれかにしがみついて
わたしは今日まで 生きてみました
そして今 私は思っています
明日からも こうして生きて行くだろうと
「今日までそして明日から」を聴きながら、またいろんなことを考える。
僕は、いつまで書いてゆけるだろう。
自分的に「虎は死して皮を残す」程度のことは、もう書いたと思っている。だからといって、終了宣言には踏み出せない。それをするには、僕はどうも書くことが好きすぎるようだ。
しかし、書こうと思ってもなかなか書けなくなってきた。
かつて量産していた時代は、いくらでも書きたいことがあった。そういう蓄積や衝動がなくなったことは確かにある。そして同時に、筆力の衰えも感じる。言葉が流れ出てこなくなった。脳の硬直化か。体力の衰えと同様のものを感じている。
でも、書きたいな、まだ。頻度は落ちたとしても。
ブログを始めた頃は、まさか10年後もこうして僕が「凛太郎」としてWeb上に棲息しているとはとても想像がつかなかった。そして今も、将来のことは全く見えない。例えば、還暦を迎えても書いているなんてイメージは全然持てない。
今後何が起こるかは、わからない。
でもしばらくは、道はまだ続いているみたいだ。
終了宣言もしないし、生涯ブロガー宣言もしない。ただ道が続いているなら、少しづつでも歩いてゆくか。そんな心境かな。
けれど それにしたって
どこで どう変わってしまうか
そうです 分からないまま生きてゆく
明日からの そんなわたしです
わたしは今日まで生きてみました
わたしは今日まで生きてみました
そして今 わたしは思っています
明日からもこうして 生きてゆくだろうと
そんな感じで、まだ凛太郎はWeb上に居ます。
いや、今もまとまった休暇があって、愉しいには違いない。だが、それだけの時間を確保するために、様々な皺寄せがあるのも事実で、ポカンとイベントを待つ気持ちにはなれない。大人になるということは、ある意味つまらないとも言える。
クリスマスは、僕が子供の頃はケーキを食べてサンタさんにプレゼントをもらう日だった。特に裕福な家庭ではなかったために、高価なものをもらった記憶は無い。菓子とか、トランプなどの遊具だったと思うが、それも嬉しかった。今は若者同士で贈り物をしてセックスをする日になったことを思うと、隔世の感がある。
そして年の瀬。正月を迎えるためにさまざまなイベントがある。大掃除。年賀状作成。また、もちつき。臼や杵の時代ではなく僕の時にはもう「餅つき機」というものがあったが、家族総出でそれを行い、つきたての餅を食べる。大晦日になれば、母はお節をつくり、紅白歌合戦を見ながら年越し蕎麦を食べる。この日だけは、子供も夜更かしをしていい。
紅白歌合戦というものを観なくなって、どれくらい経っただろうか。あれを皆で観るのも、ひとつのイベントだったような気がする。
僕にとって年末年始が旅の季節となって久しい。旅に出てしまえば、TVはほぼ観ない。もちろん冬だから宿に泊まっているが、年越しのパーティーをしたりただ呑んでいたりで、あまりTVが介在することがない。
確か西表島で、ポールサイモンが出ていたのを観た。紅白にサイモン先生が?と驚いたがそれはニューヨークからの中継で来日していたわけではなく、しかも歌ったのが「Bridge over Troubled Water」なので拍子抜けした記憶がある。テロップに「ポール・サイモン(初)」とありなんだこれはと思った。次に吉幾三が登場してTVは消された。
結婚してからは、旅はするけれども大晦日は妻の実家に滞在している。ただ津軽の正月というのは、31日がメインだ(→正月の過ごし方)。昼から盛大に呑んでいて、僕なんぞもうそんな紅白の時間には潰れている。お義母さんらは観ているようだが、僕はイビキをかいている。若くないとつくづく思う。
最後に紅白を観たのはたぶん、吉田拓郎が出たときだ。今検索したら、1994年となっている。20年くらい前か。僕はまだ20歳代だったのだな。もう結婚していたので、妻の実家で観たんだろう。若かったから大酒のあとも持ちこたえられたのかと思う。
動画があった。(youtube)
スーパーバンドで出ている。石川鷹彦さんがいるのはまあそうだろうと思ったが渡辺香津美氏がリードをとっているのでほほぅと思った記憶がある。NHKも気を使ったのだろう。吉田建さんが若いな。宮川さんはもう亡くなった。コーラスの演歌の人は不必要だったが(女性コーラスで十分)、日野皓正、大西順子他一流のバックで、やっぱりポケットに手を突っ込んで歌っている。レコ大の「襟裳岬」の授賞式のときもそうだった。吉田拓郎を知らない人が観るような場面では、こんなことをしてしまう。
なんで「外は白い雪の夜」だったのだろう。単純に、冬のうただったからだろうか。それとも、この曲のテイストが受け入れられやすいとの判断だったのだろうか。まさか「雪」とか「襟裳岬」を歌うわけにもいかないし。
ただ「外は白い雪の夜」は、いい曲だ。不遜だと言われるかもしれないが誤解を恐れずに言えば、実に細密に気を遣って作られている。松本隆作詞ということもあるだろう。作りこまれた感がある。
その松本隆の詞は、別れがテーマだが男女の掛け合いとなっている。最初は、「大事な話が君にあるんだ」と別れを切り出す男。そして次に、その別れを受ける哀しい女の心。
このうたは1978年、LP「ローリング30」の一曲として発表された。それから約10年後に、僕も同じような経験をしてしまったことがある。もちろんなぞったわけではないが。その話はまだ熟成されていないので書けないけれども、そのときは、自分はなんという身勝手な人間かという嫌悪感を抱くとともに、松本さんは巧みに表現するなとも思った。
こういう別れの場面で、男と女の両方から語るやりかたは、デュエット曲には数多いのではないかと思うが、ソロだと表現が難しいのではないか。ただ松本さんは以前からやっている。代表は「木綿のハンカチーフ」だろう。
そして、拓郎も同様のうたをかいている。「春を待つ手紙」。
このうたは1979年、シングルで発表されたが、そのB面は実は「外は白い雪の夜」である。つまり、両面とも男女の別れのそれぞれを書いている。そして拓郎作詞作曲の「春を待つ手紙」は、何と往復書簡の体裁をとっている。
僕は「春を待つ手紙」のシングルは、発売時には入手していない。最初はラジオからのエアチェックだった。だから、往復書簡であることに気づかなかった。
歌詞カードを見ると、まず「直子より」と差出人が明記されている。
追いかけましたあなたの姿だけ 幼いあの頃の想い出あたためて
あれから幾年 友さえ嫁ぎ行き その日を待つように父母も逝きました
これは、直子さんの手紙である。そして次に「俊一より」として、彼の手紙が二番となっている。三番はまた直子さんの返信、そして四番は俊一の返信となっている。だが歌詞には、俊一も直子も登場しない。だから、歌詞カードを見ないとわからない仕掛けになっている。
男が別れを切り出しているのは「外は白い雪の夜」と同じ。だが松本さんの「外は白い雪」がその別れの場面を具体的に、目に浮かぶように描写しているのに対して、「春を待つ手紙」は心情をより抽象的に(拓郎流に)、さらに哲学的に複雑な言葉で綴っている。
だから、わかりにくい。往復書簡ということも聴いただけではピンとこないし、「外は白い雪の夜」とは対照的とも思える。
ただ、言葉のひとつひとつは、沁み入る。
人間だから求めてしまうけど それこそ悲しみと知ってもいるけれど (直子)
待つ身の辛さがわかるから急ぎすぎ 気づいた時には月日だけ年をとり (俊一)
非常に印象的な歌詞がある。
約束なんて 破られるから美しい 誰かの言葉が身体をかすめます (直子)
たぶん、そんな誰かの言葉は無い。聞いたことがない。「約束は破られるためにある」という言葉ならあるが。
これを最初に聴いたときにはまだ少年だったから、そんな言葉があるのか、と素直に思ったが、この歳になっても「約束は破られるから美しいのだ」なんて言葉は未だに耳にしていない。
つまりこれは、何かの格言ではなく、もしや俊一が言ったということなのか。
そして、こんなことばが言えるということは、相当に辛辣な思いをしているからではないか。約束を破られても、それを美化しないと生きていけない経験があったから絞りだされた言葉ではないのか。
だから「男の意気地なし」である俊一をただ責めることはできないし、僕も約束が破られるたびに、この言葉が身体をかすめる。この辛い拓郎の言葉が。
「春を待つ手紙」の心象風景は、冬だ。寒い心。具体的に、外には白い雪が降っているわけではないが、その寒さは僕らを押し潰す。
今年もまた寒い冬になっている。
それは、ただ体感温度のことだけではない。あの頃は、ただ「年を越す」ということだけで愉しかった。そんな時代があった。だが今は。
傷つく事に慣れてはいないけど ましてや他人など傷つけられましょか (直子)
拓郎は「春を待つ手紙」をライブでほぼ歌っていないはず。それは、やはり前述したように、歌うことが難しいからではないのか、と思っていた。「外は白い雪」を紅白歌合戦に持ってきたのとは、本当に対照的に。
実際ライブで歌ったことがあるのかどうかを調べようと思って少し検索してみたら、こちらの方のサイトに出逢った。→泣きたい気持ちで冬を越えてきた人
拓郎は、震災復興チャリティで「春を待つ手紙」を生で歌ったらしい。知らなかった。詳しく書かれているので是非一読していただきたい。音源もあった。
胸に迫った。
このうたは、朗らかな曲調、そして明るいリードギターが救いでもある。だがこのライブVer.は、生ギターとブルースハープの弾き語り。
うたは、一番から四番までは、直子と俊一の手紙のやりとり。そして、五番がある。それは、拓郎の言葉だ。
誰もが誰かを恋しているんだね それはあてのない遙かな旅なんだね
旅する人には人生の文字似合うけど 人生だからこそひとりになるんだね
力強い。
そして次の言葉があるからこそ、拓郎は震災復興のライブでこのうたを選んだのだろう。
ここでも春を待つ人々に逢えるでしょう 泣きたい気持ちで冬を越えてきた人
二年前も、寒い冬だった。そして、この冬も寒い。
行き場を失った人もいるだろう。追い詰められている人もいるだろう。明日が見えない人もいるだろう。
深い悲しみの中にただよう人もいるだろう。何かを失ってしまった人もいるだろう。
もがいても、もうしょうがないんだ。待つ。
春が必ず来ると信じていなければ、この冬は越えられない。
そんなことを自分に言いきかせつつ、先へ進もうと思う。
辛い思いを抱えた多くの人々にも、春が訪れますように。
誰しもが、後悔を重ねて生きている。
もしもあのときああしていれば私は違った道を歩んで…という人生の岐路にかかわる事柄もあれば、もっとささやかな後悔もあるだろう。いつまでも忘れられない失敗。あのときひとことが足らなくて誤解を生んでしまった。勇気がなくて体の不自由な人に席を譲れなかった。酔って暴言を吐いてしまって呆れられた。そんなことでも夜中に思わずギャッと叫んでしまいたくなったり。それらが積み重なって、人生になっている。
じゃ時計の針を、本当に戻すことができるならばどうだろう。人生のある一点からやり直すことが出来るなら。そういう夢想の中には、いつも二種類の方法が脳内に示される。
ひとつは、とにかくただ時間を戻してくれればいい、あの頃の若かった自分に戻りたい、という考え方。そしてもうひとつは、現在の自分の経験値と解析能力を持ったまま、あの頃の自分に戻りたいという都合のいい思考。
どっちも妄想なのだが、後者は医療技術などの発達によって可能になることもあるかもしれない。つまりこれは「若返り」なのだから。現在でも、アンチエイジングの技法はかなり進んでいる。とても50歳には見えない美魔女も存在している。いくらでもやり直しがきく、とも言える。しかし、いくら頑張っても例えば18歳には戸籍上はなれないのだから、結局時計の針は戻せないとも言えるが。
僕はといえば、時計の針を戻せるとすれば現在の頭脳をそのまま持ち込まなくてもいいように思っている。確かに経験を積んで口も巧みになり洞察力も磨かれてはいるが、そのぶん記憶力も低下し感受性もかなり磨耗しているように思うから。やはり若いときの頭脳や心も欲しい。それでないと人生をやり直すことにはならないように思われる。
しかしながら、こと「男と女」の話になれば、今の経験を積んだ頭脳があの頃に少しでもあったなら…とどうしても思う。
うたの世界のなかでの主人公は、そんな後悔をどう歌っているんだろうか。
ユーミンはこんなふうに歌う。
青春のうしろ姿を 人はみな忘れてしまう
あの頃のわたしにもどって あなたに会いたい (あの日にかえりたい)
ここでいう「あの頃の私」というのは、長い人生という観点からみればちょっと前の姿を指している。当時のユーミンは二十歳そこそこであり、そんな昔のことは振り返れない。しかしそんな短い昔でも、染まっていなかった頃の自分と染まった(染められた)自分との違いはある。おそらくそんな意味だと思うので、「あの頃」に経験値を持ち込みたいと思っているようにはみえない。
中島みゆきは、こんなふうに歌う。
長い髪を三つ編みにしていた頃に めぐり逢えればよかった
彼女より もう少し早く (横恋慕)
これも、経験値を持ち込みたいと願っているようには思えない。時間さえ戻せれば、そして自分が先に彼に出逢っていれば、という後悔のみ。もっとも「たぶんだめね」というところが哀しいのだけれども。
もちろん一概に二元論では言えないことは承知だが、もしかしたら女性のほうが素直なのだろうか。今の俺ならもっとうまくやれたのに、などと考えるのはもしかしたら腹黒いだけなのかもしれない。けれども、僕はどうしても思ってしまう。あの頃の自分にただ戻っても結局同じことを繰り返すだけだろう。あの頃の自分にはなかったものを、今なら持っている。その力が、あのときに欲しかった。
僕は若かった頃、もう少し具体的に言えば学生だった頃に、女性と交際した経験がない。つまり、彼女というひとは存在しなかった(と思っている)。
こうはっきり書くことには我ながらかなり抵抗があって、社交性のない変人だったのではないかと思われてしまう可能性もある。あるいは、よっぽど女性に忌避されるような人間だったとか。事実変人だったのかもしれないしもちろん面相に自信など今に至ってもないが、それは措いたとしても、かなりのオクテだったと見られるだろう。
いまの世の中、中学生どころか小学生だって、告白し恋人同士となっているヤローもいる。そしてそれは、時代が違うのだとばかりは言えない。僕の頃だって、いくらでも事例はあった。深夜放送にはそんな話が溢れていた。そして現実の僕の周りにも、いくらでもカップルはいた。
思春期という時代は、若者は異性に対してもの凄く興味を持つ。僕もエロ本はたくさん所持していたし、老け顔だったので高校生にもかかわらずポルノ映画だって観にいった(そんな時代だったんだよなー)。しかし恋愛というものに対しては、何故か斜に構えていた。そんなことよりもっと楽しいことがたくさんあるだろう、と。
斜に構えていた、というのは当時の僕の心境なのだが、経験値を積んだ今ならそれを簡単に分析できる。結局臆病だっただけ。
高校時代、好きだった女性がいた。まあこのひとなのだが、彼女はその後友人のひとりとなった。何でも気軽に話せる間柄だったと思うが、ここで僕が「あなたのことがすきです」と言ってしまうと、全てが終わる可能性もある。恋は走り出せばall or nothing。なので、僕は踏み出せなかった。この関係性を壊す勇気はなかった。そして、そのまま卒業して終わった。
それに関しては、阿呆だったなとは少し思うが、後悔はしていない。ただ僕が、後戻り出来ないことを覚悟するほどの強い気持ちがなかっただけ。誰も傷つけてはいない。
そうして僕は、進学した。(約30年前は)極端に女性の数が少ない大学、学部だったが、出会いはそれだけではない。合コンもよくやった。学友は地方からやってきたヤツも多く、地元出身でありしかも共学の高校を出ている僕は重宝され、女子大に通う同級生と話をつけてセッティングもしばしば行った。そうして女の子たちと河原町で酒を飲んで騒ぐ集まりは、楽しかった。もちろん最初は未成年ばかりだったが、もう時効だろう。
今はとんと聞かないが「合ハイ(合同ハイキング)」も試みた。日本のあちこちから学生は京都にあつまってくる。いいところへ案内しよう。というので、例えば鞍馬山や伏見稲荷などみんなで歩いて楽しいところへ連れて行った。
そうした中で、カップルも誕生してくる。これは素直にうれしかった。自分が主催した会がきっかけならなおさら。そうして、僕はとにかくけしかける側にまわっていた。自分がアクションを起そうなどと思ったこともなかった。そのときが楽しければ、それで良し。そんな祝祭のような日々を続けていた。
もちろん、淡い気持ちを抱いたことがなかったわけではない。ただ、それ以上は自分の中では膨らんでこなかった。これは、ただ消極的だっただけとも言える。他のことではあれほど積極的であったのに。
また、僕はそれ以外に旅行にも夢中になっていた。自転車を駆って日本中を回ろうと思っていた。旅先では、同じ旅人であるというよしみで女性とも気軽に話も出来る。そんなのもまた、楽しみの一つだった。
19歳の夏。僕は北海道にいた。野宿などをする以外は、宿は主としてユースホステルを利用していた。夏の北海道のYHはとにかく混雑している。それだけ若い男女がひとつ屋根の下に集うわけで、出会いはそこかしこに転がっている。
ただそんな場所でも、僕は幹事的役割をいつも率先して行っていたような気がする。臆病云々というより、そういう性格なのだろう。そういえば鍋奉行になることも多い。
そんな旅も終わりに近づいた頃、僕はとある日本海側の宿に泊まった。とある、などともったいぶるわけでもなく増毛という町の宿なのだが、そこはあれだけ旅人が混雑している夏の北海道においてエア・ポケットのように空いていた。富良野や知床と比べて知名度が低かったのだろう(ごめんなさい)。僕も、いわば通りすがりだった。自転車でなければ、泊まらなかっただろう。
宿泊客は、僕の他は女性がひとりだけ。向かい合って食事をした。
「君、どっから来たん?」
「京都ですけど」
「あら、私も京都。生まれは滋賀なんやけど、今は仕事で京都に一人暮らし」
「へー偶然ですね。京都のどこに住んだはるんですか」
「白梅町」
「え、僕はその近くの大学に通てるんです」
彼女は26歳。髪の長い小柄な人だった。
食事が終わり(YHでは飲酒禁止であり簡単に食事は終わる)、二人で海まで夕日を見に行った。
「ビール飲む?」
「ええんかな…」
「ええやん、どうせ二人しか泊まってへんのやから」
陽は静かに水平線へと沈み、しばしの夕映えのあと、漁り火が少しづつ見え始めた。
「このあとどうするのん?」
「明日、小樽まで走って、船に乗って帰ります」
「そうなん。私ももう3日で帰るんよ。京都でまた会お…」
翌朝、彼女と別れ僕は小樽へ向けて自転車を走らせた。
そして一週間後、もう僕らは会っていた。再会したその日に、僕は彼女のマンションに泊まった。
僕は、彼女のことを深く知ろうとは思わなかった。根掘り葉掘り聞くのは得意ではないし、彼女もゆるやかな関係を望んでいた(ように見えた)。どうやら長いお付き合いをしていた男性がいたこと、そしてその人とはもう別れてしまったことくらいはなんとなしにわかったが、詮索はしなかった。たいていは僕が一方的に話し、彼女は聞き役だった。
共通の話題は、まず旅のこと。そして、音楽のこと。
彼女は、イルカさんのファンだった。
「君は、どの曲が好き?」
「そうやな…”我が心の友へ”とか好きやね」
「通やねぇ(笑)」
「姐さんは?」(そう呼んでいた)
「私は初期の頃のが好きかな。やっぱり”あの頃のぼくは”はいいよ」
「あの頃のぼくは」はイルカさんのソロデビュー曲である。伊勢正三作詞作曲。
あの頃のぼくは若すぎて君の気まぐれを許せなかった
そんな君のやさしさはおとなびていました
机の上に編みかけのセーターの残していったまま
朝から続く雨の日に泣きながら飛び出していった
そして、レコードを聴いて過ごした。
夏が終わり、秋が過ぎ、京都に底冷えの季節が訪れようとしていた。
あるとき、彼女は僕に聞いてきた。
「君は、私のことどう思ってるの」
不意を衝かれたような問いだった。
僕は、この関係を「交際」だとは思っていなかった。ひらたく言えば「付き合う」ということは、まず少なくともどちらかが相手のことを好きになって、告白して、そこから始まるものだと思っていた。彼女とは、そんなステップは踏んでいない。お互いに意思表示もしたことがない。だいいち、彼女は僕よりずっと大人だった。
もちろん、彼女のことは好きだったと思う。ただし、それが恋愛感情なのかどうなのかはわからずにいた。彼女のことを「俺の恋人なんだ」なんて気持ちは、少なくとも持っていない。それはおこがましいように思っていた。これは対等な付き合いではない。彼女のような大人の女性が、僕みたいな若造を真剣に相手にするわけがない。そう勝手に思っていた。
僕が言葉を継げずにいると、彼女は悲しげな瞳でさらに言った。
「私は、好きでもない男を何度も家に泊めたりはしないよ」
そうして、彼女との関係は終わった。
本当に馬鹿だった。
僕は、言葉は悪いが彼女に遊ばれているつもりでいた。そして、遊ばれているならそれでもいい、この関係を無理して壊す必要もないと思い、そのまま流れに身を任せていた。
そうじゃない。遊んでいたのは、彼女ではなく僕のほうだったのだ。
僕が、ただ面倒くさい部分を棚上げにして、自分本位でいただけだった。
ぼくはぼくの事しか見えなかった 君が泣いてるなんて知らなかった
自分は、なんと卑怯な人間だったのだろうか。イルカさんの「君は悲しみの」を聴くたびに、痛切にそう思う。
あの頃のぼくに、19歳のあの頃のぼくに、もう一度戻ることはできないだろうか。
イルカさんのLPは、僕は数枚しか持っていない。「いつか冷たい雨が」と「あしたの君へ」そして「我が心の友へ」。それ以外の音源は、初期のものはみな彼女にカセットへコピーしてもらったものだ。インデックスも、彼女の字。それらカセットは、まだ僕のラックに残っている。
君はもうこの古いアルバムの中の想い出の女として
小さな灰皿の中で燃えてゆくのです
君の長い髪はとても素敵だったと言いたかった
僕は、彼女の写真すら一葉も持ってはいない。あの長い髪の小柄な彼女の姿は、すべて、追憶の彼方にいる。残っているのは、そのカセットテープと、ケースに書かれた文字だけ。
もちろん、それ以降、彼女に会うことはなかった。しばらく経って一度、未練たらしくもマンションの前まで行ったことがあるが、郵便ポストの名前が消えていた。おそらく引っ越したのだろう。
あのひとは、今元気に暮らしているのだろうか。幸せになってくれているだろうか。
君はもう 二人でいつも買ってた合挽のコーヒーの
あのほろ苦い味も忘れたことでしょう
今はひとり部屋の中でコーヒー沸かしているんです
あなたの好きだったイルカさんの「あの頃のぼくは」を、久しぶりに聴いています。
あれからずいぶん時がながれました。
僕はまだまだ愚かなままだけれども、あの頃よりは少し人の気持ちがわかるようになりました。
そんなことを伝えたくとも、もうそのすべはありませんが。
僕はこの曲を聴くと、まっさんの度量の大きさというものをいつも感じるのである。
前に親父が来たときも 僕の好物のカラスミを手土産にとくれたのに
わざわざまた煮て駄目にして 「ごめんなさい」っていいながら一番笑いこけたのは君
ピンきりではあろうけれども、カラスミというものは概して高価なものである。ボラの卵を時間をかけて加工した珍味で、ちょっと立派なものならひとハラ1万円くらいしてしまう。それを薄く切って、場合によっては大根の薄切りとあわせて食べたりするが、少量づつ食べるのならそこまでせずともそのままチビチビと食べればいい。上質のものはねっとりとして、酒の肴には抜群である。
邱永漢氏が書いていたのだが、台湾では炙って、ニンニクをつけあわせて食べるらしい。そういう食べ方はしたことがないが、アリなのかもしれないな、とは思う。絶対に生で食べなければならないものではない。しかし、これを煮てしまってはどうしようもあるまい。
さだまさしの歌だから、この主人公の実家の設定は長崎だろう。カラスミの産地だから、意外に手軽に手に入るものなのかもしれない。しかしそれでも、廉価ではなかろう。それを知らないとはいえ、煮るとは。…だが、ここまではまだ僕も許せるかもしれない。ドジでかわいい新妻のしたことだ。しかし、それで「笑いこける」とは何事であるのか。義父の思いを考えれば、もう少し申し訳ない気持ちを表明してもいいのではないか。
…と、どうしても思ってしまう。僕には度量が無い。されどからすみであっても、たかがからすみではないか。これがタラコであったなら、いかに父親のことを思えども僕だって笑って済ませたのではないだろうか。値で換算するとは、なんとも僕は人間が小さい。
おっとそういう話をしようとしたのではなかった。閑話休題。
このうたは、朝の情景から始まる。奥さんが朝刊の受け売りをはじめる。
きみは早起きしたのがさも得意そうに ねぼけまなこの僕を朝食に追いたて
ねェまた巨人が負けたってさって 高田の背番号も知らないくせに
高田の背番号か。
この奥さんは背番号を知らないだけだが、今の若い人がこれを聴けば、何の話かわからないに違いない。この高田とは、高田繁さんのことである。このあいだまでヤクルトの監督、今シーズンからはDeNAベイスターズのGMとなったあの高田氏。当時は、読売Gの花形選手だった。
ちょっと調べてみると、朝刊のリリースは昭和50年。ということは、長嶋監督初年度である。前年読売GはV10を逃し、長嶋が「巨人軍は永久に不滅です」とか言って引退し、監督となった。その監督初年度は負けに負け、とうとう最下位となったが、その年のうたである。そりゃ「巨人がまた負けた」となるだろう。ちなみに高田は塀際の魔術師とも称された天下一品の左翼手だったが、翌年読売Gは日本ハムから張本勲を獲得し、張本がレフトなので高田はサードにコンバートされた。そしてこの大型補強で読売は優勝する。このチームの体質は、FA制度以前からあまりかわらない。以上、関係ない話。ちなみに高田の背番号は8である。
話題にしたいのは、時事ネタを扱ったうたである。
本来、うたというものは不変の価値をもつ。名曲は、いつまでも人々の心に残るもの。そうした中で、歌詞に時事を扱うと、とたんにうた自体が古びてしまう危険性を内包してしまう。しかしその反面「うたは世につれ世はうたにつれ」である。時代を取り込んでいかないと、ヒットしない。
こういう話をするときに必ず話題となるのが国武万里さんの「ポケベルが鳴らなくて」だろう。
ポケベルが、今も存在しているのかどうかはよく知らないけれども、携帯電話の普及によって一般的にはほぼ消滅したといっていいだろう。だが、かつては隆盛を誇ったツールだった。僕も持たされたが、そういう業務的な使用以外に、女子高生などの暗号的活用の流行など、時代の象徴だったと言っていい。
おもしろいことに、普遍的なものではなく「時代の最先端」のものを採りあげると、あっという間に古びてしまう。だから歌詞に「フラフープ」「たまごっち」「ツイッター」などは採りあげないのが良いのだが、作る側もそれを承知で「消耗品」として送り出しているのだろう。作詞したのはやはり秋元康だった。
しかし、まさかその後廃れてしまうとは思わずに作詞した場合も多いだろう。BOROは「踊り疲れたディスコの帰り」と歌ったが、ディスコがここまで衰退し「クラブ」とかいうものにとってかわられるとは予想していなかったに違いない。「私がオバさんになってもディスコに連れてくの?」と森高千里は歌ったが、その後20年経っても森高はちっともオバさんにならず、逆にディスコが無くなってしまった。
こういうたぐいのものは、いっぱいある。
電話というアイテムは、恋をうたうためには必須。昔はケータイはなくポケベルもない。ポケベルはプッシュホン文化だが、ダイヤルの時代は長かった。ダイヤル回して手を止めて恋に落ちる人。涙のリクエストをあの娘に伝えたくてダイヤルをまわす。その手段は「コイン」。公衆電話すらもう見かけない。テレホンカードではなくコインだ。やしきたかじんは「もしもし…10円玉はまだありますか」と歌った。みどりの電話さえ探さなければいけないこのご時世、赤電話の恋などいまの若者には理解できまい(暴論)。
そういううたの媒体も、またかわった。
前述のグレープの時代は、まだレコードだった。出世作「精霊流し」では、いっしょにあなたの愛したレコードも流す。このレコードの時代が終わるとは思わなかったなあ。今はCDですらなくて主体は「配信」である。いつ頃からレコードが廃れたのだったっけ。スピッツが「思い出のレコードと大げさなエピソードを…」とうたったのは、もう平成もずいぶん過ぎていたはずだから、結構命脈を保ってたんだろうか。
「レコード大賞」もまだ存在しているらしく、言葉が失われたわけではない。そして、ディスコではなく「クラブ」においてDJはまだターンテーブルの前でレコードをキュキュっと鳴らす(と聞く。見たことないけど^^;)。だから、まだ生きているとは言えるけれども、「A面で恋をして」なんて聞いて、今の子供達は瞬時にレコードを連想してくれるのかなー。
こういうのは、風俗である。設定が古びてしまうのは避けようがないのかもしれない。「ポケベルが鳴らなくて」や「夜霧のハウスマヌカン」なんてのは特殊例とも言えるのであって、たいていはその風俗描写も「少し時代を感じさせる」程度に留まっている。それに、レコードも公衆電話もなくなったわけでもない。ダイヤル電話さえ、僕の実家でまだ老いた両親が使っている。カセットテープも我が家ではカーステで使用している。擦り切れたカセットはユーミンの「リフレインが叫んでる」とともに現役である。
歌詞で困るのは、時事を扱った場合だろう。
「ミセス・ロビンソン」のジョー・ディマジオ、また「朝刊」の高田繁氏のように、固有名詞などは時代が完全に特定されてしまうために、後々困ってしまう。このうたは新婚夫婦の話でありそこが微笑ましいのだが、この「巨人が負けたって」ってことでこの年が昭和50年(1975)と特定されてしまい、ああこの夫婦はもうじき結婚して40年になるじゃないか、もうダンナは定年で孫がいて、カラスミのおとうさんはまだご健在だろうか…なんて話になってしまう。どうも調子が狂うのである。うたの登場人物は、すべてサザエさん方式に年をとらないほうが感情移入できるのではないだろうか。
このうたはグレープ時代のものであるために、さだまさしのライブではさほど登場頻度が高くないのかもしれないが、それでもいっときまっさんは「ねぇまたマリナーズが負けたってさって イチローの背番号も知らないくせに」と歌詞を変更したと聞く。無理があったと思っているのだろう。
このうたの場合は、背番号8の高田が脇役的に登場してくるだけだから、まだいい。ピンクレディーの「サウスポー」には「背番号1のスゴいヤツ」が主役として登場してくる。今の子供達には説明しないとわかってもらえないし、説明したとしても「世界のホームラン王」についての実感がないため、イメージがわかないだろうなと想像する。王貞治という名前こそ明言されていないものの、阿久悠さんもやはり、うたは消耗品だと考えていたのだろうか。
しかしながら、これには違う見方もあるだろう。うたとはそういうものだったのではないか、ということである。ことに、フォークソングは。
川上音二郎のオッペケペー節にまでさかのぼるのは行き過ぎだけれども、うたというものは芸術、また娯楽のみならず「風刺」をも時としてはらんできた。フォークはそうした流れから、最初の隆盛がうまれた。反戦フォーク。平和を我らの手に。そうしたうたは「プロテスト・ソング(社会抗議歌)」と呼ばれた。こうしたうたは「風に吹かれて」他、枚挙にいとまがない。自衛隊に入ろう。教訓Ⅰ。反戦だけではない。この東日本大震災と福島の事故によって、ふたたび忌野清志郎の「原発いらねぇ」をテーマにしたかつての歌が脚光を浴びてきている。清志郎さんはもういないけれども、新たな原子力反対のうたは生まれてきているようだ。こういうものは、「トピカル・ソング(時事歌)」ともいう。
時事をテーマに風刺をこめてうたう歌。これは、消耗されることを覚悟でうたっていると言っていいだろう。時事歌の代表として、僕はやはり高田渡の「三億円強奪事件の唄(ニコニコ)」を挙げたいと思うが、他にも様々なものがある。岡林信康に名曲が多い。
時事歌の定義というものを僕はよく知らないので、どこまで含めていいのかはわからないのだけれど。僕個人としては風刺を含んでいて欲しいが、例えば山本正之の「燃えよドラゴンズ」なども時事歌になるのだろうか。「さらばハイセーコー」とか。いずれも、その時代を切り取って、その時代だけに生きるうたとして、潔いといえばいさぎよい。時代が過ぎれば、史料的価値は高くても共感をよぶのは難しくなる。
だが、そうした時事を含んだうたも、名曲であれば必然的に生き残ってしまう。風刺ではないが「朝刊」「サウスポー」を例にしてもいい。そして、遠藤賢司の代表作と言ってもいい「カレーライス」も、名曲であるがゆえに時事を含みつつ、ここまで歌い継がれてきた。このうたには、読み込めば風刺もありまた毒もある。
君も 猫も 僕も みんな好きだよね カレーライスが
エンケンさんはもう今年(2012)、65歳になられたのだそうだ。異常に若いような気がする。亡くなられた高田渡氏とつい比べてしまうからかもしれないけど(あの人は老けすぎていたがエンケン氏より年下)。やっぱり突っ張ってらっしゃるからだろうか。岡林や拓郎と同級生ということか。
この人は、やっぱりライブがすさまじいのだろうと思うなあ。世代が違う僕は実際に拝見したことはなくTVを通してくらいしか知らないが、まあ最初に見たときはビックリした。「夜汽車のブルース」だったと思うけれども、ギターのストローク奏法においては日本一だと思った。とにかく衝撃だった。ストロークって、こんなにすごいものなのか、と。もちろん、ストロークのみならずこの方はギターの超絶テクニックを誇っておられるわけで、坂崎幸之助を最初に見たときは「うわ、うめーなー!」であったが、遠藤賢司にはひたすら驚愕の「スゲーなー」だった。こういう感想を持ったミュージシャンは、他には長谷川きよしくらいか。
遠藤賢司のうたは、そうして尖がった攻撃的なものが目立つようにも思うのだけれど、おそらく最も人々に知られているうたが、この一聴して静かにも感じられる「カレーライス」であるというのもまた不思議な思いがする。それだけ名曲であるということだろう。
君はトントン じゃがいもにんじんを切って 涙を浮かべてたまねぎを切って
バカだな バカだな ついでに自分の手も切って 僕は座ってギターを弾いてるよ
なんとも平和なうたである。むしろ、極めて平和に、静かに日常をうたっている。そのことが後に効果を生むのだが、問題の部分は後半に出てくる。
うーん とってもいい匂いだね 僕は寝転んでテレビを見てるよ
誰かがおなかを切っちゃったって うーん とっても痛いだろうにねえ
ははーぁはぁん カレーライス
この「誰かがおなかを切っちゃった」というニュースがTVで流れて彼はそれを見たのだが、その感想をただ「痛いだろうにね」でとどめる。政治的なことは一切挟まず、あくまでTVの向こう側のこととして処理し、そしてこのニュースは平和な日常風景を乱すことなく、その後もカレーが甘いのが好きか辛いのが好きか、という話を繰り返す。関心の所在は、おなかを切った人よりも、カレーライス。
つまり、このTVの向うのおなかを切った人を無視する(あるいは「痛いだろうにね」とある意味揶揄する)わけだが、この「おなかを切った」人とは、三島由紀夫のことである。つまり、1970年の楯の会事件における三島由紀夫の割腹自殺を指している。楯の会とは三島由紀夫が組織した団体であり、彼らは憲法改正を要求して、市ヶ谷の陸自総監室を占拠し、自衛隊決起を促す演説をおこない後に、三島は割腹して果てた。
遠藤賢司自身の思想がどこにあるのか、はともかくとして、このうたのなかではその三島事件を「とるにたらぬもの」的な扱いをしている。そんなことよりこの平和な日常とカレーライスのほうが大事。そういう扱いにすることにより、反戦、憲法改正反対を暗に訴えているとみることもできる。
さて、この「カレーライス」といううたが世に出たときは、もう既に三島事件から一年が経過していた。だが、この事件の衝撃は相当に強く、「おなかを切った」と言えば皆、三島事件を想起したはずだ。そうでないと、うたが成立しなくなる。
だが、この「ノーベル賞候補の作家が切腹して果てた」という三島事件は衝撃的かつ歴史的出来事であったとは思うが、時は残酷であり、残念ながら徐々に人々の記憶から薄れてゆく。「時事」である宿命をかぶり、当該部分は意味が通じなくなってゆく。
「カレーライス」の歌詞には、もうひとつのバージョンがある。以下。
そしたらどっかの誰かが パッとおなかを切っちゃったって
ははーぁはぁん 痛いだろうにね
三島事件を説明はしていないが、「どっかの」という言葉を加えることによりふくらみをもたせている。どっちにせよ三島事件を知らないとよくわからないことには違いないが、仮に知らなくてもなんとなしに意味が通るようになっている。
しかし、少し長くなった。そのことは、少し残念ではある。日常において割腹事件がカレーライスより関心を呼ばない、というところにこのうたのキモをみている僕としては。
ライブを中心に活動をされてらっしゃるはずなので、おそらくは他にも様々なバージョンがあるのではないか、と僕は推測している。
僕が知っているので、こういうのがある。今から26、7年前だが、エンケンさんが「タモリ倶楽部」に出演してカレーライスを歌ったのをVTRに録った。それが、まだ手元にある。そこでは、こう歌っていた
そしたらあの 保険をかけるのが趣味でペイズリーが趣味で 嘘泣き上手の疑惑の人がタイホされたってさ
ははーぁはぁん カレーライス
完全に破調だが、これは「ロス疑惑」で報道が過熱状態にあった三浦和義のことにおきかえられてうたわれている。三島事件から15年ほどが経ち、もう完全に風化してしまったことを踏まえての歌詞であろうと思われるが、これにはちょっとがっかりした。当時のワイドショーネタであり、風刺の精神が残念ながらこれでは消えてしまっている。
もう三浦事件からもずいぶん経った。先だって彼がロスの留置場で亡くなったと報道されたときには記憶が甦った人も多かっただろうとは思うが、今ではまた完全に過去だろう。時事の宿命からはなかなか逃れられない。
このうたを、今始めて耳にする人も多いだろう。いったいどのような感想をもたれるだろうか。ほんわかしたやわらかなやさしいうただと思うだろうか。若い人は、果たして時事歌だと気が付くだろうか。
時間の波を超えて「カレーライス」は生き残った。もちろんうたの力によってここまで永らえてきたのだとは思うが、もうひとつ、エンケンさんが現役であってくださることも大きい。いつまでも尖っていてほしいなと思う。
世間的には、未曾有の大地震があり、その他にも災害が多く、また原発事故があり収束せぬまま年の瀬を迎えている。おそらくは後年の歴史書に特筆され、また永く人々の記憶に残るに違いない。
そんな年に小さな小さなことかもしれないが、僕個人にも様々な出来事があった。
以降書くことは、一応虚構だ。僕も具体的なことは語れないしまた書けない。ならば書かなければいいのだが、何となしにその心象風景のようなものは自分史として書き留めておきたくなり、虚構の形を借りて、その思いを刻んでおくことにする。以下に書くことの骨格は作り話である。しかしながら、心が揺れ動くさまは、本当の話である。
春先、ひとつのチャンスが僕に訪れた。
それは簡単に書けば、長い間夢見ていた独立起業が可能になるかもしれない、ということだった。今まで模索しても全く取っ掛かりすら見出せなかったものが、突然に開けた。
夢が、叶う。僕は狂喜し、その日から生活が一変した。一日は24時間しかないため、睡眠を削った。厳しい日々が続いたが、僕の夢を知る家族も共に喜び、助けてくれた。何より目標があるということが、多少の無理を可能にした。僕はとにかく懸命に邁進した。
だがその夢が、ある日突然に途絶えた。
遠因には震災もあったのかもしれないが、出資者が手を引いた。それも僕の力不足だったのだろう。夢は途上で潰えた。あとには、負債のようなものが残った。
僕は悔しさに打ちひしがれていたが、同時に体調がおかしくなっていくのを感じた。いや、そもそももっと以前から体調の異変はあったのだが、そんなことに関わっている余裕がなかったため、覆い隠していたと言ってもいい。それが噴出した。
胸部の臓器が痛み出した。これは以前からそうだったのだが、ここに来て酷くなってきた。加えて、どうも身体そのものの力が減じていく実感があった。だるく、すぐ疲れ、息が切れる。
これはもしかしたら病気ではないのか。癌か。
検診を受けてからもう一年近くになろうとしていた。以降、相当に不摂生を重ねた。そういうことがあったとしても、おかしくはない。
おりしも、同時期に従兄弟が癌で死んだ。僕より年下だった。日頃から健康には留意していた、と叔母から聞いたが、分かったときには末期だったらしい。痛みが出だしたらもう終わりなのよ、と叔母は泣きながら言った。幼い頃はよく遊んだ従兄弟だったので僕も悲しかったが、「痛みが出たら終わり」という言葉が強く僕に突き刺さった。
おかしなもので、それ以外にもそういう情報がやたら入ってくる。いや、これは今まで気にも留めていなかったことに過敏になっているからだろう。若くして亡くなった人の話がとにかく耳に入る。共通していることは、自覚症状があればそれは相当に進行している、ということ。
僕は病院に行くことにした。
もちろん、直ぐに疑いが晴れることを期待していた。だが医者は、少し深刻な顔をした。とにかくその場ではシロだとの診断はつかず、さらに検査を重ねた。結果が出るのは一週間後だと言う。
僕はぶっちゃけ聞いてみた。癌の可能性はあるのか、と。医者は肯定した。そして、もしもそうであれば即座に入院加療の必要がある、と。なるほどそうか。
あの時を顧みるに、自分は非常に冷静だった、とそのときは思っていた。ある程度の覚悟は出来ていたし、精神の平衡を失うようなことはなかった。だが、根のところではやはり冷静さを欠いていたのだろう。まだ結論も出ていなかったのに、俺はもう死ぬ、と思い込んだのだから。
帰宅途中、様々なことを考えた。妻には、今日病院に行くとも言っていない。おそらくは何の心配もしていないはずだろう。もちろん、それが最悪の結果であれば、告げなければならない。そのことは、気が重い。
妻との間には、子供が居ない。二人きりの生活をずっと続けている。
結婚10年目だったか。どうも子供を授かりそうにない僕らは、こんな話をしたことがある。
「私たち、死ぬときが困るね。たぶん誰も看取ってくれる人がいないから」
「それはそうやけど、おまえは困らんやろ」
「どうしてよ」
「ワシのほうが長生きするからや」
「わたし、100歳まで生きるかもよ」
「ほんならワシは101歳まで生きる。心配するな」
「そうなったらあんたのほうが心配よ。101歳の一人暮らし(笑)」
そんな軽口を叩き合って、暫らく経った。今さらあのときの約束を反故にする、とは言いたくない。
不思議と、死ぬことは怖くなかった。ただ全てが終わりになるだけ。僕自身の感覚としては、何もかもおっぽり出して逃げる、ということに近い。これが夢の途中であれば、頑強に生への未練を持っただろうが、ちょうどその時はそういう意識もなかった。 あれもしておけば良かった、これもやっておけば…ということは、きりのないこと。そしてまた、自分という人間がそんなに値打ちのあるイキモノではない、ということもよく自覚している。僕が居なくなって困るという人はそう多くないはず。運命であればそれは受け入れる。ここまでの人生は、少なくとも幸せだった。
ただ、とにかく気懸りなのは、今一緒に暮らしている人の未来。それだけだった。親や兄妹も悲しむだろうけれども、それはいたしかたない。ただ「一生食わしていくから」といって結婚したこの人のことは、どう責任をとればいいのか。それだけは辛い。僕が資産家であれば何も恐れることはないが、そうではない。生命保険も、高額なものには入っていない。いや、かつては入っていたのだが、子供が結局出来ないことを鑑みて、積立年金型のものに変更した。将来を考えてのことだったが、それが今となっては悔やまれる。
さて、どうするか。一週間後に結果が出て、それが最悪のパターンとなった場合は当然ちゃんと妻には話さなくてはいけないが、僕はその日は何も言わなかった。それまでは、笑っていてくれ。どんなときでも笑顔を絶やさないこの人の曇った顔を見るのは好きじゃない。また、無理して笑う姿も見たくない。
その日から、僕は身辺整理を始めた。
公的には、とにかく辻褄合わせに必死だったと言っていい。何事も継続していれば、見込み報告だって出来る。しかし突然それが途切れると「何月何日には可能」と言っていたことが全て嘘になる。僕が突然いなくなっても、全てがうまく回っていくようにしておかなければいけない。仮に入院したときに「あれはどうなったのか」なんて聞きに来られるのは困る。
そして、私的にはどうすればいいか。とにかく、手続き的なことを簡略に出来るように用意したいと思った。財産と言えるほどのものはないが、少しでも今後役に立つようなものは全て妻に帰するように。大げさだが、遺言書のようなものも作成した。何せ、もしかして一旦入院すればもう出てこられないかもしれないのだ。従兄弟は、そうだった。
一日、休日があった。その日は僕も妻も別々の所用があったのだが、僕はそれをキャンセルして、一人うちに居た。
我が家には、面倒臭い性格の夫がいるために、モノが多い。これらは、僕が居なくなればほとんど必要でなくなるものばかりだ。今のうちに処分してしまおうか、流行の断捨離だ、とも思ったが、そんなことは急には出来ない。僕は、机周りから整理を始めた。
別に、見られて困るものはもうない。変態趣味のDVDなどもない。押入れの中の箱のひとつに、昔の彼女との手紙などは残っているが、まあそれも愛嬌だろう。いや、やっぱり処分しておくか。そんなことをつらつら考えながらあちこち整理した。
最も見られて困るのは、PCの中身かもしれない。そう思った。特に、僕がこんなブログを書いていることは知られたくない。恥ずかしい。いざとなれば、履歴とブックマークを消せばいい。しかし、ブログは突然途切れるな。どうしようか。僕は、オンとオフに全く接点はない。
一人気の弱い後輩が居る。こいつにだけ因果を含めて打ち明けるか。で、そういう局面が来たら「もうこれで終りです」という記事を書いてアップして、全てのPC内履歴を消す。そして「死んだらあいつには連絡してくれ」と妻に言っておく。あいつはその記事に「凛太郎は逝きました」とコメントしてくれればいい。
そんなことまで真剣に考えた。
山のような書籍は、もうしょうがない。特に値打ちのあるものもないから、ブックオフに電話して引き取ってもらえばいい。あとは、音源とか。カセットテープはもうゴミだな。ビデオテープも山ほどある。もうビデオの時代も終わったな。中身はほとんどプロレスである。僕が居なくなれば、これもゴミだ。
CDなどはあまり大したものはないが、レコードはどうだろうか。もしかしたら売れるかもしれないな。オークションのやり方を教えておこうか。そんな末梢的なことまで考えた。しかしこれもよく考えたら、今はよっぽどの好事家でないと、レコードプレイヤーさえ持っていないよね。やっぱりゴミか。
ふと思いついて、プレイヤーを開けた。しばらく使っていないが、まだ現役だ。
ラックには、LPレコードがずらりと並ぶ。どれもこれも、愛着のあるものばかり。入手したときの思い出がこもる。その中に、ごく僅かだがシングルレコードがある。
ナターシャーセブンのものばかりだ。
少年の頃は、財力がない。なので、1曲あたりのコストが高いシングルにはまず手を出さない。ただナターシャだけは特別だった。
僕が生まれて初めて買ったシングルレコードは「孤独のマラソン・ランナー」。小学生だった。ナターシャに、夢中だった。
若者が走るよ 街のビルの谷間を 若者の足どりは 風を切ってゆくよ
レコードに針を下ろすという作業も、久しぶりだった。
孤独のマラソン・ランナーは、自切俳人(北山修)の作詞作曲。北山修氏の作曲というのも珍しいと思うが、これはいい曲だ。今聴き返して、しみじみそう思った。同時に、脳内が当時にフラッシュバックした。あの頃は、夢しかなかったような気がする。
その後ナターシャは「107ソングブック」という大企画を完成させ、絶頂期を迎える。「ズバリク(京都の深夜放送)」のリスナーだった僕は、宵々山コンサートにも出かけた。
ナターシャが次に仕掛けた企画は「シングル文庫」だった。その第1弾・あき「私に人生と言えるものがあるなら」の発売は中学2年。もちろん、予約して購入した。
以降、ふゆ「時には化粧を変えてごらんなさい」、はる「春を待つ少女」と続くが、ここらで主要メンバーである木田高介氏が脱退してしまう。
木田高介氏が脱退したのは、確か冬。そして春に、木田さんは衝撃的な交通事故死を遂げる。31歳。
こういう死に方というのは、あんまりじゃないかと思う。突然にぷつりと生への道を閉ざされるのは。木田さんの奥さんの嘆きはいかばかりだったか。そのあまりの悲嘆の場面を葬儀で見ていた五輪真弓が、その嘆きをもとに「恋人よ」を作ったという話がある。
こういう予期せぬ突然の死というのは、最も避けたい。これなら、まだ別れの時間をくれる病死の方がいい。この震災で亡くなった多くの人たちも、突然に命を奪われた。またナターシャ関連で言えば、マネージャーの榊原詩朗氏がそのあと、ホテルニュージャパンの火災で死去する。こういうのは、家族にも何も告げられない。
シングル文庫の第5弾・なつ「君よそよ風になれ」が木田高介氏の編曲で、遺作となった。
君のベスト・フレンドは君だから 思いどうりに生きてごらん
やりたいことに手を伸ばして 行きたい所に足を伸ばして
僕はシングル文庫では、これがいちばん好きだった。何よりシングル文庫オリジナルであるし、爽やかだ。
ナターシャは、その後徐々に活動をしなくなり、僕が大学に入る頃には活動を停止した。僕も、この世に生を受けて以来、いろんな人の音楽を聴いてきたけれども、明確に「ファン」になったのはナターシャが最初だ。シングルもアルバムも、初めて買ったミュージシャンはナターシャ。コンサートも、初めては宵々山でありナターシャが出ていたからである。
いろんなことを、思い出していた。
僕の好きだったナターシャはもういない。坂庭省吾さんも、もう亡くなって久しい。53歳、癌だった。そんなに若いのに、とあの時は思った。しかし病魔は、年齢に関係ないんだ。
シングル文庫を聴き終わって、僕は「道づれは南風」に針を下ろした。
南の風が好きだよ 涙を吹き飛ばすから
この曲を最後に、僕はナターシャのシングルを買っていない。それは、ナターシャの活動が下火になったこともあろうし、僕も高校生となって、いろんな音楽に広がりだしてナターシャ一辺倒ではいられなくなったからだろう。
ただ、この曲は好きだ。
きみはまだ眠っているだろ 安らかな窓の下で
青い絵はがき届いたら 思い出してよ僕を
僕がこの世から消えたら。誰かはふと思い出してくれるときがあるだろうか。
もしも強く思い出す人がいたとしたら、それは忘れてもらったほうがいい。強い悲しみは僕も望むところではない。ただ、記憶の片隅に留めてくれればいいんだ。で、ときどき、あんなやつが居たな、と思い出してくれればいい。
人は忘却の生き物。そんなことこちらが望まずとも、みんな忘れてゆく。それでいいのかもしれない。
光の中のかたつむり せめて夢を背負いながら
歩いてゆくよこの道を 君に逢えるまで
「光の中のかたつむり。せめて夢を背負いながら…か」
そのとき、僕の箍が外れた。
想いが、堰を切って溢れた。出てくる涙を、もう止めることは出来なかった。嗚咽が出た。誰もいないことを幸いに、ただ泣いた。
光の中のかたつむり せめて夢を背負いながら
俺だって生きてきたんだよな。小さな存在だったけれど。
毎日、世界中で溢れんばかりの数の子供達が生まれ、そして同じように人は死んでゆく。大きな歴史の流転を考えれば、一人一人の生き死になんて、ただの小さな波にすぎない。さざなみにも満たないかもしれないよ。でもその一人一人は、懸命にもがきながら生きてるんだ。小さな夢を背負いながら。
涙は、悲しみからきたのではなかった。それははっきりしていた。じゃなんだと言われたらそれはよくわからない。強いて言えば、自分の軌跡を思い出したからかもしれない。あの両親の元に生まれて、愛されて育って、旅をして、恋をして、共に歩む人と出逢って…。よく「走馬灯のように」という形容詞があるが、あれは本当なのだなと思った。自分がいちばんよく知る物語、その追憶というドラマに心が震えてしまったのだろう。
光の中のかたつむり せめて夢を背負いながら
歩いて行くよこの道を 君に会えるまで
僕は、今も生きている。こうしてブログも書いている。
幸いにして、妻に、そして多くの人に別れを告げずに済んだ。
だからと言って、別に精神的なものでもなく、疾患がないわけでは無かったが、それでも生き延びている。しかしおそらくは、まだまだ死なないだろうと思っている。
このときのことは多分にノイローゼ的なことになってしまったのだと思うが、僕としては貴重な経験だったので、備忘録的に文章にしてみた。以後、身体を大切にしていきたいと思っている。
繰り返すが、この話は虚構である。
そう書くと、大仰な話となってしまうか。災害で本当に故郷を失った方が多い中、たかが実家が引っ越したくらいでこの大そうな物申しは反省に値する。だが、気持ちとしてはそんな感じなのである。
両親は有難いことに現在のところ健在で、隣の隣の隣の県に居るために、しばしばではないが時には顔を見せることも出来る。だが、どうも「故郷に帰った」感じは全くしない。ただ両親の家に行っただけである。武田鉄矢氏が「おかあさんがふるさとそのものです」と言ってそれは一面真理であるけれども、土地勘もなく周りを見渡しても全く馴染みが無い場所は、いくら母親が居てもふるさととは呼びにくい。
僕は、京都で生まれた。そして、そこに22歳まで居た。
その頃は、故郷なんて言葉を遣う機会は全くない。当たり前のことである。離れてこそ、生まれた街が故郷となる。
ただ、あの街に居た頃は、将来的にもこの街を「ふるさと」と呼ぶことはないだろうと思っていた。「ふるさと」という言葉とイメージが異なるのである。唱歌の「うさぎ追いし彼の山 小鮒釣りし彼の川」は、かなりの数の日本人の心情を支配しているのではないだろうか。ふるさとがしばし「田舎」という言葉で置き換えられるように、ふるさとには山河があり、緑豊かで花咲きほころぶ、そういう場所でなければいけないと思っていた。
大学時代。夏を迎え「明日から田舎へ帰るよ」なんていう友人達を見て、羨ましさを感じた。自宅から自転車通学の僕には、そういう場所はない。
学校を卒業して、僕はこの生まれた街を出た。どうしても出て行きたいという願望を持っていたわけでもないが、成り行き上そうなってしまった。そして、最初に東海地方の街に居を定めた。
その街にいる間、僕は生まれた街へ一度も帰ったことがなかった。忙しかった、ということもあるし、休みがとれればその時間は旅行に使った。親不孝者、との声が聞こえてきそうだが、親が逆に独身者だった僕のところへしばしば尋ねてきていたので、ご無沙汰しているという感じも無く。20数年前は、親も若く腰が軽かったものと思える。そして、僕はまた別の街へ移れと命じられた。今度は北陸だった。
北陸に移り住んでしばらく経ったのち。僕は出張で名古屋へ向かうため、北陸本線で南下した。米原で新幹線に乗り換えるのだが、その前、列車が敦賀を過ぎて余呉へ入ろうとするとき、僕は急に胸に迫る何かを感じた。なんだか泣きそうな気持ちになった。
疲れていて、気持ちが不安定だったからだと思うが、その時僕は「この線路は京都に繋がっている」と唐突に思ってしまったのだ。はじめて「郷愁」というものを覚えた瞬間だった。望郷の念にかられたのだ。生まれた街を出て、一年半が経っていた。言ってみれば、その時に僕の中に「故郷」という存在が発生したとも言える。
そして、次に休みがとれた時、僕は「故郷」へと向かった。
駅すらが、既に懐かしく迫っていた。この日本一長いホームを持つ古い駅から、僕は何度も旅立ち、そして最後に出て行った。列車を降りて、バスに乗った。そのバスの車窓風景全てが、懐かしかった。バスを降り、実家へと繋がるひとつひとつの建物すら懐かしく思えた。
こんな話は、ずいぶん昔のこと。その、初めて故郷へ帰ったときの思い出すら、ノスタルジーの世界となってしまった感がある。しばらくして、両親は隣県へ引っ越した。いろんな理由があるのだが、とにかく生まれた街から実家がなくなった。
そうなると、僕にとって故郷はどこになるのか。もちろん、生まれた街のはずだが、そこへ行く理由が無い。親しい友人も居るには居たが、限られた休暇では、優先順位は両親となる。
したがい、生まれた街から足が遠のいた。
それから随分と時間が経過してのち、機会があり僕は京都へ久しぶりにやってきた。何年ぶりだっただろうか。
京都駅からして、とてつもない変わりようだった。なんだこの城のような駅舎は。駅前風景も、やはり変わっていた。京都タワーはあいかわらずヌボーと建っているが、それ以外のところは、ずいぶんと様変わりした。近鉄百貨店が無くなっている。
駅前の近鉄百貨店は、もっと昔は丸物百貨店だった。僕が少年の頃の話。そして、ここでラジオ番組の公開録音をしていた頃があった。近畿放送(現KBS京都)の「丸物わいわいカーニバル」。司会は若き日の鶴瓶師匠。僕も公録を見に行った。ゲストミュージシャンも、ラブウィングスやシャトレセカンドなど懐かしい名前を思い出すが、その中でもほぼレギュラー的に出演していたのが、きたむらけん(現・北村謙)率いる「ばっくすばにい」だった。
このきたむらけんというミュージシャン、関西(いや京都か)出身のある年齢層の人には、非常に知名度が高いと思う。ラジオっ子はみんな知っているはずだ。一時期はズバリク(わかりますね)のDJもやっていた。あのヤンタンにも有吉ジュンさんと共にパーソナリティとして出演していたのだから。
金・金・金曜日の担当きたむらけ~んさんは今どうしているのかと探してみたら、HPをお持ちだった。そこで、現在の活動がわかる。今も元気にバンジョー弾かれているようだが、もう還暦という情報にあっと驚く。でも考えてみたら、そうかもなあ。
けんさんのことは、以前クライマックス「花嫁」について書いたときに触れたことがある。クライマックスに所属はしていなかったのだが、エンドレスに在籍されていた。「嫁ぐ日」とけんさんのエピソードはそこで書いた。
僕は、バックステップカントリーバンドやエンドレス時代は、古すぎてあまり知らない。やはり「ばっくすばにい」からで、「私の朝」「しあわせ京都」というシングルはよく憶えている。ナマでも何度も聴いた。
その「しあわせ京都」を今聴き返すと、わいわいカーニバルの時代、つまり少年時代にすっと戻ることが出来る。この曲は、局地的だったかもしれないけれどもよく売れたのではなかったのだろうか。
ああ路面電車の窓をふいて 京の夜景を見ているあなた
そんなあなたの顔を みている私はしあわせ
この頃は、まだ路面電車が京都を走っていた。この日本初の電車として知られる京都市電は、僕が中学生のときに廃止された。モータリゼーションの波にのまれた形だが、よく京都の街にマッチしていた。今でも北大路や西大路通に市電が走っていないとなんだか違和感を感じたりするほど、身近だった。
それにしても、この「しあわせ京都」を聴いていると、やっぱり京都はブルーグラスだなとつくづく思う。京都の駅前の変貌に故郷を見失いかけたが、バンジョーやフラットマンドリンの音が聴こえると、故郷に引き戻されるように思えるほど。
ブルーグラスは、身近だった。やはりナターシャセブンが京都に居たこと、他にもカントリーの大物ミュージシャンが目白押しだったことは大きかった。同級生でもブルーグラスでバンドを組んでいたのが何人も居た。あの頃は日本屈指の底辺だったのじゃないか。
もう京都市電はとうの昔に無く。僕は、地下鉄に乗った。目指したのは、かつて実家のあった場所。
情報は、聞いていた。両親が引っ越したとたん、その場所はすぐに更地になった、と。地主はとにかく土地をなんとか活用したかったらしい。戦前から建っていた家だったもんなぁ。限界がきていたのも確かだが、そうして僕の生まれ育った家は、僕の知らぬ間になくなったらしい。
地下鉄を降りて、そのあとは歩く。歩いてみたかったのだが、下車した地下鉄駅周辺のあまりの変貌ぶりに驚く。全く違う街に来たようだ。京都という街はもう1200年も続いていて、非常に伝統を重んじるところもあるが、一面新しモノ好きである。なので、結構街の更新も激しく行われる。僕は、その数年の間についてゆけないほど変わった街を歩いた。
商店街も変わった。昔と店が違う。好きだった佃煮屋が閉めている。お茶屋さんもない。ここのおばちゃんにはずいぶんかわいがってもらったのだが。果物屋もない。和菓子屋もない。続いている店もあるが、代替わりしていたり、リニューアルしていたり。
通った小学校の前に立つ。校舎がみな建て替わっているのはしょうがないが(相当に古かったので)、植生がかわっているのには驚いた。あの藤棚は、あの桜は、あの松はどこへ行ってしまったのか。
そして、実家のあった場所へ。
見事にマンションが建ってしまっている。面影は、全く無い。ご近所さんもみな立ち退きに遭ったのか。
その時にふと浮かんだ言葉は「根無し草」だった。なんだか、寄る辺ない人間になってしまったように思えるほど、現実はショッキングであり、しばらく立ち尽くしてしまった。生まれて育った、痛切な思い出の詰まった家、今は無し。
その瞬間に、僕は故郷を失ったと言える。
つまり僕にとっての故郷とは、生まれた街を離れて一年半ほど過ぎたあの望郷の念の時に発生し、そして、生家が失われたのを確認したこの時までの、わずか10年弱くらいの間にしか存在していなかった。あくまでも、僕の中で観念的に言えば、だが。
その後は、京都は遊びにゆく街となった。再び関西に移り住んだこともあってしばしば訪れる。妻を伴うことも多い。かつて実家がこの地にあったときは、妻は京都=実家であって、舅と姑もおり、買い物をしたり墓参りに行ったりで費やされ、あちこち見て回ることはあまりなかった。妻は、結局修学旅行以来、京都をほぼ知らない。
もう今は、自由だ。観念上は僕の故郷でもなく、旅行先と思えばいい。考えてみれば、京都は屈指の観光地。しかも、土地勘があって絶対道に迷わない歴史ヲタクがあんたの配偶者だ。どんどん活用しなさい。
三年坂を手を引きのぼる清水参道 息を切らせて
あなたの腕が自然にのびて私の肩にかかります
ああ長い階段踏みしめながら ふたりの愛を誓い合います
あなたとならどんなことでも耐えて行けると
故郷を失くしたことは、寂しくないわけではない。けれども、それは観念上のことにすぎない。呪縛から逃れた、とも言える(と、強がってみる)。そして、それからさらにひと時代過ぎた。もはや自らで故郷を作り出していかねばならない世代ともなっている。別に、無理はしないけど。
LPは買っていない。松山千春は妹の担当だったから。でも、彼女が揃え始めたのが多分「起承転結II」くらいからで、そこから遡ったはずだから、僕としてはしばらくの間はエアチェックに完全に頼っていたのではなかったかなぁ。
オールナイトニッポンは月曜一部昇格時から京都でネットされるようになり、眠い目をこすりながら聴いた。チー様にはもうひとつ番組があったような気がするが(FMだったか…「空を飛ぶ鳥のように~」がタイトルバックだったような気が)、忘却の彼方だ。どこでも「よろしく哀愁!」だったのは間違いないが。
このとき、まだ僕は北海道を知らない。なので僕の知るオホーツク海は、多くはメディアからの由来である。
北海道の海の印象として、小さな頃に刷り込まれてしまった歌がある。それは北島三郎御大の「寒流」という歌で、紅白歌合戦で聴いた。「涙さえ凍る」「アザラシの群れが啼いて暮れる」というものすごく寒さを感じさせる歌で、北海道の海なんてのはとにかく寒く厳しく凍えて耐える世界である、というイメージが僕の中で出来上がった。おそらく僕がまだ10歳にならぬ頃であり、そのイメージは中学生となっても僕を支配していたように思う。そんなときに、松山千春の「オホーツクの海」がポンと僕の中に入ってきた。
静かな そして静かな オホーツクの海よ
なんと北海道の海はのどかなんだ。そう思った。
そう思うのもむべなるかな、である。素朴すぎるほど素朴なうた。衒いも何もない。
これは、デビューアルバムである「君のために作った歌」の中の1曲なのだが、このアルバム自体が、何ともシンプルでストレート。それはそうだろう。松山千春21歳のアルバムであり、北海道で純粋培養された才能をそのまま表現すれば充分に事足りた頃のはず。小細工など必要なし。松山千春の代名詞とも言える「大空と大地の中で」も入っているが、このようなうたは、齢を重ね透明感を失ってしまっては作れないうたではないかと思う。
デビューシングルの「旅立ち」、2nd「かざぐるま」、他にも名曲誉れ高い「銀の雨」など、いかにもフォークらしい(「かざぐるま」って小椋佳っぽいよね)曲もしっかりと収められているものの、「大空と~」に代表されるような、のびやかで広がりのあるうたも多い。「この道より道廻り道」「ためらい」「今日限り」そして「足寄より」、表題の「君のために作った歌」。
その中でも「オホーツクの海」は、いかにも素直だ。唱歌か、と言われればそうかもしれないとも思う。あのさぁあ、うたなんてさ、こねくりまわさないほうがいいのさ、なんて声が聞こえてきそうである。
そして、寒くない。
季節を明言しているわけではないが、オホーツクなんて春も秋も寒いだろう。なんせ流氷が接岸する海だ。そんな「涙さえ凍る」と言われた、厳しく荒涼とした印象を持っていたオホーツク海にも、花は咲く。そんな光景が見えるようなうた。
松山千春にはもちろん、北や冬を季語にしている歌がいくつもある。そりゃ北海道のひとだもの当然なのだが、そういう歌に、僕はあまり寒さを感じないのだ。最初は、それが不思議だった。
そのものズバリの「寒い夜」という歌がある。叶わぬ夢。想い伝わらぬ女に惚れて、ひとりきり。そして「黙り込めば心の底までしばれるような寒い冬」。最後は絶唱だ。辛いよね。でも、不思議と「寒い夜」の、その寒さが強く伝わってこない。これは想像だけれども、どこかに、暖炉の火があるんだ。そんな部屋の中で、俺の辛い話を聞いてくれている人がいる。だから、心が最後まで凍えてゆくことはない。
この人のうたは、そうなんだ。そんなことに、徐々に気がついてきた。
「北風の中」という歌がある。彼女と自分との意思の疎通がうまくいっていない歌。そしてタイトルどおり北風が吹いている。いかにも寒そうな歌なのだが、この歌、ちっとも寒くない。北風なんてただの比喩だぞ。この二人、別れなどするものか。
タイトルだけだと寒く感じる歌も、やさしいやわらかなメロディーとあわせて、なんとなく温かみのあるうたにしてしまう。「雪」とか「冬の星座」とか、最近では「白い雪」とか。
「雪化粧」という歌がある。この歌の出だしはマイナーキーで、冷静に聴けば結構寒い。けれども、凍えることはない。何ゆえ徹底的な寒さではないんだろうか。もうよくわからない。「冬の嵐」にも同様の印象を持つ。
もしかしたら、松山千春の歌声そのものが、温かいのかもしれない。そんなことまで最後には考えてしまう。たとえばこの歌をさだまさしが歌ったらどうだろうか。結構寒いのではないだろうか(まっさんに温かみがない、という話じゃないですよ分かってると思うけど)。
松山千春は春だろうが冬だろうが、朗々と歌う。
北海道は、寒いのが当たり前。冬は、晴れないのが日常。昔、よく泊まった北海道の民宿の親父がそう言っていた。寒いに決まってんだよ。だから、そんなこといちいち考えてられないの、と。
寒ければ、さむくないふうにすればいいだけのことじゃないか。こごえた両手に息を吹きかけて、しばれたからだをあたためて。そしてうたは、慈愛をこめて歌えばいい。風は冷たくとも、心さえあたたかければ。
そういう強い心で、うたったきた人なのだろう。
オホーツク海を最初に見たのは、21歳の夏だった(うは、チー様デビューと同じ年だな)。
初めての北海道ではない。19歳のときにすでに来ている。けれども、その時はオホーツク海をちゃんと見ていない。自転車の旅だったため、アプローチに時間がかかりすぎ、最北端宗谷岬に到達したところでUターンをせざるをえなかった。日本海沿いに帰った。
2年後にまた北海道にやってきた。今度は、フェリーで上陸したので時間もある。北上して稚内まで3日で到達した。利尻・礼文島を堪能したあと、僕は宗谷岬へと向かった。
宗谷岬にはダカーポの歌がエンドレスに流れている。このうたもまた、寒さを感じさせない。そのことが逆に、北海道に居ることを感じさせてくれた。北の果てだから寒い歌を、というのは、本州以南の発想なのだ。そして、宗谷岬を東へと回り込んだ。まだ見ぬ風景に思いを馳せながら。ここから先は、オホーツク海沿岸となる。
オホーツクは、晴れていた。
九月。季節は秋を迎えていた。海際には、木々が生えているわけではない。風が強いからだろう。無骨な海岸。けれども、植物がいないわけじゃない。ハマナスがあちこちに茂り、プチトマトのような実が生っていた。そして、リンドウやナデシコといった秋の紫色の花がささやかに咲いている。一見荒涼としながらも、力強い生の息吹はある。そして何より、広い。どこまでも広がっている。
僕は、この風景が好きになった。
静かに沈む夕日 オホーツクの海に 風は波をさそい 夕日におどるよ
実は、オホーツクに夕日はなかなか沈んでくれない。それは、地図を思い浮かべればわかるとおり、オホーツクの海は北東に位置するからである。浜頓別からは、クッチャロ湖の夕日。そして常呂栄浦からのサロマ湖への夕日。それ以外は、だいたい山へ沈んでしまう。
オホーツクへ沈む夕日が見られるのは、知床である。それ以外は、僕が知る限りではわずかに網走の能取岬しかない。あるいは、常呂東浜の漁港でも見られるだろうか。そこまではわからない。
ただ、能取岬というところは絶景の場所であり(ホントいいところ)流氷のビューポイントとしても高名だが、断崖絶壁であり「はるかな小舟に手を振れば」というのどやかな感じではないような気がする。私見だけれども「オホーツクの海」の舞台は知床に特定してもいいように思われる。
その、初めてオホーツクの海を見た旅では、沈み行く夕日までは見ることが叶わなかった。知床では、岩尾別というウトロよりまだ先にある場所の宿にいたのだが、そこは山中である。海に沈む夕日を見るには、岩尾別川を下ったところにあるサケマス孵化場から見るのが最も良いのだが、その年は熊が出没していて出入り禁止になっていた。
翌冬にも知床へ行ったが、あいにく晴れる日はなかった。以後も頻繁に北海道には訪れていたものの、オホーツクの夕日とは縁がなかった。
オホーツクに沈む夕日を初めて見たのは、それから7年も経ってからのことだった。
その年の夏、僕は知床国設野営場の一角にテントを張った。ウトロの町から少し高台に上がった丘陵地にある。キャンプ地は林の中だが、その海際にその名も「夕陽台」という展望台がしつらえてある。真下にはウトロの町、そして港とオロンコ岩。その向うにオホーツク海が広がっている。
黄昏時が近づくと、その展望台は人でいっぱいになった。快晴とはいかない空模様だったのだが、西には雲もなく、沈む夕日はしっかりとオホーツク海を朱に染めた。
海はきわめて静か。波打ち際から見たわけではなく、その部分情緒に欠けたきらいはあったが、夕日は十二分に美しく、堪能した。
その年は、いいことばかりじゃなかった。疲れていた。休暇で北海道に逃げ出しては来たものの、なかなか気分が晴れなかった。けれども、この夕日で何かひとつ昇華したような感じもした。
「こけたら立ち上がればいいんだから」
その言葉が、なんだか沁みた。
松山千春は、オールナイトの最終回で我々リスナーに向かってそう言ってくれた。ただ録音もせず記憶なので、正確な言葉がそうだったかは自信が無い。その最終回も、月曜一部のラストだったか、火曜のラストだったかの記憶も茫洋としている。
番組の最後に、松山千春は訥々と我々に話をした。後ろにかかっていた曲は「大空と大地の中で」だったか「生きがい」だったか。午前三時前だから、僕も朦朧としていた。ただ、千春が我々に送ったそのエールだけは、強く心に残っている。
そうなんだよ。転んだら立ち直ればいいだけ。こんな単純なことに何故いつも気がつかないでいるんだろう。
そうして、以来ことあるごとにこの言葉を思い出す。こけたら立ち上がればいいんだよ。
その旅では、知床のあとに足寄町にも立ち寄った。かつて自治体として日本最大の面積を誇り、高山市や静岡市が合併によって巨大化してもまだ日本一大きな「町」は譲っていない足寄町。
その広大な町域には、北海道三大秘湖のひとつである「オンネトー」をはじめ、自然豊かな風景を抱えるが、足寄の町にはとりたてての観光スポットはなく、人はみな「松山千春生誕地」として捉えている。似顔絵を大きく掲げた生家が今も建つ。記念撮影をする人でごったがえしている。ここで「野に育つ花ならば力の限り生きてやれ」とデビュー以来繰り返し続ける松山千春は生まれた。
北海道を愛した人なのだなと改めて思う。人生きれい事だけではすまないけれども、吹きすさぶ風も積もる雪も押し寄せる流氷も、みなあたりまえのように受け止めないと生きていくことが困難な地にあって、その大地にやさしさもあたたかさも見出していた。
はるかな汐さい 耳にすれば 忘れた何かを 思い出す
静かな そして静かな オホーツクの海よ
その旅では鬱屈した心も晴れ、莞爾として住む町に帰った。
こけても立ち上がれるかどうか最近は不安に思うことも多くなったが、力の限りやれば何とかなるような気もしている。チー様の効能は、まだ続いていると思いたい。
子供の頃は楽しい時間が過ぎてゆくことへの愁いが原因であっただろう。長じれば自分が季節に取り残されることの哀しさを知ることになったからだろう。そして今となれば、自分の残り時間の少なさへの焦燥が浮き上がるからかもしれない。時間は永遠だが、ひとは永遠ではない。そのことを知ってしまうと、ゆく季節がいとおしくてたまらなくなる。お願いだから、俺を置き去りにしないでくれ。
詩人が四季の移ろいを歌うのは、必然なのだろう。
松任谷由実という人は、当世で最も人口に膾炙している詩人だと思うけれども、この人もよく季節を綴る。季節と、空模様と、人の心をいつも見ている人。みんな安定しない。
ところで、ユーミンと言えば冬だと言う人が多い。最も売れたシングルが「真夏の夜の夢」であるにもかかわらず。なんでだろうかと思う。
イメージは、わかる。ゲレンデでいつも流れているのはユーミン。広瀬香美が出てくる前は独壇場だったか。映画「私をスキーに連れてって」そして「恋人はサンタクロース」。苗場プリンスのライブ。ダイヤモンドダスト。スキー天国。ブリザード。
けれども、冬の苗場に対して夏の逗子マリーナのコンサートもずっと続いている。夏の歌も多い。もしかしたら「夏のサザン・冬のユーミン」が対句になってしまったからか。
よくわからないようでいて、これには単純な回答がある。それはもちろん、ずっとアルバムを冬に向けて発売していたからだということ。
7枚目の「OLIVE」は夏、8枚目の「悲しいほどお天気」は冬、というように、ユーミンはかつて、だいたい一年に2枚アルバムを製作し、一部例外を除いて夏と冬に向けてリリースしていた。それを、一年に一度、クリスマス(と冬期ボーナス)に向けて年末にリリースとすることにしたのは、15枚目の「VOYAGER」からである。僕は高校を卒業しようとしていた。
収録されている「ハートブレイク」のPVをTVで見て、18歳の僕はあらためてびっくりしていた。ユーミンてこういう人になっちゃったのだな、と。もちろん悪い意味で言っているわけではないことはわかっていただけると思うけれども。
それはともかく「VOYAGER」以降、20世紀の間じゅうユーミンはずっと冬リリースを続けた。それは、完全定着した。ユーミンはアルバムの人で、シングルなどこの頃数えるほどしか出していない。以降アルバムはずっとミリオンセラー。誰しもが、買った。僕ですら買った。そして、繰り返し聴いた。多分ユーミンのアルバムで僕が最も繰り返し聴いたのは、「DA・DI・DA」だろう。20歳だった。
社会人になったその年の晩秋。いきなり北陸赴任を命ぜられた。かの地は、もう11月末には初雪が降る。車で駆けずり回る機会が多かったのだが、その年の3月に京都で免許をとったばかりの僕は、雪道など全く経験がなかった。ひたすら怖かった。日の暮れた雪道は、徐々に凍り始める。高岡から金沢へ向かう国道8号線。肩に力が入って疲れた僕は、小矢部という町で小休止した。これから峠を越えなければならない。ふと車を止めたレコード屋で、「Delight Slight Light KISS」を買ったことを今でも憶えている。
どうして どうして僕たちは出逢ってしまったのだろう こわれるほど抱きしめた
「リフレインが叫んでる」を聴くと今でも僕は夜に降り積む雪と、焦燥そして孤独を思い出す。冬のイメージもまたむべなるかな、である。
けれども、僕はユーミンにはまた違うイメージも持っている。それは、荒井由実のぬぐい難き鮮烈な印象。
冬の印象が強いといっても、詩人のユーミンは春夏秋冬雪月花を自在に表現する。
「真夏の夜の夢」が最も売れた曲であるなら、ユーミンが自ら、私の代表曲はこれ、と表明していたのは「春よ、来い」。そのとおり認知度は非常に高い。
淡き光立つ俄雨 いとし面影の沈丁花 溢るる涙の蕾から ひとつ ひとつ香り始める
これを聴くたびに思うのである。なんと細やかに巧みに作られているうたであるか、と。強い郷愁を感じさせる旋律と、いくらでも深読みできる詩。どこまでも丁寧に編まれている。
これを「技巧の極み」と表現してしまえば、あちこちからお叱りが来るに違いない。「精緻な計算を施し」と書けば、もっとお叱りが来るに違いない。「オマエ何様だ」「何故いい曲を素直に受け止められないのだ」と。すいません。僕もそんな生意気なことを言うつもりはなかったので、この話は一旦引っ込める。
ともかく、春のうたとしてはキャンディーズや芳恵ちゃんと並んで定番だろう(世代的に)。そういえば、赤いスイ-トピ-を作ったのもユーミンだった。
そんなユーミンを、松任谷由実ではなく「荒井由実」と置き換えたとたん、季節は夏が終わり秋へと向かう、寂しくもの悲しい情景に僕は誘導されていってしまう。
荒井由実と言えば、「中央フリーウェイ」でも「卒業写真」でもなく「ひこうき雲」だろうと勝手に思っている。
白い坂道が空まで続いていた ゆらゆらかげろうが あの子を包む
夭逝したかのひとへの思いが主題となるこのうたは、後にどれだけ腕が研ぎ澄まされてもなかなか凌駕する曲を作るのは難しいことだと思われる。このうたを10代で書いたということにはまず驚くが、もしかしたら10代だからこそ書けたのかもしれない。もちろん、ユーミンだから、という前提がつくが。
その陽炎が燃える、空まで続く坂道。空を翔る命とともに、夏もまた終わる。
ユーミンには、その夏の終わりから秋にかけてのうたがいくつもある。「9月には帰らない」「9月の蝉しぐれ」といったそのものの曲もあるが、荒井由実時代のものはまたひと際映える。「晩夏」。「避暑地の出来事」。「旅立つ秋」。そして「さざ波」。
その中でも、僕の思う秋の荒井由実を決定付けているのは、「雨の街を」である。デビューアルバム「ひこうき雲」所収。
ピアノソロのイントロダクション。奇跡の旋律。このみずみずしさはいったいなんだろうか。
感性がきらきらと溢れ出しているように僕には聴こえる。積み上げたものでもなく重ね凝らせたものでもなく、ただこぼれ落ちているようだ。研磨を必要としない、原石がそのままでダイヤモンドであったかのような。
夜明けの雨はミルク色 静かな街にささやきながら降りて来る妖精たちよ
都市伝説かもしれないが、この鮮烈なメロディをユーミンは遥か少女の頃にもう完成させていたという話がある。レコード化したのが19歳だったというだけで、実際書いたのは中学の時だったとも。本当かどうかは知らないけれども、ユーミンならさもありなんと思える。wikipediaを見ればユーミンは15歳でソングライターとしてデビューしている。谷山浩子もそうだったが、恐ろしいほど早熟だったようだ。
ユーミンと空模様の関係だけでおそらく論文のひとつやふたつは既に発表されているのじゃないかと思うけれども、よく雨が降る。荒井由実時代も本当に雨が降りそぼっている。名曲「ベルベット・イースター」をはじめ、「12月の雨」「天気雨」「雨のステイション」「たぶんあなたはむかえに来ない」「Good luck and Good bye」そして「冷たい雨」「青い傘」「白いくつ下は似合わない」「『いちご白書』をもう一度」「霧雨の朝突然に…」。
きりがない。それらのうたの中では本当に様々な雨が降っているけれども、ここでは「ミルク色」の雨だ。雲がそのままおりてきたような細やかな水滴の描写だろうか。霧雨なのか靄なのか。空気がたっぷりと水分を含み飽和状態になっているのが感じ取れ、情景に量感が生じる。
絵画的なのかな、とも思う。多摩美で日本画を学んでいたユーミンである。しかしそれも一面でしかないかもしれない。時として水墨画であったり、点描であったりするが、また画素数の高い鮮やかなフォトグラフであったりもする。絵画であっても写真であっても、いずれにせよユーミンのうたには映像が浮かぶ。
庭に咲いてるコスモスに口づけをして 垣根の木戸の鍵をあけ表に出たら
ユーミンのピアノの後ろから、遠慮がちにバンドの音が寄り添ってくる。キャラメル・ママの面々。後のティン・パン・アレー。天才少女の下に集いし四銃士。
探したら、ニコ動だけれどお宝映像があった。これはすごい。ティン・パン・アレーがバッキングをしている。ドラムの林立夫、キーボードの松任谷正隆、ベースの細野晴臣、ギターの鈴木茂。こんなバンドが存在したことに驚く若い人もいるかもしれない。
いつか眠い目をさましこんな朝が来てたら どこまでも遠いところへ歩いてゆけそうよ
聴いた人の心に必ず残像が刻まれる。それは、時として胸を痛くさせるほど。こんな曲が世に出てきたと知った、当時音楽で生活していた人は、みな震えがとまらなかったのではないか。
僕も、この曲を初めて聴いたときからもう何十年も経つが、その古い記憶は心地よい呪縛であり、今もまた鮮烈である。俺はこんなに変わってしまったのに、と思えば、いきなり少年の頃に引き戻してくれる力も秘めている。僕の中では、間違いなくユーミンのNo.1ソングとして君臨している。
誰かやさしくわたしの肩を抱いてくれたら どこまでも遠いところへ歩いてゆけそう
秋の長雨にふさわしい。今も、窓の外はミルク色の霧雨が静かに降っている。そうして徐々に、秋は深まってゆく。
少年時代は、8月31日は夏休みの終わる日だった。東北や北海道以外ではだいたいそうだったのではないか。7月後半から約40日ほどの、あの特別な黄金の日々の終焉。
夏休みは、思い出が濃い。思い切り遊び、いろんなことを体験し、学び、心の奥に刻まれていくあれこれ。
そんなこんなが、8月31日で終わる。
少年の頃は、たいていは宿題に追われている。行く夏を惜しみ思い出を反芻しつつ、休みが終わる。中学生にもなると宿題をどのように誤魔化して提出を引き伸ばすか、なんてことばかり考えたり、高校生だともう宿題なんか記憶にはないが、その年代ごとに、それぞれの夏の終わりがあった。
8月31日が普通の夏の日になったのは、いつだっただろうか。
さまざまな思いはともかく、日付的には、大学2年の夏までだった。なんでそうはっきりしているのかと言えば、無粋な話だが大学の前期試験の日程による。大学の夏休みというのは2ヶ月近くあるのだが、それまでは試験の日程が夏休み後に組まれていた。したがって、7月の頭から大学は夏期休暇に入り、8月をずっと休み、9月に入ったら前期試験。確か夏期休暇自体は9月10日くらいまであったと思うが、いきなり試験が始まるため9月に入ったらもう遊びの雰囲気は失われてしまった。
この日程が、大学3年で変わる。7月中に前期試験を終えてしまい、その後に夏期休暇になった。楽あれば苦あり、から苦あれば楽ありパターン。したがい、夏期休暇は7月末から9月の20日前後くらいにずれた。なので大学3年の夏は、9月を過ぎてもずっと北海道をプラプラと旅行していた。もう試験は終わっているため、戻って勉強しなくとも良い。それをいいことに、大学の講義が既に始まっても僕はまだ旅の空の下に居たのではなかったか。
以降、8月31日は公的には普通の日になった。社会人になれば、ただの流れてゆく一日だ。
けれども、この歳になってもこの日は何だかちょっとした郷愁を覚えてしまう。それは、少年時代の刷り込みなのだろうか。夏が往く。この暑くてたまらん夏も、僕にとっては惜しむべき対象となる。秋はなんとなく、さびしい。
サザンオールスターズの「KAMAKURA」が発売されたのは、大学2年だった1985年の9月。ちょうど僕にとって「最後の8月31日」のすぐ後に出たため、何だか夏の終わりの象徴のようなアルバムに思えて仕方がない。
「KAMAKURA」。名盤の誉れ高い。
僕らの世代だともうサザンオールスターズというのは、わざわざ避けて通らない限りもう無意識下で自然と流れてしまう、そういう存在ではないか。浸透度が圧倒的。音楽が好きとか嫌いとか、そういうのを超えてしまっていると思われる。デビューが1978年だから、ちょうど「ニューミュージック」という得体の知れない音楽ジャンルがマスコミを席巻した頃。前年にアリスの「冬の稲妻」が出て、原田真二、世良公則、渡辺真知子がデビュー。ニューミュージックという名称はともかく、確かに新しいムーブメントがあった。私事だが深夜放送小僧だった僕は、この年にようやくギターを手に入れる。中学一年生。音楽にのめりこみだす頃。
同世代であれば絶対にわかってもらえる「勝手にシンドバット」の衝撃。あれは凄い歌であるということに異論を持つ人は少なかろう。以来サザンは、ずっと一線に居続けることになる。ニューミュージックなんて言葉が廃り、音楽シーンでは様々な栄枯盛衰があったのだが、サザンだけはずっと君臨し続けている。サザンが活動停止しても、桑田佳祐居る限りそれは君臨しているのと同じ。
そのサザンの8枚目のアルバムで、満を持した2枚組という「KAMAKURA」。このアルバムは、みんな聴いたんじゃないのか。
そのアルバム「KAMAKURA」を、実は僕は購入していない。実家に居た頃は、妹が持っていた。相当なファンだった彼女がサザンのアルバムを全て揃えていた。そうなれば、僕は所持する必要がなくなる。社会人となり独立したときは手元にサザンが無い状態がしばらく続いたが、後に所帯を持った相手がサザンのファンクラブ会員歴の長い女だった。なので、積極的に聴こうという姿勢は持たずとも結局全てのアルバムを繰り返し聴いている。だけでなく、今まで最もライブに行った回数の多いミュージシャンは、サザンである。これを言うと意外に思われるのだが、そういう家族事情がある。
「KAMAKURA」は、発売した年の秋には、実家でエンドレスのように流れていた。
おかげで、刷り込まれてしまった。
しかし、刷り込まれて良かったと思う。
「Computer Children」「真昼の情景」「古戦場で濡れん坊は昭和のHero」「死体置場でロマンスを」「顔」「怪物君の空」「Happy Birthday」…このラインナップは本当にすさまじく質が高い。遠い目の「星空のビリーホリディ」。洒落た「Long-haired Lady」。かわいい「鎌倉物語」。何とも興味深い「吉田拓郎の唄」。
シングルも「Bye Bye My Love」というサザン一流の疾走感を伴う名曲が収録されている。僕はサザンのシングルでは「Tarako」が一番好きだが、「Bye Bye My Love」もいい。「ミスブランニューデイ」「Tarako」「Bye Bye My Love」までの流れは、黄金期だなと個人的に思う。
話がそれたが「KAMAKURA」恐るべき完成度の高さと言っていいと思われる。サザンはこのアルバムのあと、ハラ坊の産休などもあって3年間活動を停止するが、その前に全ての力を投じたかのような濃密さだと言える。
その中の一曲に、夕陽に別れを告げてがある。
遠く離れてHigh-School 揺れる想い出 心にしみる夏の日
恋人の居場所も今は知らない 毎日変わる波のよう
この曲は、誤解を恐れずに言えば、「KAMAKURA」の全20曲の中では陳腐な部類に入ってしまうかもしれない。少なくとも、誰にでも平均的に良さがわかる曲だろう。
そして、僕の耳にも残って離れない。
詩から考えて、黄金色した夏の日々を過ぎ去った思い出として回顧している青年。それはもちろん、桑田さん自身の鎌倉学園高校時代に対する郷愁を投影しているに違いない。
色褪せた校舎に別れを告げる 鎌倉の陽よ サヨナラ
独り身の辛さを音楽に託して お互いに笑いあえる
なんかね、じーんとくるのだよ、昔から。そうやって、僕達も卒業してきたんだ。そして、あの夏の日々は永遠に忘れない。仮に、昨日のことですら忘却の彼方に押し流されてしまうほど耄碌しても、あの還らぬ日々のことはずっと記憶に留めておきたい。
夏の終わりには、いろんな追憶がよみがえる。
海。プール。水鉄砲。親戚の子。真っ黒に焼けた肌。スイカ。昆虫採集。盆踊り。肝試し。夏の大三角形。入道雲。夕立。蝉時雨。部活と汗。鈍行列車。田舎のバス停。陽炎。麦藁帽子の少女。キャンプ。カキ氷。ただ椅子を並べるバイト。祭囃子。花火大会。彼女の浴衣。夕焼け。見つめていただけの恋。遠かった夢。
She was in love with me one day, oh yeah 涙がこぼれちゃう
あれからどれだけ経っただろう。8月31日になると、いろんなことが思い出される。夏が終わる日。
五月雨は緑色 悲しくさせたよ一人の午後は
村下孝蔵は、遅咲きだった。この「初恋」は30歳のときの曲。オリコンチャートを駆け上がり、誰もが知る大ヒット曲となった。
好きだよと言えずに初恋は 振り子細工の心
放課後の校庭を走る君がいた 遠くで僕はいつでも君を探してた
「初恋」がヒットするのと時を同じくして村下孝蔵は肝炎を病み、メディアに姿を現すことが出来なかった。残念なことだったと本当に思う。当時、フォークシンガーにはTVに出ない人も多くいたが、村下さんはそうじゃなかっただろう。それ以前にも夜ヒットだったかは忘れたが出演していたし、またそれ以上にファンを大切に思っていた人だったから。惜しいことだった。
村下孝蔵は熊本水俣に生まれた。水泳選手として大会優勝経験も持ち、高校卒業と同時に実業団入り(新日鐵)。しかし芽が出ず退社、実家が広島に越していたため村下孝蔵も広島へ移り住むことになる。
僕はずっと長いこと、村下孝蔵は広島の人だと思っていた。広島フォーク村に居たことはよく知られていたし、後述するが「松山行きフェリー」が僕にとってあまりにも印象が強かったから。だが、実際は広島には19歳のときにやってきている。
もうこの頃自主制作レコードを出している。そしてヤマハにピアノ調律師として在籍しながら音楽活動を続け、デビューのチャンスを掴んだのは27歳のときだった。だから、村下孝蔵のプロ歌手としての歴史は、20年に満たない。
村下孝蔵がいいのは、その紡がれる叙情的な旋律もさることながら、その精緻に綴られた言葉の数々。
長い壁には落書き 頭を垂れ黙り込む空に花吹雪美しく
はらり風に舞った されど寂しき鐘の音が鳴る その紅きくちびるよ (花ざかり)
指切りしてさよならを言った遠い夕暮れに 綿毛の雲が流れた夏の日 覚えていますか
明日もきっと晴れるはずとみんな信じていた …追いかけていた小さな影に今も届かない (かげふみ)
白い壁を染めて草笛が響く丘 菜の花とそして夕月
切れた鼻緒 帰り道の少女が一人 灯りが恋しくて震えてた
あはれ 恋も知らないで睫毛濡らした少女は 悲しき夕焼けの幻か (少女)
完璧な詩人だろ、この人。曲がなくても遜色なく成り立ってる。
そして、何とも声がいい。
歌のうまさというものは相対的な部分もあり、楽曲によっても異なる。声楽における巧さと浪曲における巧さは違うだろう。そういうことを踏まえつつ、村下孝蔵は歌がうまい。さらに声の響きが実に心地いい。この声の心地よさは、小椋佳、さとう宗幸、大塚博堂と並んで僕の中では四天王。
「松山行きフェリー」という曲は、村下孝蔵のデビューシングル「月あかり」のB面であり、デビューアルバム「汽笛がきこえる街」の第一曲目に採用されている。それに、それ以前の自主制作アルバム「それぞれの風」の掉尾を飾る曲ともなっている。
村下孝蔵の代表曲が「初恋」であることに異論はない。ある一定の年齢以上であれば誰もが知っている曲。そして初期の「初恋」を中核とした「春雨」「ゆうこ」「踊り子」などの一群の曲の認知度は高く、ある意味村下孝蔵の黄金期であったとも言える。
そして後期を象徴する曲はアニメ「めぞん一刻」の主題歌となった「陽だまり」だと考えてもいい。この曲によって村下孝蔵を知りファンとなった若い世代もいる。
そうした表立って知られている村下孝蔵の曲たちに対し、「松山行きフェリー」は、もう一面において村下孝蔵を代表する曲だとずっと思っていた。裏の代表作とも言えばいいのか。村下孝蔵自身も、「ロマンスカー」などと並んで思い入れの深い曲であると発言している。だが、ファンの支持は集めてもあまり一般的な認知度は高くない。シングルになっていないので仕方の無いことではあるのだが。
こんなにつらい別れの時が 来るのを知っていたら
君を愛さず友達のままで 僕は送りたかった
なんともせつない。こんなにポップなメロディーなのにどうしてこう哀しいのか。
僕は、全くのところこういう旋律に弱い。何かが揺り動かされてしまう。Without Youに似ているが。
村下孝蔵ホームページの目次から「歴史館」→「村下孝蔵/傷心の旅」と進む。すると、エッセイが出てくる。ご本人が書かれたものかどうかはわからないが、内容から考えても村下孝蔵さん自身だろう。
そこに、
傷心の旅と、ある。このうたは、つまり実体験に基づいて書かれている。
あの日は「松山行きフェリー」(当時の歌詞は今とは違う)を書いて一年後、3月28日だった。
まだ、あの人を諦め切れないぼくは、あの人のいる松山へ向かった。おそらく、その日が最後になることを予期しながらも。(以下略)
これを読んで、ああ、別れは春だったのだなとあらためて思った。僕は、このうたを始めて知ったときと、また曲調の爽やかさから勝手に夏だと思い込んでいた。そうだな。別れの季節は、春だった。
港に沈む夕陽がとても悲しく見えるのは すべてを乗せた船が遠く消えるから
村下孝蔵という人は、前述したがとても精緻な詩でうたを提示してこられる。それが天賦の才能なのか、それとも努力の賜物であるのかそれはわからない。一切外国の言葉は使わず日本語だけで編み上げてくる。
ところがこの「松山行きフェリー」には、そういう文学的な側面は影を潜めているようにも思う。これは僕だけがそう思っていることかもしれないので異論はあっていいと思うけれども、とても言葉がストレートに感じる。
思うに、このうたは飾れなかったのかな、とも考える。あの日の想いが強すぎるのかもしれない。また飾る必要も、ない。確かにへんな衒いなど邪魔だ。素直な吐露が、強く胸に迫ってくる。
だが、これもまた術中にはまっているのかもしれない、とは思う。前の引用にある「当時の歌詞は今とは違う」という言葉。
「松山行きフェリー」の詩には、変遷があるのだ。
何度、改稿を重ねたのか、それはわからない。だが、僕らがわかる範囲で一度、歌詞はかわっている。メジャーデビュー以前の自主制作盤「それぞれの風」に収められている「松山行きフェリー」の歌詞と、デビュー以後のものは、異なっている。
インディーズ盤である「それぞれの風」は当然ながら入手困難であろうと思われるので(僕もちゃんと持っていない。一部ダビングを繰り返されたカセットテープの音源のみ)、ちょっとここに提示しておいた。
これをみると、単に言葉の調整だけではないことがわかる。
「それぞれの風」盤のほうが、強気にも見える。少なくとも、自分よりも彼女の方を気遣っている。そして「僕がいなくても」君は大丈夫さ。発展的な別れにも、見ようと思えば見られる。
しかし、メジャー盤はがらりと変わる。強い悲しみ。
別れを切り出したのは彼女だったことがわかる。その原因は、もしかしたら村下孝蔵のデビューにあったのかもしれない。ピアノ調律師のままの地道な暮らしを選んでいれば、彼女はついてきてくれたのかもしれない。けれども「そんな事など今の僕に出来はしない」のだ。
想像でしかないけれども、「それぞれ」盤のときは、村下孝蔵は本当にそんな発展的な別れだと思っていたのかもしれない。いや、思い込もうとしていたのかもしれない。そうでなければ、男は別れの悲しみに耐えることが難しい。
しかし、エッセイに書かれているように、一年後「既に婚約している」彼女と逢い、想いが噴出してしまったのかもしれないな、とこっそり思ってみる。
「貴女を乗せた船が遠く消えるから」が「すべてを乗せた船が遠く消えるから」に替わるとき。つまり貴女は僕のすべてだったのだ。そして、港に沈む綺麗な夕陽は悲しみに染まる。
先ほど「文学的ではない」と書いたことを訂正したい。異論は僕自身から出た。言葉は確かにストレートだが、その「想い」を伝えるにはそれが最上の言葉だったのだ。
しばらく前の話だが、高浜の松山港に立ち寄ったことがある。その時は自動車で旅行中であり、ちょっとのぞいてみたくなったのだ。そしてここが「松山行きフェリー」の着岸する港か、と感慨を覚えた。
広島の宇品港には、実は二十歳の時に行ったことがある。そのときは、別府から船で着いた。でもその時僕はまだ「松山行きフェリー」といううたを知らなかった。だから、残念ながら思いに浸ることは出来ずじまい。再訪したいと願っているがまだその機会を得られずにいる。
村下孝蔵さんが亡くなったのは46歳。そして、今年(2011年)とうとう僕もその年齢になった。
村下さんは学生の頃は水泳選手であり、おそらく丈夫な身体を持たれていたのだと思われる。しかし肝炎を病んでしまった。だがそんなこともあってか、体調には人一倍気を遣われていた、との話も聞く。
その村下さんは、あっという間に逝ってしまわれた。死因は脳内出血。リハーサル中に突然「体調がおかしい」と感じられて病院へ。そのまま昏睡状態となり、4日後に死去。
死は、突然にやってくる。しかしこれでは、あまりにも猶予が無い。
僕も、昨年あたりから死を強く意識するようになった。昔は「オレだけは大丈夫」と思い込んでいたし、自負もあった。けれども今はそんなことは微塵も思ってはいない。明日はどうなるかはわからない。村下孝蔵さんもそうだった。
もちろん覚悟なんて全くできないが…村下孝蔵さんはそのときどう思ったのだろう。そんなことを考えるゆとりも無かったのかもしれない。しかし、無念だっただろうことは想像できる。志半ばであったことは間違いない。我々も、今思い返しても無念だ。
でも、村下孝蔵さんはこんなにも惜しまれている。沢田聖子女史のこのうたを聴くと、本当に胸が詰まる。そして志半ばだったとしても、それまでに成し遂げたことは、あまりにも大きい。死後も、若いファンが増え続けていると聞く。
そんなことは、僕らには出来ない。何も成し遂げたものもなく、惜しまれることもおそらく、ない。けれども、遥かなる巨人として、村下孝蔵さんを見上げていきたい、とは思う。
何を書いているのかわからなくなったが、着地点が見つけられないのでこのへんで。
その中に「あなたにとっての青春ソングは?」という設問があった。もうこの「青春ソング」という言葉に強烈な違和感を持っている僕は、即座に回答を止め用紙をゴミ箱に投入しようと思ったが謝礼が出るかもしれないと思うと浅ましくもとどまった。
ここしばらく、この「青春ソング」という言葉が懐メロと同義に使用されている。
「懐メロ」という言葉も失礼な言葉だとは思うのだがそれは措いて、以前は(僕が子供の頃は)TV番組で「懐メロ大全集」なんて番組がチラホラあったものだ。出てくる方は田端義夫とか春日八郎とか三橋美智也とか。視聴者層がわかる。そういった類いの番組は今も存在するのだが、登場するうたが演歌ではなくフォークになってきている。うーむ。時代はそこまで来たのか。団塊の世代ターゲットであることはわかるのだが、さすがに「懐メロ」とは言えないのか「青春ソング」という言葉で代替している。ランキング形式にすると、たいていは「なごり雪」か「神田川」が一位になる。
僕は、フォークソングなんか全然懐かしくはない。
もちろん世代が違うということが一番の要因だろうが、もうひとつは「フォークソングが今も好き」ということが大きい。したがって、聴き続けている。昨日も今日も聴いている。こういうふうにしていると懐かしくはならない。
懐かしく思うためには、一旦それと離れなければならないのではないか。時間の経過とともに追憶の海に沈める。そこから、何かのきっかけでそれを浮き上がらせる作業をする、その過程を人は「懐かしい」と呼ぶのではないだろうか。
で、青春ソングなのだが、その言葉の気持ち悪さはさておき、「青春を感じさせるうた」ということを考えると、僕にとってはふたパターンの回答が考えられてしまう。
それは、とにもかくにも自分にとって「青春」の頃を素直に思い出す曲。そして、それに懐かしさを加味するとすれば、ある程度時間に空白が生じてしまっている曲。
そうなると、僕にとっての青春の曲とは、こんなのとかこんなのとか松山隆弘さんの歌とか、そういう系統になってしまう。こういう曲は僕にとっては「青春どストライク」なのだが、知っている人が少なすぎるので困る。しかし懐かしさも加味するならば、ある程度の時間の空白が必要であり、簡単にメディアから流れてくる曲(神田川、なごり雪etc.)は懐かしさの対象にはなかなかなりにくいのである。
もうひとつは「青春」という言葉から連想される曲。青春というイメージを内包した曲を挙げてみようとする。
青春を冠する曲は数多くある。例えば森田公一の「青春時代」。岡田奈々「青春の坂道」。チューリップの「青春の影」。「青春アミーゴ」。
そりゃみんないいうただけど、何か違うな。
人によっては、例えば金八先生の「贈る言葉」なんかを思い出す人がいるかもしれない。僕は金曜8時はプロレスを観ていたので金八っつぁんに何の思い入れもないけれども、その路線はアリかもしれないと思う。
僕は、自分が思春期を迎えてのちはほとんどテレビドラマを観なくなって、金八っつぁんとかイソップとかそういうものには縁がないが、それ以前はよく観ていた。森田健作とかね。まだ子供だった僕は盛大にあこがれ、大きくなったらあんな青春を送りたいと切に願ったものだ。その象徴のような曲が「青春の旅」。ドラマ「飛び出せ!青春」の挿入歌。
昨日の夢に住んでいられずに 明日の愛をもう待ちきれずに
それから10年くらい経って自分が高校生となるが、現実はなかなかドラマのようにはいかない。あこがれは、あこがれ。
結局僕はアンケートには深く考えることはやめて、都倉俊一の「メッセージ」と書き込んだ。
思春期の入り口を中学生くらいだと考えれば、ちょうどこの曲くらいが妥当か、と思った。この曲は、確かに懐かしい。NHK「レッツゴーヤング」のエンディングテーマだった。
五月の光とそよ風とやさしい心 それからあなたの涙
レッツゴーヤングは日曜の午後6時からのオンエアなので、MBSの「ヤング・おー!おー!」とカブる。僕は基本的にはヤングおーおーを観ていたはずなのだが、都倉俊一が司会をしていた2年間はレッツゴーヤングを観ている。なんでかな。それ以前の鈴木ヒロミツ時代、そして後の平尾昌晃時代はほぼ観ていない。別に都倉俊一のファンであったはずもなく、不思議だなと自分でも思う。
「メッセージ」は、僕はレコードを購入していない。子供だもん。テレビからカセットに録音したものが僕の唯一の音源。
しかしありがたい時代になったもので、探したら出てきた。→youtube
これを聴かせていただいて「あれ?」と思った。歌詞が違う。「涙がひと粒あればいいあなたの頬に…」これは聴いたことがない。そうか。EDは2コーラス目を使用していたのか。知らなかった。
貼ってばかりで申し訳ないが、EDバージョンもあった。僕が知っているのはこれだ。
共に司会をしていたキャンディーズ。スーちゃんの訃報からまだそれほど日が経たないので、ちょっと切ない。
愛された想いがあれば 明日からも生きられる
OPもあった。これも懐かしいなあ。
サンデーズもいた。狩人、太川陽介、川崎麻世、黒沢浩(キャロライン洋子の兄ちゃん)、未都由。未都由はその後どうしたんだろうな。me&you。そののちにキャンディーズが降板し、五十嵐夕紀、香坂みゆき、天馬ルミ子が入ってくる。天馬ルミ子さんなんかは僕とあまり歳が違わず、え、この歳でもうデビューかよと驚いた。僕なんかとは比べものにならないくらい大人に見えた。今はどうしているのかな、と思って検索してみたらブログがあった。うわー妖艶!
都倉俊一という人は、もちろんピンクレディーや山口百恵で大儲けをしたはずの人であり、ちょっとした色男なので、もちろんいいイメージは持っていない(わはは)。ただ、作曲家として「ジョニーへの伝言」を書いた人であることは知っている。あれは大好きな歌だ。
当時は、作曲家が歌をうたうことはよくあったような。平尾昌晃、森田公一、中村泰士ら。もちろん平尾昌晃はそもそもが歌手であり、このカテゴリには宇崎竜童や井上大輔を加えてもいいのかもしれない。
都倉俊一は、どっちなんだろうか。歌手から出発した人なのか、作曲家の余技でうたっているのか。その経歴を見ようと思ってHPを覗いた。
「四歳よりバイオリンを始め、小学校、高等学校を過ごしたドイツに於いて基本的な音楽教育を受ける。のち、独学で作曲法を学び、学習院大学在学中に作曲家としてデビュー。」
なるほど。なんとも都倉俊一っぽい経歴だ。エリートと言おうか。そういえば、お父さんが外交官だったと聞いたことがある。この経歴を見れば、これは作曲家の余技だ。
ただ、念のためというわけではないがWikipediaも見てみた。さすれば、ビックリするようなことが書かれていた。
「学習院大学時代には、フォーク・グループ「ザ・パニック・メン」にヴォーカリストとして参加、1968年にレコード・デビューを果たす」
えっ! 都倉俊一ってフォークでデビューしたの? 四歳でバイオリン習ってドイツで勉強した人が?
さらに驚くことが。デビュー曲は「想い出の小径」という曲だが、これはザ・ロックキャンディーズのやはりデビュー曲「どこかに幸せが」とカップリングされて発売されているのだ。へーー。もちろんロッキャンと言えば谷村新司大先生のアリス以前の最初のユニットで「どこかに幸せが」という曲も知っていたが、まさかその裏面が都倉俊一のデビュー曲だったとは。詳細はこちらで見させていただいたのだが、谷村新司と都倉俊一は背中合わせでデビューしたのか。これは知らなかった。当時は、違う歌手同士でAB面でレコードを作ることはよくあった。ジャケットを見ると「若者の唄!カレッジポップス!」と謳われている。時代だなあ。「想い出の小径」という曲は残念ながら聴いたことがない。
その後都倉俊一はジュリアンズというグループに在籍(おそらくザ・パニック・メンの発展系)し、このふたつのグループで2年くらいは活動していたらしい。知らなかった。都倉俊一のデビューがフォーク(カレッジポップス?)だったとは。そういえば、アリスの初期のシングル「青春時代」「二十歳の頃」の作曲は都倉俊一。縁が続いていたのかもしれない。
都倉さんは、時として非常に叙情的な曲を書かれる。そのルーツはフォークにあったのかもしれない、と書くと短絡的にすぎるが、山本リンダの「どうにもとまらない」「狙いうち」などの扇情的な曲、またピンクレディーのヒット曲はじめ数々のアイドルに提供してきた曲のイメージとあまり結びつかない一群の曲がある。そこが職業作曲家の凄さでもあるわけだが、ペドロ&カプリシャスや麻生よう子の「逃避行」、そして「メッセージ」など、なんともいえないやさしい気持ちになる曲を作られる。
もうあなたと逢えないでしょう 愛をこめたメッセージを下さい
この「メッセージ」を聴くと、今にして思えばちょうど少年(つまりガキ)から思春期へと移り行く時代の、例えば人を好きになり初めし頃をふと思い出す。
それが青春を象徴するうたであるかどうかはわからないけれども、懐かしさも加味して、この曲を思い出してみた。










 クリックで各カテゴリの
クリックで各カテゴリの