
小田雅久仁『本にだって雄と雌があります』
新潮文庫 2015年
本も結婚します。出産だって、します。小学四年生の夏、土井博は祖父母の住む深井家の屋敷に預けられた。ある晩、博は祖父・與次郎の定めた掟「書物の位置を変えるべからず」を破ってしまう。すると翌朝、信じられない光景が――。長じて一児の父となった博は、亡き祖父の日記から一族の歴史を遡ってゆく。そこに隠されていたのは、時代を超えた〈秘密〉だった。仰天必至の長編小説!(Amazon 内容紹介より)
=例会レポ=
●最後まで読んだが、ペダンチックというか博覧強記というか、ひけらかしを感じた。本に雄と雌があることは話の本質ではなく、つまらないダジャレの連発。自分の息子を出した最後のアイデアはいいかと思うが、日航機事件をモチーフにしたことに、いい印象はない。また、登場人物が多く家系図が欲しかった(文庫にはあり、との声)。
●読み切れない。文章がまわりくどくて面倒くさいが、しかし男女の関係もまたそうかと行き着いた。與次郎は文字の中に生きており、ミキは絵で生きているところに夫婦のバランスを感じる。戦地を生き抜いた人が不慮の飛行機事故で亡くなるところは興味深い。しかしページがなかなか進まない。
●面白いけれども疲れる。前に読み、再度読もうと思ったが読めない。この本が幻書だったというオチにはカタルシスを感じるが、この本を読むにはエネルギーが求められ、読むステージに上がる体力が必要で、それが尽きてしまうとダメ。読む人を選ぶ本で、面白さを味わえた一握りの人は幸福を味わえるのだと思う。
●以前は20数ページ、今回は44ページでギブアップ。「選ばれない」人なのかも。面白いけれどその面白さがしみ込んでこない。作者が一人で面白がっている、それに共鳴できる人じゃないとダメなのかな。関西風のアクの強さがダメ。
●流し読みで最後までたどりついた。ダジャレにイライラしたが、仕事で疲れ果ててる時に読んだら笑えた。本に相性があるってどういうことなんだろう。自分について書かれていることがあるとしたら読みたいと思うだろうか。などと考えながら読んだ。
●最初の40%くらいは「高田純次が暴走してる感じ」。與次郎が出てきたあたりからそれが変わり、ミキとのやりとりや文体の変化で気分転換はできた。與次郎の最期は実際の飛行機事故を扱っているし、ミキの臨終も「サマーウォーズ」の終わり方と似ている。いろんなことを少しずつ取り混ぜ、それが混ざり合わないまま残ってる感じ。これ自体が幻書だという終わり方もネバーエンディングストーリーを思い出させる。いろんなものを彷彿させるので、それを見つけるのは面白いのかなと思います。
●読み始めはくどいと思って放り出したが頑張って再読。5分の2くらいを過ぎ、気づいたら文章に引きこまれ、独特のテンポの良さで楽しくなってきた。後半は一気に読みました。おちゃらけた文章だから戦争の暗い部分も重すぎない。逆にどんと来るところもある。家族の温かなやりとりも嘘くさいけれどこの文章だからじんわりきたのかな、最後まで読めてそれなりに楽しかったのですが今後数年はこの人の本は読みたくないと思うくらい苦労して読みました。
●半分までしか行ってない。難解で嫌になり、毎日2、3ページしか進めない。中盤を過ぎて、さらりと読めばいいのかな、と気づいた。理解しきれないものがあるけど、さらっと読むとくすっと笑う。今は面白く読んでます。後半まで読んでみたいな。
●最後まで読んだ。最初は何度も読み直し、面白いわけではなく義務的に。苦しかった。最後の方に「独擅場」という言葉が出てきますが、20年ぐらい前に友達が「独壇場」と間違えることが腹立たしいと言ってた飲み会が蘇ってきて、そこが一番のツボでした。
●本に雄と雌があって勝手に増えてくってところは「そうよね、あたしの本も勝手に増えちゃった」と面白かったんですけど、ずっとダジャレを言い続ける人って苦手で疲れます。いろんなテーマを浅く散りばめ過ぎで、一つひとつ、もっと深めればいろんなものがあるのに、小説としてはいただけない。
●自分だけ読めないのかと思いましたが、皆さんの意見を聞いてよかった。パラパラしたら面白そうな気もしたんですけど。
●単行本のときは挫折したので、今回は死ぬ思いをして読みました。これはダジャレじゃない。「これオモロイやろ」というような形容がウダウダあって、それがダメ。関西人がやりがちな感じ。文体がダメだとストーリーもダメで、本に人格があるかと思うと一族の物語で、これを面白いという人もいるんでしょうけど、死にそうでした。
●33ページでダメでした。ここから先がんばるべきかどうか悩んで、最後のページを見てやっぱり駄目だなと諦めました。
●今朝読み終わったが、読んでいるときと読み終えてからの印象が変わった。最初は面白いと思ったが冗長で疲れてしまい、本の話と主人公の話がかみ合ってなくて一体何を書きたいのかわからず、眠くなる。面白いことをふわふわ書きながら、狂犬病や飛行機事故で圧がかかる。そこは読ませるし、中でもボルネオはきわめつけ。しかし象が出てきて、またおちゃらける、何でそうなっちゃうのかな。最後の最後で幻想図書館が出てきて、読後は面白いと思ったが人には勧めない。春に井上ひさしの『吉里吉里人』を必死で読んでくたくたになったおかげで体力がつき、この本を読むステージに上がれたんだと思う。
●(欠席者より)つまらなかった。文体は一時期の筒井康隆の真似。SFなのかファンタジーなのか一代記なのか家族小説なのかわからない
。
●私は大好きな本。蘊蓄がどうのというより、本の中から家族の一代記に入るという舞台設定が面白くて大好きだった。関西系のノリやダジャレはすっ飛ばしてもいい。戦争で本が読めなくなる状況には、涙がすっと出てくるくらい、怖さが伝わる。今回読み直し、やっぱり楽しく読めた。幻想小説としてとてもうまくできている。この本は雄雌の幻想から生まれた本だからファンタジーであり、妄想。お遊びでいいと思ってるので。次の作品が出たら私は読むと思います。
●読み始めたところで相性が悪いと思い、ムリだなと諦めた。
【講師評】
森見登美彦や井上ひさしに似ているという声が多い作家のようだが、妄想と独特の語り口で読ませる小説で、これがダメな人はついていけない。日本ファンタジーノベル大賞を獲った前作『増大派に告ぐ』は、中年のホームレスと中学生の少年の交互の視点で書いた作品で、中年ホームレスの妄想がこれでもかと描かれている。後味は悪いが、今の社会をひっくり返したような作品で、そこがリアルでもあり、構想はすごい。
今作においても妄想と語り口を重層化させるところがミソといえる。本に雄と雌がある、という切り口は読みやすく面白いが、雄雌があることの証明はできていない。ただ小説の着地点については相当考えていて見事。これは幻書で4世代史であるという構成は非常にうまい。一つの家族の精神の連続性、知の連続性を「蔵書」を用いて描いている。この作者は本を愛してるということがよくわかるじゃないですか。それがこの作家の一番いいとこなのかと。
そもそも読書家は本を取っておかないし、蔵書家は読まない。これはコレクターの本なんですね。マニアックな連中の好み。最初の語り口でこの世界に入れる人と入れない人に二分されるが、あの掴みで家族史を描き、事件を絡ませていくという構造になっている。與次郎からミキに話が移るのは、男は女に戻るということ。人間は結局そこにいくんだな。本は飛んじゃうけれども、息子が自分史を書いているところに着地点を置いたのがいい。この本が幻書だったというのは見え見えだけど、作者は才能のある人だと思うし、作家自身、精神の均衡をきっとここで保ってるんですよね。
・・・・・
ということで、欠席した推薦人からも一言。支持者Sちゃんと同じく、ダジャレは問題じゃないんです。この本を読むほどに、本を愛する人の幸福感がふつふつと湧いてくるじゃないですか。蔵書家でなくとも本屋さんや図書館にある、あの本いっぱいの充足感に包まれるじゃないですか。
小田さんの他の作品は人間の奥底に潜む闇を描くものが多いのですが、この作品はただもう本好きの理想の家族愛がストレートに描かれて迷いなく昇華されるから、面白いのです。
中でも脇キャラのイチオシは、アントニオ・パニッツィさん。数奇な運命を経て大英博物館図書館の司書舗となり、図書目録を生み出した偉大な方ですが、似非関西弁で人を煙に巻くおっちゃんって。きっと彼は今もボルネオの幻想図書館で一生懸命膨大な図書を分類しているに違いないのです。目録の偉大な歴史はTS●TA●Aにそうそう破れるものではないのです。
と熱く語りましたが、小田さんは短編にもいいものがあり、名前の挙がった作家の中では、私は筒井康隆氏の才能に迫るものを感じます。何といおうと押しの作家です。
ご参考:アントニオ・パ二ッツイさん
→https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A3










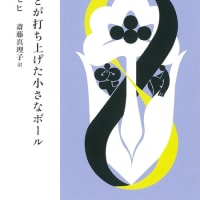
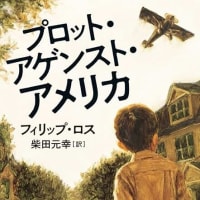













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます