
新年初の例会は、対面で15名、オンラインで1名が参加しました。
前日に公表された、おも本2代目講師の目黒孝二さんの訃報を受け、冒頭で菊池先生から目黒さんを偲ぶお話がありました。思い出話はつきませんが、謹んでご冥福をお祈りします。
***********************************************
さて、課題本の『11(イレブン)』。実はこちらも昨年50代の若さで逝去された津原泰水さんへの追悼の思いで推薦したのでした。『ブラバン』のような青春小説や探偵小説、津原やすみ名義の少女小説など、明るくさわやかな作風の小説も多い一方、SFかファンタジーかの区分けはともかく、本作のようにとても幻想的な作品を書かれる方でもありました。個人的にはこちらが作家本来の領分ではなかったかと思います。
果たして会員の評価はいかに?とドキドキしましたが、全体的にはおおむね好評。難解でとらえどころのないストーリーに「わけがわからない」という声もありましたが、大絶賛の熱弁もあり、とくに代表作の『五色の舟』についてはほとんどの会員から「強い印象を残す作品」として高い評価を得ました。戦時下のフリークショーという設定だけでなく、ち密な構成で読む者を一気に引き込む魅力が評価されたものと思います。近藤ようこさんによってマンガ化もされており、登場人物が可視化されるとまた異なるシュールレアリズムが味わえそうです。
ほかに『延長コード』や実話をもとにした『土の枕』も好評でした。
●講師からは、たとえば多和田葉子さんのように「異形の者」を扱う意味がわかる小説とは違って、やりにくいタイプの小説であると。
「頭のいい理知的な作家で、推敲に推敲を重ねた文章であることがよくわかる」
しかしフリークショーを扱う上では
「肉体や内臓感覚に特殊性を求める作家は多いし、マニアックな読者もいる。しかし、なぜ異形を使うのか、そこが読み解けるかどうかがポイント」
であり、その点で津原作品は非常にわかりづらく、
「もう一度読みたいと思わせる作家ではないが、文章がうまく、この発想がどこから生まれるのかを知りたいという興味がわく」とのこと。
今回の短編においては『五色の舟』と『延長コード』は完成度が高いと評価されました。
あらためて早すぎる逝去が惜しまれます。
まだまだ新しい作品を読みたかったです。










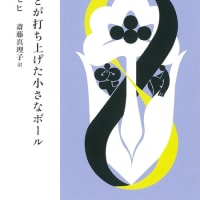
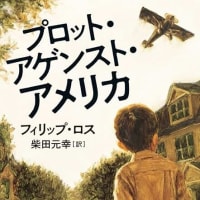













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます