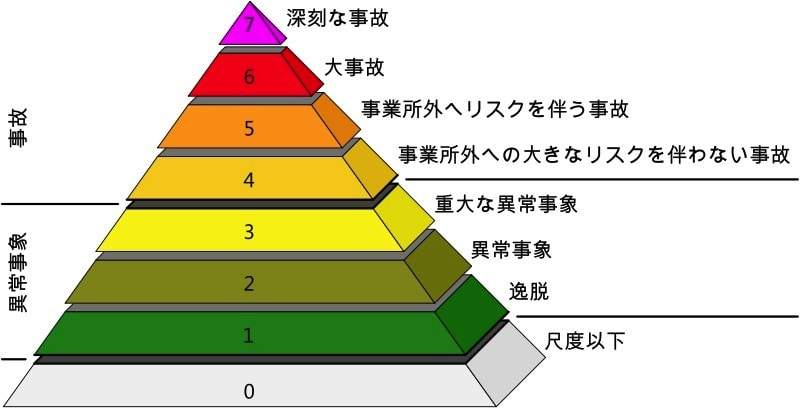9月8日 テレビをつけるとオリンピック招致が東京に決まったといい、大喜びする人の映像が紹介されていました。
私はまったくうれしくない。よせばいいのにと思う。思いはたくさんあるが、少しだけ書いておきたい。
ひとつは世界にこれだけたくさんの国があるのに同じ国が何度も開催するのはフェアでないし、ましてや同じ都市が二度も開催するのはよくないと思うから。日本で開催するにしてもほかの都市のほうがよいということ。
もうひとつは放射能汚染水の懸念についての質問に対する阿部首相の説明。「私が大丈夫と約束します」という心情を示しても何の意味もない。具体的に何をもって安全というのか。現実にはいまでも大量の汚染水が流れ出ている。あと7年もあれば汚染水はさらに流失するだろうし、タンクの貯蔵量はさらに膨大となり、3.11で地殻変動が起きて、関東での大地震が起きる確率は格段に高まっている。むこう7年のあいだに汚染水タンクに不測のことが起きる確率は小さくない。
震災関連でいえば、この国がまずなすべきはお祭り騒ぎではなく、地道なフクシマの復興であろう。そのためにはあの震災の分析と責任の所在と被災者の生活安定など急務が山積しているのに、2年半経ってほとんど進んでいない。そのことを忘れてお祭り騒ぎに浮かれるのは、阿部首相のいう「美しい日本」の国民がすることではないと思う。
具体的なデータも証拠も示さないで「大丈夫」とか「万全を尽くします」といった主観的なことばを並べて言いくるめる「技術」をもつ政治家はあやしい。私は阿部首相はスピーチがうまいし、なかなかにスマイルもいいと思う。だが、そうであればあるほど私には空虚さを感じる。彼は原発事故の直後に原因分析もなく、事故が進行中であるそのさなかに原発技術を海外に売り込んでいる人である。これほどの矛盾をニコニコしながら言いくるめてしまう技術はたいしたものである。現在の汚染水問題の深刻さをよそに、「まったく問題ない」という。しかも「過去も現在も将来も」である。私は過去も、現在も大問題があると思うし、将来については何もいえないことは自明である。私はこの「成功」が阿部政権に過信をもたせ、さらに加速することを懸念する。
そういうこともあるが、私が深いところで思うことはもっと別のところにある。それは戦後、経済復興という名のもとに日本列島を汚染し、水俣に代表される多くの人の人生を破壊し、動植物をいためつけてきた社会が、そのことに反省することもないことである。私にいわせれば、「右肩あがり」を当然よいこととしてきたことを、いいかげんにやめようよということである。1964年はそういう時代であり、あの時点での東京オリンピックは必要でもあったかもしれない。しかしあの「勢い」が日本の社会にいかに無理を強いてきたか。その結果、人は心を失い、社会は閉塞してしまった。それが「右肩あがりこそよし」とするあいかわらずの盲信によるのだということに、そろそろ気づいてもよいではないか。
しかし巷は気づくどころか、はしゃぎかえっている。オリンピック開催することの、何がうれしいのだろうか。私は選手が全力を出してフェアプレーすれば満足で、日本がたくさんメダルをとって欲しいとは思わないし、現実にも中国が独占するであろう。では何がうれしいのか。
私はヨーロッパ経験はほとんどないが、ハンガリーの小さな町に行ったことがある。美しい自然のなかに、落ち着いたたたずまいの家が集まった町があり、町の中心に教会があり、孫をのせた乳母車をゆっくりと押しながら歩くおばあさんが満ち足りた表情をしていた。そこには浮ついたものはまったくなかった。

私は東京という都市について思う。新宿の駅での乗り換えのアナウンス、20くらいの路線が紹介されるのではなかろうか。はりめぐらされた地下鉄の複雑なつながり、電車の中で会話もなくスマホに向かい合う乗客。これは大袈裟でなく、「人類史の中で人のすむ環境がここまで来てしまった」という異様な姿だと思う。その都市が「もっと経済効果を期待して」オリンピックをしたいのだそうだ。私は外国からのお客さんにこういうグロテスクな町を見てもらいたくない気持ちのほうが強い。

中学生のときに東京オリンピックを体験し、それから半世紀生きてきて、老人になり、私自身はくたびれてしまいました。「発展」はもういい。私は静かに家族に向き合い、浮かれることなく自然を眺めていたいと思います。
私はまったくうれしくない。よせばいいのにと思う。思いはたくさんあるが、少しだけ書いておきたい。
ひとつは世界にこれだけたくさんの国があるのに同じ国が何度も開催するのはフェアでないし、ましてや同じ都市が二度も開催するのはよくないと思うから。日本で開催するにしてもほかの都市のほうがよいということ。
もうひとつは放射能汚染水の懸念についての質問に対する阿部首相の説明。「私が大丈夫と約束します」という心情を示しても何の意味もない。具体的に何をもって安全というのか。現実にはいまでも大量の汚染水が流れ出ている。あと7年もあれば汚染水はさらに流失するだろうし、タンクの貯蔵量はさらに膨大となり、3.11で地殻変動が起きて、関東での大地震が起きる確率は格段に高まっている。むこう7年のあいだに汚染水タンクに不測のことが起きる確率は小さくない。
震災関連でいえば、この国がまずなすべきはお祭り騒ぎではなく、地道なフクシマの復興であろう。そのためにはあの震災の分析と責任の所在と被災者の生活安定など急務が山積しているのに、2年半経ってほとんど進んでいない。そのことを忘れてお祭り騒ぎに浮かれるのは、阿部首相のいう「美しい日本」の国民がすることではないと思う。
具体的なデータも証拠も示さないで「大丈夫」とか「万全を尽くします」といった主観的なことばを並べて言いくるめる「技術」をもつ政治家はあやしい。私は阿部首相はスピーチがうまいし、なかなかにスマイルもいいと思う。だが、そうであればあるほど私には空虚さを感じる。彼は原発事故の直後に原因分析もなく、事故が進行中であるそのさなかに原発技術を海外に売り込んでいる人である。これほどの矛盾をニコニコしながら言いくるめてしまう技術はたいしたものである。現在の汚染水問題の深刻さをよそに、「まったく問題ない」という。しかも「過去も現在も将来も」である。私は過去も、現在も大問題があると思うし、将来については何もいえないことは自明である。私はこの「成功」が阿部政権に過信をもたせ、さらに加速することを懸念する。
そういうこともあるが、私が深いところで思うことはもっと別のところにある。それは戦後、経済復興という名のもとに日本列島を汚染し、水俣に代表される多くの人の人生を破壊し、動植物をいためつけてきた社会が、そのことに反省することもないことである。私にいわせれば、「右肩あがり」を当然よいこととしてきたことを、いいかげんにやめようよということである。1964年はそういう時代であり、あの時点での東京オリンピックは必要でもあったかもしれない。しかしあの「勢い」が日本の社会にいかに無理を強いてきたか。その結果、人は心を失い、社会は閉塞してしまった。それが「右肩あがりこそよし」とするあいかわらずの盲信によるのだということに、そろそろ気づいてもよいではないか。
しかし巷は気づくどころか、はしゃぎかえっている。オリンピック開催することの、何がうれしいのだろうか。私は選手が全力を出してフェアプレーすれば満足で、日本がたくさんメダルをとって欲しいとは思わないし、現実にも中国が独占するであろう。では何がうれしいのか。
私はヨーロッパ経験はほとんどないが、ハンガリーの小さな町に行ったことがある。美しい自然のなかに、落ち着いたたたずまいの家が集まった町があり、町の中心に教会があり、孫をのせた乳母車をゆっくりと押しながら歩くおばあさんが満ち足りた表情をしていた。そこには浮ついたものはまったくなかった。

私は東京という都市について思う。新宿の駅での乗り換えのアナウンス、20くらいの路線が紹介されるのではなかろうか。はりめぐらされた地下鉄の複雑なつながり、電車の中で会話もなくスマホに向かい合う乗客。これは大袈裟でなく、「人類史の中で人のすむ環境がここまで来てしまった」という異様な姿だと思う。その都市が「もっと経済効果を期待して」オリンピックをしたいのだそうだ。私は外国からのお客さんにこういうグロテスクな町を見てもらいたくない気持ちのほうが強い。

中学生のときに東京オリンピックを体験し、それから半世紀生きてきて、老人になり、私自身はくたびれてしまいました。「発展」はもういい。私は静かに家族に向き合い、浮かれることなく自然を眺めていたいと思います。