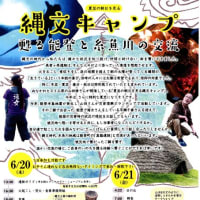輪島漆器の重箱は新品だと三重段で20~40万円前後もするが、五重段もある重箱を展示販売サポーターのどなたに託すか?

わたしが所属する整体協会(野口整体)の先輩が京都の自分の道場で展示販売をしてくれることになったので、目玉商品として託すことにした。
*展示販売先の詳細は後日に投稿
整体協会は身体感覚こそ日本文化の基層と考えるので、日常的に着物を着たり伝統民具をつかう会員が多く、佳いモノなら高価でも求める傾向があるのだ。

木箱の中で奉書紙につつまれた重箱を確認したら、重箱そのものは綺麗な状態。残念ながら黒黴がはえていた。
漆器がひどく汚れている場合は、まずお湯に浸して汚れを浮かし、中性洗剤をつけたスポンジで優しく洗う。
汚れが落ちたら充分に流水ですすぎ、木綿布などで丁寧に水気を拭きとる。
最後に乾いた布で磨けば光沢がもどる。
これは女性が日常的に洗髪や洗顔でやっているのと同じなので、ご参考まで。
つかうほどに保湿され色に深味が増し光沢がでる、「育てる器」が輪島漆器というもの。つまりは輪島漆器は生きているのだ。
イキモノとして扱うから食事の作法も変わってくる。椀の底に箸をあてず「寸止め」するようになるし、机の上の漆器を引きずって手前に寄せたり、乱暴に置く無作法もできなくなる。これは茶道の作法と同じ。
身に美しいと書いて躾(しつけ)となるが、輪島漆器はその先生といえる。
だからプラスチックの器と機能は同じなのに、輪島漆器で食事すると何かが違う。その何かとは「日本文化に触れた」充足感ではないか?
人に着せてもらった着物で街歩きしても日本文化を体験したとは言えないだろう。民族衣装を自分で着ることのできない国民が大多数となった現代日本に、伝統文化は残っているといえるか?
「輪島漆器販売義援金プロジェクト」は、日本文化が急速に失われていくことへの挽歌、最後の狼の遠吠えでもある。