7月11日、12日と二日間に渡り、ポンペイ島コロニアにおいてボランティア総会が開催された。

通常、総会は1月と7月の年二回開催される。島国国家であるミクロネシア連邦は隊員がそれぞれ数百キロ離れた4つの島に派遣されいるため、総会に参加するためにポンペイ州以外の隊員は、飛行機で移動し集まってくる。飛行機はユナイテッド社のみが就航している。毎日のように便があるわけではない。そのためアクセスは非常に悪く、総会参加のために5日から1週間の滞在が必要だ。
ちょうど、昨日ヤップ隊が帰州したのだが、13時発の便が8時間遅れというトラブルに見舞われ、本来なら昨日のうちに着くはずが、フライトの関係でグァムでの3泊の滞在を余儀なくされたとのこと。実際、こういったことはミクロネシアでは良くあることでもある。
さて、総会。ミクロネシア隊員の宿命として別の島にいる隊員は普段顔を合わせることはめったにない。そのため、ボランティアにとって年二回の総会は、お互いに密に情報共有、交流を深めることができる貴重な時間である。期間中、活動中間報告、活動最終報告、職種別分科会などが開かれ、隊員の活動状況の報告、意見交換などが行われた。

今回、自分は中間報告と参加した研修(ダンプサイト改善研修:本ブログ前号参照)について報告した。

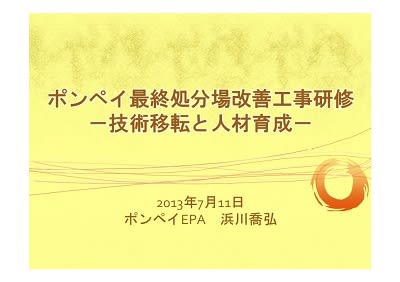
赴任して9か月が過ぎたわけだが、単に活動したことを報告するだけでは職場、環境が大きく異なる各ボランティアにとってあまり有益ではないと考え、報告の仕方を悩んだ。いろいろと悩んだ結果、「自分の活動は配属先にとってどういったものであるか?」という視点で自分の活動を整理した。
ボランティアとのニーズを横軸にとり、配属先のニーズを縦軸にとる。

このマトリックスにおいて、右上のエリアが最もボランティア、配属先それぞれにおいて効果的な活動だと考えられる。最も目指すべき領域だ。おそらく多くのボランティアにとって活動の序盤戦は右下のエリアから始まると思われる。配属先のニーズがはっきりしない中で、自分なりに活動を始めたという段階だ。このエリアは活動の成果によっては右上のエリアに移っていく可能性がある。
一方で、いつまでもここに留まっているということは独りよがりな活動になっている可能性が考えられる。
左上のエリアはボランティア自身のモチベーションは上がらないかもしれないが、配属先との信頼関係を築くという意味では取り組む価値があるかもしれない。
左下のエリアはお互いに不幸な領域で、生産性は低いと思われる。例えば、教育省の方針はこうだが、学校としては賛同できないかつボランティアも賛同できないといったケースが考えられるかもしれない。もしこの領域に活動が入った場合、しょうがないと割り切って進める、とことん配属先と話合いを重ねて新たな方向性を探るなどの対策が考えられる。
このような観点で自分の活動を振り返ってみた。序盤戦の活動は右下の領域に集中していた。半年過ぎたころからの活動はやや右上にあた。一つ意外だったのが、「職場環境改善活動」である。これは要は「職場の電気代を節約しよう!エコなオフィスを!」といった日本の会社では総務課が担当しそうな仕事である。活動当初、この極めて日本人か得意そうな仕事は同僚には馴染まない、すなわち右下のエリアにあると考えていた。しかし、実際初めて見ると局長がエアコンを率先して切り始める、スタッフが電気代を気にし始めるなど変化が現れた。
職場が活動予算がないことが日頃のスタッフの行動からはあまり感じられなかった。そのため、自分は勝手にスタッフは予算不足のことを深刻な問題とは捉えていないと考えていた。しかし、実際はみな気にしているが活動するためのきっかけがなかっただけであったのである。今では明らかに右上のエリアの活動である。
今回、一歩引いた目線で自分の活動を振り返えれたことは、今後の活動に有益になると感じている。

夜は交流会。各州アピールタイム、宴会芸が披露された。ポンペイ州は三線、ウクレレ、タンバリン、鈴を使って歌の合唱、ダンスを披露した。

チームヤップ州。ヤップ語での唄と踊りを披露。シニアボランティアの東さんを中心にノリノリの図。

各州を代表して幹事を務めてくれたボランティア。よっしー、陽ちゃん、梢ちゃん、みっつ。ほんとにご苦労様でした。
次回は自分が幹事をすることになった。今隊次からSV16名、JOCV13名とシニアの方が優勢となったミクロネシア連邦。みなが充実するような総会目指していきたい。
24年度2次隊 浜川喬弘

通常、総会は1月と7月の年二回開催される。島国国家であるミクロネシア連邦は隊員がそれぞれ数百キロ離れた4つの島に派遣されいるため、総会に参加するためにポンペイ州以外の隊員は、飛行機で移動し集まってくる。飛行機はユナイテッド社のみが就航している。毎日のように便があるわけではない。そのためアクセスは非常に悪く、総会参加のために5日から1週間の滞在が必要だ。
ちょうど、昨日ヤップ隊が帰州したのだが、13時発の便が8時間遅れというトラブルに見舞われ、本来なら昨日のうちに着くはずが、フライトの関係でグァムでの3泊の滞在を余儀なくされたとのこと。実際、こういったことはミクロネシアでは良くあることでもある。
さて、総会。ミクロネシア隊員の宿命として別の島にいる隊員は普段顔を合わせることはめったにない。そのため、ボランティアにとって年二回の総会は、お互いに密に情報共有、交流を深めることができる貴重な時間である。期間中、活動中間報告、活動最終報告、職種別分科会などが開かれ、隊員の活動状況の報告、意見交換などが行われた。

今回、自分は中間報告と参加した研修(ダンプサイト改善研修:本ブログ前号参照)について報告した。

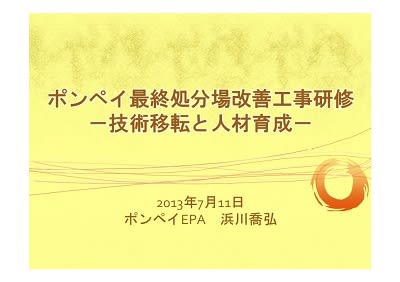
赴任して9か月が過ぎたわけだが、単に活動したことを報告するだけでは職場、環境が大きく異なる各ボランティアにとってあまり有益ではないと考え、報告の仕方を悩んだ。いろいろと悩んだ結果、「自分の活動は配属先にとってどういったものであるか?」という視点で自分の活動を整理した。
ボランティアとのニーズを横軸にとり、配属先のニーズを縦軸にとる。

このマトリックスにおいて、右上のエリアが最もボランティア、配属先それぞれにおいて効果的な活動だと考えられる。最も目指すべき領域だ。おそらく多くのボランティアにとって活動の序盤戦は右下のエリアから始まると思われる。配属先のニーズがはっきりしない中で、自分なりに活動を始めたという段階だ。このエリアは活動の成果によっては右上のエリアに移っていく可能性がある。
一方で、いつまでもここに留まっているということは独りよがりな活動になっている可能性が考えられる。
左上のエリアはボランティア自身のモチベーションは上がらないかもしれないが、配属先との信頼関係を築くという意味では取り組む価値があるかもしれない。
左下のエリアはお互いに不幸な領域で、生産性は低いと思われる。例えば、教育省の方針はこうだが、学校としては賛同できないかつボランティアも賛同できないといったケースが考えられるかもしれない。もしこの領域に活動が入った場合、しょうがないと割り切って進める、とことん配属先と話合いを重ねて新たな方向性を探るなどの対策が考えられる。
このような観点で自分の活動を振り返ってみた。序盤戦の活動は右下の領域に集中していた。半年過ぎたころからの活動はやや右上にあた。一つ意外だったのが、「職場環境改善活動」である。これは要は「職場の電気代を節約しよう!エコなオフィスを!」といった日本の会社では総務課が担当しそうな仕事である。活動当初、この極めて日本人か得意そうな仕事は同僚には馴染まない、すなわち右下のエリアにあると考えていた。しかし、実際初めて見ると局長がエアコンを率先して切り始める、スタッフが電気代を気にし始めるなど変化が現れた。
職場が活動予算がないことが日頃のスタッフの行動からはあまり感じられなかった。そのため、自分は勝手にスタッフは予算不足のことを深刻な問題とは捉えていないと考えていた。しかし、実際はみな気にしているが活動するためのきっかけがなかっただけであったのである。今では明らかに右上のエリアの活動である。
今回、一歩引いた目線で自分の活動を振り返えれたことは、今後の活動に有益になると感じている。

夜は交流会。各州アピールタイム、宴会芸が披露された。ポンペイ州は三線、ウクレレ、タンバリン、鈴を使って歌の合唱、ダンスを披露した。

チームヤップ州。ヤップ語での唄と踊りを披露。シニアボランティアの東さんを中心にノリノリの図。

各州を代表して幹事を務めてくれたボランティア。よっしー、陽ちゃん、梢ちゃん、みっつ。ほんとにご苦労様でした。
次回は自分が幹事をすることになった。今隊次からSV16名、JOCV13名とシニアの方が優勢となったミクロネシア連邦。みなが充実するような総会目指していきたい。
24年度2次隊 浜川喬弘














