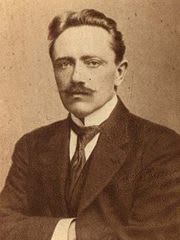モスクワの中心、アルバート地区のポワルスカヤ通り。
作家ブーニンの記念像を越えた辺り、アルバート通りを背にした右手には、モスクワ音楽院、ペテルブルク音楽院と並んでロシアの音楽教育の中核を成す三大名門高等音楽大学のひとつである、グネーシン記念ロシア音楽アカデミーが位置しています。
路地に入ったところから、トップの写真のような「女性がピアノを弾いている記念像」が見えますので、すぐに判るでしょう。
この女性は、エレーナ・ファビアーノヴナ・グネーシナ(1874-1967)で、ロシアの音楽教育に多大な貢献をした偉大な教育者です。
現在モスクワには幾つかの「グネーシン」関連の教育機関が存在します。
●子供たちが普通学校に通いながら並行して音楽を学ぶ7年制の音楽学校。
●際立った音楽的才能を持つ子供のために設立された音楽以外の一般教養科目をカリキュラムに含む10年制の中等音楽専門学校。
●そして音楽アカデミーと呼ばれる音楽専門大学・大学院とその付属高校。
こうした一連の「グネーシン記念」の音楽教育機関の中核を作ったのがこのエレーナ・ファビアーノヴナ・グネーシナと、姉妹たちです。
グネーシン家の9人の兄弟の内、長男と次男を除く、実に7人までもが音楽家となり、ロシア音楽の伝統づくりに貢献したことは驚くべきことです。
グネーシン記念ロシア音楽アカデミーや、モスクワ市立グネーシン記念中等音楽専門学校は日本を含め世界的非常によく知られていますが、その土台を作った「グネーシン家の人々」については、日本ではあまり知られていません。
グネーシン記念ロシア音楽アカデミーの講師であれグネーシン記念博物館館長を務めるヴラジーミル・トロップ(ジュニア)が、とても簡潔でわかりやすくこの「グネーシン家の人々」をまとめていますので、引用しながらご紹介したいと思います。

(グネーシン姉妹の写真は
こちらから。左からオリガ、エレーナ、エフゲニア、マリア、エリザヴェータ)
(1) 長女エフゲニア(1870-1940)は、幼い頃から音楽的天分に恵まれ、13歳の時モスクワ音楽院の前期課程に入学しました。(当時モスクワ音楽院は前期と後期課程にわかれており、前期課程は今日の中学、高校に相当します)。
やがて後期課程に進学した彼女は著名な音楽家、スクリャービン、メトネル等の先生でもあり、更にはモスクワ音楽院の大ホールを設立した学長としても知られるV.I.サフォーノフのクラスに入り、めきめきと頭角を表してきます。
エフゲニアはサフォーノフ教授の最もお気に入りの学生の一人であったばかりでなく、タネーエフやアレンスキー等、他の学科の教授たちからも才能豊かな学生として可愛がられていました。
ちなみに彼女はモスクワ音楽院でピアノ科と作曲科という二つの学科に同時に所属し、卒業した最初の女子学生となりました。
エフゲニアはまた、音楽だけではなく演劇や文学など、他の芸術分野にも造詣が深く、幅広い交友関係を持っていました。そうした人々の中にはロシア・ソ連演劇の基礎を作ったK.S.スタニスラフスキーなどがいます。
しかし彼女が最も大きな熱意を注いだのは、何といっても「教育」でした。彼女はグネーシン音楽高校の先導者となり、ピアノ、音楽理論、そしてコーラスなどの教科で教鞭をとり、45年間にわたって若い才能の育成に努めました。エフゲニア・サヴィーナ=グネーシナのクラスからは、「グネーシン」の名を最初に有名にしたニコライ・オルロフが出ています。
(2) 次女エレーナ(1874-1967)は、物静かな姉エフゲニアとは対照的な、いたずら好きで活発な女の子として育ちました。階段を勢いよく駆け下り、かのチャイコフスキーおじさんと正面衝突し、チャイコフスキーに優しく微笑まれた思い出は、死ぬまでエレーナの心の中に残っていたようです。
エレーナはエフゲニアと同様に、音楽院でサフォーノフ教授のクラスで学び、最優等の成績で卒業しました。また、ロシアに一年間教えに来ていたF.ブゾーニのもとでも学び、大変高い評価を受けました。ブゾーニは演奏家としての彼女に大きな期待を寄せ、海外に出ることを強く勧めていましたが、彼女自身の興味は世界的に有名な演奏家となることよりも、姉エフゲニアと同じようにひたすら「教育」の方に向いていました。「教えること」-それを彼女は自分の使命、天職であると認識し、それに全身全霊没頭したのです。
72年間にわたり名実ともに一連のグネーシン記念音楽教育機関の中核的存在であったエレーナは、大変優れたピアノ教師であり、そのクラスからは膨大な数の世界的なピアニストが世に出ています。
彼女の愛弟子レフ・オボーリンは、ロシアのピアニズムの伝統を全世界に知らしめた先駆的なピアニストの一人となりました。
このように、ピアノ教師として活躍しながら同時に彼女は子供のための練習曲を次から次へと作曲し、更には学校運営に関する諸問題の処理にも代表者となって精力的に取り組みました。第二次世界大戦前後の最も苦しい時期、スターリン時代 … ある時は楯となり、そしてある時は矛となって時の勢力と渡り合い、学校とそこで学ぶ子供たち、教師陣を彼女は体を張って守り抜こうとしました。
(3) 三女マリア(1876-1918)は、とても女性的で物腰が柔らかく、優しい女性でした。彼女は、姉たちと同じようモスクワ音楽院のピアノ科を卒業した後教師となり、とりわけ幼い子供たちに対する教育で際立った手腕を見せました。また造形芸術にも優れた才能を見せ、そのアプリケ細工は高い評価を得ています。
(4) 四女エリザヴェータ(1879-1953)は他の姉妹とは異なり、ピアノではなくバイオリンが専門で、当時音楽院で最も優れたバイオリンの教授として名高かったI.V.グリジェマリの門下生でした。彼女は音楽院卒業後、姉たちの活動に加わり51年間教鞭をとっています。弦楽器部門の発展に一方ならなぬ貢献をしました。
また、エリザヴェータはグネーシン姉妹の中で唯一子供を残した人です。その長男アレクサンドルは、天才的な音楽素養を持っていましたが、残念ながら幼少の頃に亡くなりました。次男ファビー・ヴィタチェック(1910-1983)は、作曲家となって活躍するのと同時に、グネーシン大学の教授として若い音楽家たちの育成に努めました。ちなみにエリザヴェータの夫E.F.ヴィタチェックは、「ロシアのストラディヴァーリ」の異名を持つほど有名な弦楽器製作者でした。
(5) 五女オリガ(1881-1963)は姉エレーナのもとで学び、グネーシン音楽カレッジの最初の卒業生となりました。彼女はその後60年間、グネーシン関連の教育機関でピアノを教え続けました。
(6) 三男ミハイル(1883-1957)は、ペテルブルク音楽院でリムスキー=コルサコフから作曲を学び、ロシアの代表的な若手作曲家の一人となりました。当時ミハイルは、同輩のストラヴィンスキーとともにリムスキー=コルサコフ門下のスター的存在でした。ロシア象徴派の詩人たちと深くつながっていた彼は、バリモント、ブローク、ソログープなどの詩人たちの詩に曲をつけています。そしてその作品はパブロ・カザルスやアレクサンドル・ジロッティーのような時代を代表する演奏家たちによって演奏されています。
正義感が強く、社会問題にも無関心ではいられなかった彼は、グネーシン大学で教え始めた後教育活動に全力を注ぐようになり、自らの創作からは少し離れるようになります。彼の代表的な教え子としてはハチトゥリャン、フレーニコフ等の作曲家などが挙げられるでしょう。
(7) 四男グレゴリー(1884-1938)の運命は最も波乱にとんだ、悲劇的なものとなりました。グレゴリーは才能豊かな歌手、素晴らしい俳優、優れた文学者として注目を集めていました。1905年のロシア第一次革命の後、革命運動に身を投じた彼はそれによって他の兄弟姉妹たちのようにきちんとした音楽教育を受けることはできませんでしたが、その音楽的天分は疑いようもなく、独特な花を咲かせました。冒険好きの彼は、憧れの国イタリアを恰も吟遊詩人であるかのように歌いながら旅してまわり、『吟遊詩人の思い出』というロマン主義的な小説を書いています。
その後グレゴリーはペテルブルク・レニングラードで役者、作家として活躍しましたが、スターリンの厳粛時代に他の多くの文化人と同様、理由もなく逮捕をされ、処刑されてしまいました。
以上が、音楽に携わってきた「グネーシン家の人々」の簡単なプロフィールです。
グネーシン記念ロシア音楽アカデミーの講師・グネーシン記念博物館館長のヴラジーミル・トロップ(ジュニア)氏についてはグネーシン記念ロシア音楽アカデミー(大学)教員データベースの
こちらへどうぞ。
■昨日の

の答え=・・・Дзэн・・・ゼン(禅)(=日本語からロシア語の中に入って定着した「外来語」です)
■今日の

=次の単語を発音してみましょう。
Васаби
(答えは・・・明日のお楽しみ)
★新プロジェクトの情報はこちら★





















 の答え=・・・Сакура・・・サクラ(桜)です。
の答え=・・・Сакура・・・サクラ(桜)です。


 =次の単語を発音してみましょう。
=次の単語を発音してみましょう。