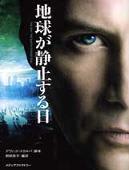「扉をたたく人」 (2007年・アメリカ)
THE VISITOR
移民の国アメリカの中でもとりわけ、さまざまな人種のエネルギーが渦巻く都市ニューヨークを舞台に、移民の青年との交流をきっかけに心の扉を開いていく初老の大学教授のエピソードを、抑えた筆致で描いた佳作。監督・脚本は「父親たちの星条旗」、「ボストン・パブリック」(FOX TVシリーズ)などに出演したトム・マッカーシー。妻に先立たれた孤独な教授ウォルター役に、名脇役として長いキャリアを持つリチャード・ジェンキンス(近作「バーン・アフター・リーディング」でも渋いバイプレーヤーぶりを発揮)。惜しくも受賞を逃したものの、ジェンキンスはこの初の主演作でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされた。
コネティカット州の大学で週に一回、経済学の教鞭を執るウォルターは、ここ何年も変わらない講義を毎年のように繰り返す無気力な大学教授。本の執筆に忙しいと言いながら、専門分野の研究にはほとんど手をつけず、趣味のピアノにも身が入らない。ウォルターはぼんやりと靄に包まれたような毎日を、ただ無気力に生きている。その彼が同僚の代理でニューヨークの学会に出席することになり、長らく留守にしてたマンハッタンの別宅に戻った時から、物語は動き出す。不動産屋にだまされてウォルターの自宅を借り受けていたシリア移民のタレク(ハーズ・スレイマン)とセネガル出身の恋人ゼイナブ(ダナイ・グリラ)との出会いをきっかけに、ウォルターの人生は少しずつ輝きを取り戻していく。閉ざされた心の扉を叩いたのは、タレクの演奏するアフリカンドラム、ジャンベのリズムだった。
ジャンベという楽器は西アフリカで作られる片面ドラムで、床に置いて素手で演奏する。仕事にも趣味にも情熱を持てず、周囲の人間にも関心を示さなかったウォルターが、タレクの叩くジャンベに誘われて、しだいに心を開いていくくだりには新鮮な感動がある。レポートの提出が遅れた学生をにべもなく切り捨てた初老の教授が、別宅を不法に占拠していた若い移民のカップルを通報もせずに自宅に留め置いたのはなぜだろう。ウォルターは無気力で人嫌いな頑固者ではなく、ただ生きる振りをするだけの自分に嫌気が差した正直な男ではなかったか。だからこそ移民のタレクに手を差し伸べた小さな好意をきっかけに、彼の人生は大きな転換点を迎えることができたのだ。ウォルターが偽りの毎日と決別し、友愛と情熱をふたたび取り戻せたのは、ジャンベのリズムが呼び水となって、彼自身が心の中から生きるリズムを刻みはじめたからだろう。
そのリズムは最初はたどたどしく戸惑いながらも、タレクたちの人生に関わることで、より着実な鼓動となってウォルターの心を後押しする。入国管理局に拘置されたタレクが送還されたのを知ったウォルターが、強い怒りをぶちまけて言う――「人をこんなふうに扱っていいのか・・・・・・こんなの間違ってる。われわれは何て無力なんだ!」そこにはもう、あの無気力な教授の姿はない。生きて、鼓動している瑞々しいひとつの魂が心を震わせる感動的な一シーンだ。慎ましやかなタレクの母親モーナ(ヒアム・アッバス)への淡い思慕も、教授の再生を彩る逸話として美しい余韻を残した。9.11後の移民問題の側面をかすめ取りながら、「グラン・トリノ」とはまた趣の異なるメッセージを伝える、静かでほろ苦い一作だ。
(6月27日に恵比寿ガーデンシネマと吉祥寺バウスシアターで公開後、7月から8月にかけて全国で順次公開されます)
満足度:★★★★★★★☆☆☆
<作品情報>
監督・脚本:トム・マッカーシー
製作:メアリー・ジェーン・スカルスキー/マイケル・ロンドン
製作総指揮:オマー・アマナット/ジェフ・スコール/リッキー・ストラウス/クリス・サルヴァテッラ
音楽:ヤン・A・P・カチュマレク
音楽監修:メアリー・ラモス
撮影:オリヴァー・ボーケルバーグ
出演:リチャード・ジェンキンンス/ヒアム・アッバス/ハーズ・スレイマン/ダナイ・グリラ
<参考URL>
■映画公式サイト 「扉をたたく人」
■関連商品 オリジナル・サウンドトラック「扉をたたく人」