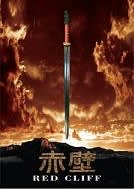「ラーメンガール」 (2008年・アメリカ)
THE RAMEN GIRL
細かく見ればいろいろ難点はありそうだが、軽めのハリウッド・コメディと割り切ればそこそこの娯楽作。恋人を追ってはるばる日本にやってきたアメリカ娘のアビー(ブリタニー・マーフィ)は、来日早々あっさり振られて途方に暮れる。ある夜、誘われるように入ったラーメン店で一杯のラーメンに救われた気持ちになり、ラーメンの持つ魅力にはまり込む。やがて頑固な店主マエズミ(西田敏行)に無理やり弟子入りを志願して、言葉も通じないまま必死にラーメン修行に励むという筋書き。主演二人のあいだで交わされる言葉はそれぞれ英語と日本語。あえて通訳に当たる役どころを置かなかったのは、双方が母国語でまくしたてることで生まれる迫力と、隔靴掻痒のコミュニケーションが醸し出す笑いを狙ったためだろうか。中途半端な“相互理解”や愛想笑いは、子弟間の切磋琢磨には不要と切り捨てたかったのかもしれない。
しかし、西田が次々と繰り出す嫌がらせやしごきには行き過ぎの感があり、アビーのセリフにもあるように“虐待”といわれても反論のしようがない。ハラスメントや虐待に敏感なアメリカ人観客には、顔が引きつるシーンの連続だろう。もしこれが日本映画だったら、もう少し親方の温情を感じさせる修行シーンになったはず。この点については、日本人の人情に疎かった監督が責めを負うべきだと思う。傷心のアビーが心を許す相手を日本男児にしなかった点や、西田がウイスキーを手放せないシーンも気になった。海外にいる息子と軋轢があることは流れからわかるとしても、言葉のわからない弟子にストレスをぶつけるほどの問題を抱えているようには見えなかった。これがハリウッド・デビュー作になるとしたら、西田にとってこの憎まれ役はよかったのかどうか。打たれ強いアメリカ人のアビーを演じたマーフィがいちばん得をしているのは、ハリウッド映画だから仕方ないか・・・・・・。
満足度:★★★★★★☆☆☆☆
<作品情報>
監督:ロバート・アラン・アッカーマン
製作:ロバート・アラン・アッカーマン/ブリタニー・マーフィ/スチュワート・ホール/奈良橋陽子
製作総指揮:小田原雅文/マイケル・イライアスバーグ
脚本:ベッカ・トポル
撮影:阪本善尚
出演:ブリタニー・マーフィ/西田敏行/余貴美子/パク・ソヒ
タミー・ブランチャード/ガブリエル・マン/石橋蓮司/山努
<参考URL>
■映画公式サイト 「ラーメンガール」
■関連商品 「ラーメンガール」 (DVD/ワーナー・ホーム・ビデオ)