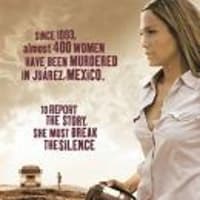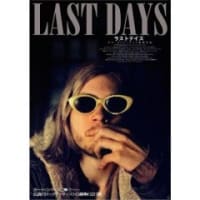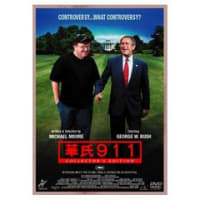「残穢」 (2012年・新潮社)
小野不由美
(このたび試行錯誤的に新たなカテゴリー「書評」を追加します。ご了承下さい。)
街の書店にこういったジャンルの本が平積みになることに、おやっ?と思い購入してみた。小野不由美は「屍鬼」上下巻の下巻半ばで投げ出してしまったため、実質的に小野作品で読了したのはこれが一作目(「残穢」と併せて読むと怖さが増すという「鬼談百景」は、店頭でさらりと見た限りでは購入するほどの魅力を感じなかった)。こういったノンフィクションの体裁をとった怪異小説は、「新耳袋」やホラー作家による“実話系”怪談、あるいは怪談コンテスト「超-1」作家による恐怖箱シリーズなど枚挙にいとまがない。こういった作品はいくら“実話”と銘打たれても、結局は騙されることを承知の上で怖さを楽しむためのフィクションだという気がしてならない。理由は、自分に実体験がないことと、それゆえこういう話の多くをリアルに感じることができないばかりか、疑いさえ差し挟んでしまう感性ゆえだと思う。けれども、読了後に暗い階下へ降りていくときや、家猫が背後の闇をじっと見つめているときなど、うなじの辺りに妙な寒気を感じてしまうのも確か。これがいわゆる“実話怪談”の効能、いや醍醐味というものなのだろうか。
この「残穢」という作品で、主人公としての書き手は、怪異を鵜呑みにすることができないたちであることを明言していて、そういう書き手が、とあるマンションの一室で起きた小さな怪異を糸口に、時を超え、場所を移して受け継がれてきた「穢れ」の正体に淡々と迫っていくくだりは、謎解きの面白みもあってページを捲る手が止まらない。しかし諸々の内容から、この書き手が著者本人であると認識してしまった時点で、この一連の怪異ははたして現実のものなのかという思いが増してくる。人が怪談を読むのは、それがフィクションであることを前提に、安全が担保された立ち位置から恐怖を楽しみたいからだ。劇場に腰を下ろすとき、映画の中の現実がスクリーンを越えてこちらの世界になだれ込むことはないからこそ、観客は作品を堪能できる。でも、その強固な壁が突然崩れてしまったら、読者はいったい作品に描かれた“現実”をどう捉えればいいのだろう。因果とは無関係に、場所を介して容易に伝播し拡散していく穢れが、読み手の世界をじわじわと侵食していくとしたら、これはもう怪談ではなく現実の恐怖そのものだろう。
これは著者が仕掛けた周到な罠なのか――私はそう思いたい。そう思わなければ、この世界は生きていくにはあまりにも恐ろしく、もう怪談もホラー映画も娯楽として成り立たなくなってしまうからだ。この作品を読んでから私は、夕刻には早めに家中を明るくし、猫の視線は追わないことに決めている。