2012-03-30初稿
2016/11/27追記
2018/4/11 加筆
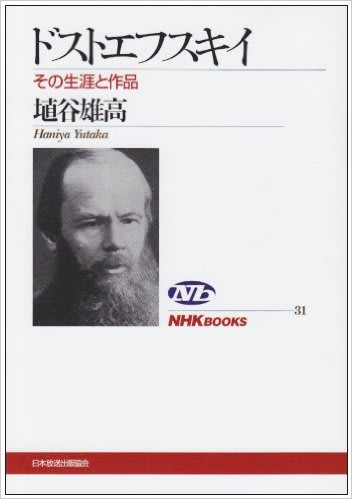
小説には物語性が重要だと村上春樹は「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」で述べている。すでにある説話的物語ととるのか、あるいはあらたな物語性の獲得ととるのか、それは「あらたな物語性の発見」であるに違いない。そんな興味に魅かれて検索をしてみたところ、次のブログを見つけた。
下記の蓮實重彦の『小説から遠く離れて』では、村上春樹の『羊をめぐる冒険』はばっさりと切られている。蓮實重彦の『小説から遠く離れて』http://yokato41.exblog.jp/12131868/
大変面白い内容なのでメモをしておく。(以下の文は上記サイト蓮實重彦の『小説から遠く離れて』の引用から成り立っている。ただし現時点でサイトはリンク切れになっている。褐色部分が引用)
①下記の4小説の特徴は「宝探し」である。
『羊をめぐる冒険』では「羊」が
『吉里吉里人』では、東北の「金鉱」が
『裏声で歌えよ君が代』「美術品としての軍刀」が
『コインロッカー・ベイビーズ』では「ダチュラという興奮剤」である。
村上春樹の1Q84を例にとると青豆という女性を探す宝探しだ。
②これらの小説の物語の構造は 「依頼」→「代行」→「出発」→「発見」の流れに収まる。ただし、村上龍の作品『コインロッカー・ベイビーズ』では「依頼と代行」のかわりに「神託」と「告白」による「宝探し」だという。
村上春樹の1Q84を例にとると「依頼」→「代行」はよくわからないが「出発」→「発見」は確かに。
③不可視の権力者の存在」
『羊』では、「強大な地下の王国」を支配している「先生」
『吉里』では、「吉里吉里国の圧殺を目論む日本国」
『裏声』は「右翼の大物」
『コインロッカー』では、この主人公である捨て子の二人を強制的に双子にした世に送り出した「社会・官僚組織」
村上春樹の1Q84を例にとると教祖が不可視の権力者の存在となる。
④「潜在的な双生児」
『羊』の僕と鼠
『吉里』の三文小説家と美貌の踊り子
『裏声』では主人公の画商梨田そのものに二重性があり(幼年学校出身のナポレオン崇拝者の過去と、汚い商売に手を染める現在)
台湾の独立運動をもくろむ洪大統領との間の双子関係も示唆される。
『コインロッカー』での捏造された双子「キクとハシ」は指摘するまでもない。
村上春樹の1Q84を例にとると青豆と環が潜在的な双生児か。
⑤どの作品でも、あるとき、女性の演ずるべき役目を物語から奪ってしまう、
つまり風俗的な恋愛が克明に描かれているにもかかわらず、ちょうどいい頃合いを見はからって、
いったんは同行者のごとき振る舞いを示しもした女性が消えてしまって、「宝さがし」の物語に加担することがない。
村上春樹の1Q84を例にとると安田という女性がこれにあたる。
この物語性に依拠した作品は、以下のようにバッサリと切り捨てられる。
欠けているのは、書くという実践的な体験としての冒険にほかならない。書くことが冒険であるのは、そこに根拠が決定的に欠けているからなのだが、多くの小説家はその無根拠を直視しえず、「宝探し」といった物語に書くことの根拠を仮託せずにはいられない。そのとき、彼らにあっては執筆は技術の問題にすり換えられ、それを統御する術をどの程度心得ているかということだけが、面白さを決定しているということになってしまう。
そこでの言葉は、震えてもいなければ、脈動を伝えてもいない。なぜなら、物語とその説話論的構造が、あらかじめ言葉を保護しているからであり、だから、人が彼らの長篇で触れうるものは、言葉ではなく、物語の普遍的な安定性ばかりである。そうした体験しか許そうとしない小説を、われわれは退屈な作品だと自信をもって断言することができる。
そこまで断言できるものか、どうか疑問だが、見方は面白い。説話的物語の枠内で書いている。
ドストエフスキーのカラマゾフの兄弟はこうした説話的物語の枠内から離れていることはよくわかる。その結果作者は当初の意図から遠く離れた結末にたどり着くことになる。蓮實重彦は上記の小説にはカラマゾフの兄弟のような先の見通せない物語性がないことが不満なのだろうか。
埴谷雄高は彼の著「ドストエフスキー」で次のように記すが蓮實重彦と同じ事を言っているようだ。
ドストエフスキーの半合理主義的意図がどうであれ彼の合理主義的詩学はそれを裏切る。
カラマゾフの兄弟で伝統的信仰と反逆的理性の相克を描き、反逆的理性が勝利することを意図したが結果は神による調和に対する攻撃はますます予言的性格を帯びていった。
パンフレット作家のドストエフスキーは単純なユークリッド的信仰に屈服することを望んだ。芸術家ドストエフスキーは何ものに屈服することをも拒絶した。
意図と成就の矛盾がドストエフスキーの作品で絶頂に達するのは、1879から1880にかけての頃である。カラマで伝統的信仰と反逆的理性との闘いにおける決定的構想を示し、そこで反逆的理性が失墜させられる図を描いてみせるはずだった。
中上健次 「小説から遠く離れ」ることで、物語的な迂回のはてに、小説への回帰を実現しようとする作家
『枯木灘』は、小説にふさわしく言葉が組織されているが故に小説なのではなく、その発生を促しているのは、むしろ物語的な典型に対する作者の執念だという。
キクやハシが隠しきれずにいる欠如としての両親への心理的執着を、(枯木灘の秋幸は)まったく持っていない(……)。捨てられたことが、肉体的にも精神的にも外傷となることがない存在、それが秋幸だ。
その無方向性とはこういうことだ。つまり、執着することが、執着の廃棄とほとんど同じにみえてしまうが故に、執念が執念の不在に似てしまうのである。あるいは、物語とは、方向の消滅へと言葉を導く不条理な誘惑なのかもしれない。
こうした物語に抗うには、いわば完璧な「他者性」ともいうべき存在、自分自身に対してさえ他者たらざるをえないような状況を引き寄せねばなるまい。
実際、捨子の二人が手を組んで権力者たる父親に反抗するといった単純な図式に還元される小説を生真面目に書くことなど、二十世紀もおしつまったこの時期に許されていいのだろうか。
人が捨子として知っているものにはまったく似たところのない状態として捨子になることへの欲求が、すべてを荒々しい色調に染めあげる(……)。
かつて、「枯木灘」を読み始めたが、途中で投げ出してしまった。しかし「人が捨子として知っているものにはまったく似たところのない状態として捨子になることへの欲求が、すべてを荒々しい色調に染めあげる(……)。」が作品の価値を決めるという意味は理解できる。
2018/4/11 加筆
蓮實重彦の三島由紀夫賞受賞時の記者会見模様だが上述の「物語の普遍的な安定性ばかりである。そうした体験しか許そうとしない小説を、われわれは退屈な作品だと自信をもって断言することができる。」と述べる 蓮實重彦らしい受けごたえなので参考に。ちなみに引用中の現在93歳になられる、日本の優れたジャズ評論家とは瀬川昌久で1941年12月8日は真珠湾攻撃の日。
――先ほど「小説が向こうからやってきた」「知的好奇心」とも仰いました。「『ボヴァリー夫人』論」を書かれたことは大きかったんでしょうか。
それは非常に大きいものであったことは確かです。ボヴァリー夫人』論に費やした労力の、100分の1も、この小説には費やしておりません。
――講評には「作品として一つの時代の完結した世界を描いている」という話がありました。この作品を現代の今、書く理由というものが、蓮實さんの中にあったのでしょうか。
全くありません。というのは、向こうからやってきたものを受け止めて、好きなように、好きなことを書いたというだけなんです。それでいけませんか?何をお聞きになりたかったんでしょうか。
小説を書くという予定はありません。書いてしまうかもしれません。なにせ小説というのは向こうからやってくるものですから。あと、ジョン・フォード論は完結しなければいけないと思っておりますが…。
向こうから来たというのは、いくつかのきっかけがあったことはお話ししておいたほうがいいと思います。
現在93歳になられる、日本の優れたジャズ評論家がおられますけれども、その方が12月8日の夜、あるジャズのレコードを聞きまくっていたという話があるわけですね。「今晩だけは、そのジャズのレコードを大きくかけるのはやめてくれ」と両親から言われたという話がありますが、その話を読んだときに、私はその方に対する大いなる羨望を抱きまして。結局、「1941年12月8日の話を書きたいなぁ」と思っていたんですが、それが『伯爵夫人』という形で私の元に訪れたのかどうかは、自分の中ではっきりいたしません。
















