20日(春分の日)に特別展「柳宗悦と丹波の古陶」が開催されている兵庫陶芸美術館を訪れた。丹波焼は、工程も作品の佇まいも質素で素朴である。民衆が普段の暮らしに使う雑器であるがゆえに、早く大量につくって安く売らなくてはならない。茶器のように技巧や芸術性を追求する必要はない。だから土や窯にこだわる必要はなく、仕事は無名の職人による無私の労働にゆだねられた。釉薬も銅などは使わず、灰でつくった並釉に鉄分を含んだ黒土や赤土を混ぜたものを使った。出来上がりは一様ではなく、同じ窯で焼いたものでも、火の流れ、天候、薪の種類、窯のなかの位置などによって、個々の作品は多様な姿を見せる。こうして、過度に人為を弄さず、自然に任せる無作為によって、人の手では及ばない力強さと美しさが生まれた。そのことを発見した柳宗悦は、それを「他力による美」「貧しさの富」と讃えた。丹波の古陶には、人智を超えた自然の叡智が宿っているという。(参考:柳宗悦著『丹波の古陶』関西図書出版、昭和56年)
この展覧会には、宗悦が「静かな渋い布」とたたえた丹波布も合わせて展示されている。かつては佐治木綿と呼ばれ、野良着などにするために使われた縞木綿である。自然から抽出された染料を用いることで、素朴な格子(縞)柄に驚くべき色彩のバリエーションが生み出される。
|
藍と茶を基本色とし、藍と茶と黄、藍と黄を合わせた緑で縞柄や格子柄を織り上げる。染料は村の周辺で手に入る植物に由来する。藍に加えて、茶色の染料として里山に自生する栗の皮、ヤマモモの樹皮、ハンノキの樹皮などを用いる。黄色は田畑の畔道に生えるコブナグサを中心に、キクイモ、ビワの樹皮を使う。これら自然の染料を媒染剤を変えたり、浸染の回数を加減することで、微妙な色調を表現する。(ウィキペディア) |
生活者の使用価値を追求する普段使いの布や雑器は、その制作工程にも作品そのものにも効率が求められる。できるだけ手間を省き、使い勝手のいいものを早くたくさんつくって安く売るためである。そこに過度な装飾を排した「用に即した美」が生みだされる余地がある。それは労働時間を短縮し、均一な製品を大量生産することで最大の利益を求めるビジネスの効率とは正反対のものである。
実用から離れることなく、実用のうちにおのずから美を表わす民衆の工藝を宗悦は民藝と呼んだ。丹波の民藝には、貧しさから生み出された無量の美しさがある。貧しく質素だからこそ生み出される美しさがあり、その美しさが人々の日々の暮らしを豊かにする。
宗悦をして民藝のもつ美の力強さに開眼させたのは、朝鮮の文化であった。朝鮮の陶磁器などを通して朝鮮民衆の生活文化の豊かさを高く評価していた宋悦は、1919年(大正8年)に起きた三・一独立運動に対する朝鮮総督府の弾圧を強く批判した。京城において道路拡張のため李氏朝鮮時代の旧王宮である景福宮光化門が取り壊されそうになったときも、柳はこれに強く抗議し、結局、移築保存されることになった。昭和15年に沖縄で強制的な標準語励行運動が推進されたときも県当局の姿勢を批判し、琉球方言を擁護した。こうした柳の政治的言論活動の根っこには、地域の生活に根差した民衆の文化への深い理解と敬意がある。
穏やかな丹波の山懐に抱かれた立杭の佇まいに心が和む。とりわけ、陶芸美術館からの眺めは格別だ。展示棟にいたる通路の一角に設けられた椅子に座ってみる眺め、ミュージアム・ショップの窓枠を通した眺め、カフェの前の広いテラスからの開放的な眺め、茶室からよく剪定された垣根越しに眺める風景、などなど。場所や方向を変え、縁取りをつけたり外したりして見る多彩さに加えて、季節や天候によって変幻する山里の風景に浸る楽しみは尽きることがない。それは、文字通り私にとっての「心のふるさと」である。(茶室で抹茶をいただくときは、丹波焼のコレクションのなかから好きな作家の茶器を選べるのも嬉しい。)
立杭の集落には多くの窯元があり、周辺には十割そばから山里料理、イタリア料理、カフェなどの食事処が、ひっそりと点在している。そこには、目立たず控えめな丹波の暮らしのスタイルが受け継がれている。散策に疲れたら、広々とした露天風呂と湯温の異なるいくつもの浴槽を備えた源泉かけ流しの「こんだ薬師温泉ぬくもりの湯」で時の経つのを忘れることができる。










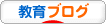



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます