新城兵一詩集『草たち、そして冥界』―死者と境涯を豊穣に生きる
この詩集を会ってもらったとき座興で、西田佐知子の「アカシアの雨がやむとき」を一緒に歌ったのだった。互いにガラ声で。やはりいいね、この唄は。ぼくは今でもよくさっちゃんの唄う数々の歌をYoutubeで聞いている。ほんとに好きだなあ、西田佐知子の歌。鼻から抜けていく高音の声に感情をこめた哀感ある歌い方がとてもいい。新城は翌日からこころの病を持つ弟を看るために宮古島へいくといっていた。十五年前の『生命(ひびき)あり』で新城は日常のなかでまろびのような生のなかにいた。そして、こうだ。
「観念(ゆめ)剥ぐれて/風韻ひょうびょう/生命(ひびき)あり」。
ぼくはこういう表現が好きだ。志から離れたあとの、精神の立っている美というか、立(闘)っている現在からほころぶように出ている。いまこういうふうに歌える詩人はどれだけいるだろうか。<生命>ということば。この文字はどうみても「ひびき」とは読めない。しかし、あえて「ひびき」とルビをふって読ませようとした。これは修辞ではない。これは確信である。このころ五十代初頭。初老(?)の年端で家族という対幻想と絶対性の生業を営みながら、その境涯で自らを問いあるいはその関係にことばを与えるようにして持久した。それは革命青春の理念から陥った観念を突き破る絶対的な生の時間である。夢で転んだ者には、生きることは居心地が悪いものである。この詩句は、詩が、生命に響くものを掬い慰謝するように働くことを歌っていると、ぼくはみる。
『生命(ひびき)あり』がおのれの打ち震えるものや近しき者との生のまろびあいの歌であったとすれば、『草たち、そして冥界』は、自らが関係した者の死へ架橋した歌だ。この詩編のⅡⅢ詩の発端は誰かの存在と死に依拠する。たとえば、父、母、いもうと、上原生男、いとこ、幸喜孤洋、叔母、中屋幸吉、そして青春期の女性……。生と死についての歌は恋の歌と同じようにポピュラリティのものだ。というのは、それは誰にもあることだからだ。だが、生も死も固有のものである。「何物も、生れ落ちると同時に、<ことほぎ>を浴びると共に<のろい>を負って来ないものはない」と折口信夫が書いていたが、それは歌のこと。では『草たち、そして冥界』はなにを歌っているか。これは固有の死に情と思念を届かした言葉が自ずから歌という形をとったものだ。個の日常が終わるのが死だ。その厳粛さが、魂の肉体にしみ、死のリアルが、ついに人の余韻に変わっていく。永遠に不在となる、その現実が死である。されば永訣の歌を、というところだが、新城兵一はさらに詠ずる。親の亡骸を自らの手で清め死装束にし火葬の骨にし、墓に納める行を終えた後、
いよいよ お父さん
おでかけですか
ふたたび帰ってくることのない
最後の たった一人の旅へ
(出立)
おかあの部屋はからっぽです
すっかり灯が消えて寂さびとしています
おかあは出かけてしまったのです
(日傘をさして)
、と。そうか、死とは、おでかけか。不在ではあるが留守であるということか。ぼくは不覚にも感涙しながら読んだ。ブラボー。また「異界論」で他界を、彼方を、カナタを、むこうを、はるかを、どこかを、異郷を、……抽象化して、それをみつめ、それにみつめられる、という関係の、みえざる郷愁の豊饒を連ねた。ここから新城にとって死者を生きることだ、といっている。これは「斯うして彼等は単純に、平和に暮して居るのである。」(池宮城積宝『奥間巡査』)といった沖縄民衆の他界観念にある<死して神となる>という発想とはちがう。
新城はこの詩編をレクイエムといっている。死者を歌った詩篇に脈打つ新城の優しさ、愛が伝わってくる。もっと言おう。死者は歌となって残るものだ。おかあの歌「日傘をさして」。この母の死をとむらうときの眼差し。存在をあらしめた絶対的な死者に流れる鎮魂の情と思念の深さ。もはや外にはいない、母の内なる彼方に言葉を届けている。日本の男は<母>に向かうとき抒情的になる。それは母が自然として言葉を必要としない無意識の根源に存在するからだ。
「なんと詫びようかおふくろに」と「唐獅子牡丹」で高倉健さんが歌った。そんな泥になくとも「吾亦紅」を聴いて、ぼくのような親不孝なものはじんときて涙腺が刺激されるのだ。なぜか?言葉をこえる何かがあるからだ。チャゲ&飛鳥が「言葉はこころを越えない……こころに勝てない」(Say Yes)と歌っていた。しみじみの感性は思わずほろりと出てくるものだ。都会の渦、東京に文学を据えている川本三郎が『同時代を生きる気分』で70年代の大衆化社会における個の拡散現象をシラケと対比して書いていたが、それからどうだ、いまの東京、日本よ。さらに個は無味乾燥な都市空間でばらけて、薄く薄く小さく小さくなりながらさまよっている。政治も経済も社会もよれよれだよ。だが、いまの都市の若い詩人は抒情詩を書きたがっているのだ。抒情詩は個を超える自然感情となりうると思っているからだ。ときにしみじみ、ときに負けずに軽快にいこうぜ。
新城はキリスト教の洗礼を受けたという。考えてみれば「異界論」あたりのみえざるものへの強い観念はその布石ではなかったか。それは転機となるのであるか。かれは本をよく読む。かれの部屋の書架には文学、思想、哲学、宗教の本がずっしりと並んでいる。しかし読んでばかり、それきりではいけない。かれの生存と思考にかけて出てくる何かを書いてほしい、と思う。知の蓄積がもったいないのだ。
詩誌アブ第8号(2010年10月)











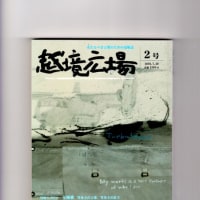
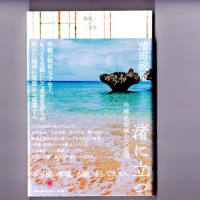
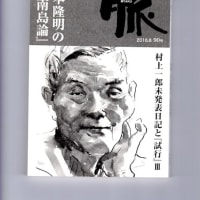
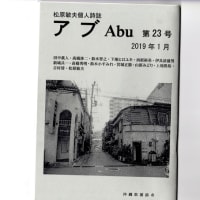
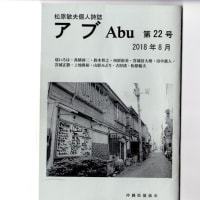
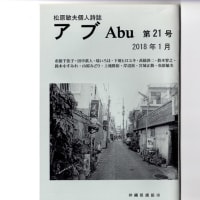
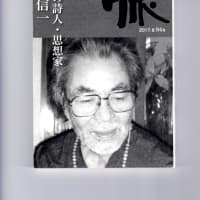
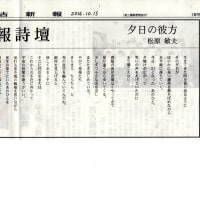
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます