水崎野里子さんが、「流動する今日の世界の中で 日本の詩とは」(「棚」246号(2007年6月))の中で、私の方言詩「いすぱぎの唄」をとりあげ、「ゼミナールの中心イヴェントとなった、沖縄の方言詩は、だが、現在、沖縄だけでなく、有馬敲氏や島田陽子氏が企画の「現代生活語詩集」、すなわち、日常使用されている言葉(非標準語・方言)により詩を書こうという、本土にもある詩の一つの流れと呼応した形で理解すべきであろう。」と書いている。ゼミナールとは2007年2月に那覇市の琉球新報ホールで行われた日本現代詩人会の「西日本ゼミナールin沖縄」のことである。そこで私は宮古方言で書いた作品を朗読した。
私の場合、有馬氏や島田氏のその流れとの呼応ではなく20数年も前からほとんど無連携で方言を使用した詩を書いていた。沖縄で文学をする者が、風土や土着を選んだとき、必ず言葉の異境感=方言の問題にあたるという現実。方言は明治以来の標準語励行や方言札という抹殺政策をくぐり抜けて続いてきた言語だ。統一言語で同化を図ってきた国家教育政策は<国語>を確立するために地方に<言語を失うこと>を求めてきた。矛盾が同居するのが近代である、とヴァレリーは言ったが、日本の近代はまさに歪な近代である。
方言は語彙や語呂、語音の面白さがあって<言葉遊び>のような広がりが作れるので、私も方言を故意に使ったりするが、そのときに<こそばゆさ>が出てくる。その<こそばゆさ>が方言の魅力でもあると私は思っている。方言は身体に流れる言語感、みえざる世界に底流する血のリズムを持っている。そのリズムが湧くとき思わず方言が吹き出してくるのは誰しもあることだ。
しかし私は、方言詩を生活語詩と思って書いてはいない。方言を<表現言語=芸術言語>のように可能化できないか、方言がその土臭さゆえに<表現として扱われていない現在>を突き抜けられないかと思ったりする。
方言で詩を書く人が多くなっているが、まだ個の表出として、あるいは詩の言語として新しい意味を作り出す言語に引き上げてはいないようだ。それは方言が意味の表出になおアポリアを抱えているからかもしれない。それに方言は圏外の他者へ意味を伝達する機能障害があると残念ながら言わざるを得ない。だから他者に読まれる詩(作品)を書くには支配的言語(標準語)を使用せざるをえない。「現代詩は結局、標準語の世界であるし、語弊をおそれずにいえば、都会に位置している」(藤井貞和「作井満の詩集」)というわけだ。それに方言は言葉を継承するシステム=表記法を持っていない。口と耳で続いてきた言語だ。つまり方言は<書き言葉>ではないのだ。
崎山多美がどこかで方言を日本文学にテロルのように使うというような言い方をしていたが、それほどの攻撃性は方言にはありえない。なぜなら日本文学は言葉の受容と排除と無視を繰り返してどん欲に変容するシステムを持っているからだ。そのシステムの中に沖縄の文学も取り込まれ、円周しているにすぎない。日本文学の枠組みの中で書いている限り方言は異境や辺境の言語として扱われる。もしそれを切り返したいなら、沖縄文学=(沖縄語・琉球語)文学として徹底するしかない。そのとき、沖縄方言は辺境という地位ではなく中心の言語として沖縄文学を生み出すバックボーン言語として自立する道が開けるだろう。だがそれは消滅していく少数民族言語のような現状に出会う。方言は使用する世代と場所を喪失しつつある。我々の言語生活をみるがいい。継承をゆだねる子供達に方言で話している家庭がどれだけあるのか。方言は家庭だけでなく学校やビジネスで普通語として使用されない限り存続しないだろう。2006年3月に9月18日がシマクトゥバの日として条例化され、方言を薦めるご時世となったが、言語を制度化する臭さを感じさせる。言葉は必要性、自然発生で使用されるべきだ。
方言は野菜サラダのようでもあるし、常に必要なものでもない。たしかに標準語は藤井がいうように「都会に位置している」わけだが、方言を身体に宿しているものにとっては風土や地方性を脱色する都会の言葉=標準語を照射する視座を持つことができる。これはアイデンティティという問題よりも自らのたつ母語と裂け目を問い直すことでもある。方言を意識して書いている物書きたちはそこから発生する言語の課題を負っている。方言を自己表現としての言葉として確立する課題をつきつめるべきだ。











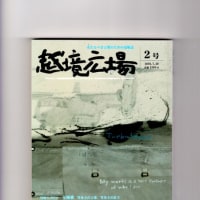
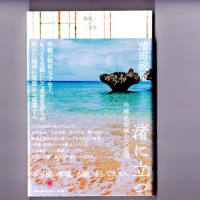
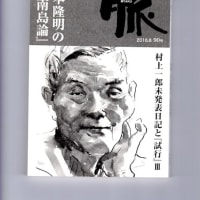
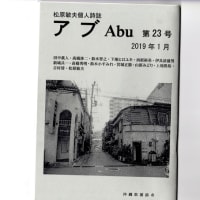
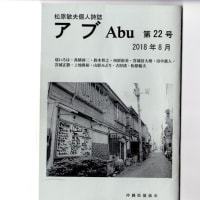
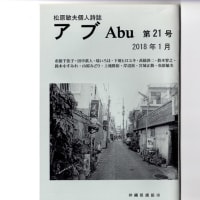
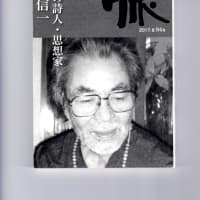
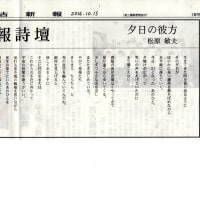
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます