
前回に引き続きアンディ・ウォーホルの作品を数点、取り上げて彼が表現したかったことはなんであったのかを考えることにしましょう。
表題の画像は前回の32個のキャンベルスープ缶の系列に属する作品です。
多数のコーラボトルを規則正しく配列した作品です。
タイトルは「緑色のコーラボトル」となっていました。
また、次のような作品もあります。

毛沢東の肖像写真を並べたものです。これも前回のモンローの作品とほぼ同じです。
これ等の作品に共通するものは何であるのかが、気になりました。
直ぐ気がつくのはその配列の仕方です。
規則正しく同一の対象が複数、置かれている事です。
そして、描かれているものは、かたやキャンベルスープ缶であり、そしてコカ・コーラの瓶である事です。どちらも日常的に大量に消費されている商品なのです。
アンディ・ウォーホルは元はコマーシャル・アーテイストとして、商品のポスターなどを造っていましたので、それらの「商品」をアートの対象にしたのだと考えるのが自然と思われます。
ですが、その理由以外にも「規則正しい商品の配列」にこだわったのには、何か理由があるはずです。
規則正しさは、それらの商品が売られている場所に行ってみれば、一目両全です。
私たちがスーパーに行ってみるとわかりますが、同じ品が棚に整然と並べられている光景を見ることが出来ます。
その光景に私たちは今では何の不思議さを覚えませんが、このような物体の配置の仕方は実は大量消費社会になってから始まった事のように思われます。
ウォーホルがこれらの絵画を制作し始めた時期は1960年代です。このころのアメリカ社会に、スーパーマーケットで同一商品を大量に棚に陳列するという販売方式が採られていたのではないかと想像できます。
さて、このような反復する物体を描いた作家に、わが国の草間彌生氏がおります。彼女もまた規則正しい水玉の配列の作品があります。
彼女はただひたすら無数の水玉を巨大なキャンバスに描きました。その制作過程の映像をテレビで紹介をしていたのを観ると、ただひたすら同じ作業を繰り返していたのです。
このように見てくると、それらの作家により表現されたものを私たちが見るときには、それを見た人がその反復の意味は人により異なっているにせよ、少なくとも私たちの日常も何らかの反復であるのは間違いないと思うのです。
これ等の意味で、ウォーホルや草間彌生の作品は現代を「模倣」したものだと言えるでしょう。
表題の画像は前回の32個のキャンベルスープ缶の系列に属する作品です。
多数のコーラボトルを規則正しく配列した作品です。
タイトルは「緑色のコーラボトル」となっていました。
また、次のような作品もあります。

毛沢東の肖像写真を並べたものです。これも前回のモンローの作品とほぼ同じです。
これ等の作品に共通するものは何であるのかが、気になりました。
直ぐ気がつくのはその配列の仕方です。
規則正しく同一の対象が複数、置かれている事です。
そして、描かれているものは、かたやキャンベルスープ缶であり、そしてコカ・コーラの瓶である事です。どちらも日常的に大量に消費されている商品なのです。
アンディ・ウォーホルは元はコマーシャル・アーテイストとして、商品のポスターなどを造っていましたので、それらの「商品」をアートの対象にしたのだと考えるのが自然と思われます。
ですが、その理由以外にも「規則正しい商品の配列」にこだわったのには、何か理由があるはずです。
規則正しさは、それらの商品が売られている場所に行ってみれば、一目両全です。
私たちがスーパーに行ってみるとわかりますが、同じ品が棚に整然と並べられている光景を見ることが出来ます。
その光景に私たちは今では何の不思議さを覚えませんが、このような物体の配置の仕方は実は大量消費社会になってから始まった事のように思われます。
ウォーホルがこれらの絵画を制作し始めた時期は1960年代です。このころのアメリカ社会に、スーパーマーケットで同一商品を大量に棚に陳列するという販売方式が採られていたのではないかと想像できます。
さて、このような反復する物体を描いた作家に、わが国の草間彌生氏がおります。彼女もまた規則正しい水玉の配列の作品があります。
彼女はただひたすら無数の水玉を巨大なキャンバスに描きました。その制作過程の映像をテレビで紹介をしていたのを観ると、ただひたすら同じ作業を繰り返していたのです。
このように見てくると、それらの作家により表現されたものを私たちが見るときには、それを見た人がその反復の意味は人により異なっているにせよ、少なくとも私たちの日常も何らかの反復であるのは間違いないと思うのです。
これ等の意味で、ウォーホルや草間彌生の作品は現代を「模倣」したものだと言えるでしょう。

















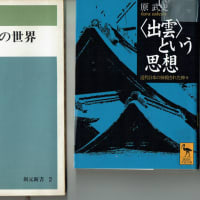



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます