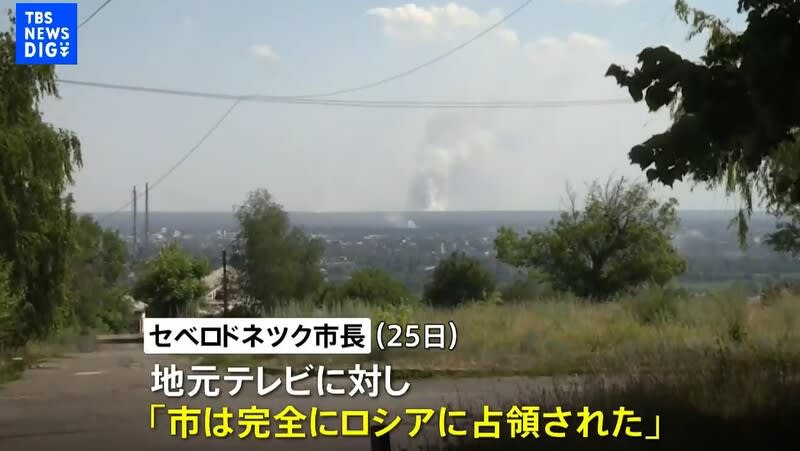◆ ロシアによる侵略から4か月 現状は 東南部戦線におけるロシア軍の支配の固定化
◆ ロシアによる侵略から4か月 現状は 東南部戦線におけるロシア軍の支配の固定化
日本において報道されるウクライナ情勢については少しずつだが、扱いが減少しているように感じられる。たまたま参議院選挙の公示があり、日本社会における関心が特に報道関係はそちらの方に向いているようで、そのぶんだけウクライナ問題が遠のいているような印象を受けるのだ。
戦闘状況はウクライナ軍の徹底的な抗戦によって、侵略者ロシア軍は東南部に焦点を合わせて軍事力を集中させ、ドネツク州やルバンスク州を事実上掌握したという形になっている。その地ではいわゆる「ロシア化」が進められ、言語のみならず社会生活も通貨のルーブル使用、ロシア政府によるパスポート発給など掌握された地域が、すでにロシアであると言う既成事実化が着々と進められている。

一方この地域で最後までウクライナが抗戦していた、ゼロドネツクから撤退したことをゼレンスキー大統領は発表する。その街がすでに徹底的に破壊され、ここで交戦していても意味がないと判断したということだろう。
他方ではゼレンスキー大統領は、掌握されたドネツク州やルガンスク州を必ず取り返すと宣言している。これまで西側諸国に最新兵器の貸与を申し出ていたが、その一部がウクライナへ到着しつつある。これらの使用訓練を経ておそらく7月から8月にかけて、ウクライナ側の総反撃が開始されるものではないかと考えられる。
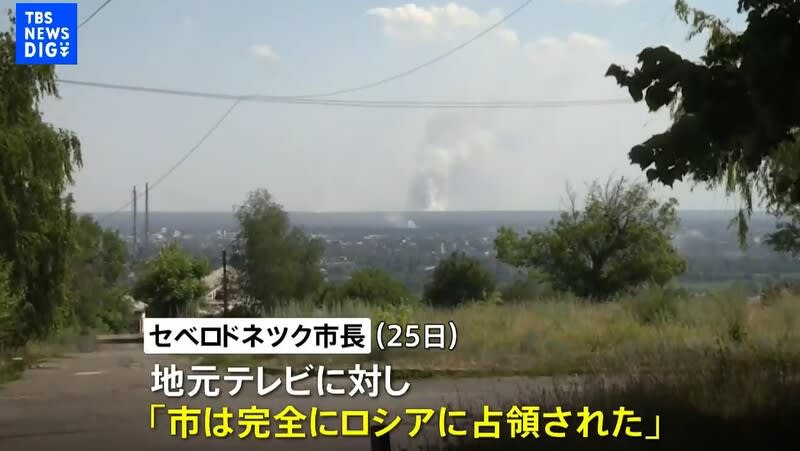
ロシアがクリミア半島をすでに自国の領土にしている実態に対して、黒海沿岸部を全て押さえることが、ウクライナを内陸化して力を弱めるのに大きな戦略的価値があると判断しているのは明らかであり、この地域についても今後、ウクライナ軍の反撃が行われるものと見られる。その意味では夏場にかけての両国の戦闘はかなり激しいものになることが予想される。
先日の国連の発表によれば、ウクライナ軍の戦死及び民間人の犠牲者は約4600人余り。負傷者が5000名以上となっている。実際には混乱した状況の中でつかめない部分もあるので、ウクライナ側の死者は優に1万人を越しているものと考えられている。
同時にロシア側の発表がないので詳細は不明だが、ロシア軍の兵士の死者はおそらく15000人を大きく越えているものと考えられている。特にロシア軍においては一人一人の兵士の意欲の低下が指摘されており、厭戦気分が広がっていると言われている。
そんな中つい先日、ロシアの友好国であるとされるベラルーシが要求していたロシアの最新鋭ミサイルが供与されることになった。そのミサイルは通常弾頭だけではなく、核弾頭を装着できるものであり、事と次第によってはベラルーシが軍隊をロシアに協力する形でウクライナへ派遣、同時に核による脅しで西側に手を出させない狙いがあるのではないかと考えられる。ベラルーシが自力開発でなくとも、核弾頭をロシアから購入すれば即「核保有国」ということになる。核拡散防止条約どころの話ではなくなるのだ。
さらにロシアはプーチン大統領が、先日改めて「ロシアには核兵器があるのだ、最新鋭ミサイルがあるのだ。」と改めて演説で述べて西側諸国の支援体制にくさびを打とうとした。

こういったところから夏場の戦闘状況によれば、再度ロシアによる核兵器の使用が現実味を帯びてくる。その場合に西側諸国の核保有国及びアメリカが、報復攻撃をすることになるのかどうかが大きな焦点となってくる。今やロシア、そしてプーチン大統領はまさしく狂気の沙汰といった状態にあるのだ。もはやあげた拳を収める機会は無いものと思われる。つまりあげた拳は勝利の拳として、ロシア国民に示さなければならないのだ。その最低限の中身がウクライナの南東部及び黒海沿岸地域の完全掌握ということになる。
◆ 経済制裁の結果「エネルギー資源」「穀物資源」の世界的な不足の問題が顕在化
西側による経済制裁は時間はかかるものの、じわじわと効き目を出しているのではないかと考えられている。プーチン大統領は通貨ルーブルの価値が一時的に落ちただけで、今現在では元に戻っているとして制裁の影響はほとんどないに等しい、と国民に話した。しかし様々な日常生活用品等の不足、及び値上がりと言ったインフレは確実に進行しているようだ。ロシアは決して豊かな国ではない。一般市民の国民生活の実態はごく一部の裕福層を除いて後は、中産階級まではいかない国民が大半だと思われる。そういった意味では日常生活用品や様々な商品の値上がりというのは必ず大きく効いてくるはずだ。
しかし一方では、ロシア及びウクライナはエネルギー資源においても穀物資源においても世界有数の生産地であり、同時に輸出国でもある。
この間ロシアは中国と急速な接近を見せており、最近では他にインドや南アフリカなどいくつかの国を集めてリモートで経済会議を行っている。ロシアにとってみれば、中国やインドといった13億14億の人口を抱える国に輸出すれば、それなりにやっていけるということになるだろう。少なくとも中国は西側の経済制裁には真っ向から反対しており、ロシアとの経済関係を密接にすることには前向きであり、これからどんどん進めると宣言している。
これらのことはとりもなおさず、世界にはいくつかのウクライナ侵略戦争を追認する国があるということを意味しており、その中で一般人に対する人権侵害をなんら気にしない国があるということを意味する。やはり国と国の間の利害関係というのは究極のところ、個々人の人権は何ら保障されないし、虐殺だろうが何だろうがそういうものは関係ないということなのだ。

そしてウクライナについては、小麦の大輸出国であり主要な輸出港であるオデーサが、ロシアによって封鎖されており、事実上輸出ができない状態に置かれている。そのためにオデーサの倉庫などには莫大な量の小麦が置かれたままになっているとのことだ。もちろんロシアも同様に小麦など穀物類の大輸出国であるが、西側制裁による報復措置で友好国以外への輸出を止めている。
このことによって日本では、小麦価格が大きく上昇し、うどんやラーメン、パンなどなど主要な食べ物が大きく値上がりする。あるいは販売不可能になると言った心配をする声が出ている。同時にロシアのエネルギー資源である天然ガスは、ヨーロッパにとって欠かせないものであるが、この輸出がストップされるという事態になっている。当然その分は OPEC諸国 の方に、またアメリカに協力を仰がざるを得なくなるのが確実だ。
日本においてはすでにガソリン価格の大幅な上昇を現段階では、国費を出して押さえ込んではいるが、これは税金を使っているということであり、車のガソリンを使う者と使わない者では不公平が出るような仕組みになっている。
このような状況にある日本では、火力発電所の再稼働や原子力発電所の再稼働を急いで行うべきだと言う声が強まっている。しかしまがりなりにも先進国だと言われている日本においては、現在の生活水準を保つために様々な政策をとったりしているが、日本のようにあまり危機感のないような、のんびりした言い方では済まない国々が世界には圧倒的に多いのだ。
 ◆ 世界規模でのエネルギー危機と食料危機が目の前に迫っている
◆ 世界規模でのエネルギー危機と食料危機が目の前に迫っている
ロシアによるウクライナへの大義なき侵略戦争の結果、今現在世界は「核の脅威」にさらされている。そしてさらにじわじわと「エネルギー危機」「食糧危機」が今以上に悪化すると言う脅威にさらされている。
日本や西ヨーロッパ諸国などのいわゆる先進諸国においては、かなり発展した2次産業3次産業の実態から、様々なエネルギーというのはどうしても必要としか言いようがない。地理的な要因で自国ではエネルギーを産出できない国が、その中には多い。従って地理的に恵まれた地域から輸入という形で補うわけだが、先進国の中でもアメリカとなると、自国でエネルギーが賄えるという条件がある。こんなに強い立場の国というのはそうざらにはない。そういった意味では西側諸国の中でも、ロシアを非難する言葉の内容も若干違ってくることがあるようだ。
それでもまだ先進国といわれる国々はまだいい方だろう。アフリカや南アジア、更には発展途上国と呼ばれているが、事実上「貧困国」と言わざるを得ないような国々が多数ある。特にアフリカにおいては長年にわたり、アフリカ大陸各地で部族間や宗教対立などなど様々な原因で、局地的な紛争が続いており、特に天然資源のある地域では、バックに欧米各国などが付いて武器供与などをしながら、利権の争奪戦が行われてきた。
その結果は形式的なな独立国は多いものの、実質的には民主主義が確立せずに国の経営が困難であり、当然経済的にも困難であり、一部の権力者が軍隊を伴って強圧的な支配を続けている国々が多数見られる。
かつてそのような、争いに国連が国連軍を投入して収めようとしたが、逆に大きな被害を出してしまい、最終的には国連軍も撤退せざるを得ないほどの事態に陥ったケースもあった。こういった国々は地理的な条件も恵まれておらず、穀物原料などは輸入や支援に頼らざるを得ない事態となっている。そういう事態にある中で、穀物の輸出大国が事実上輸出ができなくなるということは、これらの国々に大変な「飢餓」をもたらす事が容易に予想される。その結果各地で大勢の人々が餓死するような状態が現れるのが時間の問題となっている。
ただ南アジアやアフリカ諸国に対しては、中国がかねてより一帯一路政策により大金を投じて、それらの国々に支援するということを名目に、インフラ整備を行い、事実上該当国の港湾施設や空港などを整備しながら実効支配し、軍事拠点化するということを行ってきた。そしておそらく食料支援を行うことによって、さらに中国への依存度を高め、友好国というものを増やしていく動きが出てくるのは間違いないだろう。
一帯一路政策は手詰まり感があるという声もあるが、決して侮ってはいけないと思う。国連における各国の持っている一票というものは、先進大国であれ小さな途上国であれ、同じなのだ。これがいざという場合に何らかの形で反映されることになるという可能性が十分にある。
 ◆ ウクライナ情勢は、7月から8月に大きな山場を迎えることになるだろう
◆ ウクライナ情勢は、7月から8月に大きな山場を迎えることになるだろう
上にも記したように、アメリカを中心とする西側諸国の最新鋭兵器を含む様々な武器がウクライナに届き始めている。アメリカのミサイルはピンポイント攻撃が可能だと言う。今や人工衛星からの情報によって、軍隊の動きや基地の場所、移動の様子などはそれこそピンポイントで刻一刻全て把握できる状態だ。その位置座標を入力するだけでミサイルはその場所へ飛んで行く。すでにロシア側はそのようなミサイルを使用して、今日も首都のキーウに10数発のミサイルを打ち込んでいる。幼稚園にも命中したと言う。相手が軍人であれ民間人であれ、子供であれ関係なしだ。誰を殺してもいいというのがロシアの立場だ。
何としても国を守る、取り返すというウクライナ人たちは、この4ヶ月間で受けてきた残虐なやり方に激しい憤りを持っている。そのぶん新たな兵器を得て局地的な攻撃をあちこちで始めるだろう。
そんな中である意味何が起こっても不思議ではない。どこの国の人も「事と次第によっては」ということを考えておかなければならないという状況にあるのだと思う。
(画像はTVニュースより)