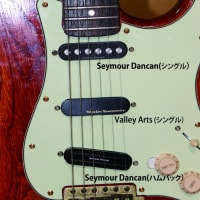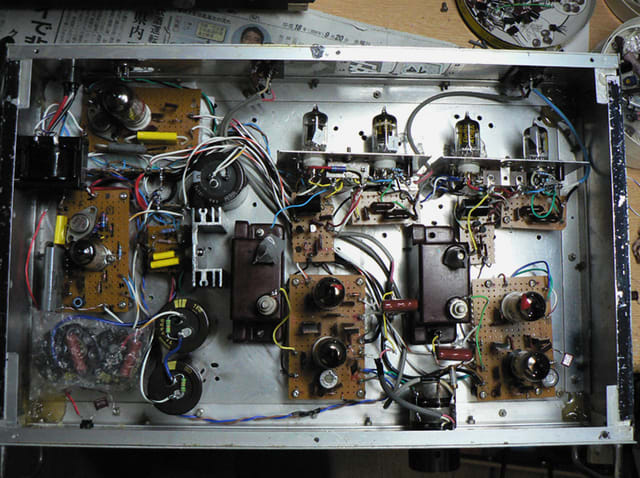
2006/12/3
クリックすると元のサイズで表示します
ようやく金田式真空管DCプリアンプの試作ができた。
なんとか数年前の失敗が取り戻せた感じだ。オリジナルとはあちこち
異なるが、まあ良しとしよう。低音用の金田式UHC-MOSのパワーアンプの
ゲインが高いもので、プリとしては使いづらくて結局、音量調整は
オリジナルのやり方を止めました。NFは固定抵抗とし、出力と
出力端子との間にスケルトン抵抗20KΩを入れて、50KΩのVRを
アース間に入れるというアッテネータ方式をとりました。
これで随分使い易くなりました。昔は金田氏もそういうやり方を
していたのを思い出してやってみました。
昨日から今日にかけては、2Wayマルチアンプ方式となっているのを
チェックしてみました。昨日までは、低音に金田式UHC-MOSのパワー、
中高域にSATRI-ICパワー(モノ2台)という構成でした。
どうも高域のキレが気になっていたので、これを逆にしてみました。
するとなんとなく、石のフラットアンプを使ったときのように
音が少し引っ込む感じです。以前からこの傾向は感じていたので
金田式の特徴かと思っています(アンプが厳密にオリジナルを
模してないからかも)。
ということで、手持ちのアンプを試すことにしました。
以前、K-yasuさんから提供してもらったDCアンプを使ってみました。
このアンプは、中高域が綺麗な音がします。
これは、なかなかいいです。
次は、もうかれこれ30数年は経つクリスキットのP-35.
これも、高域の張りは結構いいですね。少々賑やかな感じもあり。
ということで、K-yasu式アンプを使うことに決める。
が、このアンプは、VRが入っていたり、ちょっとSP端子が
使いにくい構造なので、少し手をいれる必要があるので、
とりあえず、今日のところはP-35を使うこととする。
ただし、ケミコンがさすがに古いので、手元に余っていた
ELNAにAUDIO用22,000μFに取り替える。ついでに電源部の配線材を
取り替える。何しろ、配線は球アンプに使うような、細い単線だったから
です。確か、半田メッキされた拠り線だったはずだが。
採用されたのはVer2からだったかも。
少し、中域が余裕のある音になった感じがする。
これで、夕方までレコードを聴き、最後に 例のWE429Appに
換えてみる。
うーーーん、弦楽器やボーカルは俄然、こちらがいい。
CDのプリはSATRI-ICのに換えてある。レコードもいい感じだ。
ということで、低域はSATRI-ICのパワーアンプに決めて
中高域を取り替えて楽しむというのもいいみたいだ。