
とつぜんですが、司馬さんの「覇王の家」を紹介します。
当分、忍者ものの本を紹介しようと思っていたのですが、ちょうど「覇王の家」を読み終えたので、この本を紹介します。これは徳川家康の一代記。確か、大学生時代に1度読んで、当時の印象は「つまらない」でした。
しかし、小説というのは、体調や、そのときの環境で「おもしろかったり」「つまらなかったり」すると思っているので、「つまらない」と感じた本はベストの体調のときに、もう一度読み返すようにしています。
なぜ「真田太平記」を読み終えていないのに、読んだかというと…。
池波さんの一連の忍者ものを読むうち、徳川家康という男に興味を持つようになりました。
もともと、家康には興味がなかったんですが、池波作品には巨大な男として彼が描かれています。(どの作家の作品でもそうですが…) とくに、池波さんは真田ものをライフワークにしていらしたので、常に「対・家康」というのが頭にあったと思います。だから、読者もつい「対・家康」観を持つんですね。
読んでいて思うのは、家康という人はとにかく言動と行動が一致しない。羊の皮をかぶった狼というか、まさに善人のふりをした悪人かのような印象が湧き上がってきます。そこで、家康という人物をじっくり考えてみたくなり、「覇王の家」を読み始めました。
<感想>
この作品を読んで改めて思ったのは、秀吉も家康も主人の天下を奪ったことには変わりがないんですね。しかも、どちらも謀略の限りをつくして。
ただ、後世の人や当時の人の2人の印象が違うのは、よく書かれていますが、秀吉は常に陽気で、度量があった。だから、秀吉の天下統一は爽快感があり、多くの人に、農民から天下取りが出たとの夢を与えた。
しかし、家康は吝嗇の上、律儀者のふりをしていた。この律義者というのが曲者。ほんとの律義者なら秀頼に最後まで忠誠を尽くしたはずだから。律義者のふりをしながらも、主家の家を謀略で奪い取ったから良いイメージがない。しかも、彼の謀略には権力者が時として見せるみえみえのずるがしこさがある。ま、そこがタヌキ親父なんだろうけど。この本には、家康がなぜそんな性格になったのか、という理由がさまざまな例とともに挙げられています。
<評価>☆☆☆☆★
2度目は、非常に読み応えを感じ、思わずうなってしまうところが多かったです。
たとえば、家康がその家臣団にはなぜ薄給だったのかとか、対信長との関係や、彼の生涯は常に模倣の人生だったとか。
読み応えはありますが、信長の「国盗物語」、秀吉の「新史太閤記」と続けて読むと挫折する人もいるんじゃないでしょうか。かつてのオレもそうでした。2作品は娯楽歴史小説といっていい作品ですが、「覇王の家」は「家康という人物を考える本」で2作品とは性格を異にしている感じがします。
<最後に>
今までは、徳川家康は「運がいいヤツ」「ずるいヤツ」なんていう印象がありましたが、この本を読んで「恐ろしい人」「非常に自制心が強い人」「世渡りがうまい人」という考えに変わりました。家康という人は、やはり人生の達人だったんですね。










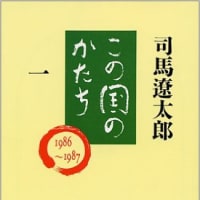
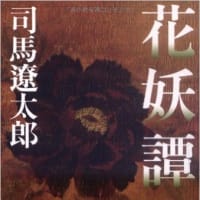
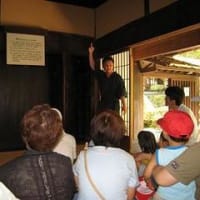
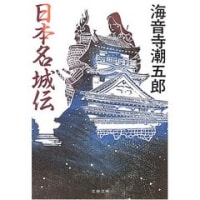
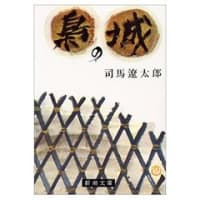
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます