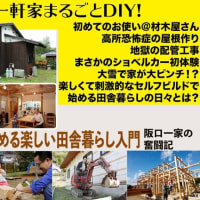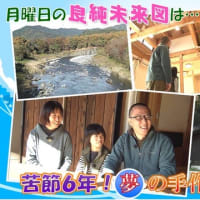それでは次に、腰掛けアリ継ぎのメス側の刻みにいってみます。
はっきり言いまして、私のやり方は完全に自己流で、
本職の大工さんが見たら絶句するかと思われますが、お気になさらずに。。。
まず墨付けはこんな感じです。

前にも書きましたが、腰掛けアリはT字に交差するところに多用しますので、
そこには柱も来ることがとても多いです。
ですので、一緒に柱の刺さる平ほぞのメスも作ります。

まずはアリの斜め線にそって、深さ6cmに合わせた丸のこで切り込みを入れます。

次に角ノミで、平ほぞの穴をあけます。
柱が土台へ刺さる場合、ほぞは貫通していた方が良いとの情報もあったのですが、
本によっては貫通させる必要なしとのものもありました。
貫通させない場合は、メスの穴はオスのほぞより半寸程度深くとのことでしたので、
メス穴を10cm、オスほぞを9cmにすることにしました。
ここからが自己流手抜き作業なのですが、

そのまま角のみの深さを6cmに合わせて、アリのメスの部分を掘ってしまいます。

さらに、横移動して腰掛けの部分も掘ってしまいます。
これは、ほんとは精度が出ないのでいけないですね、ホント・・・
基礎の上におく土台だから許されるやり方かな。
頭上の梁がこの組み方だったら、私もいやですもんね(--;)
さて角のみで、ざっと掘っただけなのでバリが多いです。
それをさらっていきましょう。

まずは、はじめに丸のこで掘った斜め線の部分を、きっちり下まで切ります。

次にノミでバリをとっていきます。

どんどんとります。

そして完成です!!

オスをはめるとこんな感じです。
何とかなりそうですね。。。あーしんどかった。
はっきり言いまして、私のやり方は完全に自己流で、
本職の大工さんが見たら絶句するかと思われますが、お気になさらずに。。。
まず墨付けはこんな感じです。

前にも書きましたが、腰掛けアリはT字に交差するところに多用しますので、
そこには柱も来ることがとても多いです。
ですので、一緒に柱の刺さる平ほぞのメスも作ります。

まずはアリの斜め線にそって、深さ6cmに合わせた丸のこで切り込みを入れます。

次に角ノミで、平ほぞの穴をあけます。
柱が土台へ刺さる場合、ほぞは貫通していた方が良いとの情報もあったのですが、
本によっては貫通させる必要なしとのものもありました。
貫通させない場合は、メスの穴はオスのほぞより半寸程度深くとのことでしたので、
メス穴を10cm、オスほぞを9cmにすることにしました。
ここからが自己流手抜き作業なのですが、

そのまま角のみの深さを6cmに合わせて、アリのメスの部分を掘ってしまいます。

さらに、横移動して腰掛けの部分も掘ってしまいます。
これは、ほんとは精度が出ないのでいけないですね、ホント・・・
基礎の上におく土台だから許されるやり方かな。
頭上の梁がこの組み方だったら、私もいやですもんね(--;)
さて角のみで、ざっと掘っただけなのでバリが多いです。
それをさらっていきましょう。

まずは、はじめに丸のこで掘った斜め線の部分を、きっちり下まで切ります。

次にノミでバリをとっていきます。

どんどんとります。

そして完成です!!

オスをはめるとこんな感じです。
何とかなりそうですね。。。あーしんどかった。