*他紙(市誌研究ながの26号)に投稿したものですが、坂井衡平の業績をネットで検索できるようにブログにあげました。字数制限により抜粋になります。
坂井衡平は、善光寺研究における最高レベルの学術書『善光寺史』の著者として知られる。その研究は著者の存命中には刊行されず、没後も長い間、信濃教育会資料室に保管された清書原稿が一部の研究者に閲覧されただけで、光が当たることはなかった。衡平が亡くなって33年経った昭和44年(1969)に、東京美術社から上下2巻、1200頁に近い本として発行された。

『善光寺史』に関わる調査は、長野市教育会の援助のもとで行われ、依頼を受けた衡平が日本各地へ足を運んで、大正13年(1924)から昭和8年までの9年という短い期間で脱稿した。参照した文献は818件と膨大で、孫引きがない。衡平は、東京大学国文科を首席で卒業した俊傑であり、卒業9年後から始まった善光寺研究は、恵まれた才能を生かし順風満帆な境遇の下での研究活動であったと誤解してしまいがちである。しかし、善光寺の調査を始めた頃の衡平は、大学の研究室から放逐され定職をもたなかった。自らの生計よりも国文学、郷土史研究を優先し、生活は極めて質素であった。家庭を持たず独身を貫き、滅私の精神で大作『善光寺史』の調査に精力を傾けた。さらに、専門の国文学分野では『今昔物語集』の研究をはじめ優れた業績を残し、著作は十冊以上にのぼった。
しかし、衡平の人物像に関する著述は少なく、断片的なものしか残っていない。衡平の死後八十年以上が経過し、彼を直接知る世代がいなくなった現在、彼の生涯を評伝としてまとめることは遅きに失した感がある。郷土のために貴重な研究資料を残した偉大な先人に光を当てることには大きな意義があり、衡平の生家の協力を得ながら、彼に関する資料を収集し、その人物像と業績をまとめた。
写真:坂井衡平肖像(昭和六年四月撮影)

1.いままでの坂井衡平に関する著述
坂井衡平の人物像について述べられたものはいくつかあるが、いずれも断片的なものである。はじめて、衡平の人物像について記したものは、昭和四十二年(一九六七)に信濃教育会の機関誌『信濃教育』へ金井清光が寄稿したものである(2)。金井は専門としていた時宗研究のため、昭和四十年に信濃教育会(長野市)を訪れ、衡平が著した『善光寺史』の清書資料を目にし、その内容に驚き、資料の存在を世に知らしめるために、『善光寺史』の概要について寄稿した。金井は、昭和四十二年に『時宗文芸研究』を刊行し、その中に『信濃教育』へ寄稿した内容に加え、西尾光一との手紙のやり取りの中で得た衡平の人物像を付記した(3)。また、同年に中世文学会の秋季大会が信州大学教育学部で開催され、金井と土屋弼太郎(衡平と長野県師範学校で同級)が、「坂井衡平氏の人と学問」というテーマで公開座談会が行われた。
金井が中心となったこれらの啓発活動が契機になり、『善光寺史』刊行に向けた動きが始まり、二年後に刊行が実現した。注目すべきは、まったく衡平と接点のなかった金井が、昭和四十二年に衡平について触れるまで、衡平の師範学校同級生、東京大学時代の知人の誰もが公の刊行物で衡平のことを触れていない点である。彼らの中では、衡平を語ることはタブーであり、晩年の衡平が孤立して、知己のあった人々を遠ざけていたという事が関係しているのであろう。長野県師範学校同級であった土屋弼太郎は、衡平を直接知る人物であるが、先の金井が企画した信州大学での座談会で、初めて公に対して衡平のことを語っている。
翌年の昭和四十三年に、西尾光一が雑誌『中世文学』で衡平について著述しているが(4)、これは、前述の信大座談会で司会を務めた西尾が、会の内容をまとめて学会誌に報告した形で、自主的な投稿ではない。西尾の父である西尾実は衡平と東京大学の同級であったが、息子の光一は衡平とは直接の接点はなかった。
昭和四十四年に『善光寺史』が刊行され、その後記に金井が衡平の生涯を概説している(5)。その翌年に、信濃毎日新聞編集局長であった坂本令太郎が、雑誌『日本の屋根』に「近代を築いたひとびと」として連載しており、その中で、「坂井衡平―東大を追われた孤高の学究」と題して取り上げている(6)(翌年に書籍化)。昭和四十五年に上伊那教育会雑誌『上伊那教育』で、「坂井衡平先生の業績と生涯」が特集され三人が寄稿している(7‐9)。上伊那は衡平の故郷であり、この企画は当時の『上伊那教育』編集委員で、衡平の親族でもあり生前の衡平と交流があった酒井源次が主導した。最後の稿は衡平の甥にあたる坂井喜夫が寄稿し、編集後記には酒井源次が衡平の思い出を述べている(10)。
その後、坂井衡平を評価する機運は下火になった。昭和六十一年に発刊された『長野師範人物誌』に衡平の記述があり、人物像と衡平が作詞した長野師範学校寮歌が掲載されている(11)。平成四年(一九九二)には吉原浩人が国文学の分野から衡平を取り上げている(12)。平成十二年に小林計一郎が著書『善光寺史研究』で坂井衡平について簡単に述べている(13)。平成十九年、善光寺門前の東町で古本屋光風舎を経営していた田中博文が自身のホームページで「坂井衡平の善光寺創建論」を述べ、さらに衡平の生涯の概略を記している(14)。
以上の衡平に関し記述された文献の中で、金井清光の『信濃教育』寄稿文、『上伊那教育』の衡平特集は、衡平と知己のあった甥の坂井喜夫、長野県師範学校の同級であった土屋弼太郎からの情報を基に記述され信頼性が高い内容である。しかし、晩年の衡平は、土屋弼太郎とも接点は持たず、甥の喜夫も遠方であったため、衡平の最後に関しては推測による記述内容が多い。今回、坂井家に残された衡平関連の資料から衡平の生涯を述べ、特に、衡平の晩年に唯一の友として親交があった佐藤新作(東京高等師範学校の同級生)の書簡が見つかり、晩年の衡平の様子が明らかになったので後述する。
2. 衡平の出生と幼少時代
衡平は、明治十九年(1886)一月一日に上伊那郡西春近村赤木(現伊那市)で出生した。父は坂井喜平(嘉永元年生)、母はゑい(嘉永四年生、東春近村中殿島の飯塚伝蔵の長女)で、五人兄妹の末っ子(次男)であった(図1)。坂井家は当地で名主を務めた名家である(写真3)。赤木地区には「さかい」姓は多いが、漢字の「酒井」姓が多く「坂井」は少ない。明治二十二年八月、衡平が三歳の時に父喜平が亡くなっている。一家の大黒柱が亡くなり坂井家は困窮した。衡平の一一歳年長の兄(長男)の坂井喜扶(きすけ)が家督を継いだ。喜扶は軍人で日露戦争にも出征し、陸軍工兵特務曹長を務めた(写真4)。大正十四年(1925)六月に五十歳で亡くなっている。父の没後、残された家族を軍人として支えた兄への感謝と功績をたたえた衡平の弔文が実家に残っている。姉二人は酒井家と春日家に嫁いでいるが、三女の姉・たけのは一七歳で亡くなっている。
図1 坂井家の系図

写真3、坂井衡平の生家(伊那市西春近、赤木駅の近く)

写真4 衡平の兄 坂井喜扶

3. 長野県師範学校、その後の教員生活
衡平は村にある西春近尋常小学校(現西春近南小学校)を卒業した。明治三十五年(1902)、16歳で長野県師範学校に入学した。同期生には土屋弼太郎、山岡勘一、峰谷義一がいた(11)。当時の師範学校は軍隊式の教育が行われ、生徒全員が寄宿舎に入った。衡平が入学した年に、皇太子(後の大正天皇)の長野県師範学校への視察訪問があった。在学中の明治三十七年には日露戦争が始まり、軍人であった兄は出征している。在学中から師範学校の学友会雑誌に、「剣峯」の号で詩歌や評論を投稿し『万葉集』に親しんだ。文学全集本を買い込んで、「僕は一生かかって此研究をやるんだぜ」と言って、周囲の友人を驚かした(4)。明治三十九年三月に長野県師範学校を卒業し、小学校正教員免許を取得後、春近尋常小学校訓導として赴任した。写真5,6は、衡平が実家に戻った際に家族と一緒に撮影したものである。
写真5 衡平が長野県師範学校在学中の家族写真。前列、右 母ゑい、中 兄喜扶、左 義姉 いちゑ、後列 衡平(明治三十八年一月撮影)

写真6 明治四十年頃の家族写真(後方右が衡平)

4. 東京高等師範学校、東京大学時代
地元の小学校に訓導として着任した衡平であるが、さらなる学究のため、就職した二年後に小学校を休職し上京した。明治四十一年(1908)四月から東京高等師範学校本科国語漢文部に入学した。高等師範学校在学中には、校長の嘉納治五郎(教育家、柔道家)の信任を得て、高等師範学校校友誌の編集兼発行者を務め、自ら投稿もしている。
明治四十五年三月に東京高等師範学校を卒業し、同校の研究科(教育、国語専攻)に入学したが、大正元年(一九一二)九月に東京帝国大学(選科)に入学のため東京高等師範学校を退学した。東大(選科)の入学時の同級には、下伊那郡豊村和合(現阿南町)出身の西尾実や秋田県出身の湯沢幸吉郎がいた。選科とは、高等学校から大学への入学定員が満たない場合に、高等学校以外の専門学校を卒業した者を試験によって選抜して入学させる制度で、選科生のまま文科大学(東京大学文学部)を卒業しても、本科生と同じ「文学士」の称号を得ることは出来なかった。衡平は、大学在学中に信濃育英会の第一回貸費生に選抜され、選科入学の翌月には高等学校卒業検定試験に合格し、高等学校卒業同等の学力を有すると認められ、大学の選科生から本科生になった。選科修了生は、大学卒業後に大学院に入ることが許されなかったことから、衡平が本科生になったのは研究の道(大学院)に進もうと考えていたためであろう。選科の同級であった西尾実は検定試験を受けないで選科のまま卒業している。傍系(高等学校以外)入学から本科生となった衡平がいかに優秀であったかがわかる。
写真7 衡平、大正元年、東京神田

衡平は、大学入学の頃から『今昔物語集』を卒業論文のテーマにすると決めていた(4)。その研究のために大学附属の図書館だけでなく、上野図書館(後の国立国会図書館支部上野図書館)の蔵書まで広く研究に利用した。大正四年に東京大学国文科を首席で卒業し、「文学士」の称号を得た。この年の卒業生の中には恩賜の銀時計の受賞者はいなかった。これは、首席であった衡平は卒業論文の点数は良かったが、単位修了の点数が足りなかったためで、授業出席よりも研究を優先させたためと思われる。衡平の卒業論文「今昔物語集の研究」は、当時の指導教授であった芳賀矢一に激賞されたとされる(15)。『今昔物語集』に関する既出の研究は、芳賀教授の『攷證今昔物語集』が唯一のもので(12)、衡平の業績が芳賀教授の研究の後継であるとみなしてもいい、質の高い内容であった。卒論でありながら、学位論文に匹敵するレベルと後の学者は評価している(4)。このことは、衡平が大学在学中に、すでに大学院レベルの研究をしていたことを示している。『今昔物語集』に関する卒業論文は、大学卒業の八年後に『今昔物語集の新研究』として刊行され、現在も古典的名著として後学に参照され続けている。
5. 東京大学大学院、文学部副手時代
衡平は、大正四年(1915)に大学を卒業した後、同大の特選給費生に推薦され、東京大学大学院に籍をおいて国文学研究を続けた。この推薦は芳賀教授の後押しがあったと思われる。この時期にすみかを嘉納家から本郷の下宿に変えている。この転居は、大学院時代に恩師(嘉納治五郎か)から、その令嬢との結婚を勧められたが拒んだことが理由とされる。縁談を断った衡平が帰郷した際に、実家で兄の喜扶と口論になったと甥の喜夫は回想している(9)。大学院時代に、東京高等蚕糸学校講師、その他の学校講師も兼務した。大正九年に東京大学文学部文学科副手に抜擢されている(副手は助手の下で研究補助役)。
ここまでは順調な研究生活であったが、この後から状況が変わり大学研究室内で衡平が冷遇されるようになった。衡平が冷遇された理由として、〈1〉大正七年に恩師であった芳賀矢一教授が国学院大学学長として東京大学を転出し後ろ盾を失った事。〈2〉芳賀教授の後任の主任教授との軋轢があった。〈3〉選科生から入った傍系であった事。〈4〉研究室に土足で入ってきた国語学の教授を叱咤したため、とされる。土屋弼太郎は、「芳賀先生が主任教授として居られたならば坂井氏の運命はもっと明るい方向へ展開した」「(芳賀先生の)後の主任教授と坂井氏はそりが合わないところがある」と述べている(8)。西尾光一が金井清光へ送った私信にも後任教授と意見が合わなかったと記している(3)。傍系で大学研究室に入った衡平が素晴らしい論文を仕上げ、当時の教室主宰者であった芳賀教授に眼をかけられたが、芳賀教授が転出した後は、後任教授から冷遇されたと考えられる。
衡平の『今昔物語集』の研究成果は、大正四年の大学卒業の時には、ほぼ完成していたにも関わらず、出版にはさらに八年の歳月を要し、当時の文学界では無名の書店(誠之堂書店)から出版されている。刊行された本の序で、衡平は「境遇も亦迫害的なる悲境に処して資財の窮乏は其常態なりき。之が爲め本書の刊行が遅々として実現せず」と述べている。この時の迫害の詳細はわからないが、前述のような衡平の境遇を考えるとある程度は想像できよう。
6. 研究室放逐後―市井の研究者として
大正九年(1920)から、衡平は教室の副手として研究を続け、東洋大学(大正九年四月から五月)、私立英学塾(大正九年四月から同十二年三月)、早稲田中学校(大正十二年四月から九月)の嘱託講師を務めている(甥の坂井喜夫の記録)。これらの兼務は東大研究室の斡旋であったと考えられる。衡平が研究室をやめて市井に下った時期は、早稲田中学校の嘱託講師をやめた大正十二年九月頃と思われる。同月に関東大震災(大正十二年九月一日)があった。この震災による被害は、火災によるものが多くを占め、衡平が嘱託講師を務めた学校も被害を受けた可能性がある。また、この時に衡平自身は無事であったが、衡平の著述したいくつかの書籍が書林とともに焼失した。同年の『信濃教育』(444号)に「大いなるそぞろ言」として投稿し、震災を「物質的精神的に実に甚大の損失である」と述べている一方で、「災害は文明の一大洗濯である」とも述べ、今回の震災から社会の弱点を洗い出して対応すべきと前向きに語っている(16)。
その後の衡平であるが、「二部屋しかないボロ屋に住む貧乏生活が始まり、手元には『群書類従』があるだけであった。坂井氏の勉強場所はもっぱら上野図書館(以下略)」((1)の後記)とされ、金銭的、物質的には厳しい環境での研究生活を強いられた。衡平は、大正十四年の『信濃教育』(465号)に、「現実の見方について」と題して投稿している(17)。国民の生活、教育界について、「現実の世は不都合や苦難の多いものと見るのがむしろ普通であろう」と述べている。さらには、「災害や迫害にあっても人類社会の努力は継続されるべきで、現実に対する適応力と、人間の持つ道徳力、精神力をもって対応することができる」としている。衡平は、投稿で述べたことを、自身も実践しつつこの難局を乗り越えようとしていたと思われる。
大学研究室のしがらみから解放されたためか、大正十二年に、ようやく彼の最大の業績である『今昔物語集の新研究』が刊行され、その後次々と彼の著作が世に出された。これらの業績は、研究室時代に完成したにも関わらず発表できなかったものと、大学から追い出され反骨精神で新たに衡平が著作したものとが含まれる。研究範囲は『今昔物語集』からさらに広げられ、日本文学史全般を対象とし、その成果が大正十五年に刊行された『新撰国文学通史』である。この頃の衡平は、後述する長野市教育会からの委託による善光寺研究により、史料・文献を基にした研究に加え、全国を歩いて実地調査も行い、苦しい生活の反面、研究面では充実した日々であったのではなかろうか。
大学を離れた後も、研究室との軋轢は続き、西尾実が企画した岩波講座の今昔物語の部の執筆を衡平に打診しに行った際には「先生(芳賀教授の後任の教授)の仕事は絶対にしない」と断ったとされる((1)の後記)。長野県師範学校の同級であった土屋弼太郎は、「友人たちが、一時地方に出てみないかとすすめても、『僕は田舎には引き込まない』といってきかなかった」と述べていて、このようなすれ違いから友人たちと疎遠になっていった(8)。衡平の死後、彼の素晴らしい業績に対する顕彰の動きが鈍かったことにもつながってくる。衡平にとって拠点を東京に置くことは、生活面では報われなかったが、研究のためには必要であった。知人の野溝粂太郎は、弔文の冒頭で、「おれは学者になる おれは田舎には住まぬ」と、上京するたびに聞かされた衡平の言葉を書いている。衡平が、国文学研究のためには「中央(東京)にいて図書を自由に見る便宜のない所では不可能」と述べている(8)。大正十四年に兄の喜扶が亡くなったが、実家の方は、母のゑいと長野県師範学校をやめて伊那に戻った喜扶の子である喜夫が守り、衡平は研究を優先して、地元に戻らず東京に残ったのである。
写真8.兄への弔文


7. 長野市教育会の善光寺研究依頼とその背景
衡平の長野市教育会とのつながりであるが、大正三年(1914)四月に長野県師範学校訓導であった村松民治郎(大正六年逝去)が『信濃教育』の初代専任編集主任になり、また、前年の大正二年には、林八十司が編集委員として加わっていた(18)。彼らが東京の衡平へ、『信濃教育』への投稿を促した。その結果、大正三年八月から衡平は同雑誌へ年二、三編の投稿をするようになり、衡平の東京での研究活動が地元長野で知られるきっかけを作った。衡平は、村松民治郎の訃報に際し、『信濃教育』へ寄稿しているが(19)、その文中、村松民治郎とは直接顔を合わせたことはなかったが、信濃育英会給費生の選抜、雑誌投稿でお世話になったと記している。
大正十三年に長野市教育会(会長は長野市長丸山弁三郎)から正式に善光寺に関する調査委託を受けた。時の副会長であった林八十司(写真9)が事業を主導した(20)。また、教育会の役員(幹事職)であった土屋弼太郎(衡平の長野県師範学校の同期)も衡平を推薦した。林八十司(明治十‐昭和二十四)は、明治十年(一八七七)に伊那町山寺彦平(現伊那市)で生まれ。長野県師範学校を明治三十三年に卒業した後、県内の小学校に勤務した(21)。大正十二年十月から長野市教育会の副会長職につき、同郷出身の衡平の才能を高く評価していたと考えられる。
写真9.林八十司(『長野城山学校百年史』より)

衡平への善光寺研究依頼であるが、一説に生活に困っているのを見かねて情けで行ったと記述したものがあるが、貴重な教育会の予算を一個人への温情に費やすようなことはありえない。他方、衡平がそのような趣意を感じたならば、辞退したであろう。この依頼の背景は、長野市教育会が善光寺の歴史的研究を希求していたことにある(22)。
当時は、大正自由教育が盛んになってきた時代であるが、一方でその流れに逆行するように、大正九年に文部省は国定教科書『尋常小学国史上・下』を発行し、大正十三年五月に国定教科書以外の副教材を使用することを禁止した。大正十三年九月に松本の女子師範学校付属小学校の川井訓導が、修身の時間に国定教科書を使用しないで、森鷗外の小説を用いて授業を行ったことにより休職処分に付せられた。長野県下の各教育会は、国の方針に逆らうように、郷土史や地理に関する自前の教材作りのために、教師が赴任先の地域の地理、歴史を調べる郷土研究が盛んになった。これは「郷土教育運動」と呼ばれた。この風潮の中で、長野市教育会は、大正十三年に善光寺の調査研究を衡平に委託し、翌年には『川中島戦史』の研究を藤沢直枝に委託している(20)。
衡平は、東大在学中に国文学研究をしながら、地元の信濃についても知見を蓄積し、その研究成果を『信濃教育』へ投稿していた。例を挙げると、大正四年から「六国史に現れたる信濃」(349、352、356号へ3回)、大正十二年に「今昔物語集と信濃」(435号)である。長野市教育会から善光寺の研究を委託された大正十三年には、衡平は善光寺や信濃の歴史に関する文献史料の面での知見をかなり把握していたと推察される。この頃、「郷土の研究」は学問として少しずつ認知され始めた時期で、大正二年に柳田国男らによって『郷土研究』という雑誌が発刊されている(23)。
『信濃教育』(368号)への寄稿文で、衡平は「近世の初頭から中期にかけて続々現れた往来文学が当時の風俗史の研究資料として極めて大切なものである」と述べている(19)。当時の民衆の風俗に関わる国文学史料内の記述を、郷土研究に役立てる手法を衡平はとっていたことがわかる。『今昔物語集』には民衆に関する記述が多く、これを専門にした衡平が、郷土研究に興味を持つことは自然な流れであり、国文学研究と郷土研究を区別するのではなく、衡平は両者を同時進行で進めていたといってもいい。衡平は東京大学を放逐され国文学研究の道をあきらめて、郷土研究をしたのではない。最初から両方の分野を研究対象にしていたのである。さらには、長野市教育会の援助によって実地調査が可能となり、衡平の研究に深みが増したといえる。『善光寺史』を見いだした金井清光は、『善光寺史』の後記で「文献至上主義の国文学者と異なり、衡平は文献の背後にある民衆の生活を考えていた先駆者」と評している。
8. 衡平の善光寺研究
善光寺の調査を依頼された衡平の研究経過については、刊行された『善光寺史』の緒言の第一章「善光寺の特色」、第二章「善光寺史編述上の難点」の他、『善光寺史』刊行報告記念式の配布資料(22)に書かれている。史料は主に東京で収集し、実地調査は長野市をはじめ全国の一五〇余の善光寺関連の寺院に足を運んだ。大正十三年(1924)は関東・奥羽地方一回、同十四年は東海道・奥州・濃尾・畿内地方三回、同十五年越後・鎌倉・北陸・山陰・九州・四国・畿内・濃尾二回、昭和二年に関東二回と調査範囲が広範囲に及んだ。その調査の一部は、昭和二年から四年にかけて雑誌『信濃教育』へ11回に渡って投稿されている。
衡平が史料だけでなく実地調査を重視した理由であるが、善光寺は学問中心の教学寺ではなく、本仏中心の寺であるため教理宗義、住僧の伝記が不明で文献資料が乏しい点にある。そのため、実際の遺跡、伝記、伝説、遺物等によって補完研究する必要があった。さらに史料の分析において、善光寺の寺史だけに注目するのではなく、背景の状況を理解するために一般史や文化史に注目し、「一般史があって初めて寺史があることを忘れてはいけない」と述べている。特に氏族史の研究は重要で、大本願、中衆や妻戸の問題、年神堂、諏訪社等の社人関係、巨勢氏、秦氏及び古い渡来人の問題をあげている。
衡平の研究姿勢を示す出来事として、絶対秘仏である善光寺本尊の閲覧を、数回に渡って善光寺へ申し入れたことである(1)。結局本尊を拝観することは出来なかったが、彼が従来からのタブーを破ってでも真実に近づこうとした探求心がうかがい知れる。
大正十五年の長野市教育会の総予算一六七六円の内、衡平の善光寺研究に対して790円(総予算の47%)が計上された(20)。内訳であるが衡平への手当が月額30円(当時の小学校教員給与の半額)で、それ以外は旅費等の所要分であったが、決して十分な金額ではなかった。
調査を委託された三年後の昭和二年(1927)二月五日に、鍋谷田小学校で長野市教育会主催の臨時講演会が開催された。衡平が講師をつとめ、演題は「善光寺史」であった(20)。これは、衡平の調査を援助した長野市教育会の会員向けの中間報告という意味があった(24)。さらに同年から雑誌『信濃教育』へ善光寺関連の投稿を行っている。
長野市内の十念寺(西後町)の先々代の住職の日記(昭和四年十一月三十日)には、「来客あり、かねて聞き知れる坂井衡平氏なり、寺の世代その他について意見の交換をなす。大いに得る所あり」と書かれ、衡平が残した名刺が一緒に挟まっていた。名刺には、「長野市教育会善光寺史編纂 坂井衡平」とあり、住所は「東京市本郷区駒込富士前町六十二番地」と書かれていた。寺への再訪問の際、衡平は寺内の「観音堂縁起」を詳細に調査したと伝わっている。
善光寺調査の主目的は、絶対秘仏である善光寺の本尊がいかなるものかであった。前述したように、本尊の閲覧が叶わなかったため、各地の主要な寺に善光寺仏があるかを確認し、その像の形態、由緒を調査している。さらには歴史上の重要な街道や峠、寺社境内の石造物、古文書、周辺の古墳に至るまで調査を行っている。出雲を訪れた際には、乃木の善光寺だけではなく、須我神社(日本初之宮)、出雲大社も訪れている。衡平は、各地を実地調査する中で、地域で粗雑に扱われ埋もれている史跡を保護する重要性も説いている(『信濃教育』489、491号)。
衡平は長野市教育会だけでなく、更級郡教育会の郷土研究にも関わっていた。昭和三年に「善光寺史と聖山」をテーマに『信濃教育』へ投稿したものが三回分ある。この内容は、更級郡教育会が昭和九年に発行した『聖山研究』の中に収載された。さらに、同教育会では、さかのぼる四年ほど前から衡平に講師を依頼し、同郡の郷土文化史について数回の講演会を開催した。その講演内容は昭和六年七月に『更級郡郷土文化史』として刊行された。この序文で衡平は、「郡の郷土史は低度、小範囲の歴史であって壮快偉大なる大事件を対象とするものではないが、地方史、国史の要因となり重要な新資料を提示する場合がある」と述べ、郡レベルでの郷土史研究の重要性を述べている。
衡平の善光寺研究が始まって6年後の昭和五年四月に、長野市教育会は『善光寺小誌』を発刊した。これは、衡平の調査成果のごく一部にすぎず、一般向けの刊行物の扱いであった。『善光寺小誌』の内容は、後の昭和四十四年に刊行された『善光寺史』の巻末にもれなく収載されている。『善光寺小誌』発刊後も、長野市教育会から衡平に依頼された善光寺研究は続けられたが、昭和八年度をもって調査が打ち切りとなっている(24)。突然の出来事であったが、教育会側の都合であった。衡平は善光寺研究をさらに続ける意向であったが、昭和八年二月に治安維持法違反で長野県内の教員が大量に検挙された「二・四事件(教員左翼運動事件)」が起こり、教育会も衡平への研究援助を続けられなくなった事情があると考えられる。結局、善光寺研究はこの時点で正式に打ち切りとなり、翌昭和九年に衡平から教育会へ『善光寺史』の草稿が渡された。この時点で衡平の国内での善光寺研究はほぼ終わっていたが、さらに中国・インドまで研究の対象を広げたいという思いがあった(1)。昭和六年に母ゑいが亡くなった後に、衡平は母に捧げる歌帖を製作しているが、母の没後六〇日たった十一月末から、善光寺研究のために朝鮮にも渡航した。関城、晋州の他、百済の最後の都があった扶餘郡を訪れて歌も詠んでいる。
9.母・ゑいの死
衡平の学究の根底には、母への敬愛があった。衡平が生涯を独身で通したのは、研究と母への思いが強く、家庭を築く余地はなかったのであろう。その母が昭和五年(一九三〇)十月から病気で寝込む様になり、翌六年九月二十四日に八一歳で亡くなった。衡平にとって母は最大の理解者であった。衡平の著作『今昔物語集の新研究』の巻頭に、「わが学びの初めの業なる此書を亡き父君の御霊と故郷に在ます老いたる母君の御手とに捧ぐ」と記していることからもわかる。
母ゑいは、嘉永四年(一八五一)九月十七日に伊那の東春近村中殿島(現伊那市)の飯塚傳蔵の長女として出生した。明治二年(一八六九)二月に坂井喜平と結婚し、二男三女をもうけた。衡平は末っ子になる。衡平が三歳の明治二十二年に父の喜平が亡くなった。当時長兄の喜扶はまだ一三歳で、坂井家をゑいが一人で守った。父喜平の死から、兄喜扶が軍を除隊する明治三十二年までの期間を、「母の家政苦闘時代」と衡平は称している(25)。苦労している母の背中を見ながら衡平は育った。衡平が東京大学を卒業した時に母ゑいは六五歳であったが、衡平の東京での生活を気にかけて高齢の身をおしながら三回上京している(大正十、十一年、昭和二年)。また、衡平も遠方にいる母を心配し何度も帰郷している。甥の喜夫は、叔父の衡平について「無類の親孝行で、祖母ゑいが亡くなるまで足しげく、家に出入りしていた」「子供の私(喜夫)が祖母に口ごたえしたりすると、衡平にひどくしかられたものである」「祖母の病床中や葬儀のときの力の入れようは非常な物であった」「祖母は、生存中はよく東京に行った。独身で、貧乏で、学問に身をささげている末子(衡平)のために、自炊生活をたすけるために」と述べている(9)。『上伊那教育』(四三号)で坂井衡平特集として取り上げた酒井源次は、衡平の父・喜平の弟・末蔵の孫にあたる。源次の父と衡平はいとこ同士になる。源次は『上伊那教育』(四三号)編集後記に、衡平の思い出を書いている。源次の父は従弟の衡平を「衡平さ、衡平さ」と呼んで親しんでいた。「東京で専ら著述生活を送っておられたこの人は、たまさか、『母上』に会うために郷里を訪れるのだが、その都度、必ずといっていいほど長い病床にある祖父(末蔵)を慰問された」とある。夫に早くに先立たれた衡平の母・ゑいを義弟の末蔵が援助し、その恩を感じていた衡平は、叔父の末蔵が存命中はその宅へよく訪れていた。
母の没後に衡平は「故慈妣小祥忌追善歌帖」というA五サイズ四頁の小冊子を作っている。最初の頁は母の略歴を、二‐四頁には母の葬儀の時から一周忌までに母のために作った五一首の歌が載っている。母の死に際し、衡平の落胆は大きかった。母の没後五年も経たずに衡平が亡くなっていることからも、彼の精神的な打撃の大きさをうかがうことができる。
写真10.「故慈妣小祥忌追善歌帖」 全4頁の最初の頁

写真11.母への弔文

10. 衡平の甥・坂井喜夫
坂井喜夫は、衡平の兄である坂井喜扶の長子として明治四十年(1925)一月に出生した。衡平と同じ長野県師範学校に入学し教師の道を目指したが、大正十四年に中退している(9)。同年に父の喜扶が亡くなり、実家を守るため師範学校を中退し、故郷の西春近に戻った。南信毎日新聞社の記者として働き、途中日本大学経済学部にも入学しているが、昭和二年(一九二七)に中退している。上伊那郡青年団、長野県連合青年団の幹事長を務め、昭和八年の二・四事件の時に検挙され(当時二六歳)、長野、市ヶ谷、小菅の刑務所に収容された。東京では、衡平は差入れのために刑務所を訪問している。衡平について「なにも言わず、ただ、ときどき面会にきて必ず差入れをしてくれた。金には困っていたろうに差入れの金だって少なくないのに」と喜夫が述べている(9)。
また、衡平は善光寺のための調査の旅先から度々絵葉書を喜夫宛てに送っている。喜夫は、叔父衡平の著書の校正を手伝っているが、衡平は必ず校正を三校以上行い、喜夫は第二校を担当したと述べている(9)。衡平の死後、喜夫は満州に渡り、戦後シベリアの抑留生活を経て昭和二十五年に帰国している。帰国後は、西春近の村会議員、公民館長、西春近村とその後の伊那市の教育委員長を務め、平成十一年(一九九九)に九三歳で亡くなった(26)。
写真12. 坂井衡平(前)、喜夫(後)(昭和二年四月撮影)

11.衡平の晩年―軍国化と郷土教育運動の下火
母の死ののち、坂井の研究生活に大きな影響を与えた出来事は、長野で起こった「二・四事件」(昭和八年)であろう。郷土教育運動は、この事件により下火になり、長野市教育会が衡平に委託した善光寺研究事業は打ち切りとなった。少額であったが衡平への調査委託料はなくなり、生活を倹約しつつ続けられた研究生活がさらに厳しくなったと推測される。この事件では、前述した衡平の甥の喜夫も検挙、収監されている。衡平のそれ以降の研究活動は、社会情勢、金銭面の事情により、昭和九年(一九三四)の『古文学研究』(以前発刊された『和歌と伝説』と『古文学の詩味』を合本したもの)の発刊、昭和十年『現代国文学講話』のみで、雑誌への投稿は見当たらない。
この頃、湯沢幸吉郎(東京大学の選科で同期入学)は東洋大学の教授になり、同郷出身でもある西尾実は、坂井が属していた東大の研究室の教授を中心に設立された国語教育学会の常任理事になって活躍する様になっていた。大学同期生であった彼らの活躍や地位を見ながら、定職に付いていなかった衡平の悔しさは想像を絶するものがあったであろう。大学で選科から本科生になって卒業し、『今昔物語集』の研究分野で素晴らしい業績をあげて文学士の称号を得た衡平の経歴からは、同級生と同等以上の社会的な立場にいてもおかしくはないはずであった。『善光寺史』刊行報告記念式の資料では、西尾実、土屋弼太郎二人の厚い友情に支えられて『善光寺史』を脱稿したとあるが(22)、この頃、二人は衡平と接点はない。失意に打ちのめされることが多かったはずであるが、衡平は亡くなる直前まで国文学の研究者としての矜持は失ってはいなかった。甥の喜夫は、晩年の衡平は東京で友人からも距離を置いていたと回顧している(9)。
晩年の衡平と唯一交流をもっていた人物が東京高等師範学校の同級であった佐藤新作であり、当時の衡平を知る唯一の人物である。佐藤が衡平の死後に甥の喜夫に宛てた手紙が残っている。衡平の晩年を知る貴重な資料であり、以下に佐藤の書簡の全文を載せる。

・佐藤新作の書簡(坂井喜夫宛 昭和十一年五月二日付)
拝啓 御叔父様衡平殿此の度突然の御病気を以て御永眠の事、何とも惜しく痛悼に禁へ申さず候。高師同期同科卒業生は、多く有之候へども親しく深く交誼ありし者は恐らく小生外にあるまじと存じ居り候。昨年末保養院入りを田舎より上京して始めて知りし為、一回御見舞致し候。間もなく退院にもなるべき様子に有之候ひし為め、その後用事にかまけ、御無沙汰に過し居り候処、突然の事にて只唯驚愕の外無之候。別紙御香料は軽少に御座候へども、友としての心情のみは余人に劣らぬつもりに御座候。その証の弔文と共に何卒御霊前に御供へ下され度、此段御願申上候。
頓首
五月二日
坂井喜夫殿 佐藤新作
(佐藤新作の弔文)
十数年の昔伊那高女在職当時、西春近に叔父様を訪ねて御宅に参りしことを思ひ出し候。私が、西巣鴨の保養院を訪うたのは去年の十二月の中頃だったと思ふ。田舎縞の筒ツぽの衣物を纒うて微笑を湛へて迎へてくれた稍(やや)憔悴気味の顔頬は痩せこけた姿が目に浮ぶ。対談約半時間位であったが君には別に異状の認むべきものがなく元気は却ってわび住居に一人で暮して居た時よりもまさって居たやうに思った。
近日中に退院を許してもらって国学研究所の拡張や研究出版に精進したいと言って居った事に何等狂ひを発見する事が出来ぬ程に健康も病状も恢復して居た。私は其の言に依っても遠からずして退院出来ることを信じ、又その一日も早からんことを祈って別れを告げたのであった。その時にまさか三ヶ月を出でずして死出の旅に上らうなどとは夢にも想像することがなかった。人の運命程分らぬものはない。明日ありと思ふ心の仇桜である。
君が警察署員の手を煩はして保養院の人となったことは君を訪ねた前の一日、国学研究所なるものを尋ねて行った時に、そこの大家から聞いた所である。責任感が強く家賃などは必ず期日にきちん〳〵と納めて居ったとの事であったが、前年来の迫害観念は容易に去らなかった。否(いな)それが痼疾となった上に身の不遇は愈々(いよいよ)その痼疾を増大せしめた。後で聞く所に依ると迫害する者があって自分の事業を頻りに妨害するが故に訴へて之を除去せんとして警察方面に訴願せしことも一再ならざりしとの事である。大家の方では之を知って如何なる突発的大事の起らぬものでもないと恐れを為して警官に依頼し、保養院入りを取計らってもらったやうである。
かくして保養院の人となったのは昨年の秋初である。君には依然として迫害観念がつゞいた。入院の始は耳に錯覚的に迫害の声が聞えるとまで言ったさうであるが、此の方は保養に従って治った。痙攣的に首を振る癖もあったが、是も治った。只迫害観念のみは何うしても去らない。それさへ消えれば退院を許されると係の人が話してやっても、それが後で復(また)出て来るといった訳で、その観念の消えるまでと係の方々も懸命に力を致されて居ったのであった。それが為め前年は暮れて本年も一月となり二月となり、だん〳〵月日は過ぎた。私はもう君が退院出来たらうとさへ考へて居た。退院とならなければ、今一度見舞って見ようと思って、三月も過ぎた。四月も匆々と経(た)ってその十日となった時、井上君の所から突然訃報と共に弔慰金の募集状が来た。あゝ驚いた。あゝ意外だ。まだ〳〵生きて保養院に居らるゝと思って居った。その君がもう此の世に姿を消して居らうとは。直にも退院出来さうに言って居った言葉が、まだ耳底に残って居る。それが三ヶ月をも出でずして何うして死に導くことになったらうと不審でならなかった。早速保養院に復出かけて行った。係に会って君の最期の状況を訊いた。果して君には突発的に死に導く事件が起きて居たのであった。三月の二日であった。午后に至り突如として歩行もふら〳〵として起きて居られぬ病状が現はれた。脳溢血である。病床に就いた。その日は食事が要らぬとて取らず、翌日は粥を相当食した。併し三日目には意識不明の昏睡状態となって来、心臓も漸次薄弱となって遂に翌日不帰の客となったのだといふ。看護婦の外は近親も知友もなき淋しき〳〵臨終であったやうである。かくして君は世の一切を終った。思へば君の一生は轗軻(かんか)不遇そのものの生活であった。有為の材を抱き乍ら時に遇はずして孤介(こかい)し全く孤介の生涯であった。訪れた人は出版社の店員の外には恐らくあるまいといふ淋しさであった。君が高師卒業来二十五年間多く病と悪闘し貧と抗争し通したのであった。一張羅の羽織が羊羹色になったのを、そのまゝ何年も着て平然と一室に閉ぢ籠り、書の外には語る者もなく日夜を過したのであった。私は時折訪ねて、この窮苦の生活をよく知ってゐるが故に、あの境遇でよくも二十五年間を過し得たとまで思ってゐる位である。故に之を俗眼を以て眺める時に、君を実に不幸の生活を送ったものと思はざるを得ない。
然し〳〵、それは俗眼で君を知らざる者の浅はかな見方である。何故か?君は現世の快楽を求めて生活した者ではなくて永遠の世にその生命を求めたのであった。現世的の善美な生活を欲した者では無かった。君は死後に、その生命の永く備はらんことを求めて、その理想を以てその一生涯を貫徹したのであった。されば君には、生前の不遇、生活の苦難、孤独の寂寞も何のそのであった。君はかくして生前十指に足る大著述を完成した。著作のあらん限り君の生命は無限永久である。君は生前の苦闘に依ってこの永久の生命を贏(か)ち得たのであった。この故に今日死に去っても何等恨の残る所はなからう。思へば、窮菴孤独の生活に在り乍らも死して悔ゆるなき足跡を辿ったのであったが故に、今日の死に対して短命であったこの不満も不平も残る筈は無いであらう。然り君のこの深き心事を知る時、たとへ臨終は淋しくとも、君は独り安んじて瞑したるべきを信ずる。今日君を弔ふに当り君の過去を顧み、君の心事を推して以上の如く長言を手向けるのも君との永別を惜しく思ひ君をくやめばこそである。冀くは在天の霊来り饗(う)けよ。
昭和十一年五月二日
佐藤新作
(東京市池袋一ノ五四 大村方)
衡平は、昭和十年(1935)八月十九日に東京の西巣鴨保養院(豊島区西巣鴨四ノ四一四)に入院した。入院時の病状は、妄想が強くなって借家の大家の意向による入院であった。甥の喜夫は、衡平が亡くなる際に、縁者・知友の付添はなく、衡平の没後に入院費が滞っていたことを知ったと述べており(9)、衡平の晩年は金銭的には厳しい状況であったことがわかる。大学研究室に属さず、母の死、善光寺研究の打ち止め、生活の困窮が衡平の精神を極限まで追い詰めた結果であろう。
衡平が入院していた頃、衡平の書いた『善光寺史』の清書を終えた城山小学校校長の小林政雄は、校正の打合せをすべく上京したい旨の書簡を送っている。それに対する衡平の返事(口絵写真)は、清書をした小林への感謝と、入院中で面会が出来ないので退院したら長野へ出向いて一緒に校正しようという旨の内容である。封筒の裏には自宅の住所の前に「国学研究所」と冠し、入院中でも国文学への研究の思いは失っていなかった。小林への書簡は理路整然とした内容であり、精神錯乱状態で書ける文面ではない。また、内容からは衡平の自殺企図はうかがえない。入院時に、多少の妄想症状と判断されたかもしれないが、入院中に支離滅裂な精神状態であったとはいえない。前述の親友の佐藤新作の書簡も同じである。
衡平の入院が長期化し、七ヵ月目に入った昭和十一年三月二日に病院で容態が急変し、五日に危篤となった。家族に連絡がされたが、甥喜夫の妻が駆け付けた時には衡平は意識不明になっていて、同日午後七時二五分に臨終となった。死因は「脳いっ血(妄想性痴呆)」とされた。妄想性痴呆の診断であるが、入院中に奇行があったためとされるが、入院前からの低栄養による心体両面へのストレスによる心因反応のようなものではなかったかと推測される。直接的な死因は、急な容態の変化と意識消失を示すことから、脳内出血の様なものであったと思われる。当時は頭部CT検査のような頭蓋内を精密に検査する方法がなく、病名を正確に診断する事は不可能であった。衡平の亡骸は、母、兄とともに、地元西春近赤木の坂井家の墓地に眠っている(写真)。菩提寺は法音寺で、戒名は「見秀院英深衡道居士」である。
入院前の衡平の住所であるが、亡くなる前年の昭和十年三月に『現代国文学講話』を刊行しているが、その序の最後に「昭和十年初春 豊島長崎の寓にて 著者記」とあり、その前の昭和六年に刊行された本の序には「本郷駒込芙蓉居」と書かれている。大学に近かった本郷駒込から豊島長崎(現在の豊島区長崎)へ転居し、ここが終の棲家になった。
結婚して家庭を築くことが一般的な幸せと考えられていた時代に、衡平は一生独身を貫いた。臨終の際も親族、友人がその場にはいなかった。多くの人間は、衡平が寂しい晩年を過ごしたと思うかもしれない。衡平にとっては、所帯を持つこと、長野の故郷に戻ることは国文学研究を妨げるものであり、人生の目標をその研究にささげ、研究を続けていれば衡平にとっては幸せであった。友人の野溝粂次郎は、上京の際、衡平を訪問し、彼が「おれは学者になる、おれは田舎には住まぬ」と、いつも口にしていたと手紙に書いている。大学の研究室から追い出されたが、逆境の中で国文学研究への情熱は死の直前まで失うことはなかった。東京で研究生活を続けながら、善光寺研究を通して郷里信濃への思いは持ち続け、大正自由教育の高まりの中で孤高の研究家として郷土史、国文学の世界に輝かしい業績を残した。社会情勢が変わったことが、衡平の死期を早めたが、晩年に付き合いのあった佐藤新作が手紙で書いているように、衡平は崇高な精神を持ち続け、数々の大著を後世のために残した。
衡平が大学研究室から冷遇されたことが、机上の研究で理論先行になりがちな国文学研究から、全国各地へ自ら足を運ぶ実地調査、さらには郷土研究につながった。惜しむべくは、もう十年郷土の為の研究を続けていたならば、『善光寺史』がさらに深いものになったのであろう。衡平の多くの著作には「文学士 坂井衡平」とあり、肩書は文学博士ではない。しかし彼の業績は博士号を受けても有り余るものであり、彼が大学の研究室で不遇であり、主流から外れてしまったために博士号を授与されなかっただけで、その業績は現在も光り輝くものである。
写真11 坂井家の墓地(伊那市西春近、赤木駅の南東二五〇メートル地点)

12. 『善光寺史』刊行までのみちのり
長野市教育会へ送られた衡平の草稿が、刊行されるまでには紆余曲折があった。衡平の生前には出版されず、昭和四十四年(1969)五月三十日に刊行された(限定1500部)。刊行に至るまでの経過を、刊行に尽力した関係者の取り組みを中心に述べたい。
(1) 城山小学校校長・小林政雄による『善光寺史』原稿の清書
昭和八年に長野市教育会の善光寺研究が打ちきられ、衡平は、それまでに調査した内容を成稿して教育会へ提出した。城山小学校に在職中であった小林政雄(写真、明治三十一‐昭和三十八)が、衡平直筆の『善光寺史』の草稿を見つけ、昭和九年十月十五日から清書を始めた。この経過は、小林政雄の日記と息子の二郎の後日談(信濃教育会蔵)に詳細が書かれている。政雄は、「『善光寺史』という大変貴重な文献が埋もれた形で見つかった。この膨大資料がこのままでは日の目を見ずに終わってしまい残念だと思った。そして善光寺のお膝元の城山小学校に奉職している自分がこれを世に出さなければ他にやるものはない」と、息子の二郎に話したとある。二郎の推察では、この時に政雄の長男が病魔に侵され闘病中であり、長男の快方を仏に祈る気持ちで『善光寺史』を清書したとされる。政雄の日記では、清書の際には、市役所に保管されていた衡平の草稿の冊子を一、二冊借りて自宅に持ち帰り、さらに衡平の草稿の写真をはがして清書本に貼った。約一年一ヵ月後の昭和十年十一月八日に政雄は一通りの清書を終わらせた。その清書本を衡平と直接会って校正するために、上京の意向を書簡で衡平に伝えた。
しかし、衡平が同年の八月中旬から入院して、すぐには会えない旨が書かれた書簡を十一月二十日に政雄へ送っている。翌年の三月五日に衡平は亡くなったため、政雄は衡平に会うことは出来なかった。『善光寺史』の校正、修正は政雄が自ら行い、昭和十一年九月十七日に製本された清書本を長野市教育会に提出した。その清書本は、同年十一月十四日に長野市教育会から信濃教育会に委託され、教育参考室に保管された。第二次世界大戦中、参考室資料は戸隠に疎開した経緯があり、市役所に保管されていた衡平の草稿の所在は不明となり、信濃教育会資料室に保管されていた政雄の清書本だけが残った。清書本は政雄により丁寧に書かれ、大変な作業であったことがうかがえる。小林政雄は小県郡大門町(現長和町大門)に生まれ、明治三十九年四月に長野県師範学校に入学し、明治四十三年三月に同校を卒業した。小県郡長久保小学校訓導を皮切りに教職を始め、昭和七年三月に城山尋常小学校訓導、校長に着任している。衡平の草稿は不明となり(*注)、小林政雄の清書へ注いだなみなみならない情熱がなければ、『善光寺史』は永遠に失われてしまったのである。
写真 小林政雄(『長野城山学校百年史』より)

(2) 時宗研究者・金井清光の尽力
昭和二十九年(1954)二月に東京大学国文学教室で開かれた中世文学研究会において、西尾光一が坂井衡平の業績を紹介した(光一は、衡平と東京大学で同級であった西尾実の長男で、大正二年(1913)に出生した)。その際に時宗研究を主としていた金井清光が聴講し、衡平の著した『善光寺史』の存在を知った。時宗研究において、善光寺聖の存在は大きく、善光寺の研究の必要性を感じていた金井であるが、当時は衡平の『善光寺史』の清書本の保管場所を知らなかった。小林計一郎著『善光寺史と長野の歴史』(昭和三十三年発刊)の最後の参考文献の欄に、「善光寺史(未刊)坂井衡平氏 信濃教育会参考室蔵、坂井氏が長野市教育会の依頼により、長い間かかって研究され、まとめられたものですが、何かの理由で出版されずに終りました。善光寺史の研究としてもっともよくまとまった本です。たゞ江戸時代以後の部は未完成です」と書かれているのを見て、昭和四十年夏に信濃教育会に赴き、小林政雄の清書した『善光寺史』を確認した。翌年の昭和四十一年四月に三日間かけてその清書本すべてをフィルムに収めた。この内容を広く世に知らしめるべきと感じ、『善光寺史』の概要と目次を『信濃教育』(第九六九号)(2)と『時衆文芸研究』(3)に「坂井衡平氏『善光寺史』について」として投稿した。
(3) 校訂、校正、出版
校訂、校正については鈴木棠三(白梅女子短期大学教授)と東京大学史料編纂所があたった。東京美術の佐々藤雄が、国文学、日本仏教史に貢献しようと長野市教育会(会長 太田美明)に出版の打診をして刊行に至った。
*注:坂井衡平の書いた善光寺史の草稿ですが、長野市公文書館に保管されていることがわかりました。(原稿の資料No 「市/H18/624-1」、年表は「市/H18/625」)
-以下、続編(同ブログ 2019.4.24投稿) 『●坂井衡平について (続編)』に続きます。










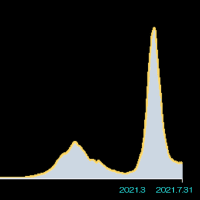





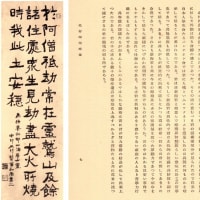



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます