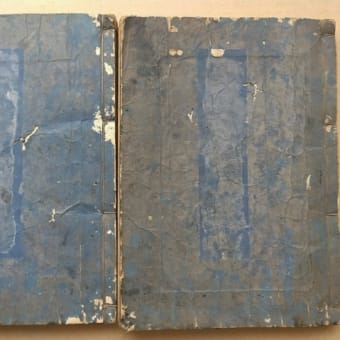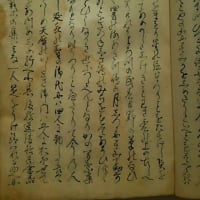■『日本書紀』に記された「鬼」が意味するものとは?
ともあれ、実はこの「鬼」なる文字は、『日本書紀』にも数多く記されている。筆者の知る限りでは、8箇所も登場しているのだ。そこでは、どのような者を「鬼」とみなしていたのか、それが今回のテーマである。
まず、最初に登場するのは、神代紀下巻の冒頭。そこには、読み下すと、「吾、葦原中国の邪しき鬼を撥(はら)ひたいらけしめむと欲ふ」とある。
高皇産霊尊(たかみむすひのみこと)が孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を葦原中国に降臨させようとした際、そこに「邪しき鬼」がいたため、前もって退治しておきたいと願ったという。
ここではそれを「邪神」と記しているが、実のところ、特段、悪逆非道だったわけでもなんでもない。国津神こと先住民族のことで、平和に暮らしていたはずの、何の罪もない民であった。
それを侵略者である天孫族が、国津神つまり先住民族をまつろわす(征服する)にあたって、その行為を正当化するために、彼らを邪鬼と呼んで蔑んだまでであった。
ちなみに国津神とは、縄文人と稲を携えてやって来た初期の弥生人(海人族か)のことを象徴的に表したものだと筆者は睨んでいる。両者は程よい関係を築きながら、特に大きな問題も起こさず共存していたとも推測している。
一方の天孫族とは天皇の祖先だが、今日の私たちは「天孫族と国津神一族の混血」というべきだろうから、多くの人には、征服者の血とともに「鬼」と蔑まれた被征服者の血をも受け継がれていることになりそう。つまるところ、「私たちの多くが、鬼の末裔である」と言い換えることもできるのだ。
■外国人も「鬼」と呼ばれ、討伐対象に
そればかりではない。経津主神(ふつぬしのかみ)と武甕槌神(たけみかづち)が大己貴神(おおあなむちのかみ)から国譲りの盟約を得た後、諸々の従わない「鬼神」を誅して天へと復命したとも記している。ここでもまた先住の民が、まつろわぬ民として鬼呼ばわりされて蔑まれているのだ。
まだまだ続く。景行紀40年7月の条では、「山に邪しき神あり、郊に姦しき鬼あり」とある。景行天皇が日本武尊に東夷を征伐させようとした際に放った言葉で、「山に邪神が、野に姦鬼がいるから心せよ」という意味である。東夷の中でも特に手強い蝦夷が対象で、「姦鬼」とまで蔑んで、討伐すべき者と印象づけようとしているのだ。
また、欽明紀5年12月の条には、佐渡島に粛慎(みしはせ)人なる異人種がやって来たことが記されているが、彼らのことを人ではなく「鬼魅(きみ)」とみなしていることに注目したい。つまり、ここでは外国からやって来た異人種までもをバケモノ扱いしているのだ。
その他、斉明紀7年8月の条にも、朝倉山の上に鬼が現れて、天皇の喪の儀式を覗いていたとか。ただし、それは単に覗いていただけで、特に危害を加えた形跡はない。それでも、怪しげなる者だったことで、鬼とされてしまったようだ。
こうして見ていけば、王権にとって征服すべき「先住の民」や「まつろわぬ民」ばかりか、「異人種」や「怪しげなる者」まで「鬼」と称されて、討伐すべき対象とみなされるようになったようである。
ならば、『日本書紀』に登場する「鬼」なるものの正体は、王権側が自分の都合の良いように作り上げた虚像だったというべきなのかも。王権側の人たちの心の中に巣食っていた「悪しき心根」が、「鬼」を生み出したと言い換えることもできそうである。