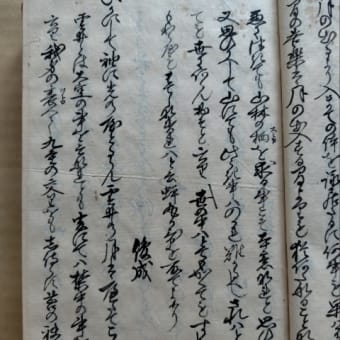大和紀伊のさかひはてなし坂にて
往来の巡礼をとゝめて奉加すゝめ
けれは料足つゝみたる紙のはしに書つけ侍る
つゝくりもはてなし坂や五月 雨 去来
髪剃や 一夜に精て 五 月雨 凡兆
日の 道や 葵傾く 五 月 雨 芭蕉
縫物や 着もせてよこす 五月雨 羽紅
七十余の老醫みまかりけるに弟子共
こそりてなくまゝ予にいたみの句乞
ける。その老醫いまそかりし時も
さらに見しれる人にあらさりけれは哀
にも思ひよらすして古来まれなる年に
こそといへととかくゆるさゝりけれは
六尺も 力おとしや 五 月 雨 其角
百 姓も 麦に取つく 茶摘哥 去来
しからきや茶山しに行 夫婦つれ 正秀
膳所
つかみ合子共のたけや 麦 畠 游力
孫を愛して

麦藁の 家してやらん 雨 蛙 智月
江戸
麦出来て 鰹 迄 喰ふ 山家哉 花紅
しら川の関こえて
風流の はしめや奥の 田植うた 芭蕉
出羽の最上を過て
眉掃を面影にして 紅粉 の花 仝
法隆寺開帳南無佛の太子を拝す
御袴のはつれなつかし紅粉の花 千邦
伊賀
田の 畝の豆つたひ行 蛍かな 万乎
膳所曲水之楼にて
蛍火や吹とはされて 鳰のやみ 去来
勢田の蛍見二句
闇の夜や 子共泣出す 蛍ふね 凡兆
ほたる見や舩頭酔ておほつかな 芭蕉
三熊野へ詣ける時
長サキ
蛍火や こゝおそろしき八鬼尾谷 田上尼
あなかちに鵜とせりあはぬ鴎かな 尚白
草むらや 百合は中々はなの 㒵 半残
つづくりもはてなしさかやさつきあめ 去来(五月雨:夏)
かみそりやいちやにさびてさつきあめ 凡兆(五月雨:夏)
ひのみちやあふひかたむくさつきあめ 芭蕉(五月雨:夏)
ぬひものやきもせでよごすさつきあめ 羽紅(五月雨:夏)
ろくしやくもちからおとしやさつきあめ 其角(五月雨:夏)
※老医 村田忠庵とある。
※六尺 駕籠かきなどの奉公人。七十余、六尺、五月雨。
ひやくしやうもむぎにとりつくちやつみうた 去来(茶摘歌:春)
しがらきやちややましにゆくふうふづれ 正秀(茶山:夏)
つかみあふこどものたけやむぎばたけ 游刀(麦畠:夏)
※游力は游刀の誤字
むぎわらのいへしてやらんあまがへる 智月(麦藁:夏)
むぎできてかつをまでくふやまがかな 花紅(麦:夏)
ふうりうのはじめやおくのたうゑうた 芭蕉(田植歌:夏)
※奥の細道
まゆはきをおもかげにしてべにのはな 芭蕉(紅粉花:夏)
※奥の細道
おはかまのはづれなつかしべにのはな 千邦(紅粉花:夏)
たのうねのまめづたひゆくほたるかな 万乎(蛍:夏)
※凡兆の句を、去来は猿蓑の採択を主張したが、凡兆が拒否して、芭蕉が添削して万乎作とした。(去来抄)
ほたるびやふきとばされてにほのやみ 去来(蛍火:夏)
やみのよやこどもなきだすほたるぶね 凡兆(蛍舟:夏)
ほたるみやせんどうゑうておぼつかな 芭蕉(蛍見:夏)
※元禄三年夏、幻住庵の頃の作。
ほたるびやここおそろしきやきをだに 田上尼(蛍火:夏)
※八鬼尾谷 十津川郷から熊野本宮へ出る果無峠付近の八木尾。
あながちにうとせりあはぬかもめかな 尚白(鵜:雑)
※鵜は無季。鴎は冬季。鵜の黒、鴎の白の競り合わないという意味。
くさむらやゆりはなかなかはなのかほ 半残(百合:夏)