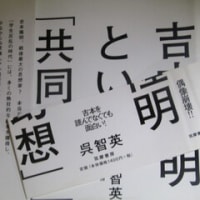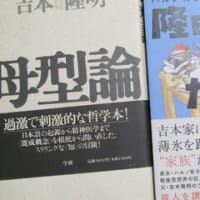夏目漱石を読むという虚栄
2000 不純な「矛盾な人間」
2500 明示できない精神
2530 和魂洋才
2531 言文二途
「明治の精神」は、明治後期の軽薄才子にありがちなスタイルを指す言葉だろう。
<彼の父は洋筆(ペン)や万年筆でだらしなく綴(つづ)られた言文一致の手紙などを、自分の伜(せがれ)から受け取る事は平生(ひごろ)からあまり喜こ(ママ)んでいなかった。彼は遠くにいる父の顔を眼の前に思い浮かべながら、苦笑して筆を擱(お)いた。
(夏目漱石『明暗』十五)>
「一致」は初出では「一途」だ。
世代間の思想的対立はなかったから、古い文体が無効になると同時に対立も消えた。
<明治初期の改良運動の一つで、国語・国字改良と類縁をなしている。改良運動とは、日本を急速に西欧近代に接近させるため、日本のさまざまな分野の制度を西欧風に改良していこうとする運動だが、その根幹となったのが言文一致を中心とすることばの組み替えの試みであった。具体的には国民の啓蒙(けいもう)を目的としていたが、結果的には日本人のそれまでの思考の変革を促す一種の精神革命として機能していった。
(『日本大百科事典(ニッポニカ)』「言文一致」山田有策)>
「明治の精神」は「一種の精神革命」に関わる事だろう。
<平安時代まで言文一致であったが、文に変化が生じなかったのに対し、言は変化し、鎌倉時代以降は言文二途の時代になる。その後江戸時代に至るまで標準的な文章体(和文)が古典的な性格を帯びたものだったために、幕末から明治期にかけて、西欧にならった言文一致の文章が求められた。
(『山川 日本史小辞典』「言文一致」)>
「言文二途」は建前と本音の使い分けと関係があるのではなかろうか。
<社会学者作田啓一によれば、普通、社会体系の外側にある理念的文化(あらゆる状況を通じて意味の一貫性を保持しようとする文化)がタテマエとして尊重されるが、それは、社会体系内の状況からの要請を入れて現実と妥協し、制度的文化となる。生活上の実際の行動を動機づけるのは、ホンネとしての制度的文化のほうである。日本のような後者が相対的に優位を占める社会では、タテマエ・ホンネ間の相互浸透や両者の使い分けが顕著であるという。
(『日本大百科全書(ニッポニカ)』「タテマエとホンネ」濱口恵俊)>
こうした「使い分け」に失敗した人の精神状態を指す言葉が「明治の精神」ではないか。
2000 「自由と独立と己れ」の交錯する「現代」
2500 明示できない精神
2530 和魂洋才
2532 分裂病的
「明治の精神」という言葉は建前の表現だ。Sは本音を隠している。静に隠しているばかりか、聞き手Pにも隠している。その隠蔽工作に作者は加担している。作者は本音を隠したまま、その気分を読者に伝達しようとしている。鬱陶しい。
<和魂洋才とは外面と内面とを使いわけるということである。これこそまさに精神分裂病質者が試みることである。あるいはこう言った方がよければ、ある危機的状況にあって、外面と内面との使いわけというこの防衛機制を用いることが、精神の分裂をもたらすのである。当人はこの使いわけによってうまく危機的状況に対処しているつもりでも、そのことが彼の人格にぬぐいがたい亀裂と傷痕をきざみこむ。そして、その結果、彼がうまく対処するつもりであった危機的状況はますます危険で脅威的となり、彼はますますこの防衛機制に訴えざるを得なくなり、ここに悪循環が生じる。洋才は外面だけのことであり、内面では和魂を堅持しているつもりでも、そうはゆかない。外的自己と内的自己とが生き生きとした統一的関係にあってこそ、いいかえれば外的自己が内的自己のありのままの自発的表現であり、かつ内的自己が外的自己の行動を自分の主体的意志に発し、自分が決定でき、自分に責任がある行動であると実感していてこそ、人格の統一性、自己同一性は保たれるのである。外的自己と内的自己を使いわけ、外的自己を危機的状況、脅威的外敵に対処するための一時の仮面とするならば、内的自己は外的自己に対するコントロールを失い、そのうち、外的自己は内的自己の意志とは無関係に振舞いはじめ、その行動は自分ではなく他者によって決定されるかのように感じられてくる。つまり、内的自己から見れば、外的自己はむしろ敵の同盟者のようにうつる。他人が自分の内奥まで踏みこんでくるという被迫害感の起源はここにある。
(岸田秀『ものぐさ精神分析』「日本近代を精神分析する―精神分裂病としての日本近代」)>
「和魂洋才」という言葉のもとは〈和魂漢才〉だ。
<日本固有の精神を以て中国から伝来した学問を活用することの重要性を強調していう。
(『広辞苑』「和魂漢才」)>
和魂漢才の実態は不明。
<明治の菅原道真ともいうべき和洋の学芸に精通した森鷗外(おうがい)は、平安以来の系統を踏んで「和魂洋才」をすすめた。それは西洋文化の摂取とともに、それと日本文化の融合を説く良識豊かなものであったが、近代日本の激流的な思想界はそれを流布させないで終わった。
(『日本大百科事典(ニッポニカ)』「和魂漢才・和魂洋才」原田隆吉)>
和魂洋才の実態も不明。
2000 「自由と独立と己れ」の交錯する「現代」
2500 明示できない精神
2550 和魂洋才
2533 造語
和魂洋才の場合、〈開化の漢語による和風の意味の表現〉だったと考えられる。原語のままではなく、「アイスクリーム」(上一)のようなカタカナ語、「印(いん)気(き)」(下十七)のような当て字を用いた。さらには、「アンドレ」(上五)を「安得烈」(上五)と書いて〈安んぞ烈しきを得ん〉などと読ませる気だったのなら、ややこしいことになる。
<アメリカの教科書(きょうかしょ)を、そのままほん訳(やく)して使ったので、かなりむずかしく、おかしな文章(ぶんしょう)が多(おお)くてたいへんでした。
(樋口清之監修『学研まんが 日本の歴史 第12巻 明治維新』)>
「おかしな文章(ぶんしょう)」が明治前期の青年にはハイカラに思えたのだろう。
<文豪・大家たちは、古くから一般的に用いられてきた四字熟語はもちろん、みずからが新たに造語したものも縦横に駆使して、それぞれ独自の文章世界を築いています。
(日本漢字教育振興会編著『知っ得 文豪・大家の「四字熟語術」』)>
漢語による造語は、江戸時代から始まっていた。
<(zenuw(オランダ)の訳語として、杉田玄白が「解体新書」で初めて用いた語。「神気配」「経脈」から造語)
(『広辞苑』「神経」)>
「神経」と「万物を生成する霊妙な力」(『広辞苑』「神気」)や「漢方で、気血が運行する主要な通路」(『広辞苑』「経脈」)の関係は不明。「人体内の生気と血液。血液の循環」(『広辞苑』「気血」)も私にはわからない。「生気」で行き止まり。
<Kの神経衰弱はこの時もう大分(だいぶ)可くなっていたらしいのです。それと反比例に、私の方は段々過敏になって来ていたのです。
(夏目漱石『こころ』「下二十八」)>
「神経衰弱に罹(かか)っている位」(下二十二)が「神経衰弱」になっている。「らしい」は伝聞か。
「それ」の指す言葉がない。「反比例に」は誤用だろう。
「過敏」を「衰弱」と並べるのはおかしい。二人は、神経質だったのではないか。
<ふつう神経質が体質性であるのと異なり、獲得性のものとされるが厳密な区別はない。
(『百科事典マイペディア』「神経衰弱」)>
何が何やら。こっちの方が「神経衰弱」になりそう。
(2530終)