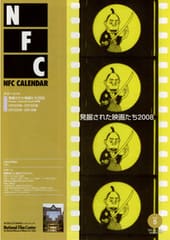
こういうのは貴重なフィルムという価値だけでさほど面白くないんでは?と思うものの、その中にあっていたく惹かれるのはやっぱり演芸映画。
ところがこれが今見ても充分楽しめるプログラムでした。
まずは・・・
「ハリキリ春部隊」
(17分・35mm・白黒)
芸人たちが落語、漫才、歌謡、バンド演奏、舞踊、フランスの人形劇、タップダンスなどを披露する楽しい作品。1930年代後半の映画館において、芸人たちがライブ・パフォーマンスをおこなう「アトラクション」興行が流行したが、本作は逆にアトラクションを映画化した「スクリーン・アトラクション」である。
'30年代後半(読売新聞社)(監)長尾史録(出)春風亭柳橋、香島ラッキー、御園セブン、静ときわ、サクラヰ・イス・オルケスタ、滝譲二、ユーナ・プーポ人形劇団、早川三兄弟
タップダンスの子供衆は早川三兄弟。恐ろしや。
サクラヰ・イス・オルケスタってバンドはマジでカッコ良し。
ラッキー、セブンはバーのスタンドに座ってのオーソドックスなしゃべくり漫才。70年の時を隔てて劇場に笑い声が満ちる。相方のかみさんネタは普遍。
唯一、知っている芸人の柳橋。やはり映像的にとても解りやすい方で、落語断片アトラクション向き。
「亞歐聯絡大飛行完成記念 神風音頭」
(2分・35mm・白黒)
1937年、朝日新聞社の飛行機「神風号」が、東京からロンドンまで94時間で飛行して世界記録を打ち立てた。本作はそのニュースに合わせて発売された歌謡曲「神風音頭」が流れる短篇作品で、「神風号」を背景に、踊り子たちが輪になって舞う映像が付されている。
'37(朝日新聞社)(作詞)飯塚飛雄太郎(作曲)中山晋平(小唄)勝太郎、山、市丸
当時のプロモーションビデオか。
振袖の踊り子盆踊りに微妙な可笑しさが・・・
「特輯 藝能たから船 藝能映畫第三輯(お笑ひ週間 笑ふ風船)」
(30分・35mm・白黒)
兵士の慰問のために組織された「芸能たから船」の船内を舞台に、松竹のスターや多くの芸能人たちが漫才、歌謡曲、ミュージカルを繰り広げる愉快な喜劇。監督の川島雄三の回想によると、本作は戦争末期に製作されたが、公開されたのは終戦後の1946年で、国策調の場面がいくつかカットされたという。ただし本プリントが戦後版なのか、戦中版なのかは不明(素材提供:手島茂氏)
'46(松竹大船)(監)(脚)川島雄三(脚)淀橋太郎(撮)亀山松太郎(出)西川サクラ、西川ヒノデ、河村黎吉、坂本武、横尾泥海男、坊屋三郎、橘薫、 並木路子、佐野周二、水戸光子、田端義夫、三井秀男、山路義人、上山草人、三浦光子、原保美、峰三枝子
作品としてこれが一番まとまっていて楽しめた。
劇場にはやはり年配の方が多いのだけれど、この中の数人はスクリーン上の芸人を懐かしく見ているわけだ。羨ましい。この川島雄三の貴重な作品を当時見て憶えている方が果たしているのだろうか?まず居ないと思う・・・
60年代生まれの私にでも顔と名前の一致する芸人さんの登場は流石に劇場が一瞬沸く。
若き坊屋三郎、横尾泥海男の古典的スラプスティック芸が見れて嬉しい。ハシゴを上るときのズッコケなどに満足。現代、無声映画時代からのこのテンポでのズッコケ要素をしっかり背景に持つ芸人さんが果たして何人居るか?寂しいものです。
田端嘉男の若さも嬉しい。三井秀男の一心太助。この方も古いんですね。
「麗人歌合戦」
(20分・35mm・白黒)
終戦後に製作された演芸映画。東ヤジロー・キタハチの漫才、歌手の柴田つる子(「悲しがらせないでね」)、松原操(「駒鳥は啼けど」)、池眞理子(「愛のスヰング」)、渡邊はま子(「蘇州夜曲」)らが登場する。特別出演として舞踊の高田せい子と山田五郎も登場。アメリカからの「返還映画」の1本で、これまでほとんど上映する機会のなかった作品。
'46-47年頃(朝日映画社)(音)平川英夫(出)東ヤジロー・キタハチ、柴田つる子、松原操、池眞理子、渡邊はま子、田せい子、山田五郎
最後は歌謡ショー。談志家元や志らくでは無いのでここで知っている歌手、歌は渡邊はま子の「蘇州夜曲」のみ。少し疲れたので子守唄としてしばしまどろむ。
画像はフィルムセンターのパンフレット。描かれているのは日本最古のコマ撮り式アニメーション「なまくら刀」
たまたま見たTV番組で中尾彬が紹介していました。
京橋 フィルムセンター


ところがこれが今見ても充分楽しめるプログラムでした。

まずは・・・
「ハリキリ春部隊」
(17分・35mm・白黒)
芸人たちが落語、漫才、歌謡、バンド演奏、舞踊、フランスの人形劇、タップダンスなどを披露する楽しい作品。1930年代後半の映画館において、芸人たちがライブ・パフォーマンスをおこなう「アトラクション」興行が流行したが、本作は逆にアトラクションを映画化した「スクリーン・アトラクション」である。
'30年代後半(読売新聞社)(監)長尾史録(出)春風亭柳橋、香島ラッキー、御園セブン、静ときわ、サクラヰ・イス・オルケスタ、滝譲二、ユーナ・プーポ人形劇団、早川三兄弟
タップダンスの子供衆は早川三兄弟。恐ろしや。
サクラヰ・イス・オルケスタってバンドはマジでカッコ良し。

ラッキー、セブンはバーのスタンドに座ってのオーソドックスなしゃべくり漫才。70年の時を隔てて劇場に笑い声が満ちる。相方のかみさんネタは普遍。

唯一、知っている芸人の柳橋。やはり映像的にとても解りやすい方で、落語断片アトラクション向き。
「亞歐聯絡大飛行完成記念 神風音頭」
(2分・35mm・白黒)
1937年、朝日新聞社の飛行機「神風号」が、東京からロンドンまで94時間で飛行して世界記録を打ち立てた。本作はそのニュースに合わせて発売された歌謡曲「神風音頭」が流れる短篇作品で、「神風号」を背景に、踊り子たちが輪になって舞う映像が付されている。
'37(朝日新聞社)(作詞)飯塚飛雄太郎(作曲)中山晋平(小唄)勝太郎、山、市丸
当時のプロモーションビデオか。
振袖の踊り子盆踊りに微妙な可笑しさが・・・
「特輯 藝能たから船 藝能映畫第三輯(お笑ひ週間 笑ふ風船)」
(30分・35mm・白黒)
兵士の慰問のために組織された「芸能たから船」の船内を舞台に、松竹のスターや多くの芸能人たちが漫才、歌謡曲、ミュージカルを繰り広げる愉快な喜劇。監督の川島雄三の回想によると、本作は戦争末期に製作されたが、公開されたのは終戦後の1946年で、国策調の場面がいくつかカットされたという。ただし本プリントが戦後版なのか、戦中版なのかは不明(素材提供:手島茂氏)
'46(松竹大船)(監)(脚)川島雄三(脚)淀橋太郎(撮)亀山松太郎(出)西川サクラ、西川ヒノデ、河村黎吉、坂本武、横尾泥海男、坊屋三郎、橘薫、 並木路子、佐野周二、水戸光子、田端義夫、三井秀男、山路義人、上山草人、三浦光子、原保美、峰三枝子
作品としてこれが一番まとまっていて楽しめた。

劇場にはやはり年配の方が多いのだけれど、この中の数人はスクリーン上の芸人を懐かしく見ているわけだ。羨ましい。この川島雄三の貴重な作品を当時見て憶えている方が果たしているのだろうか?まず居ないと思う・・・
60年代生まれの私にでも顔と名前の一致する芸人さんの登場は流石に劇場が一瞬沸く。

若き坊屋三郎、横尾泥海男の古典的スラプスティック芸が見れて嬉しい。ハシゴを上るときのズッコケなどに満足。現代、無声映画時代からのこのテンポでのズッコケ要素をしっかり背景に持つ芸人さんが果たして何人居るか?寂しいものです。

田端嘉男の若さも嬉しい。三井秀男の一心太助。この方も古いんですね。
「麗人歌合戦」
(20分・35mm・白黒)
終戦後に製作された演芸映画。東ヤジロー・キタハチの漫才、歌手の柴田つる子(「悲しがらせないでね」)、松原操(「駒鳥は啼けど」)、池眞理子(「愛のスヰング」)、渡邊はま子(「蘇州夜曲」)らが登場する。特別出演として舞踊の高田せい子と山田五郎も登場。アメリカからの「返還映画」の1本で、これまでほとんど上映する機会のなかった作品。
'46-47年頃(朝日映画社)(音)平川英夫(出)東ヤジロー・キタハチ、柴田つる子、松原操、池眞理子、渡邊はま子、田せい子、山田五郎
最後は歌謡ショー。談志家元や志らくでは無いのでここで知っている歌手、歌は渡邊はま子の「蘇州夜曲」のみ。少し疲れたので子守唄としてしばしまどろむ。

画像はフィルムセンターのパンフレット。描かれているのは日本最古のコマ撮り式アニメーション「なまくら刀」
たまたま見たTV番組で中尾彬が紹介していました。

京橋 フィルムセンター
















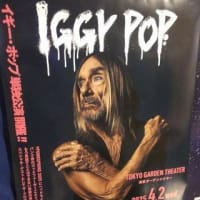



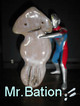







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます