一休は、女色も男色もほしいままにした。隠れてこそこそし
たのではない。平気でそのことを『狂雲集』に披露した。自
分のことを「骨軆露堂々、純一将軍誉、風流好色腸」(骨体
はまことに堂々としていて、一休宗純は将軍の誉れ、しかも
はらわたの奥まで好色で詰まっている)などと豪語した。こ
んな七言絶句もある。
一生受用する米銭の吟
恥辱無知にして万金を攪む
勇色美尼 惧に混雑
陽春の白雪 また 哇音
どういう意味かというと、お経を読んでいさえすれば、坊主
なんてものは一生食いっぱぐれない。適当に恥をかき、無知
を承知でいれば大金は入る。そこへもってきて男色に遊び、
ついでに尼さんをものにしていれば、これは陽春(堺の陽春
寺)でほとばしる「白雪」だっていつもピュッピュと飛ばせ
て、気持ちいいこと限りない、くだいて言えば、まあ、こう
いった内容だ。
一休は天真爛漫なのではなく、「毒」をもっていたのだ。毒
だけではなく、「悪」がある。悪だけではなく、「狂」があ
る。そもそも自身であえて「狂雲子」あるいは「夢閨」(む
けい)と号したほどである。狂雲子は風来とともに風狂風逸
に生き抜くことを、夢閨は夢うつつのままに精神の閨房をた
のしむことを意味した。
これを偽善に対する偽悪の姿勢とみてもよいけれど(一休の
偽悪者ぶりはこれまでもさんざん語られてきたが)、それだ
けではない。野僧であろうとしながら大徳寺をとりまとめた
し、破戒僧でありながら一休文化圏をつくりきった。飯尾宗
祇、柴屋軒宗長、山崎宗鑑、村田珠光、金春禅竹、曾我蛇足、
兵部墨溪‥‥、いずれもその後の文化を大成していった連中
の多くが、一休文化圏の住人だった。
一休はまた、尊皇の気概もすさまじかった。
次の七言絶句の漢詩と、その現代語訳の試みをくらべるとよい。
秀句寒哦す 五十年
愧(は)ずらくは乃祖洞曹の禅に泥(なず)みしことを
秋風に忽ち洒(そそ)ぐ小時の涙
夜雨青燈 白髪の前
俺の人生寒かった、洞春おやじがうらめしや。
風が誘った幼児の涙、青い灯火に白髪が光る。
これは、禅語録として『狂雲集』を研究し、上田堪庵の一乗
寺野仏庵では1年にわたって狂雲集講座ともいうべきを語り
つづけた柳田聖山の訳である。まるで歌謡曲である。しかし
柳田さんは、ぼくが思うにいま最も一休を理解できている人
なのである。
また、次の「懐古」という漢詩では、はやくから一休に惚
れこんで日本詩人選に『一休』(筑摩書房)を書き、好きな
漢詩を片っ端から大胆でポップな現代語にしていった富士正
晴が、以下のような訳をほどこした。
愛念愛思、胸次を苦しむ
詩文忘却一字無し
唯悟道有って道心無し
今日猶愁う生死に沈まんことを
エロスは 胸を苦しめる
詩文は忘却 すっからかん
ロゴスあれども パトスなし
まだまだ気になる 生き死にが
うまい、うまい。さすが飄逸の富士正晴だ。が、こういう意
訳で当たっているのかどうかという問題ではない。一休その
人が、いま、このような応接を、われわれに迫っているとい
うことなのである。
菩薩とは、修行を完了した者が他者を意識したときの姿の本
来のことをいう。そこに向かうことが菩薩行である。それを
することを仏教史では「大乗」とよんできた。
禅も、むろんこの大乗の菩薩を意図して、他者に向かって
いく。禅が自己の悟りを求めているなどというのは、わずか
20年だけのことなのだ。みだりに禅と自己発見などをつな
げないほうがいい。
正恁麼(しょういんも)の時」といって、「まさしくこの時、
この状態をどうするか」という、正念場を迫るときにしょっ
ちゅう使われる「どうしてくれますか?」なのである。「さ
あ、やるのか、やらないのか、正恁麼」「行くのか、行かな
いのか、正恁麼」というふうに。道元も『正法眼蔵』でこれ
を乱発した。
仏教では、供養は心からのお節介ができるかどうかというこ
となのだ。お節介ができない者など、そもそも仏門にすら入
れない。供養というのはそもそも衣食住すべての世話をする
ことで、古代インドでは四種供養といって、衣食住に薬を加
えて病気の世話も供養と考えた。
たのではない。平気でそのことを『狂雲集』に披露した。自
分のことを「骨軆露堂々、純一将軍誉、風流好色腸」(骨体
はまことに堂々としていて、一休宗純は将軍の誉れ、しかも
はらわたの奥まで好色で詰まっている)などと豪語した。こ
んな七言絶句もある。
一生受用する米銭の吟
恥辱無知にして万金を攪む
勇色美尼 惧に混雑
陽春の白雪 また 哇音
どういう意味かというと、お経を読んでいさえすれば、坊主
なんてものは一生食いっぱぐれない。適当に恥をかき、無知
を承知でいれば大金は入る。そこへもってきて男色に遊び、
ついでに尼さんをものにしていれば、これは陽春(堺の陽春
寺)でほとばしる「白雪」だっていつもピュッピュと飛ばせ
て、気持ちいいこと限りない、くだいて言えば、まあ、こう
いった内容だ。
一休は天真爛漫なのではなく、「毒」をもっていたのだ。毒
だけではなく、「悪」がある。悪だけではなく、「狂」があ
る。そもそも自身であえて「狂雲子」あるいは「夢閨」(む
けい)と号したほどである。狂雲子は風来とともに風狂風逸
に生き抜くことを、夢閨は夢うつつのままに精神の閨房をた
のしむことを意味した。
これを偽善に対する偽悪の姿勢とみてもよいけれど(一休の
偽悪者ぶりはこれまでもさんざん語られてきたが)、それだ
けではない。野僧であろうとしながら大徳寺をとりまとめた
し、破戒僧でありながら一休文化圏をつくりきった。飯尾宗
祇、柴屋軒宗長、山崎宗鑑、村田珠光、金春禅竹、曾我蛇足、
兵部墨溪‥‥、いずれもその後の文化を大成していった連中
の多くが、一休文化圏の住人だった。
一休はまた、尊皇の気概もすさまじかった。
次の七言絶句の漢詩と、その現代語訳の試みをくらべるとよい。
秀句寒哦す 五十年
愧(は)ずらくは乃祖洞曹の禅に泥(なず)みしことを
秋風に忽ち洒(そそ)ぐ小時の涙
夜雨青燈 白髪の前
俺の人生寒かった、洞春おやじがうらめしや。
風が誘った幼児の涙、青い灯火に白髪が光る。
これは、禅語録として『狂雲集』を研究し、上田堪庵の一乗
寺野仏庵では1年にわたって狂雲集講座ともいうべきを語り
つづけた柳田聖山の訳である。まるで歌謡曲である。しかし
柳田さんは、ぼくが思うにいま最も一休を理解できている人
なのである。
また、次の「懐古」という漢詩では、はやくから一休に惚
れこんで日本詩人選に『一休』(筑摩書房)を書き、好きな
漢詩を片っ端から大胆でポップな現代語にしていった富士正
晴が、以下のような訳をほどこした。
愛念愛思、胸次を苦しむ
詩文忘却一字無し
唯悟道有って道心無し
今日猶愁う生死に沈まんことを
エロスは 胸を苦しめる
詩文は忘却 すっからかん
ロゴスあれども パトスなし
まだまだ気になる 生き死にが
うまい、うまい。さすが飄逸の富士正晴だ。が、こういう意
訳で当たっているのかどうかという問題ではない。一休その
人が、いま、このような応接を、われわれに迫っているとい
うことなのである。
菩薩とは、修行を完了した者が他者を意識したときの姿の本
来のことをいう。そこに向かうことが菩薩行である。それを
することを仏教史では「大乗」とよんできた。
禅も、むろんこの大乗の菩薩を意図して、他者に向かって
いく。禅が自己の悟りを求めているなどというのは、わずか
20年だけのことなのだ。みだりに禅と自己発見などをつな
げないほうがいい。
正恁麼(しょういんも)の時」といって、「まさしくこの時、
この状態をどうするか」という、正念場を迫るときにしょっ
ちゅう使われる「どうしてくれますか?」なのである。「さ
あ、やるのか、やらないのか、正恁麼」「行くのか、行かな
いのか、正恁麼」というふうに。道元も『正法眼蔵』でこれ
を乱発した。
仏教では、供養は心からのお節介ができるかどうかというこ
となのだ。お節介ができない者など、そもそも仏門にすら入
れない。供養というのはそもそも衣食住すべての世話をする
ことで、古代インドでは四種供養といって、衣食住に薬を加
えて病気の世話も供養と考えた。













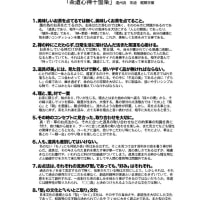
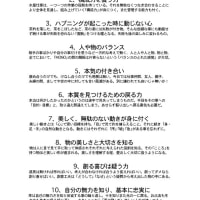
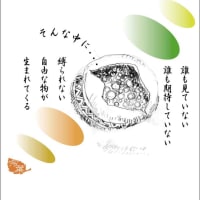

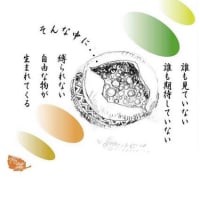
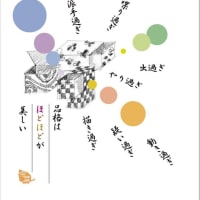
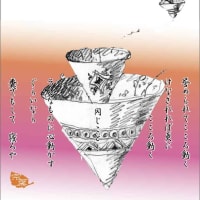
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます