茶室の空間特性を軸に、利休までの茶の湯(侘茶)の系譜を確認していく
●壁の出現
物理的に壁を作り閉鎖空間を形成する茶室は、日本古来の建築と比較すると非常に特殊な空間といえます。
茶室はまた、空間を認識上のものとして考える日本文化と、無常観を持つ仏教文化との寄り合いの結果生まれたのです。
たとえば、千利休は黒い壁で閉ざされた二畳台目の『待庵』を作りました。その小さな空間は、人間の精神を凝縮し、追い込むためのものなのです。
「利休は壁だけで空間を作りたかったはずだから、壁の延長として小さな躙口(にじりぐち)が生まれた」。そうしたことから「躙口は入口の否定の結果だ」と内田氏は言います。
●茶室と無常観
平安時代の僧、栄西が宋より持ち込み始まった茶の湯。当初は薬用として利用されていたものが、次第に貴族や武家、一般庶民の生活にまで入り込んでゆきました。室町時代には、殿中茶湯(でんちゅうちゃのゆ)といった支配者層の儀式にまで発展します。
ここに表れたのが、無常観・隠者の文学に大きな影響を受けた村田珠光。それまでの茶の湯に対して、「足下の文化を見直そう、派手な遊びではなくもっと深い、質素な心の中を見つめよう」という「侘茶」を生み出します。
●会所の成立 ── 北山文化
人々が集まって歌を詠んだり美術品を鑑賞したりするところが、会所(かいしょ)。最初は普通の邸宅を一時的にしつらえて会所としていたのですが、次第に専用の部屋を作るようになります。会所が独立して一つの建築となった例が、金閣寺(鹿苑寺)です。
唐物賞翫(からものしょうがん)、茶の湯の遊芸化の流れの中、儀礼的空間である会所で行われた殿中茶湯が台子の茶(だいすのちゃ)に発展します。
●数寄の展開 ── 東山文化
唐物を飾るにふさわしい会所を追求した結果生まれたのが書院造。足利義政の慈照寺(銀閣寺)東求堂同仁斎は、付け書院と違い棚を持つ書院造でありながら、日本最初の四畳半茶室です。
数寄屋造は、このような書院造の型から逸脱し、西行のような隠者が暮らす草庵(そうあん)や、宮廷文化の装飾性などが融合して生まれたと言われています。
●茶室の変遷
唐物中心の茶の湯に、同時代の文学や禅や能、連歌といった日本の思想を取り込み「和漢の境をまぎらか」して、村田珠光が生んだ侘茶。
利休の師である武野紹鴎が珠光を引き継ぎ、和風化を進めさらに侘茶を深めます。そして、時間や空間にまで侘茶の世界を拡げ、大成したのが千利休です。
利休の茶室の成立過程では、縁や土間、庭が捨てられ、装飾も排除されます。それは、空(ウツ)の空間であり、今の瞬間 ── つまり季節 ── を取り入れ、皆で共有する閉ざされた空間でした。そのために、表の世界が入り込めないような壁を作ったのです。
しかし一方で、利休は台目構(だいめがまえ)を作り、そこで茶室に新たな景色を存在させています。内田氏は「このような(演出を考えた)利休は何者だろうか」と言います。
侘茶を大成した千利休、利休以降の政治・武家の茶の湯を代表する古田織部、小堀遠州という3茶人の比較から、茶室や庭といった空間の特徴を考える
●千利休
利休(1522~91)の茶室は、それまでの開放的な日本建築を裏切ったものでした。黒い色調、躙口(にじりぐち)や壁による物理的な閉鎖。これらによって茶室から外部を遮断し、濃密な内部空間を成立させます。(「侍庵」)
空間を小さくすることで心の中に無限を生んだのです。
「利休は茶の湯そのものを草体化した」。
‘自然に従う時代の完成者’である利休。「自然そのものをもう一回作った結果、できたものが自然なものになる、というのが利休の論理です」。
露地は、茶室に行くためだけの存在となり‘渡り六分 景四分’が良しとされます。
延段(のべだん)は自然石だけを漆喰で固めたものでした。
「景色にとらわれすぎると深い茶の湯ができないから、あまり景色を作ってはいけない」と言った利休。利休の茶の湯の根底には‘無作為の作為’という精神があるのです。
「利休は井戸茶碗が大好きで、最後は長次郎の黒楽に至るが、非常に作為のない、すっとした茶碗を好んで使う」。他の茶道具も「利休の茶席ではその中に、すっとあるという感じ」と内田氏は解説します。
●古田織部
利休七哲の一人で利休の高弟であった織部(1544~1615)。しかし、織部は利休とは全く違う茶の湯を始めます。「自分の時代の茶をやったのです」と内田氏。
織部の生きた慶長年間は、街が活気づく一方、幕藩体制が確立し武家政権が安定し始めた時代です。そうした中、武家の茶を作れと言われたのが織部。
「武家の茶を確立しなければならない、一方で自分の心の中にあるアヴァンギャルドな精神をどう抑えようか。この矛盾が、建築など様々なものに出てくる」。
織部は‘自然を造形する時代のパイオニア’といえます。
露地には赤い実を付ける木を一本だけ使うなど、景色が重視され‘渡り四分 景六分’が良しとされます。延段も、切石と自然石を混ぜた作りになりました。
茶室に窓を作ることで、庭との関係は強まり、室内は明るくなります(「燕庵」)。柱の美しさを強調するなど、‘座敷の景’も存在するようになります。また相伴席(しょうばんせき)を設け、茶席に身分の上下関係を導入したのも織部です。
独特な図案、色彩、形の茶碗を好んだ織部。利休と比較して「織部の茶席では道具が堂々としている」と内田氏は言います。
●小堀遠州
遠州(1579~1647)の時代は江戸幕府三代将軍・家光の頃で、社会は固定化していました。利休や織部の時代とは違って、茶の湯は自立した世界を持ち政治と深く関わっていません。
「茶の湯に対してまっすぐに取り組むことができた」遠州。
彼は、平安、室町、安土桃山、町衆などの文化を全部取り入れて、その上で‘きれいさび’という理念で茶の湯を構成してゆきます。
「遠州は、建築的天才だった」と内田氏。草庵の意図を書院的に再編集した遠州の茶室
(「忘筌」)。茶会は、小間・鎖の間・広間を併用して開き、美術品の鑑賞と喫茶が混じり合った新たな茶の湯の形式を作ります。
‘自然を造形する時代の完成者’遠州は、「作為を洗練させた」と内田氏は評します。
秋になると全体が紅葉し、延段は切石だけで構成される遠州の庭。自然のモチーフを編集して使用し、そこに水平感覚など日本的な要素を盛り込んでいます。
また遠州は、名物(めいぶつ)を自ら認定するなど、道具を見せることを重視しました。白色の端正な洗練された茶碗などが、遠州の好みです。
●壁の出現
物理的に壁を作り閉鎖空間を形成する茶室は、日本古来の建築と比較すると非常に特殊な空間といえます。
茶室はまた、空間を認識上のものとして考える日本文化と、無常観を持つ仏教文化との寄り合いの結果生まれたのです。
たとえば、千利休は黒い壁で閉ざされた二畳台目の『待庵』を作りました。その小さな空間は、人間の精神を凝縮し、追い込むためのものなのです。
「利休は壁だけで空間を作りたかったはずだから、壁の延長として小さな躙口(にじりぐち)が生まれた」。そうしたことから「躙口は入口の否定の結果だ」と内田氏は言います。
●茶室と無常観
平安時代の僧、栄西が宋より持ち込み始まった茶の湯。当初は薬用として利用されていたものが、次第に貴族や武家、一般庶民の生活にまで入り込んでゆきました。室町時代には、殿中茶湯(でんちゅうちゃのゆ)といった支配者層の儀式にまで発展します。
ここに表れたのが、無常観・隠者の文学に大きな影響を受けた村田珠光。それまでの茶の湯に対して、「足下の文化を見直そう、派手な遊びではなくもっと深い、質素な心の中を見つめよう」という「侘茶」を生み出します。
●会所の成立 ── 北山文化
人々が集まって歌を詠んだり美術品を鑑賞したりするところが、会所(かいしょ)。最初は普通の邸宅を一時的にしつらえて会所としていたのですが、次第に専用の部屋を作るようになります。会所が独立して一つの建築となった例が、金閣寺(鹿苑寺)です。
唐物賞翫(からものしょうがん)、茶の湯の遊芸化の流れの中、儀礼的空間である会所で行われた殿中茶湯が台子の茶(だいすのちゃ)に発展します。
●数寄の展開 ── 東山文化
唐物を飾るにふさわしい会所を追求した結果生まれたのが書院造。足利義政の慈照寺(銀閣寺)東求堂同仁斎は、付け書院と違い棚を持つ書院造でありながら、日本最初の四畳半茶室です。
数寄屋造は、このような書院造の型から逸脱し、西行のような隠者が暮らす草庵(そうあん)や、宮廷文化の装飾性などが融合して生まれたと言われています。
●茶室の変遷
唐物中心の茶の湯に、同時代の文学や禅や能、連歌といった日本の思想を取り込み「和漢の境をまぎらか」して、村田珠光が生んだ侘茶。
利休の師である武野紹鴎が珠光を引き継ぎ、和風化を進めさらに侘茶を深めます。そして、時間や空間にまで侘茶の世界を拡げ、大成したのが千利休です。
利休の茶室の成立過程では、縁や土間、庭が捨てられ、装飾も排除されます。それは、空(ウツ)の空間であり、今の瞬間 ── つまり季節 ── を取り入れ、皆で共有する閉ざされた空間でした。そのために、表の世界が入り込めないような壁を作ったのです。
しかし一方で、利休は台目構(だいめがまえ)を作り、そこで茶室に新たな景色を存在させています。内田氏は「このような(演出を考えた)利休は何者だろうか」と言います。
侘茶を大成した千利休、利休以降の政治・武家の茶の湯を代表する古田織部、小堀遠州という3茶人の比較から、茶室や庭といった空間の特徴を考える
●千利休
利休(1522~91)の茶室は、それまでの開放的な日本建築を裏切ったものでした。黒い色調、躙口(にじりぐち)や壁による物理的な閉鎖。これらによって茶室から外部を遮断し、濃密な内部空間を成立させます。(「侍庵」)
空間を小さくすることで心の中に無限を生んだのです。
「利休は茶の湯そのものを草体化した」。
‘自然に従う時代の完成者’である利休。「自然そのものをもう一回作った結果、できたものが自然なものになる、というのが利休の論理です」。
露地は、茶室に行くためだけの存在となり‘渡り六分 景四分’が良しとされます。
延段(のべだん)は自然石だけを漆喰で固めたものでした。
「景色にとらわれすぎると深い茶の湯ができないから、あまり景色を作ってはいけない」と言った利休。利休の茶の湯の根底には‘無作為の作為’という精神があるのです。
「利休は井戸茶碗が大好きで、最後は長次郎の黒楽に至るが、非常に作為のない、すっとした茶碗を好んで使う」。他の茶道具も「利休の茶席ではその中に、すっとあるという感じ」と内田氏は解説します。
●古田織部
利休七哲の一人で利休の高弟であった織部(1544~1615)。しかし、織部は利休とは全く違う茶の湯を始めます。「自分の時代の茶をやったのです」と内田氏。
織部の生きた慶長年間は、街が活気づく一方、幕藩体制が確立し武家政権が安定し始めた時代です。そうした中、武家の茶を作れと言われたのが織部。
「武家の茶を確立しなければならない、一方で自分の心の中にあるアヴァンギャルドな精神をどう抑えようか。この矛盾が、建築など様々なものに出てくる」。
織部は‘自然を造形する時代のパイオニア’といえます。
露地には赤い実を付ける木を一本だけ使うなど、景色が重視され‘渡り四分 景六分’が良しとされます。延段も、切石と自然石を混ぜた作りになりました。
茶室に窓を作ることで、庭との関係は強まり、室内は明るくなります(「燕庵」)。柱の美しさを強調するなど、‘座敷の景’も存在するようになります。また相伴席(しょうばんせき)を設け、茶席に身分の上下関係を導入したのも織部です。
独特な図案、色彩、形の茶碗を好んだ織部。利休と比較して「織部の茶席では道具が堂々としている」と内田氏は言います。
●小堀遠州
遠州(1579~1647)の時代は江戸幕府三代将軍・家光の頃で、社会は固定化していました。利休や織部の時代とは違って、茶の湯は自立した世界を持ち政治と深く関わっていません。
「茶の湯に対してまっすぐに取り組むことができた」遠州。
彼は、平安、室町、安土桃山、町衆などの文化を全部取り入れて、その上で‘きれいさび’という理念で茶の湯を構成してゆきます。
「遠州は、建築的天才だった」と内田氏。草庵の意図を書院的に再編集した遠州の茶室
(「忘筌」)。茶会は、小間・鎖の間・広間を併用して開き、美術品の鑑賞と喫茶が混じり合った新たな茶の湯の形式を作ります。
‘自然を造形する時代の完成者’遠州は、「作為を洗練させた」と内田氏は評します。
秋になると全体が紅葉し、延段は切石だけで構成される遠州の庭。自然のモチーフを編集して使用し、そこに水平感覚など日本的な要素を盛り込んでいます。
また遠州は、名物(めいぶつ)を自ら認定するなど、道具を見せることを重視しました。白色の端正な洗練された茶碗などが、遠州の好みです。













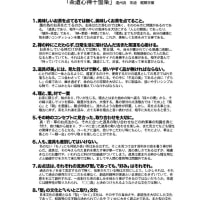
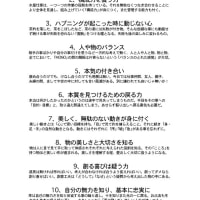
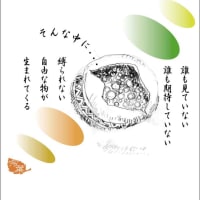

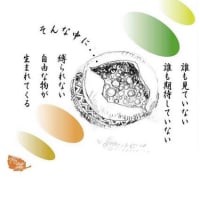
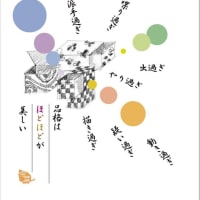
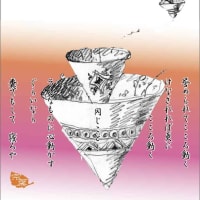
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます