「茶事・茶会に招かれたときに」
●待合での会話
待合や寄付などでの客同士の挨拶として決められた言葉があるというわけではなく、時間帯にもよりますが、まず日常生活での挨拶と変わりない挨拶を交わします。また、どのようなときでも客同士が交わす折に用いられるのは、
「本日はよろしくお願いいたします」
「お相伴させていただきます」
という挨拶です。
「お相伴」というのは、茶道では正客に隣席していっしょにもてなしを受けることをいい、正客を除く連客を相伴といいます。正客は、連客がそろったところで、扇子を前に置いて、
「本日、正客をつとめさせていただきます○○と申します。まだまだ未熟ものではございますが、よろしくお願いいたします」
などと挨拶しておきます。また、お詰(末客)も同様に、
「お詰をっとめさせていただきます○○と申します。本日は行き届かないこととは存じますが、どうかよろしくお願いいたします」
などと挨拶します。この挨拶に対して、連客一同は、
「こちらこそ、どうそよろしくお願いいたします」
などの挨拶を返します。
「大寄せ茶会」
大寄せの茶会などでは、待合に通った順に席入りする場合が多くあり、したがって正客がその場で決められることも多く、その場合は、着座の後、扇子を前にして連客一同に、
「皆様を前にたいへん僭越ながら、正客をつとめさせていたくことになりました○○と申します。何かございましたときは、どうぞよろしくお願いいたします」
などの挨拶をしておくとよいでしょう。連客は、それぞれの両隣りの客に、
「お相伴させていただきます」
とひとこと挨拶しておきましょう。もし、茶会が初めての場合やまだ慣れていない場合は、上座の客に、
「初めてのお茶会で何もわかりませんので、よろしくご指導ください」
「まだまだ不慣れでございますので、どうかよろしくお願いします」
などと伝え、下座の客には、
「作法も何も心得ておらず、ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします」
などと断っておくと丁寧になります。さらに大寄せの場合、流派の異なる席が混在することがありますが、遠慮をする必要はなく、席中、両隣りの連客に対して、
「流派が違うのでご無礼をするかもしれませんが、よろしくお願いいたします」
と挨拶しておくことも大切でしょう。
■席中での会話
亭主は客が定座についた気配を見計らって茶道口を開け、主客総礼。
そして正客は、
「どうぞお入りください」
と声をかけます。亭主が席に入ると、正客は扇子を膝前にしてひと膝進み、苧王に向かって今日の茶事に招かれた礼を述べます。お祝いの席であれば、
「本日はまことにおめでとうございます。このようなお祝いの席にお招きいただきまして、ありがとうございます」
などと申し上げます。また、
「本日は、結構なお席にお招きいただきまして、ありがとうございます」
などがよく用いられます。次客以下は、
「本日はお招きをいただき、ありがとうございます」
と簡単な挨拶が望ましく、初めての場合などは、.
「初めてのお茶会でございます。私までお招きいただき、たいへん緊張しております。お目だるいこととは存じますが、心してつとめさせていただきます」
という挨拶をしておくのもよいでしょう。
「茶事・茶会に招かれたときに」
お詰(末客)は、お招きのお礼の言葉に続いて、
「本日はお詰を仰せつかり、まことに光栄です。ふつつかものですが、何とぞよろしくお願い申し上げます」
連客の挨拶が一巡すると、亭主は、
「今日はお忙しいなか、はるばるお越しくださいまして、ありがとうございます。こころばかりで十分なおもてなしはできませんが、どうぞごゆっくりお過ごしください」
などと述べます。そして、正客は連客一同を代表して、
「先ほどは待合でお湯をありがとうございました」
と挨拶し、待合の掛物などをたずね、その心入れに感謝し、露地の風情をたたえ、本席の掛物などについて亭主におたずねします。茶会では、花や花入、香合が飾られていることが多いので、掛物に続いてうかがいます。ただし、席入り後の会話があまり長すぎると、この後に続く茶会の進行に支障をきたすことになりかねないので、簡潔にするように心がけておきましょう。
《犬寄せ茶会》
茶事、小寄せの茶会、大寄せの茶会において基本的には主客の挨拶はかわりませんが、正客が亭主より年配の場合には、亭主のほうから、
「本日はご多忙の折にもかかわらず、ようこそおいでくださいました。どうぞ、ごゆっくりお楽しみください」
などと挨拶します。この場合、正客は、
「ありがとうございます。大変楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします」
などの返礼をします。客の人数が多い茶会では、次客以下に亭主から、
「ご一同様もようこそ……」
と声がかかることもあり、連客一同は扇子を前に一礼します。次客までは亭主と挨拶を交わし、三客以下は省略することもあります。
床飾りについての問答
正客「本席のお掛物は」
亭主「○○筆でございます」
正客「ご立派なお筆でございますね。どうかお読み上げください」
亭主「△△△△△△△△と読みます。……という意味が込められております」
正客「ありがとうございほした。大変含蓄に富むすばらしいお言葉でございますね」
などといった問答がかわされます。花・花入については、.
正客「お見事なお花でございますが、何という名前でございますか」
亭主「白玉椿でございます」
正客「お花入のお作は」
亭主「○○作の竹一重切で、銘を○○と申します」
正客「いいお姿でございますね。ご銘が今日のお茶会にいかにもふさわしいと感じました」
亭主「そういっていただきますと、とてもうれしく思います」
などという問答が続きます。焼物の花入ならば、窯元をうかがいます。また、香合も飾られていた場合には、風炉の時季には、香合、香銘、塗りや材質、作者、炉では香合、香銘、窯元などをたずねます。
《大寄せ茶会》
席入り後、すぐに床飾りや花入、花などにっいての間答は時間が隈られているため、できないことが多く、その場合は点前中か、お茶が点てられた後などにたずねるようにするとよいでしょう。
「茶事・茶会に招かれたときに」
●炭手前の場合
亭主は炭斗を茶道口に置いて、
「お炭を直させていただきます」
などと挨拶します。亭主が点前座で釜を上げると、正客は釜の作者や造作をたずね、その後、正客は手順に従ってたずねていきます。香を炉中でたき、香合の蓋を閉めると、正客は、
「香合の拝見を」
と所望し、亭主はそれを受けて、香合を定座に出し、いったん水屋に引き上げ、頃合いを見て席にもど力、定座に返された香合の前に座って一礼し、正客の質問に答えます。たとえば、
正客「お見事な香合ですが……」
亭主「○○でございます」
正客「たいそうご立派ものですね。お作は?」
亭主「○○作の○○焼でございます」
正客「いつごろのものなのでしょうか」
亭主「△△時代頃のものと承知しております」
正客「お香もとても結構なもので、ありがとうございました」
などといった問答が交わされることになり、会話が進むに連れ、亭主の趣向や心入れが通じることになります。
●濃茶をいただく場合
亭主は正客が濃茶を一口飲んだときに、
「お服加減はいかがでございますか」
とたずね、正客は茶碗を左手に持ったまま、右手を膝前について、
「たいへん結構でございます」
「たいへんおいしゅうございます」
などと答えます。続いて客が一口飲んだ頃に、
正客「ありがとうございました。よい服加減で大変おいしくいただきました。ところでお茶銘は」
亭主「○○でございます」
正客「お詰はどちらでございますか」
亭主「○○でございます」
という問答があり、このとき茶銘をたずねるのは、亭主への礼儀になっていますが、濃茶に対してのみというのが約束。お詰とは、ここでは茶舗(茶師)のことを意味し、茶銘・お詰をたずねることは、その日のお茶の銘柄と製造元をたずねていることになります。
●主菓子などについて
濃茶席での濃茶、その茶銘・お詰について、主客の挨拶が交わされたのち、客は亭主に菓子と菓子器についてたずねます。たとえば、
「先ほどは、お心入れのお菓子をたいへんおいしく頂戴いたしましたが、どちらの御製でございましょうか」
亭主が、それに対して、
「○○です」
など菓子舗名などを答えると、正客は続けて、-
「ご銘は」
と問います。亭主は、
「銘は△△と申します」
などと答えます。
そして、点前座の道具についておたずねします。釜、棚、水指、炉縁、風炉先屏風などの順にうかがい、亭主の心入れに感謝しっっ趣向などが伝わるよう会話をひろげてゆきます。
よく用いられる言葉は、
「けっこうでございますね」「素晴らしいです」「ご立派と存じます」「お珍しいのではないでしょうか」「面白い一と存じます」
などがつかわれます。しかし、濃茶席の会話は簡潔に末客がお茶をいただき終わるまでに終えるように心がけます。
末客から茶碗、あるいは茶碗と古常紗がもどされると、正客はそれぞれを拝見し、次客以下に回します。正客は亭主に、窯元、作者、箱書、銘、形状などを問います。たとえば・
「大ぶりでたいそうどっしりとしたお茶碗ですが、どなたのお作で」
などとたずね、亭主は、
「○○の○○の作でございます」
などと答えます。正客は、
「さすがにご立派な景色でございますね」などと受けますが、もしこの茶碗の銘や形などが趣向にかなったものであれば、それを引き出すような問答をすると、茶会にいっそう興を添えることになります。また、古串紗については、裂地の名称、あれば裂の由緒などをたずね、
「素晴らしい文様でございますね」.
「○○緩子でございます」といった問答がかわされます。
《大寄せ茶会》
限られた時間のなかなので、、正客はあらかじめ道具を選んでたずねるようにします。会記を入手したら、席入り前によく拝見し、道具組のなかで、とくに亭主にたずねたいものを確認しておくとよいでしよ・つ。
●薄茶をいただく場合
薄茶はくつろいだ和やかな雰囲気で進行します。干菓子が配られたら頂戴し、正客は、
「このお干菓子のご製とご銘は?」
などとたずねます。順に薄茶をいただき、正客は頃合いを見計らって、連客に、
「皆さん、充分にいただかれましたでしょうか」
とたずねます。連客から、
「充分にいただきました」
との答えがあると、正客は、亭主が茶碗の湯を建水に捨て、
「もう一服いかがですか」
と問いかけるのに対して、
「もう充分いただきましたので、どうぞお仕舞いを」
と申し上げ、亭主は受け礼ののち、茶碗を下に置いて、
「それではお仕舞いさせていただきます」
と答えます。また、正客から、
「充分に頂戴いたしましたので、どうぞお仕舞いくださいませ」
と申し上げます。薄茶席での会話は、決まりきった応答ばかりでなく、この茶会が楽しい雰囲気になるように主客で時季や場所、茶会の趣旨に応じて話題を工夫したいものです。ただし、雑談にまで発展させることがないよう主客ともに心得ておきます。
●待合での会話
待合や寄付などでの客同士の挨拶として決められた言葉があるというわけではなく、時間帯にもよりますが、まず日常生活での挨拶と変わりない挨拶を交わします。また、どのようなときでも客同士が交わす折に用いられるのは、
「本日はよろしくお願いいたします」
「お相伴させていただきます」
という挨拶です。
「お相伴」というのは、茶道では正客に隣席していっしょにもてなしを受けることをいい、正客を除く連客を相伴といいます。正客は、連客がそろったところで、扇子を前に置いて、
「本日、正客をつとめさせていただきます○○と申します。まだまだ未熟ものではございますが、よろしくお願いいたします」
などと挨拶しておきます。また、お詰(末客)も同様に、
「お詰をっとめさせていただきます○○と申します。本日は行き届かないこととは存じますが、どうかよろしくお願いいたします」
などと挨拶します。この挨拶に対して、連客一同は、
「こちらこそ、どうそよろしくお願いいたします」
などの挨拶を返します。
「大寄せ茶会」
大寄せの茶会などでは、待合に通った順に席入りする場合が多くあり、したがって正客がその場で決められることも多く、その場合は、着座の後、扇子を前にして連客一同に、
「皆様を前にたいへん僭越ながら、正客をつとめさせていたくことになりました○○と申します。何かございましたときは、どうぞよろしくお願いいたします」
などの挨拶をしておくとよいでしょう。連客は、それぞれの両隣りの客に、
「お相伴させていただきます」
とひとこと挨拶しておきましょう。もし、茶会が初めての場合やまだ慣れていない場合は、上座の客に、
「初めてのお茶会で何もわかりませんので、よろしくご指導ください」
「まだまだ不慣れでございますので、どうかよろしくお願いします」
などと伝え、下座の客には、
「作法も何も心得ておらず、ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします」
などと断っておくと丁寧になります。さらに大寄せの場合、流派の異なる席が混在することがありますが、遠慮をする必要はなく、席中、両隣りの連客に対して、
「流派が違うのでご無礼をするかもしれませんが、よろしくお願いいたします」
と挨拶しておくことも大切でしょう。
■席中での会話
亭主は客が定座についた気配を見計らって茶道口を開け、主客総礼。
そして正客は、
「どうぞお入りください」
と声をかけます。亭主が席に入ると、正客は扇子を膝前にしてひと膝進み、苧王に向かって今日の茶事に招かれた礼を述べます。お祝いの席であれば、
「本日はまことにおめでとうございます。このようなお祝いの席にお招きいただきまして、ありがとうございます」
などと申し上げます。また、
「本日は、結構なお席にお招きいただきまして、ありがとうございます」
などがよく用いられます。次客以下は、
「本日はお招きをいただき、ありがとうございます」
と簡単な挨拶が望ましく、初めての場合などは、.
「初めてのお茶会でございます。私までお招きいただき、たいへん緊張しております。お目だるいこととは存じますが、心してつとめさせていただきます」
という挨拶をしておくのもよいでしょう。
「茶事・茶会に招かれたときに」
お詰(末客)は、お招きのお礼の言葉に続いて、
「本日はお詰を仰せつかり、まことに光栄です。ふつつかものですが、何とぞよろしくお願い申し上げます」
連客の挨拶が一巡すると、亭主は、
「今日はお忙しいなか、はるばるお越しくださいまして、ありがとうございます。こころばかりで十分なおもてなしはできませんが、どうぞごゆっくりお過ごしください」
などと述べます。そして、正客は連客一同を代表して、
「先ほどは待合でお湯をありがとうございました」
と挨拶し、待合の掛物などをたずね、その心入れに感謝し、露地の風情をたたえ、本席の掛物などについて亭主におたずねします。茶会では、花や花入、香合が飾られていることが多いので、掛物に続いてうかがいます。ただし、席入り後の会話があまり長すぎると、この後に続く茶会の進行に支障をきたすことになりかねないので、簡潔にするように心がけておきましょう。
《犬寄せ茶会》
茶事、小寄せの茶会、大寄せの茶会において基本的には主客の挨拶はかわりませんが、正客が亭主より年配の場合には、亭主のほうから、
「本日はご多忙の折にもかかわらず、ようこそおいでくださいました。どうぞ、ごゆっくりお楽しみください」
などと挨拶します。この場合、正客は、
「ありがとうございます。大変楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします」
などの返礼をします。客の人数が多い茶会では、次客以下に亭主から、
「ご一同様もようこそ……」
と声がかかることもあり、連客一同は扇子を前に一礼します。次客までは亭主と挨拶を交わし、三客以下は省略することもあります。
床飾りについての問答
正客「本席のお掛物は」
亭主「○○筆でございます」
正客「ご立派なお筆でございますね。どうかお読み上げください」
亭主「△△△△△△△△と読みます。……という意味が込められております」
正客「ありがとうございほした。大変含蓄に富むすばらしいお言葉でございますね」
などといった問答がかわされます。花・花入については、.
正客「お見事なお花でございますが、何という名前でございますか」
亭主「白玉椿でございます」
正客「お花入のお作は」
亭主「○○作の竹一重切で、銘を○○と申します」
正客「いいお姿でございますね。ご銘が今日のお茶会にいかにもふさわしいと感じました」
亭主「そういっていただきますと、とてもうれしく思います」
などという問答が続きます。焼物の花入ならば、窯元をうかがいます。また、香合も飾られていた場合には、風炉の時季には、香合、香銘、塗りや材質、作者、炉では香合、香銘、窯元などをたずねます。
《大寄せ茶会》
席入り後、すぐに床飾りや花入、花などにっいての間答は時間が隈られているため、できないことが多く、その場合は点前中か、お茶が点てられた後などにたずねるようにするとよいでしょう。
「茶事・茶会に招かれたときに」
●炭手前の場合
亭主は炭斗を茶道口に置いて、
「お炭を直させていただきます」
などと挨拶します。亭主が点前座で釜を上げると、正客は釜の作者や造作をたずね、その後、正客は手順に従ってたずねていきます。香を炉中でたき、香合の蓋を閉めると、正客は、
「香合の拝見を」
と所望し、亭主はそれを受けて、香合を定座に出し、いったん水屋に引き上げ、頃合いを見て席にもど力、定座に返された香合の前に座って一礼し、正客の質問に答えます。たとえば、
正客「お見事な香合ですが……」
亭主「○○でございます」
正客「たいそうご立派ものですね。お作は?」
亭主「○○作の○○焼でございます」
正客「いつごろのものなのでしょうか」
亭主「△△時代頃のものと承知しております」
正客「お香もとても結構なもので、ありがとうございました」
などといった問答が交わされることになり、会話が進むに連れ、亭主の趣向や心入れが通じることになります。
●濃茶をいただく場合
亭主は正客が濃茶を一口飲んだときに、
「お服加減はいかがでございますか」
とたずね、正客は茶碗を左手に持ったまま、右手を膝前について、
「たいへん結構でございます」
「たいへんおいしゅうございます」
などと答えます。続いて客が一口飲んだ頃に、
正客「ありがとうございました。よい服加減で大変おいしくいただきました。ところでお茶銘は」
亭主「○○でございます」
正客「お詰はどちらでございますか」
亭主「○○でございます」
という問答があり、このとき茶銘をたずねるのは、亭主への礼儀になっていますが、濃茶に対してのみというのが約束。お詰とは、ここでは茶舗(茶師)のことを意味し、茶銘・お詰をたずねることは、その日のお茶の銘柄と製造元をたずねていることになります。
●主菓子などについて
濃茶席での濃茶、その茶銘・お詰について、主客の挨拶が交わされたのち、客は亭主に菓子と菓子器についてたずねます。たとえば、
「先ほどは、お心入れのお菓子をたいへんおいしく頂戴いたしましたが、どちらの御製でございましょうか」
亭主が、それに対して、
「○○です」
など菓子舗名などを答えると、正客は続けて、-
「ご銘は」
と問います。亭主は、
「銘は△△と申します」
などと答えます。
そして、点前座の道具についておたずねします。釜、棚、水指、炉縁、風炉先屏風などの順にうかがい、亭主の心入れに感謝しっっ趣向などが伝わるよう会話をひろげてゆきます。
よく用いられる言葉は、
「けっこうでございますね」「素晴らしいです」「ご立派と存じます」「お珍しいのではないでしょうか」「面白い一と存じます」
などがつかわれます。しかし、濃茶席の会話は簡潔に末客がお茶をいただき終わるまでに終えるように心がけます。
末客から茶碗、あるいは茶碗と古常紗がもどされると、正客はそれぞれを拝見し、次客以下に回します。正客は亭主に、窯元、作者、箱書、銘、形状などを問います。たとえば・
「大ぶりでたいそうどっしりとしたお茶碗ですが、どなたのお作で」
などとたずね、亭主は、
「○○の○○の作でございます」
などと答えます。正客は、
「さすがにご立派な景色でございますね」などと受けますが、もしこの茶碗の銘や形などが趣向にかなったものであれば、それを引き出すような問答をすると、茶会にいっそう興を添えることになります。また、古串紗については、裂地の名称、あれば裂の由緒などをたずね、
「素晴らしい文様でございますね」.
「○○緩子でございます」といった問答がかわされます。
《大寄せ茶会》
限られた時間のなかなので、、正客はあらかじめ道具を選んでたずねるようにします。会記を入手したら、席入り前によく拝見し、道具組のなかで、とくに亭主にたずねたいものを確認しておくとよいでしよ・つ。
●薄茶をいただく場合
薄茶はくつろいだ和やかな雰囲気で進行します。干菓子が配られたら頂戴し、正客は、
「このお干菓子のご製とご銘は?」
などとたずねます。順に薄茶をいただき、正客は頃合いを見計らって、連客に、
「皆さん、充分にいただかれましたでしょうか」
とたずねます。連客から、
「充分にいただきました」
との答えがあると、正客は、亭主が茶碗の湯を建水に捨て、
「もう一服いかがですか」
と問いかけるのに対して、
「もう充分いただきましたので、どうぞお仕舞いを」
と申し上げ、亭主は受け礼ののち、茶碗を下に置いて、
「それではお仕舞いさせていただきます」
と答えます。また、正客から、
「充分に頂戴いたしましたので、どうぞお仕舞いくださいませ」
と申し上げます。薄茶席での会話は、決まりきった応答ばかりでなく、この茶会が楽しい雰囲気になるように主客で時季や場所、茶会の趣旨に応じて話題を工夫したいものです。ただし、雑談にまで発展させることがないよう主客ともに心得ておきます。













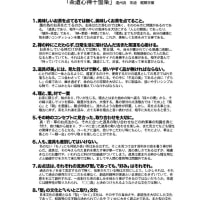
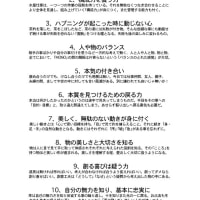
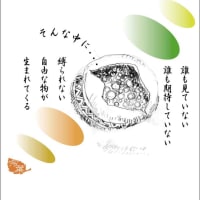

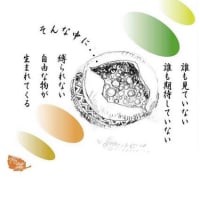
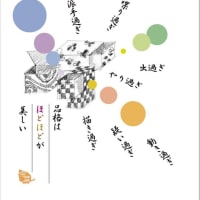
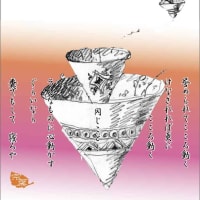
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます