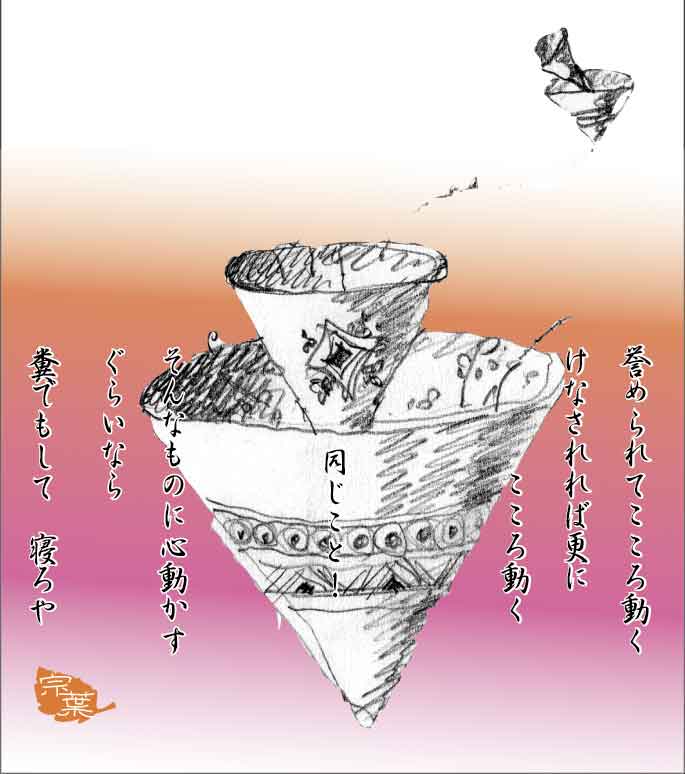
茶道の世界に「和敬清寂」という言葉があり、茶会の床等に掛かっているが他に、茶道を語るには切っても切れない代表的な「詫び」と「寂び」が良く使われてる。どちらの意味も、その人の立場、立場で解釈の違いが出て理解しづらい物がある。凡人の少ない経験からは、どうしても頭で理解しようとする働きが生まれ直覚的な判断に迷う事が多い。
それではこれらの意味を漢字一文字に置き換え、もっと身近な言葉で、言っている事の内容も解りやすい物は何か無いかな~と考えていた。
ジャジャジャジャ~ン、お待ちどうさん。苦節10年とは言わないが出ました。知りたい?それは「■」です。茶の湯の「心・技・体」の何処に当てはめてもお点前、道具(日本の美)、組み合わせ、に於いても、十分に使われても可笑しくはない「■」だと思う。
今まで「おもてなし、おもてなしの心」とよく使われ大衆化された言葉だが「何が?どんな?」という所で具体的なイメージが湧かなかったがこの言葉に置き換えてみると凡夫の私にも少しは理解できる。
それは、つつしむ、つつしみぶかい、つつましいの、心を表す立心偏に真人、真実、真理の真を従えた[慎]の文字である。
俺が、俺がの世界、自分にご褒美、金使って太り、又金使って痩せる。
殺伐とした世の中、ここらで、ちっとはこの文字「慎み」を見直してみよう。
辞書より、「慎ましい」の意味を拾ってみる。
1、遠慮深く物静か
2、控えめ
3、出しゃばらない
4、礼儀正しくしとやか
5、隅々まで行き届いた心
6、謙虚な気持ちでいる事











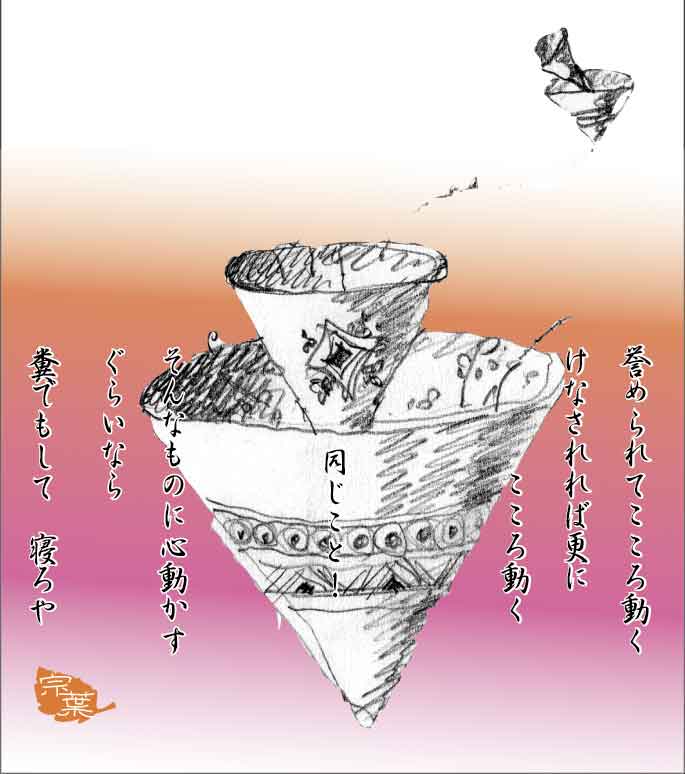 茶道の世界に「和敬清寂」という言葉があり、茶会の床等に掛かっているが他に、茶道を語るには切っても切れない代表的な「詫び」と「寂び」が良く使われてる。どちらの意味も、その人の立場、立場で解釈の違いが出て理解しづらい物がある。凡人の少ない経験からは、どうしても頭で理解しようとする働きが生まれ直覚的な判断に迷う事が多い。
茶道の世界に「和敬清寂」という言葉があり、茶会の床等に掛かっているが他に、茶道を語るには切っても切れない代表的な「詫び」と「寂び」が良く使われてる。どちらの意味も、その人の立場、立場で解釈の違いが出て理解しづらい物がある。凡人の少ない経験からは、どうしても頭で理解しようとする働きが生まれ直覚的な判断に迷う事が多い。
 この程度なら、誰でも出来る?
この程度なら、誰でも出来る?

