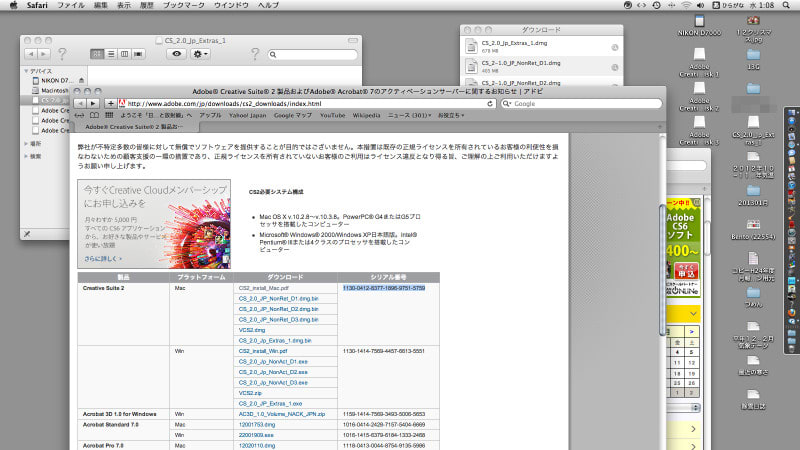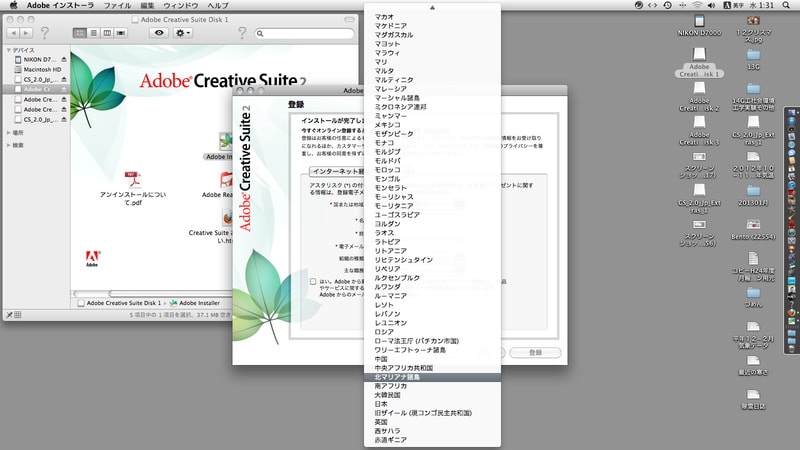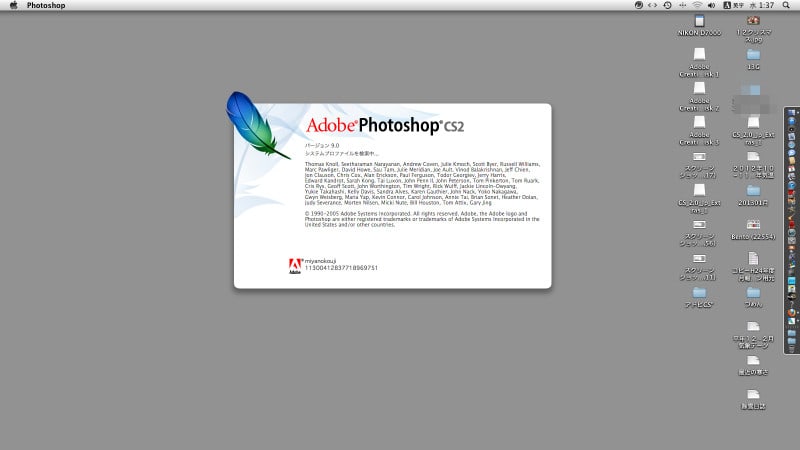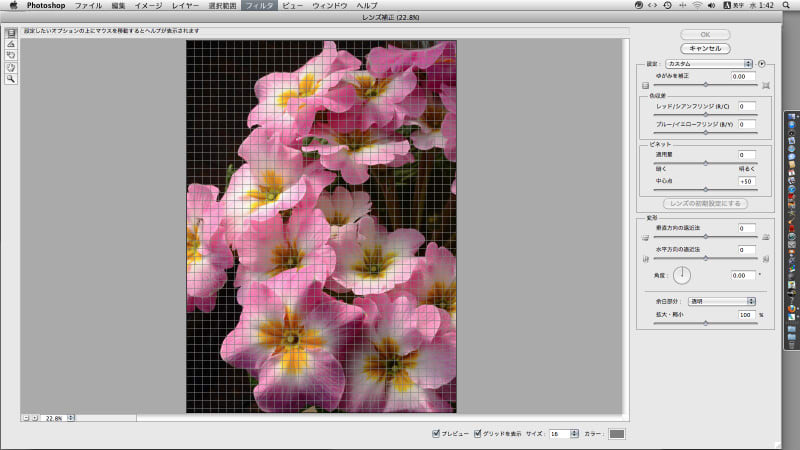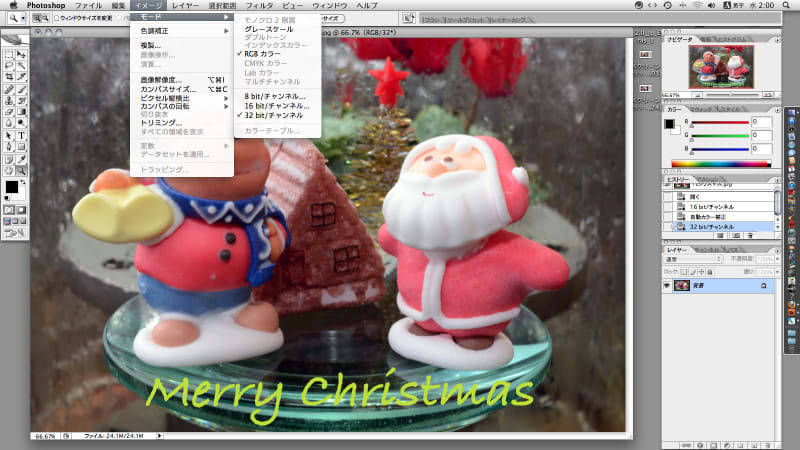天皇陛下が運転免許の更新に伴う、高齢者講習をうけられたそうだ。
記事はこちら。
さて運転免許と天皇陛下とは、この組み合わせに驚いた。ご自身で車を運転する姿が想像できない。もしも公道に出たら白バイ先導で、前後にSPのった車がつくのだろう。そもそも教習所はどうしたのだろうか。路上は絶対ある。軽井沢とか那須のご用邸付近で極秘に練習したのだろうか。都内でやった日には、通過する道路はほとんど警察で埋め尽くされて、下手すると信号まで操作されて、都内大渋滞が起きるだろう。
大体誰が教官になったのだろうか。やっぱり警視庁パトカー隊の隊長とかなのだろうか。
まあ戦前でないからそこまではと思うが、天皇が動くと実際そうなる。皇太子時代にとったにしても、同様だ。
ただ何で運転免許が必要なのだろうか。いまでも自分の庭を運転しているだけに過ぎない。実は一応公用地の道路だから、公道なのだろうか。マジメな天皇は、そのために免許を取ったのだろうか。考えられるが、さすがにこれはないだろう。
まさか、なのだが2・26の反省からイザとなったら一人ででも逃げられるように、免許を取ったのだろうか。あり得ない訳ではない。
不思議な話題である。
PS
皇太子は運転免許を持っているのだろうか。宮内庁のホームぺージには、皇室の免許等は載っていないようだ。
記事はこちら。
さて運転免許と天皇陛下とは、この組み合わせに驚いた。ご自身で車を運転する姿が想像できない。もしも公道に出たら白バイ先導で、前後にSPのった車がつくのだろう。そもそも教習所はどうしたのだろうか。路上は絶対ある。軽井沢とか那須のご用邸付近で極秘に練習したのだろうか。都内でやった日には、通過する道路はほとんど警察で埋め尽くされて、下手すると信号まで操作されて、都内大渋滞が起きるだろう。
大体誰が教官になったのだろうか。やっぱり警視庁パトカー隊の隊長とかなのだろうか。
まあ戦前でないからそこまではと思うが、天皇が動くと実際そうなる。皇太子時代にとったにしても、同様だ。
ただ何で運転免許が必要なのだろうか。いまでも自分の庭を運転しているだけに過ぎない。実は一応公用地の道路だから、公道なのだろうか。マジメな天皇は、そのために免許を取ったのだろうか。考えられるが、さすがにこれはないだろう。
まさか、なのだが2・26の反省からイザとなったら一人ででも逃げられるように、免許を取ったのだろうか。あり得ない訳ではない。
不思議な話題である。
PS
皇太子は運転免許を持っているのだろうか。宮内庁のホームぺージには、皇室の免許等は載っていないようだ。