私は受験していませんが、カリフォルニア州の司法試験の結果が出たようです。これで主要な州の結果は出そろったんじゃないかと思います。全体の合格率が48.6%ということで、昨年からは7%の合格率低下のようです。
以前からお伝えしているように今年は合格率が大幅に下がる州ばかりなのですが、この点についてABAジャーナルの記事が出ていました。簡単にいうと、試験実施団体(NCBE)側が今年の合格率の低下は受験者が悪いという趣旨の手紙を各ロースクールの学長に送り付けて炎上したようです。
ところで、日本でもロースクール生の進路が社会問題化していますが、こちらのロースクール生はある意味もっと深刻で、奨学金の選択肢は日本よりも多いものの、卒業生は1,500万円近くの借金をおって卒業することが普通ですので、就職先が決まらないことや合格ができないのは死活問題です(特に一流のロースクールではない場合、仮に合格しても法律家として就職先がないというのは聞きなれた話です)。そして仮に就職できても、初年度年収が1600万円を越えるようないわゆるビッグローではないと中々すぐに返せる大きさの金額ではありません。
ではよく言われるようにアメリカは弁護士が余っているのでしょうか?
この点について2014年10月にABAの記事が出ています。
つまるところ、(経済合理性を追求するとそうなると思いますが、)アメリカでも都市部に弁護士が集中しているということです。アメリカでも弁護士が不足しているエリアがあることを意外に思う方もいるんじゃないでしょうか。
視点を変えて、NYのプロボノ制度についても賛否両論があります。(個人的にも複雑な思いです)
NYのプロボノ制度は50時間のプロボノを義務付けるものですが、これはあくまでも新たにロースクールを卒業して受験する人にしか義務付けられていません。従って、すでにNYで働いている弁護士や他州資格をもとにWaiveInしてくるローヤーには適用されません。
NY側としては、
・毎年1万人以上受ける受験者が50時間プロボノをやれば、50時間×1万人だけ普段リーガルサービスを受けられない人を助けることができる。
・受験者側が座学では得られない経験や知識を得られる。
といったことをこの制度の意義としているようです。
確かにそういう面はあるのだと思います。
しかしながら、反対派の見解も説得力があります。
・1500万円超の借金を負った人たちに、50時間のただ働きを強制することになる。
・加えて、プロボノ要件は50時間と言っても、50時間ぴったりで終わる仕事なんてそうそうない。
・大きな事務所であればプロボノに人員を割く余裕があるが、小さな個人事務所ではなかなかそうはいかない。
・強制されるプロボノはプロボノと言えるのか。サービスをする側のモチベーションが低いおそれ。
・専門家ではない学生にプロボノを受けてもいいサービスが得られるとは思えない。
上記に個人的な経験をさらに加えるとすると、
・非弁行為を避けるためにはすでに誰かがやっているプロボノに参加するしかない。つまり既に弁護士が一人でやっているプロボノを学生が入って二人でやっているだけなので50時間×1万人にはならない。
・時間の長さを要件としているので、だらだら仕事をやる方が早く要件を満たすことができるという負のインセンティブが働く。
といった問題点があるように感じています。
個人的にはプロボノ活動を通じて、この機会がなければ知ることのなかった社会問題を知ることができましたし、非常にいい人生経験になったとは思います。なにより、困っている人を助けることができたのは良かったです。
しかしながら、せっかく実施したプロボノが(監督者側の問題で)NYのアドミッション要件を満たさなかったがために、0から50時間をやりなおす羽目になったなど、不愉快な思いをさせられたのも事実です。
あくまでも初年度ですので、これからこの制度もいろいろと改善されていくことになるとは思いますが、今後に期待します。
以前からお伝えしているように今年は合格率が大幅に下がる州ばかりなのですが、この点についてABAジャーナルの記事が出ていました。簡単にいうと、試験実施団体(NCBE)側が今年の合格率の低下は受験者が悪いという趣旨の手紙を各ロースクールの学長に送り付けて炎上したようです。
ところで、日本でもロースクール生の進路が社会問題化していますが、こちらのロースクール生はある意味もっと深刻で、奨学金の選択肢は日本よりも多いものの、卒業生は1,500万円近くの借金をおって卒業することが普通ですので、就職先が決まらないことや合格ができないのは死活問題です(特に一流のロースクールではない場合、仮に合格しても法律家として就職先がないというのは聞きなれた話です)。そして仮に就職できても、初年度年収が1600万円を越えるようないわゆるビッグローではないと中々すぐに返せる大きさの金額ではありません。
ではよく言われるようにアメリカは弁護士が余っているのでしょうか?
この点について2014年10月にABAの記事が出ています。
つまるところ、(経済合理性を追求するとそうなると思いますが、)アメリカでも都市部に弁護士が集中しているということです。アメリカでも弁護士が不足しているエリアがあることを意外に思う方もいるんじゃないでしょうか。
視点を変えて、NYのプロボノ制度についても賛否両論があります。(個人的にも複雑な思いです)
NYのプロボノ制度は50時間のプロボノを義務付けるものですが、これはあくまでも新たにロースクールを卒業して受験する人にしか義務付けられていません。従って、すでにNYで働いている弁護士や他州資格をもとにWaiveInしてくるローヤーには適用されません。
NY側としては、
・毎年1万人以上受ける受験者が50時間プロボノをやれば、50時間×1万人だけ普段リーガルサービスを受けられない人を助けることができる。
・受験者側が座学では得られない経験や知識を得られる。
といったことをこの制度の意義としているようです。
確かにそういう面はあるのだと思います。
しかしながら、反対派の見解も説得力があります。
・1500万円超の借金を負った人たちに、50時間のただ働きを強制することになる。
・加えて、プロボノ要件は50時間と言っても、50時間ぴったりで終わる仕事なんてそうそうない。
・大きな事務所であればプロボノに人員を割く余裕があるが、小さな個人事務所ではなかなかそうはいかない。
・強制されるプロボノはプロボノと言えるのか。サービスをする側のモチベーションが低いおそれ。
・専門家ではない学生にプロボノを受けてもいいサービスが得られるとは思えない。
上記に個人的な経験をさらに加えるとすると、
・非弁行為を避けるためにはすでに誰かがやっているプロボノに参加するしかない。つまり既に弁護士が一人でやっているプロボノを学生が入って二人でやっているだけなので50時間×1万人にはならない。
・時間の長さを要件としているので、だらだら仕事をやる方が早く要件を満たすことができるという負のインセンティブが働く。
といった問題点があるように感じています。
個人的にはプロボノ活動を通じて、この機会がなければ知ることのなかった社会問題を知ることができましたし、非常にいい人生経験になったとは思います。なにより、困っている人を助けることができたのは良かったです。
しかしながら、せっかく実施したプロボノが(監督者側の問題で)NYのアドミッション要件を満たさなかったがために、0から50時間をやりなおす羽目になったなど、不愉快な思いをさせられたのも事実です。
あくまでも初年度ですので、これからこの制度もいろいろと改善されていくことになるとは思いますが、今後に期待します。















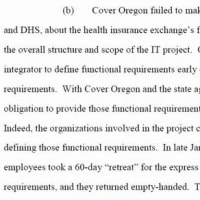
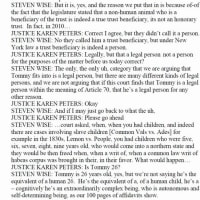
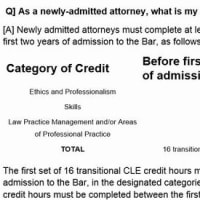
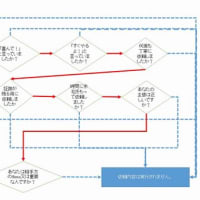

私も企業法務、LLMで、本年7月のNY barに合格したものです。私はすでに帰国して、日本で仕事をしながらプロボノの機会を探しています。現在、国際的な人権NGOでプロボノの機会をもらえそうなのですが、これが必ずしもlaw relatedという側面が強くないようで、少し気になっています。NGOでの監督者は弁護士ですので、supervisionはクリアすると思います。著者さんは、すでに行ったプロボノがqualifyされなかったという経験をお持ちなのですか。どのような点が問題になりましたか。どの程度詳しく審査されましたか。特に米国外で行うプロボノについては、詳述するように、NY barのFAQやaffidavitに書いてあり、心配しています。
少々長くなりますが、私に発生した事象を具体的に申し上げます。私はLLM在学中にとある州(以下、「A州」)のNPO法人の某オフィスでlaw relatedのプロボノを完了しました。プロボノ内容はA州法ではなく連邦法にかかわる問題でした。
ところがAffidavitをいざ取得する段になってみると私を直接監督していた弁護士がA州の資格を持っていないことが判明しました。これはNYのFAQのNo11で言うところの”an attorney admitted to practice and in good standing with the bar in the jurisdiction in which the work is performed”を満たさないことになります。(彼の弁護士自身はおそらくpro hac viceか何かで活動していたということなんだと思いますが詳細は分かりません。半年近く調整しましたがそのオフィスの別の弁護士のサインももらえませんでした。)
その後、ダメもとで匿名メールにてNY州裁判所のプロボノ質問窓口に上記のような事情で取得したAffidavitの有効性を問い合わせたところ、つれない返事が返ってきてしまいまして、結局プロボノを最初からやり直したということになります。
前置きが長くなりましたが、私の場合は仕事の内容そのものがレビューされて却下されたわけではなく、監督者の資格の有無でNGとなりました。また、Admission資料の提出後の審査でNGと言われたわけではなく、事前相談です。(正直なところ、アメリカ人のすることですので、しれっと上記のAffidavitを提出してもさらっと通る気もしていますが、そんなリスクは冒せないよなーと思ってスパッとあきらめました。)
個人的な感想ですので聞き流していただければと思いますが、初年度ということもありますし、Affidavitのプロボノ実施内容記入欄も大したことが書けるようになっていないですし、そもそも数千人も合格者がいますので、記入内容自体はいちいち細かくレビューされることはないんじゃないかなと思っています。おそらく、law relatedな業務をある程度強調した書き方になっていればOKと思われます。
(例えば単純なcopy作業とかそういうものは例えやっていたとしても要らぬ誤解を招きそうなので書かない方がいいと思っています)
お話しにくい事情もあったと存じますが、ご経験を共有いただき、ありがとうございました。私だけでなく、これからプロボノをする全員に有用な内容だと思います。
fed lawであればどの州の弁護士でもpracticeは可能なのにそんな点が問題になるとは。。。
私は、ngoでのプロボノについて、念のため、仕事内容をプロボノfaqの最後に書いてある質問用emailに送ってqualifyするか聞いてみました。数時間で返事が来て、[たぶんok、でもリーガルスキルを要求される範囲のみね、あと最終判断は、character fitness committeeがするから]とのこと。結局、やってみなければ、審査の厳しさはわからなそうです。
無事にqualifyすることを祈ります。ngoでの仕事は、企業法務で経験できるような仕事でなく、人脈もやや異なるので、ワクワクしてます。大いに楽しみたいと思います。
Mattさんの企業法務ネタの投稿も面白いです。eg. 法務部の生産性向上 私の会社も米系で、acc会員ですが、興味深い資料が多いですよね。今後もホットな投稿期待しています。ありがとうございました。