海外生活の目的のひとつに「異文化理解」というものがあげられることが多いと思います。そして、あまり違和感なく「そうだよね」と受け入れられているキーワードかと思います。ただ、じゃあ具体的に何をもって異文化理解をしたことになると、とても説明が難しいところです。
とりあえず文化というものに関してWikipediaの定義を拝借すると、
”・・・総じていうと人間が社会の成員として獲得する振る舞いに複合された総体のことである。社会組織(年齢別グループ、地域社会、血縁組織などを含む)ごとに固有の文化があるとされ、組織の成員になるということは、その文化を身につける(身体化)ということでもある。・・・もっとも文化は、次の意味で使われることが多い。
・ハイカルチャーのように洗練されたもの
・象徴的な思考や学習による信念やふるまいのパターン
・ある社会組織に共有されている価値観”
とのこと。とりあえずこんなもんかなーという定義な気がします。
さて、異文化理解というからには「異」文化なるものが存在することを前提として、その人たちを「自分の文化」との比較という観点で評価しなさいということなんだと思いますが、果たして「海外生活→異文化理解」という式は常に成り立つのでしょうか。成り立たせようと思ったら、どのような条件を満たすことが必要なんでしょうか。さらに言うと、「海外で外国人と交流すること」だけが異文化理解なんでしょうか。
★(異)文化理解が成り立つための条件
パッと思いつきで書いてみると
・ステップ0:異文化理解をしようというモチベーションとある程度のゴール感があり、自身の関心分野について以下のステップ1-4を回す心構えをしている。
・ステップ1:モノサシとしての自分の文化を認識している
・ステップ2:自分に接点のある相手方をモノサシで分析をし、差異を見出すことができる
・ステップ3:見つけた差異について、特定のグループに発現する行動様式であるとの抽象的/普遍的な評価ができる
・ステップ4:行動様式について、その行動様式を形成するにいたった背景事情を確認又は推察することができる(異文化モノサシの形成)
といったところでしょうか。
0.モチベーション
何事もそうですが、とくに考えなしに生きていると、とくに何も気づかずに生きていくことはよくあることです。46時中気を張って生きていくのも現実的ではありませんのでこれはこれでしょうがないのですが、たまに街中を歩いていて妙なものに遭遇しても「なんであれに気づかないの?」と指摘を受けたりしましたので、異文化理解を目的とするならば、やはりこういう心持ちは重要でしょう。もちろん、関心がない分野はこの限りではありません。
1.モノサシ
よく留学生へのアドバイスとして「日本の文化を学んでいったほうが良いよ」というものがあると思います。これは相手に日本を理解してもらうとか、自分を理解してもらうとか、そういった意味合いのほかに、モノサシとしての自分の文化が良くわかっていないと、異文化理解もおぼつかないということもあるのではないかと思います。これは別に日本では正月にもちを食べるとか、神社がそこら中にあるとか、そういった典型的な文化という話だけではなくて、ファッションだったり、漫画だったり、職場の様子だったり、政治や法制度だったり、自分の関心のある分野について理解を深めるということも含まれます。もっとも、卵と鶏の議論のように、自分が海外に行ってマイノリティになることで初めて自分の所属している文化の外縁が明確になってくるということもありますのでなかなか難しいのですが、やはり自分の物差しは意識しておくべきでしょう。
2.差異
実際に接した情報を分析するステップです。ここも意識して取り組まないとおろそかになるステップだと思います。なぜか。それはやはり21世紀のこの時代ですから、たいていの情報は目新しくないわけです。例えば、もしハロウィンでかぼちゃをくりぬくことを知らない人がいれば、ハロウィンの時期に加工されたかぼちゃ街中に並んでいることについて驚きをもって発見することができて、かつ記憶に強く刻まれると思いますが、そういったことをすでに知っていると、特にこれが異文化か!と感動し差異として認識することもあまりないのではないかと思います。もちろん巷の情報を自分の目で確認したというところにバリューはあると思いますが、これは異文化理解とはすこし異なる気もします。
他方で、ある程度相手の文化についての情報がないと、とてもチープな発見しかできません。悩ましいところです。
そのほかに考慮すべき点として、いわゆる先進国ですと(途上国はあてはまらないといいたいわけではありません)、普通に生活するだけでしたら、根本的には自分たちと同じような価値観と生活を共有していることも多いです。特殊なコミュニティルールがあるようなディープな世界には通常は入れませんので、そもそも見つけようと持っている差異なんてものが実はないかもしれません。これも自分自身の分析の細かさの単位というか精度によるとは思いますが。
3.評価
ここも悩ましいところです。文化というものが一個人の性格や習性を超えた、ある程度のコミュニティの総体としての振る舞いをさす概念ですので、例えばある友人Aから見聞きした話があったとしても、その人のコミュニティ全体に有意性をもって出現するものか判断は難しいわけです。これは例えば10人に話を聞いても当てにならないけど15人ならOKとかそういった話でもないですし、聞いてみる人の人選も注意が必要です。もちろん一個人が全知全能であることは不可能なんですが、一を聞いて十を語るような度を過ぎたグルーピングは場合によっては偏見みたいになるリスクもあるので悩ましいですね。
よく言われる異文化理解はここまでがスコープかと勝手に思っています。学生時代だったら、これでも貴重な経験と刺激になるし、「視野の広がり」として許されると思います。自分の所属するコミュニティの外にはこんな世界があったんだと。
4.理解
おそらく、ビジネスとして海外に行く場合はホントはここまで求められている・期待されていることが多いんじゃないかと思います。なぜかというと、0-3までは所詮「目に入ったものに気づきました」という情報認知のレベルですが、これはあくまでも「過去」の話で、そのときにその瞬間に得た知識や情報なだけです。一方で「今後」への一手としての派遣をしているほうとなると、「じゃあそれを踏まえて今後はどうするの」というところが本当の関心事となってくるかと思います。そこで異文化として認識したものについて、ある種の公式めいたものを見出す(理解)ことではじめて、応用力になるってことでしょう。
だからこそ、ネットやそのほかの手段で海外情報を集めることで済ますのではなくて、わざわざコストをかけて人間を現地に送っているわけです。海外生活で上記のプロセスを廻す訓練を日々繰り返すことで、やがて必然的に陳腐化することになる知識や情報ではなくて、ベーシックな処理能力としての、OSとしての能力が磨かれると期待していると思われます。今後どこかのタイミングで遭遇する可能性のある”異文化”は人種も国籍も性別も規模も中身も異なると思いますが、上記の訓練によって培われたOSが助けてくれる、ということかと思います。
最後に傍論ですが、上記のプロセスは別に外国人との間でだけで成立するものでもないと思っています。外国人と外国語で外国の中で交流しているとどうしても強く意識されますし、実際に上記のような理解力もおおいに要求されますが、実はコミュニティの単位の考え方次第では日本での日々の生活でも毎日同じプロセスが発生しているわけです。(だからこそ、急に外国に住んでも生きていけるわけです。)
だけども、そうしてみたときに、自分はどこまでまともに”異文化”理解に熱心だったかなというと反省すべきところがあるなと感じます。
以上、あまりまとまってませんし抽象的にしすぎた嫌いはありますが、自己反省を含めて、今後の方の参考に。
とりあえず文化というものに関してWikipediaの定義を拝借すると、
”・・・総じていうと人間が社会の成員として獲得する振る舞いに複合された総体のことである。社会組織(年齢別グループ、地域社会、血縁組織などを含む)ごとに固有の文化があるとされ、組織の成員になるということは、その文化を身につける(身体化)ということでもある。・・・もっとも文化は、次の意味で使われることが多い。
・ハイカルチャーのように洗練されたもの
・象徴的な思考や学習による信念やふるまいのパターン
・ある社会組織に共有されている価値観”
とのこと。とりあえずこんなもんかなーという定義な気がします。
さて、異文化理解というからには「異」文化なるものが存在することを前提として、その人たちを「自分の文化」との比較という観点で評価しなさいということなんだと思いますが、果たして「海外生活→異文化理解」という式は常に成り立つのでしょうか。成り立たせようと思ったら、どのような条件を満たすことが必要なんでしょうか。さらに言うと、「海外で外国人と交流すること」だけが異文化理解なんでしょうか。
★(異)文化理解が成り立つための条件
パッと思いつきで書いてみると
・ステップ0:異文化理解をしようというモチベーションとある程度のゴール感があり、自身の関心分野について以下のステップ1-4を回す心構えをしている。
・ステップ1:モノサシとしての自分の文化を認識している
・ステップ2:自分に接点のある相手方をモノサシで分析をし、差異を見出すことができる
・ステップ3:見つけた差異について、特定のグループに発現する行動様式であるとの抽象的/普遍的な評価ができる
・ステップ4:行動様式について、その行動様式を形成するにいたった背景事情を確認又は推察することができる(異文化モノサシの形成)
といったところでしょうか。
0.モチベーション
何事もそうですが、とくに考えなしに生きていると、とくに何も気づかずに生きていくことはよくあることです。46時中気を張って生きていくのも現実的ではありませんのでこれはこれでしょうがないのですが、たまに街中を歩いていて妙なものに遭遇しても「なんであれに気づかないの?」と指摘を受けたりしましたので、異文化理解を目的とするならば、やはりこういう心持ちは重要でしょう。もちろん、関心がない分野はこの限りではありません。
1.モノサシ
よく留学生へのアドバイスとして「日本の文化を学んでいったほうが良いよ」というものがあると思います。これは相手に日本を理解してもらうとか、自分を理解してもらうとか、そういった意味合いのほかに、モノサシとしての自分の文化が良くわかっていないと、異文化理解もおぼつかないということもあるのではないかと思います。これは別に日本では正月にもちを食べるとか、神社がそこら中にあるとか、そういった典型的な文化という話だけではなくて、ファッションだったり、漫画だったり、職場の様子だったり、政治や法制度だったり、自分の関心のある分野について理解を深めるということも含まれます。もっとも、卵と鶏の議論のように、自分が海外に行ってマイノリティになることで初めて自分の所属している文化の外縁が明確になってくるということもありますのでなかなか難しいのですが、やはり自分の物差しは意識しておくべきでしょう。
2.差異
実際に接した情報を分析するステップです。ここも意識して取り組まないとおろそかになるステップだと思います。なぜか。それはやはり21世紀のこの時代ですから、たいていの情報は目新しくないわけです。例えば、もしハロウィンでかぼちゃをくりぬくことを知らない人がいれば、ハロウィンの時期に加工されたかぼちゃ街中に並んでいることについて驚きをもって発見することができて、かつ記憶に強く刻まれると思いますが、そういったことをすでに知っていると、特にこれが異文化か!と感動し差異として認識することもあまりないのではないかと思います。もちろん巷の情報を自分の目で確認したというところにバリューはあると思いますが、これは異文化理解とはすこし異なる気もします。
他方で、ある程度相手の文化についての情報がないと、とてもチープな発見しかできません。悩ましいところです。
そのほかに考慮すべき点として、いわゆる先進国ですと(途上国はあてはまらないといいたいわけではありません)、普通に生活するだけでしたら、根本的には自分たちと同じような価値観と生活を共有していることも多いです。特殊なコミュニティルールがあるようなディープな世界には通常は入れませんので、そもそも見つけようと持っている差異なんてものが実はないかもしれません。これも自分自身の分析の細かさの単位というか精度によるとは思いますが。
3.評価
ここも悩ましいところです。文化というものが一個人の性格や習性を超えた、ある程度のコミュニティの総体としての振る舞いをさす概念ですので、例えばある友人Aから見聞きした話があったとしても、その人のコミュニティ全体に有意性をもって出現するものか判断は難しいわけです。これは例えば10人に話を聞いても当てにならないけど15人ならOKとかそういった話でもないですし、聞いてみる人の人選も注意が必要です。もちろん一個人が全知全能であることは不可能なんですが、一を聞いて十を語るような度を過ぎたグルーピングは場合によっては偏見みたいになるリスクもあるので悩ましいですね。
よく言われる異文化理解はここまでがスコープかと勝手に思っています。学生時代だったら、これでも貴重な経験と刺激になるし、「視野の広がり」として許されると思います。自分の所属するコミュニティの外にはこんな世界があったんだと。
4.理解
おそらく、ビジネスとして海外に行く場合はホントはここまで求められている・期待されていることが多いんじゃないかと思います。なぜかというと、0-3までは所詮「目に入ったものに気づきました」という情報認知のレベルですが、これはあくまでも「過去」の話で、そのときにその瞬間に得た知識や情報なだけです。一方で「今後」への一手としての派遣をしているほうとなると、「じゃあそれを踏まえて今後はどうするの」というところが本当の関心事となってくるかと思います。そこで異文化として認識したものについて、ある種の公式めいたものを見出す(理解)ことではじめて、応用力になるってことでしょう。
だからこそ、ネットやそのほかの手段で海外情報を集めることで済ますのではなくて、わざわざコストをかけて人間を現地に送っているわけです。海外生活で上記のプロセスを廻す訓練を日々繰り返すことで、やがて必然的に陳腐化することになる知識や情報ではなくて、ベーシックな処理能力としての、OSとしての能力が磨かれると期待していると思われます。今後どこかのタイミングで遭遇する可能性のある”異文化”は人種も国籍も性別も規模も中身も異なると思いますが、上記の訓練によって培われたOSが助けてくれる、ということかと思います。
最後に傍論ですが、上記のプロセスは別に外国人との間でだけで成立するものでもないと思っています。外国人と外国語で外国の中で交流しているとどうしても強く意識されますし、実際に上記のような理解力もおおいに要求されますが、実はコミュニティの単位の考え方次第では日本での日々の生活でも毎日同じプロセスが発生しているわけです。(だからこそ、急に外国に住んでも生きていけるわけです。)
だけども、そうしてみたときに、自分はどこまでまともに”異文化”理解に熱心だったかなというと反省すべきところがあるなと感じます。
以上、あまりまとまってませんし抽象的にしすぎた嫌いはありますが、自己反省を含めて、今後の方の参考に。
ひそかに気になっていたけれども、訴状が長すぎて読む気がしなかったのが、オラクルとオレゴン州のシステム開発をめぐる訴訟。
・参考:オレゴン州によるプレスリリース(Complaintへのリンクあり)
少し時間を作って気合を入れて読んでみることにしました。
本件がどんなものか端的にパラ1が表しているように思いますので抜き出してみます。刺激的な感じです。
※下線は私が入れてます。
> Oracle America, Inc. ("Oracle") fraudulently induced the State of Oregon (the "State") and the Oregon Health Insurance Exchange Corporation ("Cover Oregon") to enter into contracts for the purchase of hundreds of million of dollars of Oracle products and services that failed to perform as promised. Oracle then repeatedly breached those contracts by failing to deliver on its obligations, overcharging for poorly trained Oracle personnel to provide incompetent work, hiding from the State the true extent of Oracle's shoddy performance, continuing to promise what it could not deliver, and willfully refusing to honor its warranty to fix its errors without charge. Over the last three years, Oracle has presented the State and Cover Oregon with some $240,280,008 in false claims under those contracts. Oracle's conduct amounts to a pattern of racketeering activity that has cost the State and Cover Oregon hundreds of millions of dollars. Accordingly, plaintiff Ellen Rosenblum, the Attorney General for the State of Oregon, along with the State and Cover Oregon, brings this lawsuit to recover losses to the State and Cover Oregon caused by Oracle's fraud, racketeering, false claims, and broken contracts.
以下、起こった事象のうち興味深い記載(オレゴン側の主張ー適当にまるめて以下訳しています)
・オラクルは"Oracle Solution"がオレゴン州の要望を満たすことができるかどうかについてウソをついた。例えば、同商品がフレキシブルで、インテグレイテッドで、ほかのプログラムと簡単に連動して、ほとんどカスタマイズがいらなくて、すぐにセットアップできるといっていたがそうはならなかった。(パラ3)
・オラクルは同商品を購入する前のプレゼン、デモ、Q&Aセッションで詐欺的な説明を行っていた。第三者の評価者も騙された。(パラ4)
・オレゴンは最初は独立したシステムインテグレーターを別途雇おうと思ったのにオラクルがSIerは仕事を遅らせるだけだと抵抗した。オラクルは自己のコンサルサービスをSIerの代わりとして使わせた。(パラ5)
・オラクルの情報統制のせいでオレゴン州はソフトウェア開発の進捗状況をオラクルからのレポートで判断するほかなかった(パラ6)
・オラクルは進捗の80%が完成しているといっていたのに、納期遅延の段になって、開発範囲の減少などを訴えてきた。リリース日は遅らせられないので(注:オバマケアの為)仕方がないから開発スコープの減少に同意したのに、それでも納期に遅延した。納期遅延は明らかな状況にもかかわらず、オラクル側は納期までに完成すると言い続けた。(パラ7、8)
・オラクルは義務を果たしていないのにもかかわらず支払いだけは要求してきた。ちなみに納期は延長しても毎回守られなかった。(パラ9)
・オラクルのせいでオレゴン州側は余計な人員を雇って手動作業で保険等の申し込み手続きに対応させられた(パラ9)
・オラクルはシステムが完成したといってきたが、検査をしてみたらシステムは使える品質にないことが分かった。第三者評価をさせてみたら直すのにはtens of millionsのコストで1年以上かかるといわれるレベルだった。(パラ10)
・オラクルはWarrantyを守らずシステムの修正を拒否した。支払いを要求したうえに、支払わないなら、プロジェクトから抜けると言い出した。(パラ11)
いかがでしょうか。一方当事者の主張ですので、オラクル側は違う意見を持っているかとは思いますが、日本のトラブル事例でも聞いたようなことが書いてあります。オラクルは自社商品に詳しいはずなんじゃないかと思われますが、それでもこんな事態になったのはなぜなんでしょうね。
勝手な推測:
オバマケアのような政争の的だったものなので、仕様がよくわからない段階ではあるけども、リリース日だけ決まってしまったのでとりあえず契約することになった。ところが仕様がなかなか見えない状態だったので、自社パッケージが使えると思っていたが使えなかった。州側の担当者もなにを作ればいいかわかっていなかった。いざ開発を進めてみたらあれやこれやと政治的な外的な要因で要求仕様と開発スコープが増大していったのでいつまでたっても終わらない感じになった。採算が取れないので撤退することにしたら訴えられた。
ってところでしょうか?気になります。
…ここまで書いたところで、OracleがOregonを訴えたComplaintも見つけました。提供元はこちらのニュースサイトの記事です。
私の読みも遠からずってとこのようです。
例えばこちら:
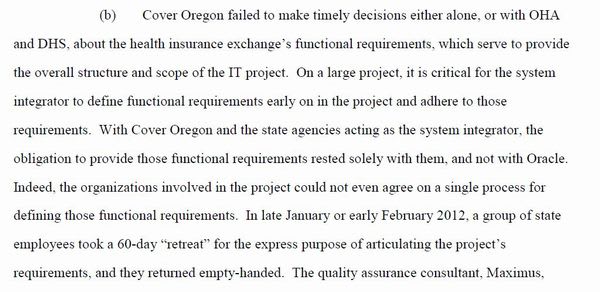
↓のくだりからも炎上プロジェクトにつき合わされたオラクル側の怨念が渦巻いて見えました…。

ところで、本件、オレゴン州側はホームである州裁判所で戦おうと思っていて、オラクル側はより中立的な連邦地裁で戦おうとしていましたが、州裁判所で戦うことになったようです。連邦裁判所に行くためにはsubject matter jurisdictionについてはFederal QuestionかComplete Diversity& $75,000が+必要ですが、FQ取得のために州による著作権法違反を持ち出すのは若干飛び道具な感じがしました。
・Oracle America accuses Oregon of violating federal copyright law in health exchange fight
・Oracle v. Oregon: State wins round one, but it's still early
おまけ:イギリスで発生した似たような炎上プロジェクト(NHS National Programme case)
関連して、某F社に関するニュース。
・参考:オレゴン州によるプレスリリース(Complaintへのリンクあり)
少し時間を作って気合を入れて読んでみることにしました。
本件がどんなものか端的にパラ1が表しているように思いますので抜き出してみます。刺激的な感じです。
※下線は私が入れてます。
> Oracle America, Inc. ("Oracle") fraudulently induced the State of Oregon (the "State") and the Oregon Health Insurance Exchange Corporation ("Cover Oregon") to enter into contracts for the purchase of hundreds of million of dollars of Oracle products and services that failed to perform as promised. Oracle then repeatedly breached those contracts by failing to deliver on its obligations, overcharging for poorly trained Oracle personnel to provide incompetent work, hiding from the State the true extent of Oracle's shoddy performance, continuing to promise what it could not deliver, and willfully refusing to honor its warranty to fix its errors without charge. Over the last three years, Oracle has presented the State and Cover Oregon with some $240,280,008 in false claims under those contracts. Oracle's conduct amounts to a pattern of racketeering activity that has cost the State and Cover Oregon hundreds of millions of dollars. Accordingly, plaintiff Ellen Rosenblum, the Attorney General for the State of Oregon, along with the State and Cover Oregon, brings this lawsuit to recover losses to the State and Cover Oregon caused by Oracle's fraud, racketeering, false claims, and broken contracts.
以下、起こった事象のうち興味深い記載(オレゴン側の主張ー適当にまるめて以下訳しています)
・オラクルは"Oracle Solution"がオレゴン州の要望を満たすことができるかどうかについてウソをついた。例えば、同商品がフレキシブルで、インテグレイテッドで、ほかのプログラムと簡単に連動して、ほとんどカスタマイズがいらなくて、すぐにセットアップできるといっていたがそうはならなかった。(パラ3)
・オラクルは同商品を購入する前のプレゼン、デモ、Q&Aセッションで詐欺的な説明を行っていた。第三者の評価者も騙された。(パラ4)
・オレゴンは最初は独立したシステムインテグレーターを別途雇おうと思ったのにオラクルがSIerは仕事を遅らせるだけだと抵抗した。オラクルは自己のコンサルサービスをSIerの代わりとして使わせた。(パラ5)
・オラクルの情報統制のせいでオレゴン州はソフトウェア開発の進捗状況をオラクルからのレポートで判断するほかなかった(パラ6)
・オラクルは進捗の80%が完成しているといっていたのに、納期遅延の段になって、開発範囲の減少などを訴えてきた。リリース日は遅らせられないので(注:オバマケアの為)仕方がないから開発スコープの減少に同意したのに、それでも納期に遅延した。納期遅延は明らかな状況にもかかわらず、オラクル側は納期までに完成すると言い続けた。(パラ7、8)
・オラクルは義務を果たしていないのにもかかわらず支払いだけは要求してきた。ちなみに納期は延長しても毎回守られなかった。(パラ9)
・オラクルのせいでオレゴン州側は余計な人員を雇って手動作業で保険等の申し込み手続きに対応させられた(パラ9)
・オラクルはシステムが完成したといってきたが、検査をしてみたらシステムは使える品質にないことが分かった。第三者評価をさせてみたら直すのにはtens of millionsのコストで1年以上かかるといわれるレベルだった。(パラ10)
・オラクルはWarrantyを守らずシステムの修正を拒否した。支払いを要求したうえに、支払わないなら、プロジェクトから抜けると言い出した。(パラ11)
いかがでしょうか。一方当事者の主張ですので、オラクル側は違う意見を持っているかとは思いますが、日本のトラブル事例でも聞いたようなことが書いてあります。オラクルは自社商品に詳しいはずなんじゃないかと思われますが、それでもこんな事態になったのはなぜなんでしょうね。
勝手な推測:
オバマケアのような政争の的だったものなので、仕様がよくわからない段階ではあるけども、リリース日だけ決まってしまったのでとりあえず契約することになった。ところが仕様がなかなか見えない状態だったので、自社パッケージが使えると思っていたが使えなかった。州側の担当者もなにを作ればいいかわかっていなかった。いざ開発を進めてみたらあれやこれやと政治的な外的な要因で要求仕様と開発スコープが増大していったのでいつまでたっても終わらない感じになった。採算が取れないので撤退することにしたら訴えられた。
ってところでしょうか?気になります。
…ここまで書いたところで、OracleがOregonを訴えたComplaintも見つけました。提供元はこちらのニュースサイトの記事です。
私の読みも遠からずってとこのようです。
例えばこちら:
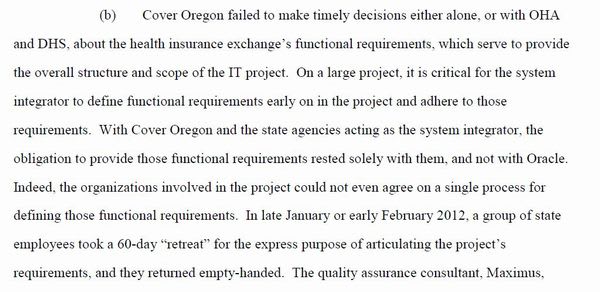
↓のくだりからも炎上プロジェクトにつき合わされたオラクル側の怨念が渦巻いて見えました…。

ところで、本件、オレゴン州側はホームである州裁判所で戦おうと思っていて、オラクル側はより中立的な連邦地裁で戦おうとしていましたが、州裁判所で戦うことになったようです。連邦裁判所に行くためにはsubject matter jurisdictionについてはFederal QuestionかComplete Diversity& $75,000が+必要ですが、FQ取得のために州による著作権法違反を持ち出すのは若干飛び道具な感じがしました。
・Oracle America accuses Oregon of violating federal copyright law in health exchange fight
・Oracle v. Oregon: State wins round one, but it's still early
おまけ:イギリスで発生した似たような炎上プロジェクト(NHS National Programme case)
関連して、某F社に関するニュース。
※注意:以下、ややセクシャルな内容が含まれていますので、気分を害するかもしれない方はこの記事をスキップしてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本がロースクール制度を導入した時の議論を呼び起こしてみると、多様なバックグラウンドを要する人材を法曹に、というのがあった気がします。実際どうなっているかは皆さんの方が詳しいところかと思いますが、日本のロースクール制度の参考ともなったここアメリカで、先日ひときわ目を引くニュースがアメリカの法律ネタを報道するブログに出ていました。
邦訳するならば、
「元A●女優がアメリカで一番難しい司法試験に合格」
といったところでしょうか。
※若干セクシーな写真が含まれていますのでオフィスで開く際はご注意を(笑
ヘザーさんはロースクールをJDとして卒業後、難関と言われるカリフォルニアのBARを一発で合格したそうですが、なんと今はストリッパーとして働いている人のようです。ニュースになるくらいなのでアメリカでも珍しいんでしょうが、今後はどのようなキャリアを選択されるのか気になります。
ところで気になるのが弁護士資格を取得する際のCharacter & Fitness審査。これは弁護士として活動するにふさわしい人格や適正であることを審査するものです。例えば、否定された事例として、多額の借金を抱えている人の例があります。
職業に貴賤はないといえど、こういった産業に厳しい意見を持っている人もいることが想像に難くないわけですが、はたしてどうなるんでしょうね。あるいは法的な観点だと対価を得て作品に出演していると違法行為になったりするのかな?とも思われ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本がロースクール制度を導入した時の議論を呼び起こしてみると、多様なバックグラウンドを要する人材を法曹に、というのがあった気がします。実際どうなっているかは皆さんの方が詳しいところかと思いますが、日本のロースクール制度の参考ともなったここアメリカで、先日ひときわ目を引くニュースがアメリカの法律ネタを報道するブログに出ていました。
邦訳するならば、
「元A●女優がアメリカで一番難しい司法試験に合格」
といったところでしょうか。
※若干セクシーな写真が含まれていますのでオフィスで開く際はご注意を(笑
ヘザーさんはロースクールをJDとして卒業後、難関と言われるカリフォルニアのBARを一発で合格したそうですが、なんと今はストリッパーとして働いている人のようです。ニュースになるくらいなのでアメリカでも珍しいんでしょうが、今後はどのようなキャリアを選択されるのか気になります。
ところで気になるのが弁護士資格を取得する際のCharacter & Fitness審査。これは弁護士として活動するにふさわしい人格や適正であることを審査するものです。例えば、否定された事例として、多額の借金を抱えている人の例があります。
職業に貴賤はないといえど、こういった産業に厳しい意見を持っている人もいることが想像に難くないわけですが、はたしてどうなるんでしょうね。あるいは法的な観点だと対価を得て作品に出演していると違法行為になったりするのかな?とも思われ。









