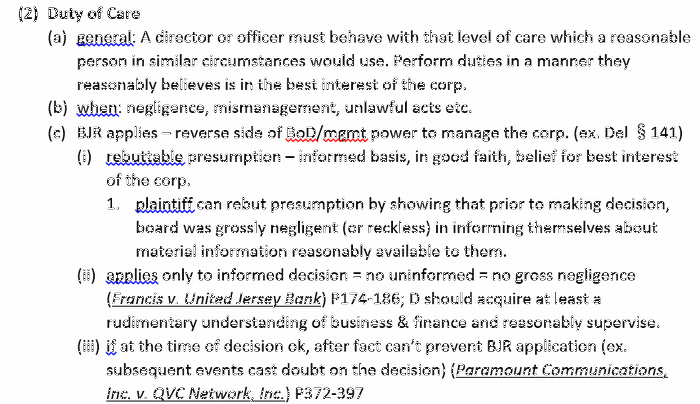こんにちは。前回の投稿から時間があいてしまいました。
体調不良で数日寝込んでいたのと、その後、ちょいと小旅行に出かけていたので更新ができませんでした。
体調不良については、日本からもってきていた風邪薬がなくなったこともあり、こちらの薬局で適当に薬を見繕って服用して回復しましたが、日本と違って病院に行くという選択肢が安易に取りづらいのは大変なところもあるなと身をもって体験しました。
さて、こんなときに心にしみるのは人のやさしさでして、寝込んでいて授業に出られなかったときに、特に頼んでもいなかったにもかかわらず、「今日、クラスにいなかったよね?」と休んだ回の授業ノートをメールで送ってくれたクラスメートがいました。アメリカに来てから一番感激したかもしれません。。。
そのほかの出来事としては、
・FORM8843提出準備開始(結局、Fビザの学生は全員提出が必要との大学からの指示)
・OPT提出準備開始(卒業後の滞在資格確保)
・卒業写真撮影
・卒業用衣装手配
といったところを通常の学生生活に加えて実施していました。そのほかMPRE、NYBAR、プロボノといった諸要件についても少しずつ準備を始めています。
何かと忙しい春学期ですが、体調に気を付けて、各種準備を進めていきたいと思います。
体調不良で数日寝込んでいたのと、その後、ちょいと小旅行に出かけていたので更新ができませんでした。
体調不良については、日本からもってきていた風邪薬がなくなったこともあり、こちらの薬局で適当に薬を見繕って服用して回復しましたが、日本と違って病院に行くという選択肢が安易に取りづらいのは大変なところもあるなと身をもって体験しました。
さて、こんなときに心にしみるのは人のやさしさでして、寝込んでいて授業に出られなかったときに、特に頼んでもいなかったにもかかわらず、「今日、クラスにいなかったよね?」と休んだ回の授業ノートをメールで送ってくれたクラスメートがいました。アメリカに来てから一番感激したかもしれません。。。
そのほかの出来事としては、
・FORM8843提出準備開始(結局、Fビザの学生は全員提出が必要との大学からの指示)
・OPT提出準備開始(卒業後の滞在資格確保)
・卒業写真撮影
・卒業用衣装手配
といったところを通常の学生生活に加えて実施していました。そのほかMPRE、NYBAR、プロボノといった諸要件についても少しずつ準備を始めています。
何かと忙しい春学期ですが、体調に気を付けて、各種準備を進めていきたいと思います。