
幼い子たちが、おもちゃ代わりにタブレット端末をいじっている。
東京新聞にワタシ的には、かなりショッキングな写真を見つけ、滅入ってしまいました。
ついに乳幼児まで・・・。
パパ・ママが、すでに中高生のころから、ケータイを使っていた世代になっているわけで、電子機器を与えることに、何の抵抗もないということだろうか。
記事では、(相変わらず)ソフト面からだけの注意もあるけど、機器の体に及ぼす影響は、まったくスルーされている。
(詳しくは、当ブログのカテゴリー電磁波・電磁波過敏症・化学物質過敏症をクリック。)
人類は、日本人は、大丈夫なのか。
<子どもとネット>幼児用アプリ注意点は? 子守に使わず親が一緒に
おもちゃ代わりに、スマートフォン(スマホ)やタブレット端末で子どもを遊ばせる親が増えている。知育やしつけ目的で活用するケースも多いが、子守の道具として安易に頼っている場合も。使わせる場合は、利用時間や目的などルールをしっかり決めたい。 (砂本紅年)
子どもの夏休み期間中、東京・有楽町で開かれた親子向けイベント。多くの家族連れでにぎわい、タブレット端末の体験コーナーにも子どもたちの行列ができた。ベビーカーの乳幼児も目立ち、母親らとともに、職業体験ゲームや絵本アプリなどを楽しんでいた。
「遊びながら何かを学んでもらえれば」。出展者の男性スタッフ(40)も男の子三人の父親。二歳の末っ子はタブレット端末で動画サイト「You Tube(ユーチューブ)」を見るのがお気に入り。上の二人も知育アプリやゲームでよく遊ぶ。特に渋滞中の車の中では欠かせないといい、「九歳の長男はぼくより検索が早いからびっくりします」
◇
ベネッセ教育総合研究所の今年三月の調べでは、乳幼児の母親の六、七割がスマホを所有。二十代では八割に達した。子どもにスマホを使わせる場面は、レストランや電車など、公共の場で静かにしてほしい待ち時間が多く、二、三歳児の親の二割以上が「週に三、四回」から「毎日」使わせていた。一方で、「目や健康に悪い」「夢中になりすぎる」「依存しないか」と心配する声も多かった。
◇ ◇
こうした現状に、ネット依存予防に取り組む情報教育アドバイザーの遠藤美季さん(52)は「使うなとは言わないが、親子の愛着関係に問題が起きるかもしれない、などのリスクを承知した上で、利用目的をはっきりさせた使い方を心掛けてほしい」と話す。幼児期から刺激のある映像に多く触れることで、将来の読書離れを懸念する専門家もいる。
一方、東京大大学院情報学環の山内祐平准教授(学習環境デザイン論)は「子どもに発達上の影響があるかないかは、議論や研究によって違う」と断った上で、「唯一明らかなのは、親子の会話が減ること。使うなら、創造性のあるアプリを選び、親が話し掛けながら一緒に使うことが大事だ」と指摘する。
「子どもの興味、関心を広げるために使ってほしい」と強調するのは、幼児対象の教育工学が専門の東海学院大・佐藤朝美専任講師。子守の代わりといった受け身の姿勢ではなく、「主体的、能動的なかかわり方が理想」という。しつけのために子どもを怖がらせるアプリもあるが、「あまりお勧めしない」。
佐藤さんは「そもそも、公共の場で子どもを静かにさせなければいけないという、ゆとりのない社会の方が問題。子どもを黙らせるためにスマホなどが使われるのは、日本の親が追い詰められているからではないか」とも話している。
◇ ◇ ◇
子どもにスマホやタブレット端末を使わせる場合は、制限機能を上手に使いたい。幼児向けアプリ開発会社「スマートエデュケーション」は、「長時間の使用」「意図しないネットへのアクセス」「勝手な課金」などの親の不安に対応する制限機能を盛り込んだ無料アプリを公開。利用時間やアプリ、動画、料金を制限できる。
おもちゃ代わりに、スマートフォン(スマホ)やタブレット端末で子どもを遊ばせる親が増えている。知育やしつけ目的で活用するケースも多いが、子守の道具として安易に頼っている場合も。使わせる場合は、利用時間や目的などルールをしっかり決めたい。 (砂本紅年)
子どもの夏休み期間中、東京・有楽町で開かれた親子向けイベント。多くの家族連れでにぎわい、タブレット端末の体験コーナーにも子どもたちの行列ができた。ベビーカーの乳幼児も目立ち、母親らとともに、職業体験ゲームや絵本アプリなどを楽しんでいた。
「遊びながら何かを学んでもらえれば」。出展者の男性スタッフ(40)も男の子三人の父親。二歳の末っ子はタブレット端末で動画サイト「You Tube(ユーチューブ)」を見るのがお気に入り。上の二人も知育アプリやゲームでよく遊ぶ。特に渋滞中の車の中では欠かせないといい、「九歳の長男はぼくより検索が早いからびっくりします」
◇
ベネッセ教育総合研究所の今年三月の調べでは、乳幼児の母親の六、七割がスマホを所有。二十代では八割に達した。子どもにスマホを使わせる場面は、レストランや電車など、公共の場で静かにしてほしい待ち時間が多く、二、三歳児の親の二割以上が「週に三、四回」から「毎日」使わせていた。一方で、「目や健康に悪い」「夢中になりすぎる」「依存しないか」と心配する声も多かった。
◇ ◇
こうした現状に、ネット依存予防に取り組む情報教育アドバイザーの遠藤美季さん(52)は「使うなとは言わないが、親子の愛着関係に問題が起きるかもしれない、などのリスクを承知した上で、利用目的をはっきりさせた使い方を心掛けてほしい」と話す。幼児期から刺激のある映像に多く触れることで、将来の読書離れを懸念する専門家もいる。
一方、東京大大学院情報学環の山内祐平准教授(学習環境デザイン論)は「子どもに発達上の影響があるかないかは、議論や研究によって違う」と断った上で、「唯一明らかなのは、親子の会話が減ること。使うなら、創造性のあるアプリを選び、親が話し掛けながら一緒に使うことが大事だ」と指摘する。
「子どもの興味、関心を広げるために使ってほしい」と強調するのは、幼児対象の教育工学が専門の東海学院大・佐藤朝美専任講師。子守の代わりといった受け身の姿勢ではなく、「主体的、能動的なかかわり方が理想」という。しつけのために子どもを怖がらせるアプリもあるが、「あまりお勧めしない」。
佐藤さんは「そもそも、公共の場で子どもを静かにさせなければいけないという、ゆとりのない社会の方が問題。子どもを黙らせるためにスマホなどが使われるのは、日本の親が追い詰められているからではないか」とも話している。
◇ ◇ ◇
子どもにスマホやタブレット端末を使わせる場合は、制限機能を上手に使いたい。幼児向けアプリ開発会社「スマートエデュケーション」は、「長時間の使用」「意図しないネットへのアクセス」「勝手な課金」などの親の不安に対応する制限機能を盛り込んだ無料アプリを公開。利用時間やアプリ、動画、料金を制限できる。
「子供用アプリ」で検索したら、やたら出てきた。

が、幸いなことには、- babycom ecology - というサイトに、子どもと電磁波の特集があったので、ブックマークに入れました。
不自然が跋扈した現代社会、子どもをそれらから守るのは、昔よりずっと大変だと思いますが、ケータイやスマホも無防備に子どもに持たせる前に、どうか下記のサイトや、子どもと携帯・ウィーン医師会の健康ルール10か条など、参考になさっていただきたいと心から思います。
 babycom ecology 電磁波特集
babycom ecology 電磁波特集子どもには、絵本がいいです。
公共の場で静かにできるように、小さな絵本をバッグに忍ばせてほしい。

宮崎さんの笑顔、いいなあ
宮崎駿さんは、「この世は生きるに値するんだ」ということを子ども達に伝えたかったと、引退記者会見で言われていました。私も同じことを思っていたので、とても嬉しかった。
宮崎さんの作品は、これからもずっと、子どもたちが大好きな映画であり続けるでしょうし、すぐれた絵本もまた同じ。
そういう絵本や作品は、時間を経過しても色褪せず、子どもたちが支持し続けているのです。本当にいいものは、変わらない。
それらに触れていると、親も癒されるし、体の細胞にも、悪影響はないし、むしろ、とてもよい。
なぜなら、トトロがそうであるように、長く子どもたちに愛され、残ってきたものは、人に元気なエネルギーを与えてくれるものに自然と淘汰されてゆくから。
絵本をたくさん読んでもらって、本好きになった人も多いのではないだろうか。
人は本を読むことで、自分とは違う立場や世界があることを知る。行間の向こうに、壮大なイメージが見えてきて、創造力という翼が羽ばたく。ストーリーを把握する力がつくことで、物事に対して、客観的、俯瞰的な視点を持つことができる。それはそのまま、その人の生きる力につながってゆく。
ネットの掲示板などのように、自分自分ばかりの人が増えて、自分とは違う他者へ思いを致すことが出来る人間が少なくなれば、現実の社会も殺伐としてしまう。
昔、テレビに子育てを任せるな、と言われていたけれど、スマホに子育てを任せるなら、成長期の心と体に与える影響がわからない今は、自分の子どもで人体実験しているのだという覚悟をしなければならないでしょう。
それから、余談ですが、作家の柳美里さんが、ブログにこんな記事を書いていましたよ。
携帯電話を解約しました。(柳美里の今日のできごと)
機器は次々新しいもの新しいものと変化していくのに、心は体は、ついていっているでしょうか。道具は使うものであり、使われるものじゃない。こういう決断をする人がいても不思議はないと思います。
★関連記事
根っこ・見えない部分を育てる


















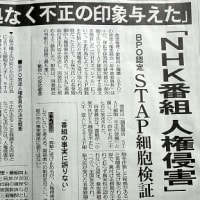






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます