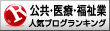こんなことができないか
訪問介護をプランに組み込んだ場合、私の立場から訪問介護をみると注意をしてほしいと思うことがある。一人暮らしの高齢者が多い、これから増える。いまでも数多くひとりで暮している高齢者がいる。そこへヘルパーが1人で介護で入る。さて、訪問介護の事業所さんとしては心配なことはないのでしょうか、たとえばお客様から何かされないか、怒られないか、トラブルは起きないか、などなど。そうした管理はどうしているのでしょうか、信頼関係でしょうか。事業所さんとしては信頼がおける人です、でいいのでしょうが、お客様に説明するときに事業所内で信頼されていますから、信頼できる人です、といって納得していただけるのでしょうか。
やはり労務管理です、では、どうするか、たとえば、ヘルパーさんの報告書に記載してある内容がいつも同じような内容となっていないか、使用している語彙が他のヘルパーさんに比べて少なくないか、記述項目が似通っていないか、こうした項目をみることでヘルパーさんの業務内容が推測することができるのでなないかと思います。
ヘルパーの労務管理を通して介護の向上がもたらせると期待しています。
サービス提供責任者さん、一度、考えてもらえませんか。
訪問介護をプランに組み込んだ場合、私の立場から訪問介護をみると注意をしてほしいと思うことがある。一人暮らしの高齢者が多い、これから増える。いまでも数多くひとりで暮している高齢者がいる。そこへヘルパーが1人で介護で入る。さて、訪問介護の事業所さんとしては心配なことはないのでしょうか、たとえばお客様から何かされないか、怒られないか、トラブルは起きないか、などなど。そうした管理はどうしているのでしょうか、信頼関係でしょうか。事業所さんとしては信頼がおける人です、でいいのでしょうが、お客様に説明するときに事業所内で信頼されていますから、信頼できる人です、といって納得していただけるのでしょうか。
やはり労務管理です、では、どうするか、たとえば、ヘルパーさんの報告書に記載してある内容がいつも同じような内容となっていないか、使用している語彙が他のヘルパーさんに比べて少なくないか、記述項目が似通っていないか、こうした項目をみることでヘルパーさんの業務内容が推測することができるのでなないかと思います。
ヘルパーの労務管理を通して介護の向上がもたらせると期待しています。
サービス提供責任者さん、一度、考えてもらえませんか。