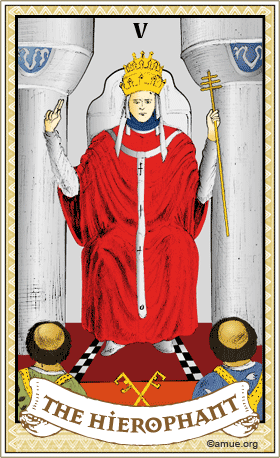ハードウェアの進化そのもの以上に注目したいのが、Apple Watchの役割が変化しつつあるということだ。もともとApple Watchは、iPhoneのコンパニオンデバイスとして誕生した。iPhoneの通知を腕で受けたり、より体に密着したデバイスとしてアクティビティーのログを取ったりするのが主な役割だ。それ自体は今でも変わっていないものの、新たに登場した「ファミリー共有設定」で、独立した携帯電話としての顔も持つようになった。ここでは、Apple Watchの進化の歩みを振り返りつつ、その意義やAppleの狙いを読み解いていきたい。
正統進化で機能を強化したSeries 6に加え、廉価版のSEが登場
Appleは、従来1モデルで展開していたApple Watchを2つに拡大し、価格や機能にバリエーションを持たせた。1つが初代Apple Watchの流れをくむ正統進化版のSeries 6、もう1つが初めての投入になる廉価モデルのSEだ。iPhoneの場合、SEは相対的にコンパクトで、かつリーズナブルな端末に付けられているが、Apple Watchでは価格にその特徴を反映させた。


金額は、Series 6が4万2800円からなのに対し、SEが2万9800円から。モバイルデータ通信が可能なセルラー版はその差がさらに大きくなり、Series 6が5万3800円からなのに対し、SEは3万4800円になる。
【訂正:2020年9月19日9時40分 初出時に「Series 3が5万3800円から」としていましたが、正しくは「Series 6が5万3800円から」です。おわびして訂正致します。】
Apple Watch Series 6は、新たに血中酸素ウェルネスセンサーを搭載し、血液中の酸素濃度を測定することが可能。“ウェルネス”と銘打たれているように医療目的には使えないものの、Apple Watchが得意としていたヘルスケア分野の機能をさらに強化した格好だ。形状はSeries 5とほぼ同じだが、常時表示ディスプレイが非アクティブ時に25%明るくなっていたり、Wi-Fiが5GHz帯に対応していたりと、ベースとなるハードウェアも着実に進化している。


対するApple Watch SEも、廉価モデルとはいえ、機能は充実している。ディスプレイサイズはSeries 4以降のApple Watchと同じで、サイズは40mmと44mmの展開。Series 5で導入された常時表示のディスプレイには非対応だが、加速度センサーやジャイロセンサーなどは備え、転倒検出は行える。チップセットは「S5デュアルコアSiP」で、ベースになっているのは2019年に登場したSeries 5とみていいだろう。そこから一部の機能をそぎ落としつつ、低価格を実現した格好だ。

Apple Watchは購入者の75%以上が新規の利用者で、スマートウォッチの中では圧倒的なシェアを誇るが、競合も徐々に増えている。調査会社カウンターポイント・テクノロジー・マーケット・リサーチが8月に発表した2020年第2四半期のシェアは、Appleが30%で1位だったが、2位のHuaweiは14%で、その差は徐々に縮まっている。トップシェアを維持しているうちに、より市場を広げておき、盤石の体制にしておきたいと考えても不思議ではない。
watchOS 7のファミリー共有設定で“独立した携帯電話”に
シェア拡大の上で鍵になるのが、watchOS 7のファミリー共有設定だ。廉価なApple Watch SEを投入した理由も、この機能と深くリンクしている。ファミリー共有設定を利用すると、iPhoneとは別の電話番号、別のApple IDでApple Watchを使うことが可能になる。一度設定してしまえば、あとはiPhoneなしで利用可能。これは、Apple Watchが1台の“独立した携帯電話”になることを意味する。

Appleが想定しているユースケースは、子どもや高齢者の見守りだ。GPSで子どもの居場所を調べ、いざというときには親と通話する――ジャンルで言えば、キャリアが投入してきた低年齢向けの見守り端末に近い。ドコモの「キッズケータイ」やauの「mamorino」、ソフトバンクの「キッズフォン」が、これに該当する。ただし携帯電話とは異なり、Apple Watchは腕に巻くことができるため、常時身に着けられる。ヘルスケア機能を備えているため、高齢者が自身の健康管理のために使いつつ、子どもが見守ることも可能だ。


Apple Watchの歴史をひもとくと、徐々に“iPhone離れ”を進めてきたことが分かる。まず、Series 3でeSIMを搭載し、iPhoneがない状態でも通話やデータ通信が可能になった。ただしwatchOS 6までは、あくまでiPhoneがそばにないときに単独で通信するための、補助的な通信機能と位置付けられていた。そのため、iPhoneとは同じ電話番号で運用する仕組みが採用されている。watchOS 7では、これに追加される形でファミリー共有設定が導入された。

iPhoneからの独立という観点では、watchOS 6でスタートしたApple Watch版のApp Storeも、その準備だったと考えることができる。それまでもwatchOSでは、iPhone経由でしかアプリをインストールできなかったが、watchOS版App Storeの登場によって、Apple Watch単体でそれが可能になった。iPhoneとひも付けて自分でApple Watchを使う分には、そこまで必要性は高くなかったものの、単体で機能するとなれば話は別だ。watchOS 6では「計算機」や「ボイスメモ」といった、スマートフォンにとっての必須機能も加わっており、単体で動作させることを意識していたことがうかがえる。

日本ではauがファミリー共有設定に対応、ただし料金には課題も
電話として運用する以上、ファミリー共有設定に対応するにはキャリアとの協力が不可欠になる。スペシャルイベントでは、世界各国で対応するキャリアの一覧が発表され、auの名前も挙がった。ドコモとソフトバンクは、ともに「現時点で決まったことはない」というため、まずは1社でのスタートになる。

Apple Watchの発表と同日、KDDIはファミリー共有設定に対応した「ウォッチナンバー」を発表。既存の「ナンバーシェア」から移行した際に受けられる割引キャンペーンも実施する。割引額は1年間1630円で、家族割プラスを適用すると、1GB以下の場合の料金は1年間350円になる。割引後の金額は、ナンバーシェアの350円に合わせた格好だ。KDDIはコンテンツサービスでAppleとの協業を深めており、こうした関係が素早い提供開始につながったという。
ただ、子どもや高齢の親に持たせるユースケースを考えると、不可解な点も残る。ウォッチナンバーの料金は「ピタットプラン 4G LTE」がベースになっており、2年契約時の料金は1GB以下で2980円。ナンバーシェアからの移行キャンペーンが終了してしまうと、この金額がフルにかかってしまう。設定用のiPhoneが必要になるため、少なくとも夫婦どちらかがau回線を持っていたとしても、家族割プラス適用で2480円からとまだまだ高く、見守り端末として持たせるにはためらう金額だ。

ファミリー共有設定は子どもや親に端末を渡すことが前提になっているため、キャンペーンがナンバーシェアからの移行というのも使い勝手が悪い。いったん、自分のApple Watch用に契約していたナンバーシェアからウォッチナンバーに移行しなければならず、改めてApple Watchのセルラー機能を使おうと思ったら、ナンバーシェアを再契約しなければならない。なぜ、専用の料金プランを用意しなかったのだろうか。
KDDIによると、スマートフォンと同じ料金設定になってしまったのは、総務省のガイドラインにのっとったためだという。ウォッチナンバーを契約したApple Watchは、いわゆる見守り端末とは異なり、電話に加えてインターネットへのアクセスもできる。先に述べたように、App Storeも用意されているため、超小型のスマートフォンと見なされる。同じスマートフォンである以上、キャンペーンを除いた正価を極端に変えることはまかりならんというわけだ。
確かに、iPhoneで使ったApple Musicの1GBと、Apple Watchで使ったApple Musicの1GBが異なる価格設定になっているのは、公平とはいえない。とはいえ、Apple Watch単体で利用できるデータ通信には限りもある。LTEはカテゴリー1でスマートフォンに比べると通信速度が遅く、テザリングもできなければ、ブラウザもメールなどに記載されたリンクからでないと起動しない。Apple Watchのような端末を見守り端末として普及させるには、こうしたユースケースを踏まえた適切な制度設計も必要になりそうだ。