実は別のブログをやっておりますが、特殊な領域で、自分の考えていることをつぶやくには少々窮屈になってきたので、
新しいブログを開設した方がいいかな、と思い、まずは試みとしてこちらのブログを利用させていただくことにしました。
記事の第一弾は既存のブログからのコピペ、です。
数週間前、ネットで、「ニューヨーカー (The New Yorker)」という雑誌に掲載された
マルグリット・デュラスの「バイブル」という短編の英訳に出会った。
短い小説だし、フランス語原文を英語に翻訳したものであるが、
乾いた簡潔な文体は、まるで英語教本に出てくるテキストのように読みやすい。
デュラス独特の人称や時制の自由変化もなく、
また抒情や感傷が入り込む余地もないほど、
あっさりした文章は、かえって読者との距離を置いて
感情移入を拒否しているようにも感じられる。
これは本当にデュラスの作品なのだろうか、
という疑問がわくほどであったが、
先日、ようやく手に入れたデュラスの『戦争ノート』という本の中に、
この短編が収められているのを発見して、
思わず、声をあげて感激してしまった。
この『戦争ノート』という本は、デュラスの死後に発見された
4冊のノートをまとめたものだが、
1943年から1949年までの間に書かれた
小説の原案や草稿である。
デュラスに関しての
素晴らしい資料でもあり、
また読み物としても手ごたえがある。
この本についてはまた別の機会にご紹介することにして、
きょうは『バイブル』という短編のみについて語ろう。
どんな話か、というと、パリで20歳の大学生の男性と、
靴屋の店員をしている18歳の女性が
ある晩、知り合い、付き合い始める。
彼はイスラム教やバイブルのことを彼女に話す。
二人はベッドを共にするが、彼はバイブルを彼女に読んで聞かせたり、
あらゆる聖書のことやイスラム教について、彼女に語ってきかせる。
彼女は神を信じてはいなかったが、彼を優しい人だ、と思い、
黙って、彼の話を聞いていた。しかし、彼女にとって彼は退屈だった、
という、他愛のないお話なのだが、
最後の部分を少々長いが、引用しよう。
彼は彼女に靴下を一足買ってやったことがあるが、
それが彼流のやさしさであった。
だが、二人がいっしょに寝るようになってから、
彼女に喜びがなくなっていった。(中略)
彼女の力すべて、生きてゆく若い喜びが、彼と接していると萎え衰え、
それをどうしたらいいのかわからなくなってくる。
それでも彼女は、ある意味でこれは幸運なのだと
気を奮いたたせ、彼といっしょのおかげでいろんなことを学んだ、と考えた。
だがそのいろんなことが、彼女になんの楽しみも与えてくれないのだ。
そんなことはとうに知っていたことだし、いまさら学ぶ必要なんか
たいしてありはしないのだ、という気がしてくる。
それでも彼女は、彼の気に入ろうと努め、
彼と会った晩、相手の要求どおりに福音書を読んだりした。
キリストが母親に言ったことが、彼女を泣きたくさせた。
彼があんなに若くして母親の目の前で、十字架にかけられたのは、
言語道断だ。だが、それは彼の落ち度ではない。
彼女はある種の感動から先へ行くことはできなかった。
彼女は、この男が神であるとは思えなかった。
非常に気高い計画をもっていたひとりの人間であり、
その死は彼にその人間性を返したのであり、彼女がキリストの物語を、
引退して一年目を迎えた去年、トロッコにひかれて
死んだ父親の死のことを考えずに
読むことができないのも、キリストの人間性のせいなのだ。
彼は、大昔に始まった、ある不正行為の犠牲となったのだ。
地上でこの不正がやんだことは一度もなく、
人間の幾世代を通して続けられてきた。
(『戦争ノート』マルグリット・デュラス 田中倫郎訳 P.396 - P.397)
ここにデュラスの宗教観がかいま見られる。
デュラスは無神論者ではない。むしろかなり宗教的な倫理観、
束縛があったように思われる。
訳者の田中倫郎氏の解説によれば、「デュラスがバイブルを
本格的に読むようになったのは
インドシナ半島を引き上げ、パリで大学生活を送るようになってから、
学生仲間のあるユダヤ人青年と親しくなり、彼から勧められて
バイブルを読むようになるのだが、
彼女は旧約聖書にすっかり心を奪われてしまう」という
経緯があった、という。
デュラスの最初の夫、ロべール・アンテルムはユダヤ人であった。
ロベールがドイツの強制収容所に入れられて、その後生還した話は
デュラスの『苦悩』という作品に詳しく描かれているが、
この『戦争ノート』には『苦悩』の原案となる草稿がいくつか載せられている。
デュラスは「内臓をえぐりとってやりたい」ほど
キリスト教会や聖職者を嫌悪しているが、
「私は信仰をもってはいない。ただ、イエス・キリストの
地上の存在を信じているだけよ」と言及している、という。
デュラスの宗教性について、田中氏は『苦悩』の解説でこう書いている。
デュラスは本質的には非常に宗教性の濃い作家であるが、
それはいわゆる聖観念とは無縁の宗教性である。
穢れに徹することこそ聖にいたる道なのだという
短絡的逆説も成り立たない。彼女の言う宗教性は、
人が人を裁くという悲劇が限界に達し、自分の意志で制御不可能な
「説明できないもの」に衝き動かされる所業が問題にされる時あらわれてくる。
目では捕捉不可能なその「説明できないもの」の
作動因を彼女は神と呼ぶ。
(『苦悩』 マルグリット・デュラス 田中倫郎訳 解説P.281 - P.282)
さて、田中氏の訳なのだが、誤訳ではないか、と思われる点を
一つ指摘しておきたい。
わたしが読んだのは英語版なので、フランス語の原文は
チェックしていないのだが、
英語版との違いを比較しておく。
(田中倫郎訳)
引退して一年目を迎えた去年、トロッコにひかれて
死んだ父親の死のことを考えずに
読むことができないのも、キリストの人間性のせいなのだ。
(ニューヨーカー、英語訳版)
彼女はこの話を自分自身の父親の死を思わずには読むことができない。
父親は前の年に、トロッコにひかれて死んだのである。
定年になる一年前のことであった。
(拙訳)
引退して一年目、というより
定年になる一年前、というほうが
悲劇性が増すのではないか。
この短編、英語訳からいつか自分なりに
翻訳してみたい、と思っている。
出典:THE NEW YORKER
THE BIBLE
By Marguerite Duras
December 25, 2006
『戦争ノート』 2006年
マルグリット・デュラス
田中倫郎訳
河出書房新社
日本語訳初版発行 2008年
『苦悩』 1985年
マルグリット・デュラス
田中倫郎訳
河出書房新社
日本語訳初版発行 1985年














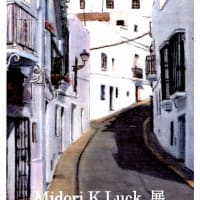





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます