暑いので、よほど用事がない限り、家にこもっているが、
やはり退屈でありますね。
こういうときには、暗いリビングのソファに寝転がって、
DVDの映画を見るのが一番のひまつぶしとなる。
英国アマゾンから取り寄せた、小津安二郎監督の映画を見る。
「東京物語」
「晩春」
「麦秋」
「戸田家の兄妹」
「一人息子」
「淑女は何を忘れたか」
「父ありき」
「秋日和」
「彼岸花」
「秋刀魚の味」
「おはよう」
以上が今までに観た小津映画の一覧表である。
その中で印象に残ったのは、「晩春」「麦秋」「東京物語」という、
原節子を起用した「紀子三部作」、
そして一番気に入ったのは「戸田家の兄妹」であった。
それらの映画の感想は、別のブログに書いたのだが、
コメントの中で実に興味深い、と思ったのは「晩春」に関してであった。
そのコメントによると、「晩春」の鎌倉の家には、仏像や神棚など、
「死」を暗示する小物が実にたくさん置かれていて、
この家が「呪われた死の家」であり、紀子は「巫女」存在であるから、
なかなかお嫁にいけないのだ、というのだ。
そして、紀子のお見合い相手として叔母が持ってくる縁談の相手の名前が
「熊太郎」といい、その叔母が鶴岡八幡宮で財布を
拾ったことで、縁談が決まったような経緯になって、この縁談の相手が
ことごとく貶められる、それによって、紀子は結婚しても
決して幸せになれないことを暗示しており、そんな娘の将来を案じて
父親は京都の宿で、娘に幸せになるように、としつこく
繰り返して言うのである、そして結婚式の様子も映像にはされず、
結婚式のあと、一人家に戻った父親の落胆は、この結婚が
不幸なものであることを象徴し、娘の不幸を嘆くがあまりに、
父親は首をたれるのだ、というような解釈である。
しかし仏教には「巫女」は出てこないはずだし、「巫女」の生きる神道では
死者は「黄泉の国」へ行ってしまって、「神」になってしまうのだから
成仏できずに生きているものたちの周りにしつこく付きまとうはずはないのである。
杉村春子演じる紀子の叔母は、ユーモラスな役柄で、財布を拾って縁起がいい、
と言い、紀子の将来の夫、熊太郎という人物を
「クーちゃん」と呼ぶことにした、など、日常を逸する
「ハレ」の人物として描かれている、とわたしは思ったのである。
亡き母の霊が現れ出でて、嫉妬を見せるようにみえる能楽堂の能鑑賞の場面も
京都の旅館での紀子の表情の変化や
「お父さんのそばにいさせて、お父さんが好きなの」と、
まるで愛の告白のようにさえ思えるきわどいシーンも、穏やかな
父親の説得で、スーッと消滅し、紀子は我にかえる。
ここに小津監督の仕掛けたツボがあるのだ、とわたしは思う。
映画を見るものをハラハラさせながら、このお話は父親と娘が
お互いに思いやり、相手の腹をさぐり、疑心暗鬼に陥りながらも、
結局は娘が結婚する、という幸せのために
孤独になる父親の心理を描いているのだ、と。
おどろおどろしい神がかった呪いのようなものを感じる、という
その人のコメントに、そういう見方もあるのか、と驚いたが、
映画でも小説でも結局は見る側、読む側の心理や人生観によって、
これほど感じ方が変わる、と言うことなのであろう。
しかし、そういう見方もあるのか、と思って「麦秋」を顧みてみると、
これまた不思議なお話である。
まさに幸福を絵に描いたような家族の一員、紀子という晩婚の独身貴族が、
近所の子持ちの男やもめの嫁さんになることを示唆され、
それを承諾することによって、一家が散り散りになっていく。
映画の冒頭で、年老いた父の兄が、奈良の大和から東京へ出てくるお話がある。
その兄は耳が遠いので、一家の子供たちが馬鹿にしたりするのだが、
そういうこともすべてわかってニヤニヤしているような鷹揚な翁なのだ。
歌舞伎鑑賞をする場面では歌舞伎の舞台は画面に出てこない。
セリフ回しだけが聞こえ、花道に近い桟敷席でそれを聞いている
翁の顔が大写しになる。
そして、だれもいない歌舞伎座の光景…。実に不思議である。
「大和においで、大和は国のまほろば」と言って、父の兄は奈良に戻っていく。
映画の最後では、老夫婦が長男一家に鎌倉の家を空け渡し、
大和の長兄の家にいる場面がある。
あたりは一面の麦畑。刈入れ間近な黄金の海の中を、花嫁行列が通っていく。
「どこに片付いていくんでしょう、紀子は幸せかしら」
「そうだね、でも私たちはいいほうだよ」「そうですね、幸せでしたね」と
いうような会話が囲炉裏を囲む老夫婦のあいだでかわされるのだが、
二人の向こうでは長兄がゆったりとくつろいで座って
無言でキセルをふかしている。
もう一つ、時間が前後して少し前の場面になるが、鳥のえさを買いに行く、と言って
家を出た老父が踏切を渡ろうとすると遮断機がおりてしまう。
電車が通過するのを待っている間、
どんな思いが彼の胸に去来したのであろうか、
遮断機があがっても、彼は路傍の石に腰かけたまま、動こうとしないのである。
もうこれ以上、今の生活を続けるのはやめよう、大和に戻ろう、と決心したことが、
映画の最後になってわかる、という示唆的な一場面である。
この「麦秋」では一家の次男昌二が南方へ出征して戻ってこない設定である。
昌二の同級生であった近所の男やもめは、
昌二から届いた最後の手紙には麦の穂が同封されていた、と紀子につげる。
「そのころ僕は『麦と兵隊』という小説を読んでいたんだ」、と。
最後の麦畑の場面は、まるでこの世からあの世へ、と初夏の風にいざなわれて
渡っていくような哀愁が漂っている。
この年老いた父母は、子育てが終わり、現世のごたごたを乗り越え、
戦争から戻ってこなかった次男への思いを残しながら、家族とは離れて
彼岸へと達していく、そのような境地を描いているようにもおもえるのである。














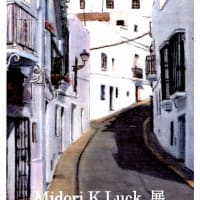





例えば、婚期というシリアスな題材などをユーモアとペーソスと無常の人生観で見つめている普遍さが、ホームドラマで世界の金字塔(ベストシネマ)となった理由でしょうか。
『麦秋』でのラスト・シーンは、たしかに『ひまわり』の一場面のように、戦死したあまたの兵士たちの静かなためいきのように思われますね。
小津映画が古さを感じさせないのは、人間の根幹にある感情をさりげなくきわだたせながらも、感傷におちいることなくユーモア漂う日常の光景に置き換えていることだと思います。