
『神々と男たち』
原題: DES HOMMES ET DES DIEUX
2010年フランス映画
監督 グザヴィエ・ボーヴォワ
以下、DVDの解説を引用。
1990年代のアルジェリア。フランス人修道士たちが
現地のイスラム教徒と宗派を
超えて交流していた。互いの尊敬と慈愛に満ちた、
静かで平和な日々。しかし
アルジェリア軍とイスラム原理主義者による内戦は
激化の一途をたどり、
暴力の波が僧院の周辺まで迫ってきていた。
政府の警告通り、遂に
武装集団が彼らを狙いはじめる。
周辺住民たちにとって、修道院が最後の
頼みの綱。彼らを見捨ててこの地を去るか、
死を覚悟して留まるか―――
苦悩しながらも修道士たちが下した決断とは・・・?
現地のイスラム教徒と宗派を
超えて交流していた。互いの尊敬と慈愛に満ちた、
静かで平和な日々。しかし
アルジェリア軍とイスラム原理主義者による内戦は
激化の一途をたどり、
暴力の波が僧院の周辺まで迫ってきていた。
政府の警告通り、遂に
武装集団が彼らを狙いはじめる。
周辺住民たちにとって、修道院が最後の
頼みの綱。彼らを見捨ててこの地を去るか、
死を覚悟して留まるか―――
苦悩しながらも修道士たちが下した決断とは・・・?
この映画は1996年にアルジェリアで実際に起きたイスラム原理主義者による
フランス人修道士誘拐・殺害事件をもとにして制作された、という。
アルジェリアのアトラス修道院ではトラピスト修道士たち、8人が畑を耕し、
養蜂ではちみつをとり町の市場で売って小銭をかせぎ、祈りと労働の日々を
送っていた。修道士たちは村の住民たちの治療も修道院内の小さな診療所で
行い、また村人たちのさまざまな相談にものって、慕われていた。
しかし、バスの中でスカーフをしていなかった女性が殺されたり
クロアチア人たちが惨殺されたりして、テロリストたちの蛮行がひどくなっていく。
修道士たちはそのような残虐行為にもなぜ神は沈黙しているのか、と問う。
クリスマスの夜、医者が要る、といって、テロリスト集団が修道院に押し入ってきた。
修道院長のクリスチャンはアラビア語にもたけているし、イスラム文化にも
造詣が深い。集団のリーダーに、コーランを知っているか、と話しかける。
「信仰者に一番親愛の情を抱くのはキリスト教徒たちである。それは彼らの間には
司祭と修道士がいて彼らは高慢でないためである・・・」
リーダーは、われわれは隣人だ、と言い、クリスチャンに握手を求めて、去っていく。
彼はフャヤティヤという名の男で、イスラム過激派として知られていたが、
修道院には敬意を払ってくれるようになった。
負傷したテロリストが修道院に運ばれてきても、黙って治療する修道士たち
であったが、やはりテロリストの味方をしている、とアルジェリア政府に
思われることは得策ではない。
しのびよる危険に、修道士たちは会議を開いて、出発するか、残るか、相談する。
生きるために修道士になった。殉教するつもりはない、という人もいる。
発つことは逃げることだ、村人たちを見捨てるわけにはいかない、
よき羊飼いはオオカミが来ても羊を見捨てることはない、という修道士もいる。
とどまるか、発つべきか、意見はバラバラだったが、
院長のクリスチャンは、結論を下すにはまだ時期尚早、ということで
様子をみることにする。
仏蘭西内務省から、修道士たちの帰国命令が下される。
「アルジェリアの紛争はフランス植民地政策、組織的略奪のせいだ、
帰国せよ」と政府関係者から言われても、修道士たちは決心がつかない。
紛争は激化の一途をたどり、テロリスト集団のリーダー、
ファヤティアも政府軍につかまって惨殺されてしまう。
悩む修道士たち。
村の住民たちとも話し合う。
鳥がいつ枝から発つか、それは鳥の自由だ、という修道士に、
村のある女性が言う。「鳥はわたしたちよ、あなた方は枝。枝がなくなったら
鳥はどこに止まればいいの?」
平和だった村にさえ、過激派の虐殺行為はおよんで、村人たちも
ストレスで高血圧などの症状が出ている。
「フランスに帰っても、向こうにわたしの人生はない」
「野の花は光を追って動くことはない。神は花のあるところで
受粉してくださる」
修道士の会議では、こんな言葉が発せられ、8人全員、残るほうに手をあげる。
クリスチャン院長の言葉。
キリストは私たちをどこへ導いているのか。
人は生まれて、また生まれる。
受肉とはイエスの神の子としての現実を、人の中に受けることだ。
その神秘は、私たちが生きることにある。今まで生きてきたこと、そして
さらに生き続ける、ということだ。
修道院に、もう一人の修道士が到着する。彼は手紙や薬や
聖体拝受用のパンなども携えてきた。
そしてワインも。
9人の修道士たちの夕食の席では、いつもの祈りの言葉の代わりに
音楽がかけられる。それはチャイコフスキーの「白鳥の湖」。
ワインのボトル二本が開けられ、修道士たちは音楽をききながら
沈黙のうちにグラスを傾ける。
院長のほほに涙がこぼれる。
静かにほほ笑む修道士もいる。
その夕食は最後の晩餐となってしまった。
夜半、いきなり武装イスラム集団が修道院に押し入り、
7人を拉致して去ってしまう。
運よくまぬがれたのは二人だけであった。
政府に拘留されているテロリストの仲間たちと
ひきかえのため、人質となった7人の修道士たちが、
雪の中を連行されて歩いていくシーンで、映画は終わる。
最後には、7人の消息が、文字でスクリーンに現れる。
1996年5月21日、殺害された、と。
修道院内の質素で静かで平和な世界と、
外の内戦の様子が対照的である。
修道士たちは、祈りの言葉をグレグリオ聖歌で唄う。
数か国語に長け、アルジェリア、そしてイスラム世界を
愛する院長のクリスチャンの悩み、彼が死を覚悟して
したためた手紙の一部が映画の最後で朗読される。
彼ら修道士たちが、フランス本国へ帰らなかった理由は
それぞれだろう。しかし、この修道院が、彼らの人生であり、
生活であったことは確かだ。殉教、などという大それた意識はない。
みな、死は恐ろしい、でもそれを覚悟し、恐怖に耐える。
修道院長のクリスチャンの苦悩、
そして医者でもある高齢の修道士の、人生を達観したような
表情、そして言葉が心にしみる映画である。
さて、題名の『神々と男たち』
一神教であるのに、なぜ「神々」か。
この映画の冒頭で、スクリーンには旧約聖書の一節が
引用されている。
わたしは言った。「おまえたちは神々だ。
おまえたちはみな、いと高き方の子らだ。
にもかかわらず、おまえたちは、人のように死に、
君主たちのひとりのように倒れよう。」
詩編82:6,7
おまえたちはみな、いと高き方の子らだ。
にもかかわらず、おまえたちは、人のように死に、
君主たちのひとりのように倒れよう。」
詩編82:6,7
神々、という言葉、そして映画の中でクリスチャンがつぶやく
キリストの受肉、の解釈。
神の子として人のように死に、キリストになる、ということ。
つまり院長が言っていた、受肉、なのだろう。
だから「神々」なのである。
フランス語の原題は DES HOMMES ET DES DIEUX。
HOMMES、には男たち、と言う意味もあれば、人間たち、と言う意味もある。
つまり、「人間たちの、そして神たちの」という意味である。
カトリックの国、フランスでは、このようなタイトルや
修道士たちの言葉は、映画を見る人に深い感動をもたらすのだろう、
と、つくづく思った映画である。
実話の殉教した7人の修道士たちの肖像画

この記事は、わたしのもう一つのブログの記事をコピペしたものです。
http://blogs.yahoo.co.jp/maximthecat/33057370.html










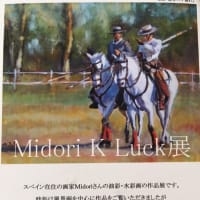

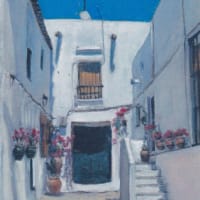

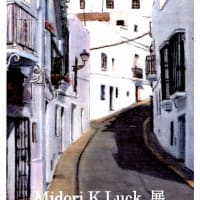



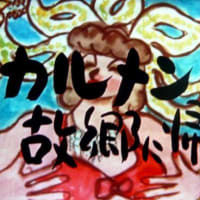

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます