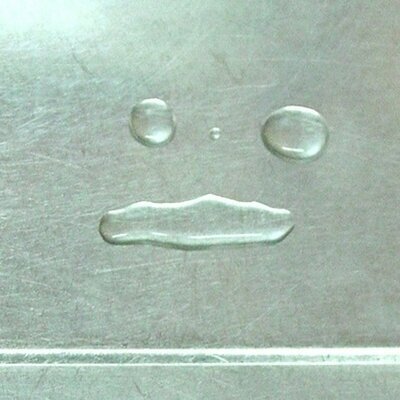伊勢神宮へ行った。その4(おかげ横丁) よりつづく

おかげ横丁からバス停のあるロータリーに戻り、宇治橋の方へ歩く。
鳥居が立派だ。五十鈴川を渡るのだ。

木除杭が見える。杭のてっぺんにいちいち小さな屋根がのっている。

橋を渡って右に曲がり道なりに歩いてゆくと、五十鈴川に下りてゆく。御手洗場(みたらし)というらしい。

風日祈宮橋。向こうに風日祈宮(かざひのみのみや)がある。

内宮の木も大きい。

風日祈宮橋で振り返る。木陰が濃い。

伊勢神宮へ行った。その6(内宮その2) へつづく

おかげ横丁からバス停のあるロータリーに戻り、宇治橋の方へ歩く。
鳥居が立派だ。五十鈴川を渡るのだ。

木除杭が見える。杭のてっぺんにいちいち小さな屋根がのっている。

橋を渡って右に曲がり道なりに歩いてゆくと、五十鈴川に下りてゆく。御手洗場(みたらし)というらしい。

風日祈宮橋。向こうに風日祈宮(かざひのみのみや)がある。

内宮の木も大きい。

風日祈宮橋で振り返る。木陰が濃い。

伊勢神宮へ行った。その6(内宮その2) へつづく