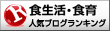◎高齢者の食事 Meal of elderly こうれいしゃのしょくじ
全体人口のなかで65歳以上の人口が7%を超えた社会を高齢化社会と呼び14%を超えると高齢社会、21%を超えると「超高齢社会」 と国連で定めています。日本は1970年に7%を超えその後1994年には早くも14%を超えて高齢社会の仲間いりをしました。 2007年現在で100歳以上は3万人、2018で7万人にも達し、65歳以上が2018年(平成30年)に28.1%に達しています。
厚生労働省は9月15日、全国の100歳以上の高齢者が同日時点で8万450人に上り、初めて8万人を超えたと発表していました。昨年より9176人多く、50年連続で過去最多を更新。女性が7万975人(88.2%)を占めた。統計を取り始めた1963年には全国で153人でしたが、1981年に1000人、1998年に1万人を突破、2012年には5万人を超えました。
高齢者人口は、2020年まで増加しその後は、横ばい状態が続きます。しかし総人口が減少に転じるとされ高齢者の割合(高齢化率)は上昇していくといいます。昭和25年(1950年)の総人口に占める割合が4.9%、1985年(s60年)10.3%、2015年には、3,277万人(26%)、2050年には35,868万人(35.7%)と上昇していくと見込まれてます。
中高年になって近年では、メタボリックシンドロームという言葉も聞かれ高脂血症(脂質異常症)、肥満症、動脈硬化症、高血圧症、糖尿病、がんなどの疾患が増えてきます。1955年~1980年ごろまでは、脳血管疾患、脳卒中が死因の第一位でしたがその後は、悪性新生物・ガンが首位の座を保っています。戦前、戦後の食生活事情の良くなかった時期、たんぱく質の少ない食事で血管の弾力が弱く脳卒中の発症が考えられ、戦前は食塩を20~30gも摂取していたともいわれ脳いっ血、高血圧症が多発していました。野菜はNaを排出させてくれるカリウム(K)を多くとることができます。Na(ナトリウム):K(カリウム)=2:1(一日の摂取量)以下がよいとしています。
最近ではたんぱく質の摂取は満たされ、むしろ多めであり、肥満などにより過剰摂取による栄養バランスの乱れ、加工食品からの食品添加物の摂取がガンの発症に関(かか)わっているものと思われます。
日頃からの運動、休養、栄養のバランスが大切なわけですが、高齢者では長年の習慣もありそのことを十分に考慮されなければなりません。千差万別といえます。 いまや認知症(痴呆)老人は100万人以上に達し、85歳以上では女性30%、男性22%に痴呆症状があるといわれています。原因として脳の血管が詰まったり破れたりする血管性痴呆、老化により脳が萎縮して発病するアルツハイマー型認知症とで9割をしめるとも言われます。そのほかでは現時点で治療可能な慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症等がありますが、大きな社会問題でもあります。
最近まで医療機関の栄養管理に対する認識はとても低い状態でした。糖尿病治療に食事療法は必要なく、薬物療法でよいという考えをもつ専門家まで現れ、いわれたこともあります。病院で栄養状態を知る指数としてアルブミン値3.0g/dl以下、リンパ球数800/μl以下、BMI18.5以下などがあげられ病院によっては入院患者数の約4割に低栄養(PEM:Protein Energy Malnutrition)状態が見られるといいます。
私達は、できるだけ美しく、健康で元気に生涯を送れることを願っています。70歳以上の方の食生活状況は国民健康栄養調査からカルシュウムが少し不足している程度で平均栄養摂取状況は良好です。
戦前から終戦後の日本の食生活を調査、研究された近藤正二先生の記録があります。まだ地域の特徴ある食生活が残っていて片寄った食事と病気、寿命についてまとめておられます。今日の食生活の栄養に関する情報は、即刻日本、いや世界各国に一斉に伝達される時代です。 平均的には満たされてはいるわけですが、個々にはどうであるのか、自分自身は、果たして満足の行く食生活を送っているか振り返って見てみる必要があります。問題なのは、平均ではなくて自分自身のことなのですから。ここではあくまでも平均でしかお話できませんのでご了承ください。
今まで一生懸命仕事をしてこられ一段落しホットはするものの徐々に孤独で単調になりがちです。 幸いに日本は、四季があり、それぞれに旬の食材が、季節ごとに行事があります。
忘れかけていた懐かしい郷土の行事食などを盛り込みメリハリをつけましょう(おせち:正月 豆まき(食べるなら甘納豆、卵ボーロ):節分 散らし寿司:桃の節句 ぼたもち・おはぎ:彼岸(春・秋) お重弁当:お花見 柏餅:端午の節句 ソウメン:七夕 団子:月見団子等) 筋力の衰えが見られますが、70歳代ぐらいまでは脂肪が増えてくる傾向が見られます。肥満は、要注意です。
基礎代謝の低下によって、適応能力が緩慢になり元の状態に戻るのに時間が掛かり疲れが取れにくいことがあります。サルコペニアSarcopenia(筋減弱症)は、進行性および全身性の骨格筋量および骨格筋力の低下がみられる症候群です。筋肉Sarco量の低下・喪失peniaにより、筋力または身体能力の低下のいずれかが当てはまればサルコペニアと診断しています。適度に身体を動かし無理のない規則正しい生活を送ることが大切です。暴飲暴食もいけませんね。
最近ではよく噛むということも脳への刺激が伝わりボケ予防効果があることが分かっています。私の母は、入れ歯でしたがそれでたくわんを「ぼりぼり」食べていました。歯ぐきも年とともに衰えるといいます。かみ合わせのあった入れ歯をすることがとても重要です。入れ歯の状態により、もち、せんべい、ガム、キャラメル、イカ、タコ、たくわん、豆類、牛蒡、胡麻、とうもろこしが食べにくい食材としてあげられます。胃腸も胃酸の分泌も少なくなってきているのでよく噛むことは脳を刺激して胃腸への負担を軽くします。噛む力は、体重と同じぐらいといいます。
腸の働きが弱くなって便秘しがちになります。年ともに腸内の細菌の種類が腐敗菌、悪玉菌と言われるピロリ菌などが増えてきます。よくヨーグルトの乳酸菌がピロリ菌をやっつけてくれるといわれています。便秘を防ぐのに野菜をよく噛んで取るのもいいですが30品目を目標にバランスの取れた食事が大切です。多少の脂肪も便通をよくするのに役立ちます。規則正しい排便の習慣をつけ、充分な水分の補給も一日あたり1.5~2L、脱水症状を起こしやすいこともあり必要です。なかなか手が掛けられないときには、離乳食用の缶詰、低栄養状態の改善にMCT(Medium Chain Triglyceride:中鎖脂肪酸)を利用するのもよいでしょう。
女性は閉経後は女性ホルモンの分泌が衰え骨折しやすくいわゆる骨粗鬆症になりやすくなってきます。カルシュウム(乳・乳製品等)を取ることが欠かせないですが、高齢者には、牛乳を飲むと下痢しやすい、お腹がごろごろするなどの乳糖不耐症が多く見受けられます。牛乳の他にカルシウムを多く含む食品としてヨーグルト、ごま(15gで180mg含まれ蜂蜜と混ぜペーストにしてトーストに塗るとよい。)骨ごと食べられる鯖缶、鮭缶、いわし缶の水煮缶、小魚、吸収をよくしてくれるマグネシュウムも比較的多く含まれて、カルシウムも一緒に取れる貝類のかき、納豆などがあります。
薬の服用(ある種の血圧降下剤・抗生物質等)、老化により味覚障害を起こしていることもありますので味付けは濃くしがちになりますので注意しましょう。 特に孤独になりがちで精神的ストレスが食欲、病気の引き金にも影響を浮けやすくなります。特に男性は 普段から家事、地域との関わりを持つことが求められます。特に日常的に必要とされる3度の食事、料理作りは脳の活性化、働かせるのに最も大切な役割を果たします。献立の組み合わせ、必要な材料の買出し、調理、きれいな盛り付けをすることによって認知症の予防、改善につながります。特に男性は積極的に参加するようにしましょう。無理のないようにやれる範囲でいいのです。
n-3系脂肪酸(EPA,DHAなど)と植物に多い抗酸化成分(ポリフエノール類)を摂取することは、認知症のリスクを減少させると考えられています。さらに比較的軽症の認知症にビタミンが有効との発表がイギリスのBBCニュースで2010年9月8日に報じています。イギリスのオックスホード大学教授のデビットスミス博士によって調べられています。比較的症状が軽い認知障害の高齢者168人を2つのグループに分け、1つのグループにのみ葉酸とビタミンB6、ビタミンB12を組み合わせたビタミンB群を2年間投与し実験しました。 ビタミンB群を投与されたグループはもう一つのグループと比べ、認知症の原因となる脳収縮速度が平均で30%も遅れていることが分かりました。ビタミンB群が認知症予防に役立つ事が判明しています。ビタミンB6,B12と葉酸は、ホモシステインの値が高いと血栓などにより認知症を引き起こしますが、その数値を抑制します。
さらに認知症に抗酸化力のあるビタミンE、ビタミンC、神経伝達物質のアセチルコリン、血流をよくするEPA,DHAが記憶力減退を軽減させます。 食事量の配分は、3.4.3とし夕食は就寝2時間前には終えるようにして身体全体を休ましてあげましょう。
近年、100歳を越える長寿の増加が著しく喜ばしいことでありますが、その反面寝たきりになってしまったり、普通の食事を食べられなくなってきている人の増加が社会問題化しております。高齢化とともに消化と吸収力の衰えがみられ、さらに嚥下障害(食物が飲み込みにくくなる)、誤嚥(誤飲:食べ物、飲み物が誤って気管、肺の方へ飲み込まれてしまう)起こす人の割合が増えて肺炎を起こしやすく、摂取不足にもつながり低栄養(PEM:Protein Energy Malnutrition)、脱水状態に陥りやすくなります。調理の工夫が必要です。
ここで少し嚥下(えんげ、えんか)障害の食事について触れておきます。
嚥下障害の食事 栄養補給が第一の目的になりますから喉ごしがよく、柔らかく、そして少しでも食欲をそそるような見た目にも配慮しましょう。喫食される方の体調により刻んで、つぶして、マッシュ状に、とろとろにして差し上げましょう。いたみやすいですので作り置きは厳禁です。調理盛りつけしたら直ぐに食べてしまう方がよいです。
ゼリー状 材料をフードプロセッサーにかけたり、下ろし金ですりおろしたりしたものに片栗粉でむせないようとろみを付けたり、ゼリーでプリンのように形を作って固めましょう。食品として一般のスーパーに置いてある細かく刻んだ納豆昆布を水、お湯で溶いて食材と一緒に混ぜるのもいいです。時間がたってもとろみがなくなりません。
市販のものでとろみ調整食品の藻類、豆科植物より抽出された増粘多糖類(アルギン酸、カラギナン、グァーガムなど)、でん粉の混合されたものもあります。このときの状態は、かたすぎると飲み込めなく食道をふさぐことになり、柔らかすぎると気管に入って思わぬ事故につながります。
主食・・・・・体調により人肌ぐらいの暖かさでスプーンで一匙一匙少しづつ様子を見ながらおかゆ、パンがゆ、くず湯、とろとろうどん(そばがきより少しとろとろにして)にします。餅の類で、よくノドに詰まらせる事故が、お正月に多く発生しています。噛み切りにくいもち米100%のものでなく、白玉粉と上新粉を混ぜ合わせた餅とすると噛み切りやすくノド越しもよいようです。上新粉を混ぜることによって噛み切りやすく、水、上新粉の分量の加減で堅さを調節しましょう。
汁物・・・・・片栗粉、増粘多糖類でとろみをつけます。市販のとろみ食用のもので時間が経つと必要以上に固まりやすいのがありますので注意してください。
副食(魚・肉・野菜・果物)・・・・・加熱した物をフードプロセッサーにかけ片栗粉、増粘多糖類でとろみをつけたり、ゼリーで固めます。果物でジュースにして飲み込みが悪いときにはゼリーにした方がよいでしょう。夏場は特に衛生管理に注意しましょう。
副食(豆腐・卵・ヨーグルト・芋類)・・・・・できるだけ形在るようにして差し上げたいですから、茶碗蒸し程度の柔らかさでしたら一匙づつすくって少しづつ食べられるようにします。
*注 挽肉・刻んだ凍み豆腐は、むせやすいですのでフードプロセッサーで滑らかにして差し上げた方が食べやすいでしょう。喉(のど)にへばりついたりして詰まらせる物(餅・ワカメ・のり・こんにゃく・マシュマロ・ウエハウス)の摂取は特に注意が必要ですし、とろとろにしてから差し上げた方がよいでしょう。圧力鍋、缶詰、離乳食の利用の利用もよく、近年では、溶けないアイスクリームまで登場です。
家庭・家族だけでは、介護されることも、介護することもお互いのQOL(Quality Of Life:生活の質、人生の質)を高め、向上させることにつなげていくのに模索し続けることは大変大きな負担が強いられています。介護保険が使えるようになりましたので、何にも遠慮することなく女性への比重の重い現代社会において生活に積極的に取り入れていきましょう。
最近は、単身生活の高齢者が増加傾向にあり、容器の包装にもう少し配慮があってもいいのではないかと感じられます。開けられない牛乳、ヨーグルトパック、ビン詰め、缶詰め、茹で麺類のはさみの入れどころのない包装等開封のしやすさに配慮があってもいいのではないかと思われます。
焼き海苔のチャックつきのものはあまり見かけません。湿気やすく袋が空いたままでは食味を悪くします。レタスの包み紙は一度開くと閉じることができません。袋入りにしてもらえたら助かります。小瓶に入った市販薬の蓋が機械締めされているのでしょか。普通の人でも開けるのに苦労し、閉口します。不要の調味料が一食ずつに納豆、麺類に、刺身に付く醤油、わさび類があります。ゴミとして処分しきれず、利用しますが開封に手間がかかり、調味料の常備はしているのでから一食ごとに付けるのは捨てるのに忍びないですから、付けないでほしいです。ビスケット類が、個別に、そしてそれをまとめての包装で、その中身は1/3、キラキラの中身の見えない袋に入っています。手で触ってみないと量が分からないし、実際のどんなビスケット類なのか見ることができません。一昔前は、おみやげの過剰包装が問題になっていましたが、最近ではリサイクルできると称してか、刺身、魚の切り身が立派なかさばる容器に詰められ見た目よろしく並べられています。
報道で、少し見られたのが、過剰包装のトレイをスパー内で処分しゴミ箱に捨てて行って様子で、スパー側では困っているということです。製造者、販売者の、もっと優しい配慮が必要と思います。 宅配の過剰包装、かさばる容器の代金、廃棄に消費者は苦慮しています。カップ麺のやたらと多い子袋では、お湯を注いで3分で食べられず、手間暇がかかり、疲れていたり、忙しい時のためのものが、そうでなくなってきている傾向です。生産者、製造者と消費者の利便性がかけ離れ、この辺のコミニュケーションに欠けているようです。半調理された水煮のパック詰めは重量がありますので真空パックにしたら助かります。
製造者自身がスーパーで購入したものを開封・盛り付け、ゴミだしする消費者となって実際に利用してから多くの消費者に届けて頂けることを切に願います。 冷凍のほうれん草、枝豆、コーンなどが以前からありましたが、近頃では、マンゴー、ブルベリーのすぐに食べやすいように皮をむいてカットした冷凍品があったりしてゴミの軽減化にもなり少しずつ便利にもなってきました。
高齢になっても体調に細心の注意を払いながらもできるかぎり多少なりとも体を動かす(運動)ようにして栄養、休養とのバランスをはかるよう努めることが求められます。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
(初版2020.9.21)