日露戦争で日本軍が大きな被害を受けたものの一つがロシア軍の装備する機関銃である。
当時のロシア軍が装備したのはマキシム系のM1905で、
この機関銃に関しては先日紹介した「現代文 肉弾」の155ページから
「さて機関砲であるが、これぞ実にわれらの最も恐るべき火器であった。」という一文から始まり、
1ページ半を割いてこの機関銃がいかに脅威であったかについて書かれている。
日露戦争より後にM1905を改良して第一大戦・第二次大戦に投入されたのがこのM1910。
M1910 Maxim Heavy Machine Gun
「肉弾」の記述を見るに桜井氏の目にしたM1905にはM1910同様、防楯つきのソコロフ銃架が装着されていたことが分かる。
ちなみに動画のM1910は大型の水投入口がバレルジャケットについた後期型で、
ベルトもかなり後の時代の金属製の物が使われているが、
第2次大戦初期まではキャンバス地(要は布製)のものが使われていた。
マキシム機関銃はイギリス人発明家、ハイラル・マキシムの発明した機関銃で、
反動利用により500発毎分以上の連射能力を持つ。
それまでの(信頼性に欠ける)ものと異なり、高い信頼性を持つマキシム機関銃は世界各国で採用されることになるが、
ドイツのように「毎分500発以上」という売り文句に疑問を持ち、
不審人物として国外に出て行くまで監視を付けた例もあった。
マキシム機関銃の性能は各国の植民地における戦闘などに投入され、
名前を知られるようになったが、
その名声を決定づけたものは日露戦争でロシア軍が投入したそれであり、
ドイツ(プロシア)においては観戦将校がその威力を目の当たりにして本国に報告、
採用に至ったとされている。
当時は近代的機関銃の黎明期であり、各国とも運用・運搬方法(大型の台車に載せて輓曳したりしていた)などに試行錯誤していた。
これはそれまでとは軽量になったとはいえ、銃本体で25キロ以上、大型の脚を含むと50キロを優に超えるという点も影響していた。
小銃と異なり圧倒的に多くの弾薬を同時に運搬する必要があり、銃身冷却用の水まで必要とされていることも関係した。
既に書いたが、採用当初は各国とも布製の弾薬ベルトを使用したが、これは新品だと硬くて動作不良を起こし、
扱いが悪いと弾薬がズレて同じく動作不良を起こす欠点があったが、
第2次大戦後期には分離式の金属製ベルトリンクが登場した。
この点はマキシムに限らず、ブローニング系機関銃も同じである。
各国の状況を見てみよう。
・ロシア
既に書いたが鋼鉄製で車輪と防楯のついたソコロフ銃架と組み合わせて第2次世界大戦でも大量に使用された。
・ドイツ
ドイツ帝国・プロイセン時代の1908年にMG08として採用。
運搬を容易にするため、橇式の銃架に載せられた。
German MG08 Maxim
しかし、重いので機動性はあまり変わらなかったようである。
(革製のベルトを使って数人で引っ張る)。
銃口のあたりにある丸い円盤はマズルブースター(発射速度を向上させる)から出る発砲炎を隠すもので、
先端の細長い漏斗状の物はフラッシュハイダー。
機動性に明らかに劣るのでピストルグリップとストック、二脚を着けて(若干の)軽量化をしたのがMG08/15。
後のブローニングM1919におけるA6的な発想である。
弾薬ベルトを収納するドラムマガジンも考案された。
MG 08/15 Machine Gun
銃身の過熱が心配されたが、単連射(バースト射撃)を行うことで回避できた。
このほか、複葉機時代の戦闘機にも搭載された。
これらMG08系統(航空機用は除く)は第二次大戦でも不足する機関銃を補うために使用された。
・イギリス
ヴィッカース社が改良を加えたものをヴィッカース機関銃として採用。
頑丈な三脚に載せ、第一次大戦をはじめ、第二次大戦でも使用された。
冷却水を節約する工夫としてウォータージャケットから出る水蒸気をゴムホースで繋いだ復水缶(単に水の入った缶のようだ)に通すことで再利用する事ができた。
Vickers Machine Gun Video
動画の後半に登場する銃口部の膨らんだ部品は後期型のマズルブースター。
マキシム機関銃は水冷方式を採用しているため弾薬と共に水の補給が不可欠であり、
また、銃身の交換(ウォータージャケットとの隙間にアスベスト製の紐を巻きつける必要があり、この作業にも熟練を要した)がやりにくく、
重量が嵩む(この点に関しては他の同時代の機関銃も同じようなものだが)欠点があったが、
他方、高い信頼性と耐久性を有しており、第二次大戦でも拠点防衛など機動性を必要としない場面では重宝された。
同時期の機関銃としてマキシムと同じく水冷式のブローニングM1917、
マキシムと正反対の特徴を持つフランスのホチキス、
カテゴリー違いとも言えるルイスなどがあるが、それはまた別の機会に。
当時のロシア軍が装備したのはマキシム系のM1905で、
この機関銃に関しては先日紹介した「現代文 肉弾」の155ページから
「さて機関砲であるが、これぞ実にわれらの最も恐るべき火器であった。」という一文から始まり、
1ページ半を割いてこの機関銃がいかに脅威であったかについて書かれている。
日露戦争より後にM1905を改良して第一大戦・第二次大戦に投入されたのがこのM1910。
M1910 Maxim Heavy Machine Gun
「肉弾」の記述を見るに桜井氏の目にしたM1905にはM1910同様、防楯つきのソコロフ銃架が装着されていたことが分かる。
ちなみに動画のM1910は大型の水投入口がバレルジャケットについた後期型で、
ベルトもかなり後の時代の金属製の物が使われているが、
第2次大戦初期まではキャンバス地(要は布製)のものが使われていた。
マキシム機関銃はイギリス人発明家、ハイラル・マキシムの発明した機関銃で、
反動利用により500発毎分以上の連射能力を持つ。
それまでの(信頼性に欠ける)ものと異なり、高い信頼性を持つマキシム機関銃は世界各国で採用されることになるが、
ドイツのように「毎分500発以上」という売り文句に疑問を持ち、
不審人物として国外に出て行くまで監視を付けた例もあった。
マキシム機関銃の性能は各国の植民地における戦闘などに投入され、
名前を知られるようになったが、
その名声を決定づけたものは日露戦争でロシア軍が投入したそれであり、
ドイツ(プロシア)においては観戦将校がその威力を目の当たりにして本国に報告、
採用に至ったとされている。
当時は近代的機関銃の黎明期であり、各国とも運用・運搬方法(大型の台車に載せて輓曳したりしていた)などに試行錯誤していた。
これはそれまでとは軽量になったとはいえ、銃本体で25キロ以上、大型の脚を含むと50キロを優に超えるという点も影響していた。
小銃と異なり圧倒的に多くの弾薬を同時に運搬する必要があり、銃身冷却用の水まで必要とされていることも関係した。
既に書いたが、採用当初は各国とも布製の弾薬ベルトを使用したが、これは新品だと硬くて動作不良を起こし、
扱いが悪いと弾薬がズレて同じく動作不良を起こす欠点があったが、
第2次大戦後期には分離式の金属製ベルトリンクが登場した。
この点はマキシムに限らず、ブローニング系機関銃も同じである。
各国の状況を見てみよう。
・ロシア
既に書いたが鋼鉄製で車輪と防楯のついたソコロフ銃架と組み合わせて第2次世界大戦でも大量に使用された。
・ドイツ
ドイツ帝国・プロイセン時代の1908年にMG08として採用。
運搬を容易にするため、橇式の銃架に載せられた。
German MG08 Maxim
しかし、重いので機動性はあまり変わらなかったようである。
(革製のベルトを使って数人で引っ張る)。
銃口のあたりにある丸い円盤はマズルブースター(発射速度を向上させる)から出る発砲炎を隠すもので、
先端の細長い漏斗状の物はフラッシュハイダー。
機動性に明らかに劣るのでピストルグリップとストック、二脚を着けて(若干の)軽量化をしたのがMG08/15。
後のブローニングM1919におけるA6的な発想である。
弾薬ベルトを収納するドラムマガジンも考案された。
MG 08/15 Machine Gun
銃身の過熱が心配されたが、単連射(バースト射撃)を行うことで回避できた。
このほか、複葉機時代の戦闘機にも搭載された。
これらMG08系統(航空機用は除く)は第二次大戦でも不足する機関銃を補うために使用された。
・イギリス
ヴィッカース社が改良を加えたものをヴィッカース機関銃として採用。
頑丈な三脚に載せ、第一次大戦をはじめ、第二次大戦でも使用された。
冷却水を節約する工夫としてウォータージャケットから出る水蒸気をゴムホースで繋いだ復水缶(単に水の入った缶のようだ)に通すことで再利用する事ができた。
Vickers Machine Gun Video
動画の後半に登場する銃口部の膨らんだ部品は後期型のマズルブースター。
マキシム機関銃は水冷方式を採用しているため弾薬と共に水の補給が不可欠であり、
また、銃身の交換(ウォータージャケットとの隙間にアスベスト製の紐を巻きつける必要があり、この作業にも熟練を要した)がやりにくく、
重量が嵩む(この点に関しては他の同時代の機関銃も同じようなものだが)欠点があったが、
他方、高い信頼性と耐久性を有しており、第二次大戦でも拠点防衛など機動性を必要としない場面では重宝された。
同時期の機関銃としてマキシムと同じく水冷式のブローニングM1917、
マキシムと正反対の特徴を持つフランスのホチキス、
カテゴリー違いとも言えるルイスなどがあるが、それはまた別の機会に。
















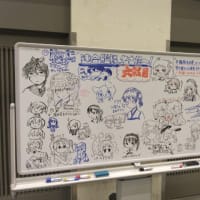









昔の重機関銃はロマンに溢れてますな。
運用は大変そうですが・・・
趣は異なりますがM2はじめ、
ブローニングってホント凄いなぁと思う。
色んな意味で無理ですが…。
余談ですが、その昔、電動FA-MASのメカを組み込んだマキシムM1910をフルスクラッチしてる人がいました…。
>ブローニング
確かに鬼才と呼ばれる人ですが、
銃身交換のアイデアがあれば完璧だったと思います。