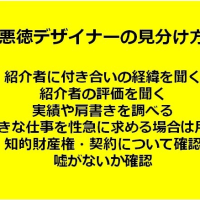<写真>ミニクーパー
◆商品の存在理由
229:【デザインのコツ・デザインのツボ100連発!】第29発 商品企画
こんにちは!「工業デザイン相談室」の木全(キマタ)です。デザイナーの実像・デザイナーとの付合い方・デザイナーとのトラブル回避法など書いていきます。御相談がありましたら、コメントをくださいね。
記事の目次
デザイン相談室の目次 デザインの考え方と運用について
デザインのコツ・ツボの目次 商品企画とデザインワークについて
アクセスランキング
人気blogランキングへ
なんとか、本の執筆、第一稿は完成しました。これから、図版の作成や、編集の方が校正してくださる第二稿のチェックをしなければなりません。まだ、書き換えなければならないところがたくさんありそうです。参考写真も大目に盛り込んでいますので、版元に確認して使えない場合、どうするかなどもこれからの課題ですね。
しかし、とりあえず書き終えたので、少し気が抜けた感じです。でも、まだまだこれからですよね。
近況が長くなってしまいますが、「ものづくりデザイン道場」の第一回も、9月27日に無事終わりました。暴風雨の中、出席率が気になりましたが、全社出席していただき、企業の方の前向きな気持ちが伝わってきました。こちらも、これからです。私の担当は「デザインの心・技・体」の「技」、コンセプト作りです。
講義の内容の詰めもかねて、しばらく商品コンセプトの話をしていこうと思います。
商品コンセプトは、次の10項目が一般的です。私が本を書く際にも、このコンセプトをすべて検証しました。我ながらコンセプトはしっかりしていますので、いい本になるはずなのですが。。。。(苦)
1) 商品の存在理由 (なぜ、今必要なのか?)
2) 差異化要因 (今までの製品とどこが違うのか?)
3)ターゲット設定 (誰がどこで買い、誰が使うのか?)
4) ニーズ設定 (使う人が求める機能は何か?)
5) シーン設定 (だれがいつどこでどう使うのか?)
6) 企業理念の確認 (なぜ、作るのか?)
7) シーズ設定 (どのように作るのか?)
8) 販売ルート設定 (どのように売るのか?)
9) 商品構成 (どのような商品にするのか?)
10)デザインコンセプト (どのようなイメージにするのか?)
今回は、「商品の存在理由 (なぜ、今必要なのか?)」について考えてみます。
■その商品はほんとうに今必要ですか?
「その商品はほんとうに今、必要ですか?」
こんな質問は、ちょっと開発担当者の方に失礼かもしれませんが、これは、商品開発、販売のモチベーションに大変重要です。誰が聞いても、納得できる「商品の存在理由」が、コンセプトの第一歩です。
「誰が聞いても、納得できる」というところが肝心です。
お客さんが、聞いても納得できる
お店の人が、聞いても納得できる
問屋さんが、聞いても納得できる
販売担当者が、聞いても納得できる
生産担当者が、聞いても納得できる
仕入担当者が、聞いても納得できる
納入業者が、聞いても納得できる
家族が、聞いても納得できる
子供が、聞いても納得できる ……
立場の違う人たち全員が、「確かにその商品は今必要だね」と納得できる「商品の存在理由」、それがないと、その商品を今、作る必要がありません。
確かに全員が納得できるような商品は、あまりないかもしれません。
しかし、
お客さんが納得しなければ、買ってもらえない
お店の人が、納得しなければ、陳列してもらえない
問屋さんが、納得しなければ、流通しない
販売担当者が、納得しなければ、積極的に営業できない
生産担当者が、納得しなければ、心を込めて作れない
仕入担当者が、納得しなければ、いい資材を購入しない
納入業者が、納得しなければ、心を込めて作れない
家族が、納得しないような商品を親父は作っていいのか
子供が、納得しないような商品を親父は作っていいのか ……
『誰が聞いても、納得できる「商品の存在理由」』がない商品は、買う側にとっても作る側にとっても魅力がありません。
「商品の存在理由」がなくても、大企業であれば、高めの給料や手厚い福利厚生を与えて、モチベーションを高めることはできますが、中小企業では、それはなかなか難しい。それよりも、自分が今たずさわっている商品開発自体が、人の役に立ち、必要だと信じていれば、自然にモチベーションが上がるはずです。
中小企業にとっては、『誰が聞いても、納得できる「商品の存在理由」』こそが、「商品開発、販売のモチベーション」を高める最高の手段です。
■ミニクーパー
『誰が聞いても、納得できる「商品の存在理由」』とは、どんなことか?
ちょっと昔の例ですが、最近BMWからニュー・ミニクーパー出て、また見直されているミニクーパーを例にして、お話します。
一九五〇年代後半のオイルショックが発端となり、ミニクーパーは開発されました。
オイルショックにより、求められた『誰が聞いても、納得できる「商品の存在理由」』は、「小さなボディと大人四人と荷物が納まるエコノミーカー」でした。
ガソリンが高くなっても、車は手放せない。低燃費で大人が4人乗れて荷物まで詰める車があればいいのに。。。。誰もが納得する「コンセプト・商品の存在理由」です。
設計者のアレック・イシゴニスは、そのコンセプトに答えて、革新的な設計思想を盛り込み、自動車工学の奇跡と言える画期的なスモールカーを開発したのです。
小型化のための
・モノコックボディ
・史上初のFF(フロントエンジンフロントドライブ)の開発
(横置きエンジンをミッションと二階建て)
安定性と重心の低下のための
・四隅ギリギリのタイヤレイアウト
・四輪独立懸架サスペンション
・十インチホイールタイヤの開発
ミニクーパーは、技術的にも画期的でしたが、「小さなボディと大人四人と荷物が納まるエコノミーカー」という「コンセプト・商品の存在理由」がなければ、生まれてくることはありませんでした。このコンセプトは普遍的だったため、FFをはじめイシゴニスの設計思想はそのまま、現代でも日本メーカーの小型車に受け継がれています。
■永遠のコンセプト
優れた「コンセプト・商品の存在理由」は永遠に使い続けることができます。
そして、優れた「コンセプト・商品の存在理由」は、常に他のコンセプトを内包しています。ミニクーパーの場合は、「小さなボディと大人四人と荷物が納まるエコノミーカー」という言葉の中に、すでに、以下の六個のコンセプトも含まれています。
2)差異化要因 (今までの製品とどこが違うのか?)
3)ターゲット設定 (誰がどこで買い、誰が使うのか?)
4)ニーズ設定 (使う人が求める機能は何か?)
5)シーン設定 (だれがいつどこでどう使うのか?)
6)企業理念の確認 (なぜ、作るのか?)
9)商品構成 (どのような商品にするのか?)
そうして、天才的設計者のアレック・イシゴニスによって、下の二つのコンセプトに素晴らしいアイデアが盛り込まれました。
7)シーズ設定 (どのように作るのか?)
10)デザインコンセプト (どのようなイメージにするのか?)
小さなかわいらしい車体に、まるで押し込まれたよう大人が乗っている風情は、ユーモアがあり懐かしさを誘う温かさを感じさせ、大ヒットしました。しかし、残念なことにメーカーや販路に問題があり
8)販売ルート設定 (どのように売るのか?)
だけが、うまくいかず、ミニクーパーは、モーリス・オースチン・ローバー・BMWといくつものメーカーを渡り歩き、生産されることになりました。
とにかく、ミニクーパーが四十一年間生産され続け、五三〇万台も出荷され続けたのは、製品のコンセプトとデザイン、特に「コンセプト・商品の存在理由」が時代を先駆け、優れていたからです。
デザインのコツツボですので、企画の話よりも、デザイン実務の話を中心に進めていたのですが、やはり、企画の話は避けて通れないみたいです。しばらく、企画寄りの話をしていきます。
でも、極力デザイン実務に近いところから攻めていこうと思っています。
デザイン相談室の目次 デザインの考え方と運用について
デザインのコツ・ツボの目次 商品企画とデザインワークについて
アクセスランキング
人気blogランキングへ
◆商品の存在理由
229:【デザインのコツ・デザインのツボ100連発!】第29発 商品企画
こんにちは!「工業デザイン相談室」の木全(キマタ)です。デザイナーの実像・デザイナーとの付合い方・デザイナーとのトラブル回避法など書いていきます。御相談がありましたら、コメントをくださいね。
記事の目次
デザイン相談室の目次 デザインの考え方と運用について
デザインのコツ・ツボの目次 商品企画とデザインワークについて
アクセスランキング
人気blogランキングへ
なんとか、本の執筆、第一稿は完成しました。これから、図版の作成や、編集の方が校正してくださる第二稿のチェックをしなければなりません。まだ、書き換えなければならないところがたくさんありそうです。参考写真も大目に盛り込んでいますので、版元に確認して使えない場合、どうするかなどもこれからの課題ですね。
しかし、とりあえず書き終えたので、少し気が抜けた感じです。でも、まだまだこれからですよね。
近況が長くなってしまいますが、「ものづくりデザイン道場」の第一回も、9月27日に無事終わりました。暴風雨の中、出席率が気になりましたが、全社出席していただき、企業の方の前向きな気持ちが伝わってきました。こちらも、これからです。私の担当は「デザインの心・技・体」の「技」、コンセプト作りです。
講義の内容の詰めもかねて、しばらく商品コンセプトの話をしていこうと思います。
商品コンセプトは、次の10項目が一般的です。私が本を書く際にも、このコンセプトをすべて検証しました。我ながらコンセプトはしっかりしていますので、いい本になるはずなのですが。。。。(苦)
1) 商品の存在理由 (なぜ、今必要なのか?)
2) 差異化要因 (今までの製品とどこが違うのか?)
3)ターゲット設定 (誰がどこで買い、誰が使うのか?)
4) ニーズ設定 (使う人が求める機能は何か?)
5) シーン設定 (だれがいつどこでどう使うのか?)
6) 企業理念の確認 (なぜ、作るのか?)
7) シーズ設定 (どのように作るのか?)
8) 販売ルート設定 (どのように売るのか?)
9) 商品構成 (どのような商品にするのか?)
10)デザインコンセプト (どのようなイメージにするのか?)
今回は、「商品の存在理由 (なぜ、今必要なのか?)」について考えてみます。
■その商品はほんとうに今必要ですか?
「その商品はほんとうに今、必要ですか?」
こんな質問は、ちょっと開発担当者の方に失礼かもしれませんが、これは、商品開発、販売のモチベーションに大変重要です。誰が聞いても、納得できる「商品の存在理由」が、コンセプトの第一歩です。
「誰が聞いても、納得できる」というところが肝心です。
お客さんが、聞いても納得できる
お店の人が、聞いても納得できる
問屋さんが、聞いても納得できる
販売担当者が、聞いても納得できる
生産担当者が、聞いても納得できる
仕入担当者が、聞いても納得できる
納入業者が、聞いても納得できる
家族が、聞いても納得できる
子供が、聞いても納得できる ……
立場の違う人たち全員が、「確かにその商品は今必要だね」と納得できる「商品の存在理由」、それがないと、その商品を今、作る必要がありません。
確かに全員が納得できるような商品は、あまりないかもしれません。
しかし、
お客さんが納得しなければ、買ってもらえない
お店の人が、納得しなければ、陳列してもらえない
問屋さんが、納得しなければ、流通しない
販売担当者が、納得しなければ、積極的に営業できない
生産担当者が、納得しなければ、心を込めて作れない
仕入担当者が、納得しなければ、いい資材を購入しない
納入業者が、納得しなければ、心を込めて作れない
家族が、納得しないような商品を親父は作っていいのか
子供が、納得しないような商品を親父は作っていいのか ……
『誰が聞いても、納得できる「商品の存在理由」』がない商品は、買う側にとっても作る側にとっても魅力がありません。
「商品の存在理由」がなくても、大企業であれば、高めの給料や手厚い福利厚生を与えて、モチベーションを高めることはできますが、中小企業では、それはなかなか難しい。それよりも、自分が今たずさわっている商品開発自体が、人の役に立ち、必要だと信じていれば、自然にモチベーションが上がるはずです。
中小企業にとっては、『誰が聞いても、納得できる「商品の存在理由」』こそが、「商品開発、販売のモチベーション」を高める最高の手段です。
■ミニクーパー
『誰が聞いても、納得できる「商品の存在理由」』とは、どんなことか?
ちょっと昔の例ですが、最近BMWからニュー・ミニクーパー出て、また見直されているミニクーパーを例にして、お話します。
一九五〇年代後半のオイルショックが発端となり、ミニクーパーは開発されました。
オイルショックにより、求められた『誰が聞いても、納得できる「商品の存在理由」』は、「小さなボディと大人四人と荷物が納まるエコノミーカー」でした。
ガソリンが高くなっても、車は手放せない。低燃費で大人が4人乗れて荷物まで詰める車があればいいのに。。。。誰もが納得する「コンセプト・商品の存在理由」です。
設計者のアレック・イシゴニスは、そのコンセプトに答えて、革新的な設計思想を盛り込み、自動車工学の奇跡と言える画期的なスモールカーを開発したのです。
小型化のための
・モノコックボディ
・史上初のFF(フロントエンジンフロントドライブ)の開発
(横置きエンジンをミッションと二階建て)
安定性と重心の低下のための
・四隅ギリギリのタイヤレイアウト
・四輪独立懸架サスペンション
・十インチホイールタイヤの開発
ミニクーパーは、技術的にも画期的でしたが、「小さなボディと大人四人と荷物が納まるエコノミーカー」という「コンセプト・商品の存在理由」がなければ、生まれてくることはありませんでした。このコンセプトは普遍的だったため、FFをはじめイシゴニスの設計思想はそのまま、現代でも日本メーカーの小型車に受け継がれています。
■永遠のコンセプト
優れた「コンセプト・商品の存在理由」は永遠に使い続けることができます。
そして、優れた「コンセプト・商品の存在理由」は、常に他のコンセプトを内包しています。ミニクーパーの場合は、「小さなボディと大人四人と荷物が納まるエコノミーカー」という言葉の中に、すでに、以下の六個のコンセプトも含まれています。
2)差異化要因 (今までの製品とどこが違うのか?)
3)ターゲット設定 (誰がどこで買い、誰が使うのか?)
4)ニーズ設定 (使う人が求める機能は何か?)
5)シーン設定 (だれがいつどこでどう使うのか?)
6)企業理念の確認 (なぜ、作るのか?)
9)商品構成 (どのような商品にするのか?)
そうして、天才的設計者のアレック・イシゴニスによって、下の二つのコンセプトに素晴らしいアイデアが盛り込まれました。
7)シーズ設定 (どのように作るのか?)
10)デザインコンセプト (どのようなイメージにするのか?)
小さなかわいらしい車体に、まるで押し込まれたよう大人が乗っている風情は、ユーモアがあり懐かしさを誘う温かさを感じさせ、大ヒットしました。しかし、残念なことにメーカーや販路に問題があり
8)販売ルート設定 (どのように売るのか?)
だけが、うまくいかず、ミニクーパーは、モーリス・オースチン・ローバー・BMWといくつものメーカーを渡り歩き、生産されることになりました。
とにかく、ミニクーパーが四十一年間生産され続け、五三〇万台も出荷され続けたのは、製品のコンセプトとデザイン、特に「コンセプト・商品の存在理由」が時代を先駆け、優れていたからです。
デザインのコツツボですので、企画の話よりも、デザイン実務の話を中心に進めていたのですが、やはり、企画の話は避けて通れないみたいです。しばらく、企画寄りの話をしていきます。
でも、極力デザイン実務に近いところから攻めていこうと思っています。
デザイン相談室の目次 デザインの考え方と運用について
デザインのコツ・ツボの目次 商品企画とデザインワークについて
アクセスランキング
人気blogランキングへ