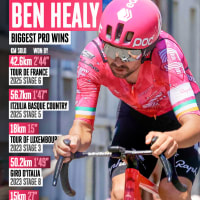そんな折、とある本と出合うことになりました。髙石鉄雄著 『自転車に乗る前に読む本 生理学データで読み解く「身体と自転車の科学」』です。ロードバイク歴10年以上の私にとって「自転車に乗る前に読む本」ではありませんが、「身体と自転車の科学」という言葉に惹かれ電子書籍を購入しました。私のブログにのカテゴリーにも「ロードバイクの科学」があるように、どんな些細なことでも科学的に分析するのが大好きなのです。しかも、「生理学データで読み解く」というのですから、興味津々でした。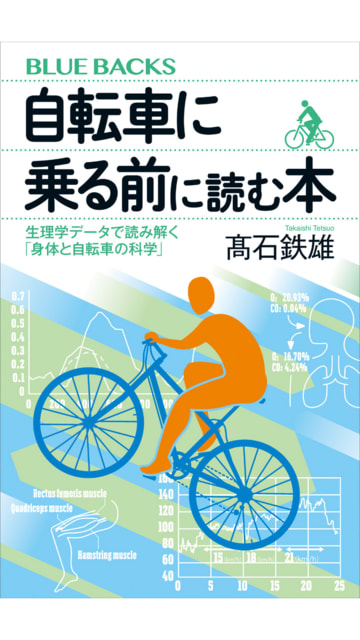
特に私にとって有効だったのは第2章の「運動強度の目安は『心拍数』だった」です。勿論、ロードバイク乗りなので「運動強度」や「心拍数」に関しては良く知っていたつもりです。特に心拍数が上がりやすく、心拍が上がり過ぎる坂が苦手な私には「心拍数」は重要なキーワードです。50代終盤では160bpsで1時間は走ることが出来、それなりの峠や山をこなして来ましたが、60代も終盤を迎え、70歳という年齢が間近になった今、150bpsでも1時間走りきれるかどうか…
この本ではカルボーネンの式で「運動強度(%)」は(運動時心拍数--安静時心拍数)÷(最大心拍数--安静時心拍数)×100で求めています。私がジム通いしていた時は「メッツ(METs)」を基本に考えていましたが、計算が複雑で…この式なら「最大心拍数」「安静時心拍数」「運動時心拍数」が分かればいつでも簡単に計算が出来るのがメリットです。私は2年前からスマートローラーのSUITOを使っていますし。今年からスマートウォッチをXiomiのスマートバンド7を使い始め「安静時心拍数」が51bpmだと分かっています。
この本ではこの「運動強度」を「運動予備能」と呼び、この「運動予備能」50%と「最大酸素摂取量」50%がほぼ一致していることから、運動予備能50%以上の運動を30分程度継続して行うことが健康に良いことを様々な生理学データで検証しているのです。ここでは詳細は省きますが、9月頃から「運動強度60%程度の運動を30分以上」を目安に、バイクに乗ったり、ローラートレを始めました。その結果、毎月1kg程体重が落ち始め、年の瀬の今は71kg代迄の減量に成功しています。
最大心拍数は「220-年齢」として求めるのが一般的なようですが、この計算だと私の最大心拍数は「220-68=158」となりますが、実測では165bpsあります。50代後半には182bpsだったこともあります。安静時心拍数は51前後ですから、運動強度50%時の心拍数=(X-51)÷(165-51)×100となり0.5×(165-51)+51=108です。従って私の運動強度の目安は120程度で30分以上で考えることにしました。運動強度が70%を超えると無酸素域に入ってしまうので、出来る限り有酸素運動になるようにしていると、脚の負担も軽減され、ほぼ毎日ローラートレが続けられるようになりました。
これまでは平均速度やトレーニング時間が目安で、結構、キツ目のトレーニングになっていたようです。高強度の運動をすれば、年齢的に筋肉疲労が溜まり抜け辛くなるのは必然なのに、平均速度30km/hで1時間などというトレーニングにはそもそも無理だったのです。これ迄のローラートレは心拍数が高目で、大汗をかく為一時的に体重は1kg以上減りますが、回復の為に間隔を空けることで体重は戻ってしまいます。
「運動強度50%以上の運動を30分以上」を目安に運動を始めてからは、毎月コンスタントに1kgずつ体重が減り続けています。トレーニングの負荷はあまりかけずに、回数は週に5・6日、30分から50分程度で、前後のストレッチを入れても1時間前後です。来月には70kg代を目標に、来シーズンインには70kgを切れればと考えているところです。