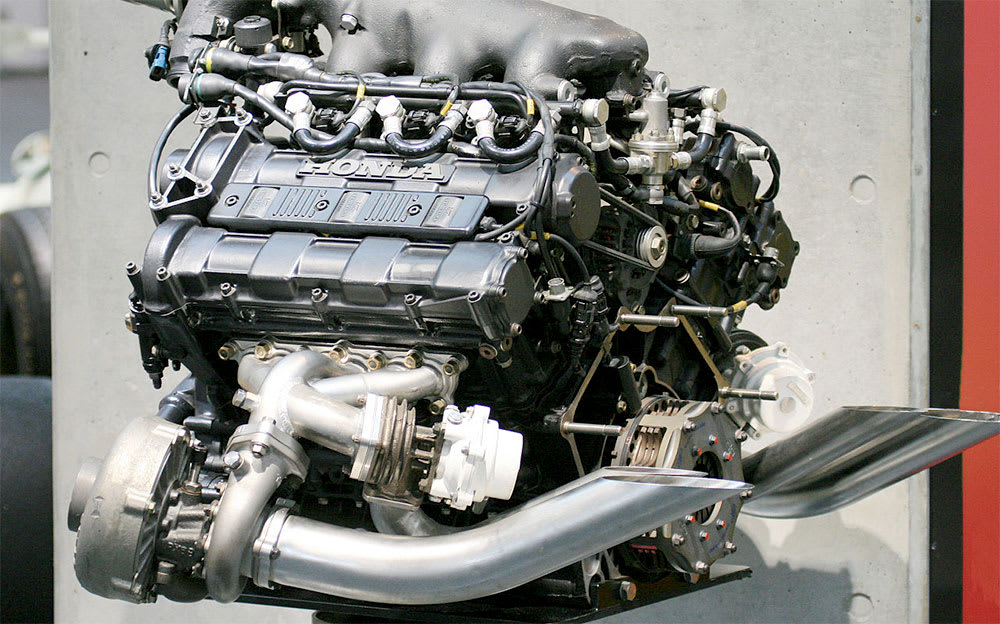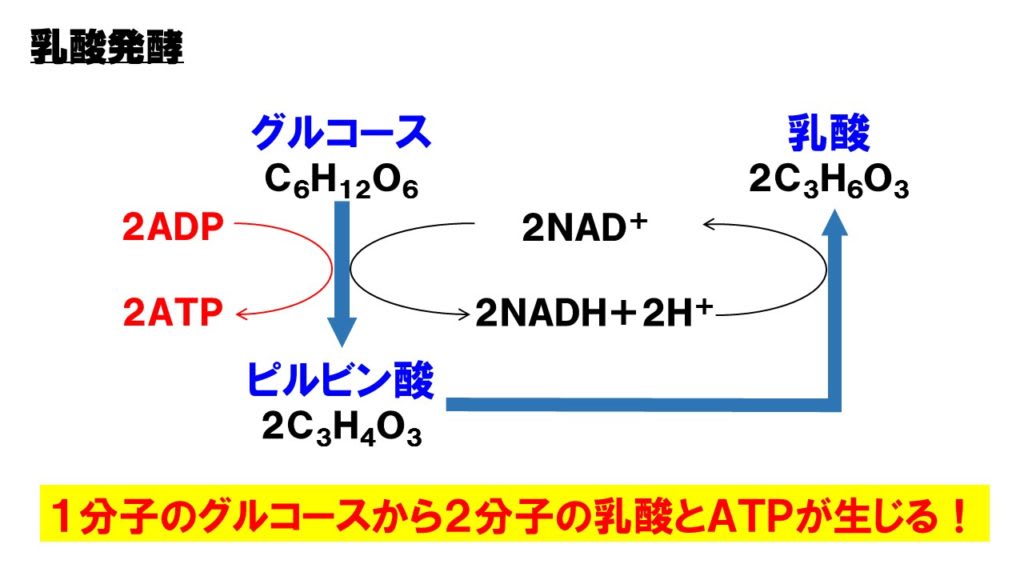「エース」は、もともとトランプのカードであるA(1)に由来する言葉で、現在では「最高の」「最も優秀な」という意味で広く使われています。野球ではチームの中心となる投手、ゴルフではホールインワンを意味し、また様々な分野で優れた人物や物を指す言葉としても用いられます。

サイクルロードレースでは末尾が「1」のゼッケンを付けることが多く、チーム内で最有力の選手がエースと呼ばれることになります。ただ、この「1」のつくゼッケンは時に選手の重荷になることもあるのです。

マンガの「ダイヤのエース」では高校野球における背番号「1」の重さが絶妙に表現されていました。「弱虫ペダル」でも2年生になった小野田坂道君がインターハイで初めて背番号「1」を付けたシーンも印象的でした。

2020年のツール・ド・フランスでUAEチーム・エミュレーツの末尾「1」を背負っていたのが若干21歳のタディ・ポガチャルでした。ステージ2勝を挙げ、最後の個人TTでユンボ・ヴィスマの絶対的エースだったプリモシュ・ログリッジを破り、初出場でマイヨジョーヌを獲得るという大偉業を達成しているのです。

ログリッジにとっては最もマイヨジョーヌに近づいた年で、それ以降はリタイヤが続き、ブエルタ4勝、ジロ1勝という実績を持ちながら、唯一手の届かないものになりつつあるのです。この絶対的エースのリタイヤを見事に活かして見せたのが、2022年のヨナス・ヴィンゲゴーでした。その時のヴィンゲゴーのゼッケンは「18」だったのですから。その年のゼッケン「1」はツールを連覇中のポガチャルだったのですが、怪物ポガチャルを負かしたヴィンゲゴーには驚かされました。強いチームには隠れた才能を秘めた選手がいるものだなあと感心した記憶があります。

サイクルロードレースではチームのエースに様々な種類の選手がいます。チームの支柱としてチームを纏める存在もいれば、積極的にチームを牽引する存在、さらにはチームに守られる存在等です。サイクルロードレースではアシストはエースを勝たせために様々な役割が与えられるという特殊性があります。簡単に言えばエースの犠牲になるということです。

野球ではエースはチームを勝たせるための重要な支柱ですが、打者が得点を取らなければチームは勝てないスポーツですが、サイクルロードレースの勝者は一人なので、他のアシストはエースを勝たせるためだけに力を使い切るのが仕事な訳です。リスクのある場面では、エースを安全に走らせるために位置取りをし、エースが力を温存するために前に出て風を受ける等々です。