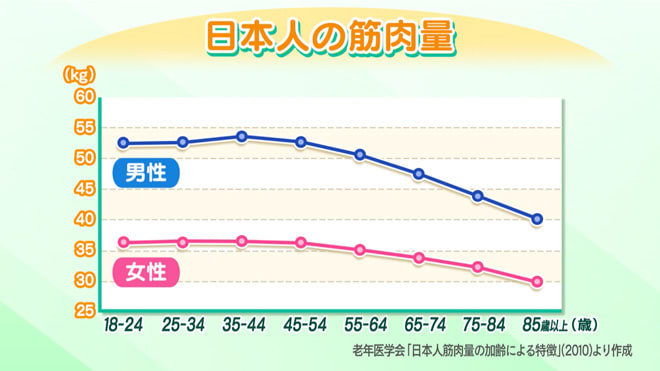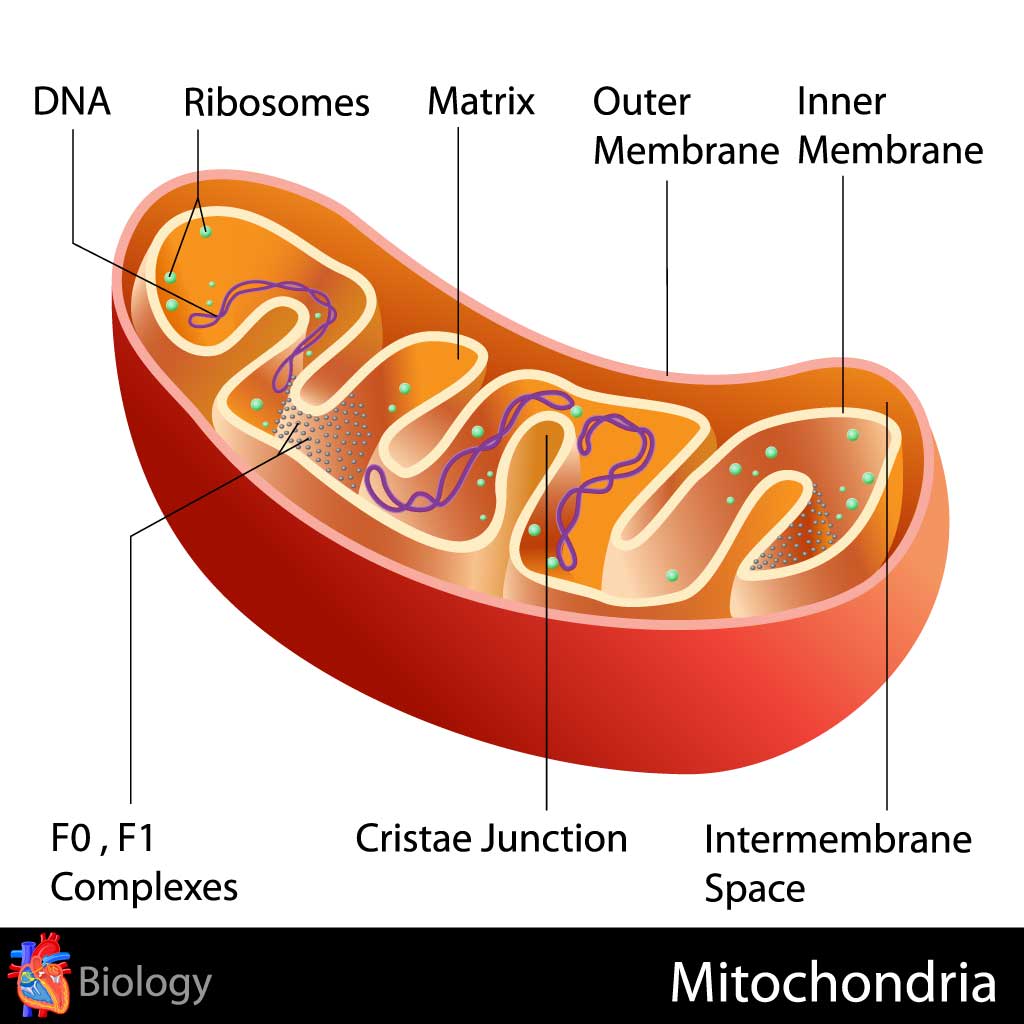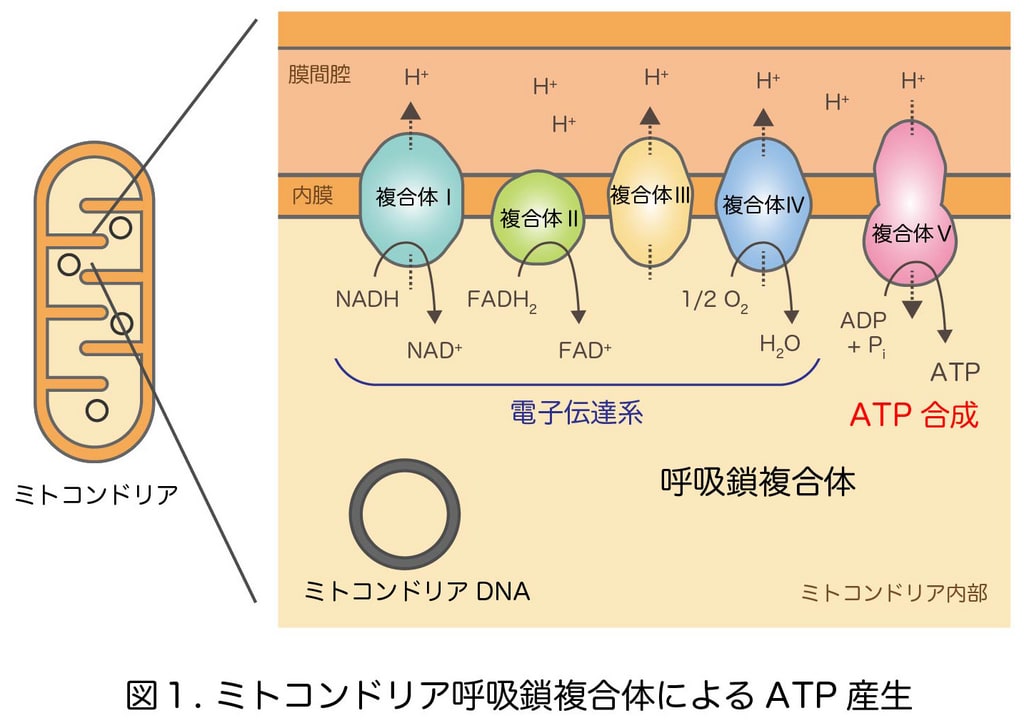今年に入りフィジークの3DプリントサドルVento Antares Adaptiveを購入したことに伴い、ローラー台に設置しているCAAD10で実際に乗り心地を確認する作業に入りました。併せて、いままで使用して来たサドルも含めて乗り比べも行いました。

その結果分かってきたことがいくつかあります。そのひとつはやはり高額のサドルはそれなりに座り心地も脚の回りも良いということでした。ただ、Vento Antares Adaptiveは座面が滑らない為、最初のポジションを正確に出さないと、宝の持ち腐れになり兼ねないことも分かりました。高額な製品でも正しい使い方をしないと、製品の良さが活かせないこともあることは知っておいて損はないと思います。

一方、これまで使用して来た過去のサドルを色々と試してみて、とりあえず、フィジークのアリアンテ・ヴァーサスを使用し続けて来たのですが、このところなかなか1時間のトレーニングが出来なくなって来たのです。ヴァーサス(溝あり)タイプでないアリアンテは座面中央の盛り上がりがやや高目で、股間の圧迫感が強く、溝のあるヴァーサスの方が股間の血流を妨げないと思っていたのですが、どうやら溝にお尻の肉が食い込むことが違和感の原因だったようです。

過去にもロングライドで落ち込んだ部分が股擦れの原因になり、使用を止めたという経緯があるサドルでした。ただ、1時間程度のトレーニングなら問題なさそうだったのですが、実際に1週間・2週間と使って来ると、次第に長くトレーニングが続けられなくなって来たのです。

疲労の蓄積なのかと考えていたのですが、思い切ってトレーニングの途中でサドルを第4世代のSupersix EVOから取り外したFabricのCellにサドルを替えてみることにしたのです。3つあるCellの中で最も新しい製品です。そうすると、1時間のトレーニングに耐えられるようになりました。加えて、脚に係る負荷も低減された感じなのです。

Vento Antares AdaptiveやNAGO R4では1時間で20数㎞のトレーニングが出来ていたので、Vento Antares Adaptiveは第4世代のSupersix EVOで、NAGO R4は第3世代のSupersix EVOでそれぞれ使用する予定です。実走ならダンシングが容易なので、血流が悪くなれば腰を上げれば解決するのですが、ローラー台ではダンシングが出来ないので、どうしても血流を戻すには脚を止めなければいけないのです。

アリアンテ・ヴァーサスの時は30分で1度バイクを降りないといけませんでしたが、FabricのCellなら1時間はサドルの上にいられそうな感じなのです。改めて自分に合ったサドルなのだと実感しているところです。重量があり過ぎるので、Supersix EVOには新しいサドルを装着しますが、ローラー台のバイクにはこのままCellを使い続けようと思っています。自分のお尻に合ったサドルならトレーニング時間も増やせて、脚への負担も少ないというのは新たな発見です。











![[Morethan] サイクルビブパンツ 裏起毛 (M/ロング/ブラック) 秋 冬 メンズサイクルパンツ (サイドポケッ...](https://m.media-amazon.com/images/I/31bmO7pu7fL._SL160_.jpg)