これは昭和35年に制定された同条第2項の「車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。」という規定が65年振りに改められることになるのですが、そのことはほとんど報じられていないのは残念です。今の道交法では「歩行者の側方」とあるだけで「自転車はそれに準ずる」という解釈がされているに過ぎない存在だったのです。

今回の道交法の改正はこの第18条の改正が土台にあって自転車の青切符(罰則規定の追加)があると考えるのが妥当だと思います。ただ、ひとつ残念なのは「十分な間隔」や「安全な速度」の定義が曖昧なことです。できるなら、今国会の中でここを欧州のように明確に定義することができないかも審議してもらえることを期待しています。それでも、この規定がドライバーに徹底されれば、今よりは自転車の車道走行は安全になると思います。
欧州では自転車は車道を走ることを前提に車から自転車を守るという発想に進んでいるのですが、この国では自転車が安心して安全に走る空間すら無いというのが実情なのです。自転車に赤切符が導入された平成27年頃から、この国でも「SHARE THE ROAD」という言葉が取り上げられるようになり、私自身も期待を膨らませたことを良く覚えています。しかし、やはりこの国では道路は歩行者と自動車のもという考え方から脱却できずにいるようです。
















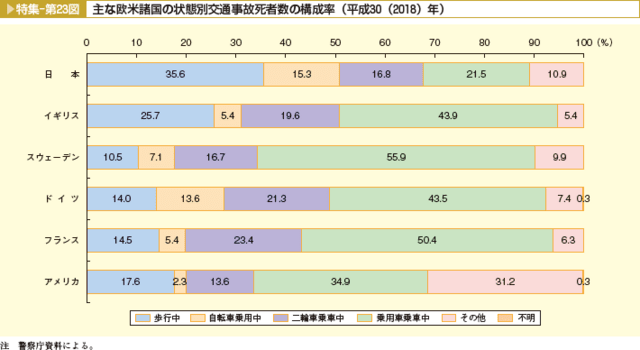




![【サイクルプロショップ推奨】[unizom] 自転車 ヘルメット 大人 【CE認証・超軽量250g・高通気性】 ロ...](https://m.media-amazon.com/images/I/51+P55YtDxL._SL160_.jpg)




