魔がさして糸瓜となりぬどうもどうも 正木ゆう子
「1970年代の日本とチリ 左翼の崩壊と新自由主義」 関川宗英
1970年10月、人民連合政権アジェンデ政権がチリに誕生した。
選挙によって成立した、世界初の社会主義政権だった。
しかし1973年9月11日、ピノチェトによる軍事クーデターが起き、アジェンデ政権はわずか3年で崩壊する。
ピノチェト軍事政権はクーデター後、左派の弾圧を強めた。逮捕者は政府発表で54万人、うち9000人が国外に追放された。また、チリの人口の1割にもなる100万人が国外に亡命した。そして、処刑、あるいは行方不明となった犠牲者は3000人以上になったと言われている。
アジェンデ政権を支持した人々の願いとは何だったのだろうか。
クーデター直前の9月4日、およそ100万人のチリ国民が「アジェンデ!アジェンデ!国民はあなたを守るぞ!」とシュプレヒコールを上げながらデモ行進した。それは、チリ史上最多の参加者を集めたデモだったという。
僅差で大統領となったアジェンデを、アメリカやチリ右派はさまざまな工作で陥れようとしていたが、一般民衆の支持は高まるばかりだった。
アメリカはアジェンデのチリに対して、露骨な金融封鎖に踏み切る。米国の銀行および国際金融機関に対し、チリに融資を行わないよう圧力をかけたのだ。そして、チリの輸出収入の80%を占めていた銅の輸出と生産を妨害した。さらに、右派勢力の系列下にあるトラック業者によるストライキを扇動した。チリ国内の流通の生命線であるトラックが止まれば、モノは回らなくなり市場の物資は不足する。商店にはモノがなくなり、人びとはわずかな食料を求めて長蛇の列を作った。一方商品の買いだめ、闇市場にあふれる商品。チリはインフレを招き、経済は衰退、社会的混乱に陥った。
しかしチリの民衆は、自分たちでトラックを動かした。ストには参加せず工場に働きに出た。自分たちで調達した商品を、地域別グループが自主的に運営した店で人々の手に配る。工場や農地を占拠・運営・警備し、暴利をむさぼる闇市場に対抗し、近隣の社会奉仕団体と連携していく。こうした活動は、アジェンデを支持する人々の結束をさらに強め、1973年3月の総選挙では、アジェンデ側はさらに得票を伸ばす。
そんな人々の動きが、クーデターの直前まで盛り上がっていた。アジェンデ政権は崩壊したが、政権を支持する人々のうねりは高まるばかりだった。
2020年の今、あらためて考えてしまう。1973年、人民連合政権を支持した労働者たちやアジェンデは、何に負けたのだろうか。
「一つの妖怪がヨーロッパにあらわれている、ーー共産主義の妖怪が。」
『共産党宣言』の最初の言葉だ。マルクスとエンゲルス共著の『共産党宣言』は1847年に発表された。
資本主義の発展により矛盾が増大すると、社会革命(社会主義革命、共産主義革命)が発生する。プロレタリア独裁の段階を経由して、共産主義社会が生まれる。階級抑圧の機構としての国家・軍隊・戦争なども消滅するとされた。
ロシア革命、キューバ革命、共産主義革命のうねりは世界を席巻したが、マルクスの言ったような世界革命につながらなかった。逆に、ソ連や東欧など社会主義国家は崩壊していった。
アジェンデ政権が誕生した1970年、日本では三島由紀夫が割腹自殺している。
日本の60年安保闘争は敗北、70年安保闘争も盛り上がらないまま、左翼運動は衰退して行く。日大全共闘、東大全共闘の敗北後、1972年に連合赤軍あさま山荘事件が起きる。日本の左翼運動は壊滅的な打撃を受け、さらに衰退して行く。
北川透は安保闘争について、次のように書いている。
《視線と拠点》創刊号では、中森敏夫が「真にラジカルな精神とは何か(Ⅱ)」を書いている。主として渡辺武信の詩の批評にあてられているが、「今も私達の私達である根拠は、その貧困のさなかにしか求めようがない」「貧困の自覚とその質的転換こそが、私達の今日負っている闘いでなくてなんであろう」という彼の批評の基調になる意識にぼくは共感する。この貧困というのは、たとえば樺美智子の死をヒロイックな死として演出するような内部の貧困さをさしており、そしてそれこそが時代的貧困、空白への広がりをもつものとされている。安保体験は少数の知識人の孤立せる営為を除いて、まだ何ほどかの思想的な結実をも、もたらしていない。(『未明の構想』1982年)
「安保闘争は戦後大衆運動の原点」(手塚英男 『薔薇雨(ばらう)1960年6月』 2020年刊)の声もあるが、北川透が書くように、日本の左翼運動は安保闘争を総括できないまま、いわゆる政治の季節を終えた。その後は、衰退の一途をたどって、今に至っている。
三島由紀夫の自殺を、左翼の崩壊と重ねて考えることは難しい。しかし、三島の自殺も左翼の崩壊も、戦後日本が突き進んできた時代の高揚といったもの、人々が共有できた熱いもの、その終わりを象徴しているように思える。
1970年代の日本の左翼の崩壊は、高度経済成長後の新しい日本の模索、混迷の時代の始まりだった。
そして、1973年のチリのアジェンデ政権の崩壊。
チリと日本が、同じような時期に混迷の時代を迎えたことは、偶然ではないだろう。
その意味を考えていきたい。
井浦 新インタビュー
ーー 映画館という
かけがえのない場所
俳優として、気鋭の監督たちから厚い信頼を寄せられる一方で、造詣の深いアートやファッションの分野の仕事にも引っ張りだこ。それでもなお寸暇を惜しんで映画と映画館に寄り添おうとする真摯な姿勢は、多忙を極めても全国の映画館に駆けつけ、上映後のティーチインを大切にする是枝裕和監督や、名古屋に自らの映画館シネマスコーレを立ち上げ、批評家よりも身銭を切って映画館に駆けつける観客を信じた故・若松孝二監督らの薫陶によるものだろうか。
「もちろん影響はあると思いますが、もともと僕の中にある何かが、監督たちの資質と共鳴して、引き寄せられるように出会ってきたように思います。人と人は、お芝居みたいなもので、誰かを真似しても何も生まれない。ちゃんと個と個で向き合って、互いに反射し合ってこそ何かのきっかけが見えてきたり、重なり合うことによって前に進めたりするんだなと。是枝監督や若松監督の作品や背中を見ながら、広い視野で見つめ、知ることを惜しまず、その上で自分の想いをしっかり発言していくということを学びました」
映画館は6月より再開されたが、新型コロナウイルスの感染防止対策として座席の稼働率が50%と定められたため、満席となっても収益は平常時の半分という状況が3カ月以上続いた。9月中旬にはその制限が一部緩和されたものの、感染収束が見られない中、映画館は依然、深刻な状況を強いられている。それでも建築基準法の下、厳しい換気システムが順守された映画館の暗闇で、心ときめく映画と対峙する時間が至福のひとときだと知る人々が懸命にスクリーンに映画をかけ続けている。
初夏から延期されていた井浦の出演作『朝が来る』(2020年)も遂に10月公開となる。河瀨直美監督が辻村深月の同名小説を映画化し、今年のカンヌ国際映画祭「オフィシャルセレクション2020」に選ばれた話題作だ。「特別養子縁組」で男の子を迎える夫婦と、中学生で妊娠し、子どもを手放さざるを得なかった産みの母。双方の人生がスリリングに交差する人間ドラマのなか、井浦は永作博美さんと、養子を授かる清和、佐都子の夫婦を演じる。

© 2020『朝が来る』FILM PARTNERS.
「河瀨監督は、その独特の役作りの仕方を『役を積む』と呼んでいますが、この役を積む時間がなければ、河瀨組の現場には立っていられない。普通は台本をもらって、ひとりでいろいろ考えて、撮影当日に『よーい、はい』で初めて演技することが多いですけれど、河瀨監督とは一緒に作品のこと、役のことを考えながら撮影当日を迎えるやり方で、とても理にかなっていると思います」
かつて若松監督から突然、三島由紀夫役を託され、その映画『11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち』に割腹自殺目前の三島の魂を鮮烈に刻みつけてみせた井浦。当然、役作りはお手のものだが、河瀨監督といえば、撮影前から俳優にこの「役積み」を徹底させ、ともに昼も夜も語り合いながら役柄を紡ぎ出してゆくという独特の手法で知られる。
「今回、実際に養子縁組されたご家族や、不妊治療の医師にもヒアリングさせてもらいました。たとえば、不妊治療の病院に行きますよね。入り口までは映画のスタッフの方がいるんです。でも受付からは永作さんと、佐都子、清和の夫婦としてふたりだけで受付を済ませ、待合室でふたりして待って。検査のために精子を取るところも、どんな部屋でどういう状態で取るのかとか、その検査結果を受けて、どういうふうに医者が清和に話をするのかとか。すべて撮影前の段階で、役柄になって実際にやってみるんです。その一連の過程をすべて体の中に落とし込んでから撮影に向かうんです」
不妊治療以前に清和と佐都子が出会い、デートを重ねて結婚し、養子を引き取りに広島に向かう旅程も、監督が後ろについて、ずっとふたりを見守っていたのだという。
「佐都子とのデート先も、建築が専門の清和なら、こういうところに行くだろうと全部僕が旅程を考え、レンタカーを運転して佐都子を連れていくんです。知らない人が見たら、週刊誌に載ってしまう図だよなと思いながら(笑)。そうやって役を積むことによって、実際に撮影が始まると、芝居を通り越してカメラの前に立っていられるんです。監督には監督それぞれの撮影方法があるので、みんな違って当然なんですが、それでも今回の河瀨監督の撮り方って、なんて楽しいんだろうって思いました」

有明のタワーマンションに住み、互いに支え合い、朝斗と名づけた養子を我が子のように慈しむ佐都子と清和。一方で、カキの養殖棚が湾を形成する、光の美しい広島の島で母性を育み、のちに社会に翻弄される朝斗の実母ひかり。映画『朝が来る』は、誰をも裁くことなく、命を等しく肯定する。子どもがいなかった高齢夫婦の養女になり、血のつながりがないスタートから日々の暮らしを通して絆を紡いだという河瀨監督は、自身の経験をもとに、愛をもって柔軟に対峙することで未来が開けると信じていると語っていた。
「河瀨監督とみんなで悩んで、苦しんで、希望の光を見た。あの生々しい人間の生というものを、ひとりでも多くの人たちに見ていただきたいなと。そして何を感じるのかは見てくださった方たちそれぞれに委ねたい。家族として、血のつながりは必要なのか、必要じゃないのか。そもそも家族って何なのか。人間が命を授かって生きていくこと。人と人とが関わり合い、支え合いながら生きていくこと。この映画が、そんなさまざまな側面で、見てくださった方たちの考えるきっかけになればいいなと切に思います」
本来なら今年の5月に河瀨監督とともに、この映画を携えてカンヌ国際映画祭のコンペに臨むはずだった。しかし映画の祭典への参加も未曾有のコロナウイルス禍によって阻まれてしまった。「『朝が来る』をカンヌという場で問うてみたかったから残念です」
それまで、たぎる映画への情熱を静かに語っていた井浦が、一瞬、悔しそうな表情を浮かべ、すぐにまた穏やかな笑みをのぞかせた。
映画『朝が来る』予告篇 10月23日(金)公開
youtu.be『朝が来る』
栗原佐都子(永作博美)と清和(井浦 新)夫婦は実の子を持たず、特別養子縁組で男の子(佐藤令旺)を迎え、慈しんできた。彼が6歳になったある日、産みの母・片倉ひかり(蒔田彩珠)を名乗る女が夫婦を訪ね、「子どもを返してほしい」と切り出すが……。
2020年10月23日(金)より、TOHOシネマズ 六本木ヒルズほか全国公開
公式サイト
ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅢ「THE EXQUISITE CORPUS2015」完璧な身体 を見る聴く、 『エイガニッキ』 SASHI-ハラダ 2020/10/17
海に出ていく裸のカップル、小舟に乗って、ヨット、二人は天使か、神々か、いや、群れから遁走した者たちだろうか、広い海、風、空、波間、岸、入り江、彼方を見詰める、何かを求めて、探して、岩場の他二人、やはり男女のカップル、泳ぎ、漁、この二人の見いだすヨット、白い帆の張られたヨット、荘厳な不安な音楽、高見に現れる集団、彼等は何を見詰める、岩場の二人か、ヨットか、ヨットの二人から見いだされる、入江の先の彼方の塔、此処は、やはり、国家、権力、集団の世界、浜辺に一人の娘が倒れて、眠っているのか、ヨットのカップルが見出し、近づいて、ヨットの娘が倒れこんでいる娘の傍に、語りかける、起こさんと、この二人のショットの最中、雷、稲妻、神なのではないか、ヨットにて逃れ来たったカップルの見出した神、今、豊かな眠りから目覚めるべく、いや、反対に、訪れた娘を神として見出すのではないか、寝ていた娘が、互いの衝撃、感動、祈り、希求、この交わりの中にこそ神が、集団の人々から遠く離れ寝ていた娘、その娘のもとに現れたまれ人、海を渡り訪れた二人の前に現れた寝ているまれ人、多様に解釈はなりたとう、いずれにしても、違った場、間の、者たちの対面、ヨットは、岸部を彷徨った、そして浜辺の娘の元に、雷とともに、フラッシュバック、過去、未来、そこに、高層ビルの一室の女、窓の外の高層ビル、街中、現代、モデルの娘が、歩く、映像は揺れ、動き、重なり合って、上下に、一人の娘の重なり、歩く、リズミカルな音楽、着飾った衣装、モノクロで陰っているが、座っているスカートの女の腰、横の男が手を伸ばし、股間に手を、間探る、欲望、セックス、男のズボンの腰、女が座り男のズボンのジッパーを開け、まさぐる、娼婦の女、色目、誘いの顔、部屋の中に現れ、反復される、女はやはり、重なり合って、多様に、乱射、右に左に、下着姿、舞い、踊る、胸を露わに、ベッドから目覚める女、恐怖、覚醒、気付いて不審顔の男、その男が見詰めるのが、目覚めた女か、その前の娼婦か、娼婦の誘いの中に男の顔が、男の顔に変わって青年の顔、表情、いかにも、この娼婦の招きの場に、いるごとく、誘われているごとく、これらのシーンは、いや、全てが、公開映画の一部ではなかろうか、確かに、映画を見るとは、こんな多様な広がり、重なりの中に、在る、千々に、飛び散り、舞い、繋がり、光り、影り、フラッシュバック、森の中を彷徨う裸の女、女たち、探し、求め、不安げに歩く、更に重なっていく映像達、唇、男、女、悶え、幾人もの肉体が、手、足、上に、下に、どのように、絡まっているかすら判明できないままに、更なる映像たち、岸辺のカップルの釣り、網、その網が、縦に、横に、糸、絡まる、フィルム自体の姿も現れ、蠢き繋がれて、捕えるものとしてか、カメラ、映像、見る、撮る、捕える、縦に、横に、重層的に、夢か、幻か、過去か、未来か、誰の見つめる映像か、私の、どのわたしだろうか、あらゆるところから映像が飛び出し、切れ切れに、飛び、散り、跳ね、輝き、何を見ているのか、何が見られているのか、何が見せられているのか、捕えられているのか、判らないままに、この網目の混沌の中、中央の輪の中にヨットが、始まりのヨットのカップルの映像か改めて招かれる、ゆっくり岸辺に近づいていく、浜辺には、やはり、始まり同様に、一人の娘が横たわっている、娘はヨットから降り立ち、倒れている娘の横に、顔を向け、起こさんと、寝ていた娘の目が開き、現れた娘の顔を見つめる、笑みの二人、神の来迎、だが、神は何処に、まさに、はじまり、世界の始まり、再生、男と女の、欲望、葛藤、モデルというビジネス、娼婦、覚醒の女、振り返る女、見詰める男、セックス、あらゆる世界の絡まりの中、カオスの中、目が、人物の目ばかりか、動物の目が、目そのものが、浮かび、重なり、見せられて、見るとは何、混沌の中に、中央の輪の中に、来迎、しかし、この来迎もまた一つの幻、混沌の中の、見せられ招かれてある世界の一齣に過ぎない、来迎、神、可能性として、見るとは、撮るとは、聞くとは、この危うい可能性を生きるしかないのだ、絡まる映像たちの外へと向かって、ラストの見つめ合う笑みの二人の娘に、安易に楽観などしては居れない、取り敢えずの終わりに過ぎないのだし、これはまた新たなる混沌、混乱の始まりに過ぎないのだから、
蓮實重彦、『スパイの妻』を絶賛 関川宗英
10月16日の朝日新聞で蓮實重彦が、『スパイの妻』(黒沢清 2020)を絶賛していた。
『スパイの妻』は、主人公聡子(蒼井優)とその夫の優作(高橋一生)、そして聡子の幼馴染、映画では憲兵隊の分隊長として登場する泰治(東出昌大)、この3人が織りなすドラマだ。
蓮實重彦はこの記事で、黒沢清の映画について、「小泉今日子主演の『贖罪』(12年)シリーズ以降、監督の描くものは、予測不能な女たちの変貌ぶりの描写へと推移している」と書いている。
『スパイの妻』で変貌するのは、聡子(蒼井優)だ。聡子は、憲兵隊の司令部で泰治(東出昌大)から、夫の優作(高橋一生)の疑わしい言動を聞かされる。
「その言葉に毅然として耳を傾ける和服姿で日本風の髪を整えた蒼井優が、圧倒的に美しい」と、「いつの間にか行動する女へと変貌し始める聡子」を讃えている。
「聡子が演じてみせる変貌が戦後日本という名の世界を救うことになる。傑作である。」
蓮實重彦は明快な賛辞の言葉で、記事を締めくくっている。
辛口の蓮實重彦だが、彼の目にかなった映画ならとことん擁護する。
『表層批評宣言』『反日本語論』など刺激的な言葉で、日本にこれまでなかった新しい批評の地平を切り開いた蓮實重彦。そして、数々の映画評論、「リュミエール叢書」の創刊など、日本映画界にもたらした影響は計り知れない。
「リュミエール叢書」や「季刊リュミエール」は、蓮實重彦のお気に入りの監督、映画がまとめられているが、どれも映画への賛辞と映画への愛で満ちている。なぜこの映画は素晴らしいのか、このシーンはなぜ美しいのか、それを彼は知的に語るのだ。その言葉が、いつも刺激的だった。
たとえば、「季刊リュミエール」の創刊号の編集後記をかれは次のように書いている。
「自信をもって、そしてその自信の嵩にあった深い恐れの気持ちとともに、『リュミエール』第一号を皆様方にお送りする。」
蓮實重彦こそ、映画の素晴らしさ、美しさを、知的に言語化できる人だと熱い視線を送っていた。
山形のドキュメンタリー映画祭で、彼の姿を見たことがある。
京橋のフィルムセンター(今の「国立映画アーカイブ」)で、夫婦で映画を見ていたこともある。
それが近年、執筆活動もすっかり減ったと思っていた。
そんな蓮實重彦が、一本の映画にこれほどの賛辞を贈る新聞記事を読んで、ちょっとわくわくするような、どこかうれしいような気持ちになった。
『スパイの妻』の劇場版は、10月16日から東京・新宿ピカデリーほか全国で上映。
「スパイの妻」の黒沢清監督に監督賞 ベネチア映画祭
2020/9/13 朝日新聞

第77回ベネチア国際映画祭は最終日の12日夜(日本時間13日未明)、イタリア・ベネチアのリド島で授賞式があり、コンペティション部門に参加した「スパイの妻」の黒沢清監督(65)が銀獅子賞(監督賞)に選ばれた。日本映画で同賞を受けるのは、2003年に「座頭市」で参加した北野武監督以来17年ぶり。
黒沢監督は、授賞式にビデオメッセージを寄せ、「長い間、監督に携わってきましたが、この年齢で喜ばしいプレゼントになりました」と語った。
黒沢監督が初めて挑んだ歴史映画「スパイの妻」は、太平洋戦争の開戦前夜の神戸で生きる福原聡子(蒼井優)が主人公。日本が戦争へと突き進んでいくなか、満州で恐ろしい国家機密を知ってしまった夫の優作(高橋一生)の暗躍のために、憲兵隊から「スパイ」の嫌疑をかけられる夫婦の姿を描く。高精細の8Kで撮影され、NHKのBS8Kで6月に放送されたドラマを劇場版として再編集した。
最前線にいた元皇軍兵士14人が中国人への加害を告白──『日本鬼子』の衝撃
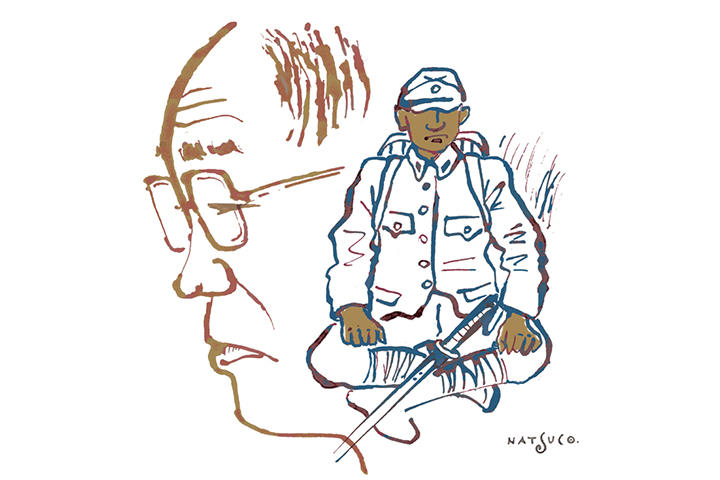
ILLUSTRATION BY NATSUCO MOON FOR NEWSWEEK JAPAN
<捕虜の生体解剖や生体実験を行っていた731部隊員、南京虐殺に加担した兵士、捕虜の大量処刑に関わった憲兵。年老いた彼らが淡々と語るかつての加害行為。これは中国の映画ではない>
『日本鬼子』と書いて「リーベン・クイズ」と読む。中国語圏で日本人を指す蔑称だ。ただし中国の映画ではない。日本で制作されたドキュメンタリー映画だ。
満州事変で始まった日中戦争は15年に及んだ。このとき最前線にいた皇軍兵士14人が、半世紀以上の時間が経過してから、中国兵士や一般国民に対する自らの加害行為を告白する。14人の中には捕虜の生体解剖や生体実験などを日常的に行っていた731部隊員もいるし、南京虐殺に実際に加担した兵士や、捕虜の大量処刑に関わった憲兵もいる。
すっかり年老いた彼らは自宅の居間や縁側、ホテルのロビーや診療所で、かつての加害行為を淡々と語る。村を襲撃した元兵士は家の中で幼児と共に震えていた若い妊婦をレイプしようとしたが抵抗され、髪をつかんで家から引きずり出して井戸にたたき込んだという。泣き叫びながら井戸をのぞき込もうとした幼児も滑り落ち、その後に彼は部下に命じて、井戸の中に手榴弾を投げ込ませた。
こうした顚末を淡々と話しながら彼は、自分の孫を膝の上に乗せている。そしてふと気付いたように、あのときの子供とこの孫は同じくらいの年だったかも、とつぶやいた。
スタンリー・キューブリック監督はベトナム戦争が題材の『フルメタル・ジャケット』で、兵士たちが壊れていく過程をドラマにした。人は本来なら人を殺したくない生き物だ。だから勇敢な兵士にするには、そのバリアーを崩さなければならない。海兵隊の訓練はその典型だ。ところがベトナム戦争後、兵士の多くは社会復帰できないほど壊れてしまったことにアメリカは気付く。ベトナム帰還兵のPTSD(心的外傷後ストレス障害)がテーマの映画は、ほかにも『タクシードライバー』『ディア・ハンター』『ランボー』など数多い。イラク戦争後には『アメリカン・スナイパー』が話題になった。
僕は『日本鬼子』を、『A2』が招待された香港国際映画祭で観た。日本兵の加害行為をテーマにした作品はそれまでにもいくつか観ていたが、そのほとんどは「上官に命令されて」「同僚が加害行為に加担したらしい」など、受け身で傍観者的な証言だった。ところがこの映画に登場する14人は全て加害の当事者だ。語ることで閉じ込めていた記憶が喚起され、呆然としていることも共通している。衝撃だった。多くの中国(香港)人と一緒に映画を観ながら、僕はずっと歯を食いしばっていた。
この映画が公開されてからほぼ20年。日本では今も、南京虐殺はなかったとか、従軍慰安婦はいなかったと主張する人が後を絶たない。あの戦争はアジア解放が大義だ、虐殺などあるはずがない、と。だから認めない。直視しない。多くの人が使う「先の大戦」という呼称が象徴的だ。固有名詞がないのだ。今さら『主戦場』が激しい論争を呼び起こすことが、この国の現状を端的に示している。つまり日本は今も、自分たちの加害行為を歴史にできていない。
上映が終わって出口に向かう通路を歩いていたら松井稔監督と擦れ違った。静かに握手を求められたけど、感想は何も言えなかった。「圧倒されました」とつぶやいたかもしれない。それが精いっぱいだった。
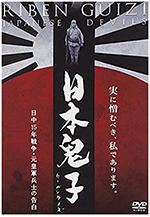 『日本鬼子(リーベンクイズ) 日中15年戦争・元皇軍兵士の告白』(2001年)
『日本鬼子(リーベンクイズ) 日中15年戦争・元皇軍兵士の告白』(2001年)
©「日本鬼子」製作委員会
監督/松井 稔
ナレーション/久野綾希子
https://www.newsweekjapan.jp/mori/2020/09/post-5_1.php














